ソロモン諸島上空を飛行する零戦二二型
サイトからの抜粋です![]()
サイトからの抜粋です![]()
↑↑
レスダブりm(_ _)m
ヘルシアさん、非常に良いスレの題材だとは思いますが、カテゴリー的にはここより国家・軍隊カテゴリーでスレ立てた方がピッタリ合っていると思いますが、いかがでしょうか?
添付画像は数ある零戦の型の中から厳選して代表的な型を待受サイズに合うように一枚にまとめた画像です。
↑この画像の零式艦上戦闘機は上から下へ順番に二一型、二二型、三二型、五二型です。
三二型以外は全て現存する飛行可能な零戦です。
尚、零戦の○○型という型式番号は一桁目が機体改修回数で二桁目が発動機の改修回数にあたり、読み方は二一型ならニジュウニガタとは読まず、ニイイチガタという具合に読みます。
失礼!
画像の順番は上から下へ順番に二一型、三二型、二二型、五二型でした。
ゴメンなさい。
二一型は太平洋戦争前半の代表的な型、三二型、二二型は中盤戦の代表的な型、五二型は後半戦の代表的な型です。
4、5※さん、![]()
まったくおっしゃる通り です、やはり軍カテゴリーでした、
スレが上がってたので覗いてみました、![]()
しかし 素晴らしい知識 お見それしました。
m(_ _)m
待ち受け画像 頂戴しましたよ、![]()
しかしまぁ、
私は零戦は、みんな同じに見えますハィ![]() 、
、
零戦は、我々日本人の
誇りですね、
零式艦上戦闘機も細かく細分化するとそれぞれの○○型の後に甲型や乙型や丙型や丁型などが付く型もありますが、これは割愛します。
太平洋戦争初期の一一型や二一型は長大な航続距離と空中戦格闘性能重視の造りでしたが中盤戦の三二型や二二型は動力性能向上を重視していました。
後半戦の五二型は更に機体強度強化、武装強化と防弾装備強化を盛り込みましたが日本の場合強力なエンジンに恵まれず動力関係が最後までネックとなりました。
したがって初期型、中期型、後期型を比べると姿は似ていてもそれぞれ別の性格の戦闘機となっていました。
塗装も勢いのあった初期に比べ時が経ち守勢にまわって行くにつれ、より迷彩効果を狙った地味なものへと変化して行きました。
ってこんな感じで自分で調べて勉強していくといろいろと発見することもありますね。
9※さん、素晴らしい![]()
私は飛行機は、まったく素人です、
知っているのは、零戦は、当時では、飛行距離では、負けなかった。
初期は 軽く薄く、回転が早く、
しかし 人命無視の攻撃型と、言われ何度も改良された
ときいてました、
軍と三菱重工業での話はもつれたでしょうね、
私はそこまで詳しくは知りませんでした、
大東亜戦争時代の、戦闘機、面白くなりました。![]() 勉強します、
勉強します、
ありがとうm(__)mです、
また 面白い話や、何かありましたら、教えて下さいね、お願いします、
零戦で最初の量産型である零式艦上戦闘機一一型が中国大陸で実戦投入された際に初のデビュー戦となった空中戦で対戦相手となった中国空軍戦闘機の一つ(ソ連製のポリカルポフI-16モスカ)の画像。
モスカとはハエという意味。
この戦闘機は大量に生産され第二次大戦初期の時期ヨーロッパでもアジアでも大量に出回っていたため、たくさん空を飛んでいた。
ドイツ軍や日本軍の撃墜王が途方もない数字の撃墜数を出していたことには少なからずこの戦闘機が貢献しているのも事実。
零戦のデビュー戦は凄まじかった。
日本海軍の零戦13機と中国空軍のポリカルポフI-15戦闘機(複葉戦闘機)とI-16戦闘機合計27機が空中戦をして日本側は撃墜された機体はゼロで中国側は一方的に全機撃墜されてしまった。
だったと思います。
しかも零戦は友軍爆撃機を守る護衛任務を果たしたあとに引き返した末の空中戦での敵機全機撃墜でしたから零戦の航続距離の長大さは当時の世界中の戦闘機の常識を遥かに超えていたことが判ります。
記憶が確かならね。![]()
11、12※さん![]()
![]()
さすがです、
ポリカルポフ←なんか舌を噛みそうな、( ´艸`)知りませんでした、
当時の零戦乗組員は、
かなりの操縦技術を持ってたのでしょうね、
そうしたパイロット方々は、殆どミッドウエーで、亡くなられたようです、
当時の中国軍の軍用機は全て外国製の飛行機の寄せ集めといっても過言ではない状況で勿論自前で開発する能力などは皆無でした。
外国製をコピーする力すら皆無でした。
ソ連製のポリカルポフI-16は出現当初は世界で初めての金属製低翼単葉引き込み脚付きの戦闘機でしたが零戦相手に戦うのは少々無理があり過ぎでした。
ポリカルポフI-16はスペイン内戦でもドイツとソ連が戦った東部戦線でもいつもやられ役でした。
中国大陸でも同じでした。
数はうるさいハエのようにたくさん居るのにいつも落とされてばかり世界中どこへ行ってもハエを意味するようなニックネームで呼ばれていました。
ドイツ軍戦闘機パイロットに撃墜数三百数十機なんて途方もない数を誇る者が現れたのも納得なわけです。
東部戦線でのドイツ軍戦闘機パイロットたちは戦争の初期に大量に保有されていたポリカルポフI-16などの戦闘機を撃ち落とし尽くしたまでは大量スコアで良かったのですが、代わりに戦線に投入されて来るミグ(ミコヤン&グレヴィッチ)やヤク(ヤコヴレフ)やラグ(ラボーチキン)の新型戦闘機に苦慮する羽目に陥りました。
これらのソ連製新型戦闘機は低中高度での空中戦ではドイツ軍のメッサーシュミットBf109やフォッケウルフFw190戦闘機と互角に戦えたからでした。
おまけに数はこれまた怒号のように大量に押し寄せたので堪らないという状況に陥って徐々に敗戦へと向かいました。
これらのソ連製新型戦闘機群は木製、木金混合製、金属製の機体があり、ソ連が大量に保有していた非戦略物資である木材(ソ連には広大な森林地帯がある)を大量活用していたため怒号のような大量の戦闘機が戦線へ送り込まれたとうわけでした。
さすがのドイツ軍もタジタジになったのもうなずけるでしょう。
ソ連製新型戦闘機群は木製、木金混合製、
↑↑
木製 金属混合の戦闘機 ![]()
![]()
ビックリです、
メッサーシュミットは
知ってます、ハィ![]()
戦争を始める時は資源の調達が継続して可能かどうかを真剣に考える必要性が必須です。
特に戦略物資の他に非戦略物資であっても活用可能かどうかを考慮に入れておくくらいの慎重さが国の指導者には不可欠です。
戦略物資である金属以外で非戦略物資である木材を使用して成功を収めた事例としてはイギリスのデハビラント・モスキートがあり強度と軽量化のバランスをうまく取ることに成功したため偵察機や夜間戦闘機としても一級品の軍用機になりました。
ドイツ軍のメッサーシュミットBf109やフォッケウルフFw190もプロペラブレードは木製合板と接着剤を多用していました。
日本はというと戦争の旗色が悪くなった戦争後半に戦略物資が枯渇して来て遅ればせながら軍用機の木製化や鋼製化の試作機を造りましたが、普段から研究していなかったためノウハウが足りず失敗に終わりました。
戦略物資と非戦略物資の調達を考えることは地味な裏方の仕事のようですが実は戦争の勝敗を大きく左右する事柄でした。
そういう意味合いもあり実はアメリカが1番恐れていた日本の兵器は和紙で作られた風船爆弾でした。
冗談話のように受け取られがちですが、戦後アメリカ自身が公表した事実です。
無尽蔵に作れて偏西風を利用するため推進動力要らずで爆弾以外の毒ガス兵器や細菌兵器にも積み替え可能であったためアメリカは本気で怖がっていたのでした。
厳密にいえば、使われていたのは和紙とコンニャクと縄(ロープ)でした。
いずれにしても非戦略物資ばかりで構成されていたのは確かです。
そして本当はハイキングをしていたアメリカ人の幼稚園児たちと先生が風船爆弾の被害に遭っていたのですが、被害の真実をまともに報道したら日本人が調子に乗って戦意高揚のプロパガンダに利用するとしてアメリカは箝口令を敷き報道官制を敷いて一切報道しませんでした。
そのため日本では風船爆弾の効果は薄いとして大々的な打ち上げはしませんでした。
しかし、真実を見抜き大々的な風船爆弾攻撃を実施していたらアメリカ本土のアメリカ人たちをパニックに陥れる効果は十分期待出来る兵器でした。
風船爆弾によるアメリカ人被害者の記念碑は今もアメリカにあります。
風船爆弾![]()
![]()
![]() ?
?
知りませんでした、![]()
そのような、映画や小説など、ありませんでしたから、
何年か前に実際にこの風船爆弾の製作にあたっていた当時、勤労動員の女子高生が今はお婆さんとなりNHKの特集番組に出て来て当時の実話をお話されていました。
今の日本人が聞きたがらず知りたがらないお話。
楽しくも面白くもない今の日本人には聞き心地の悪いお話、でも本当は大事なお話でした。
現代の復元技術を使って飛行可能なところまでレストアされた零式艦上戦闘機二一型(A6M2b)。
アメリカ大陸上空を飛行しているところです。
現代のジェット戦闘機は多目的戦闘機と呼ばれるものが普通になっていますが、日本が作った零戦は当時としては時代を先取りしたような戦闘機でした。
スピードは世界各国の戦闘機より若干劣るが、後続距離は4〜5倍はあり空中戦時の機動性は群を抜いており武装は強力で爆弾も搭載出来て、この当時から既に何でもこなす多目的戦闘機でした。
おまけに世界各国の陸上専用戦闘機よりも性能が良く陸上基地でも海上の空母でも使うことが出来た正に多目的な戦闘機でした。
世界各国の戦闘機が航続距離700〜800kmもしくは長い戦闘機でも1200km程度だった同じ時代にあって日本の零戦二一型は3225kmという破格に長い航続距離を持っていたため陸上基地から渡洋攻撃を受けた時のアメリカ軍司令官はまさか零戦が大洋を遥々渡って攻撃して来たとは信じられず、近海に必ず日本の空母が居るはずだといって探しまくったという実話まで残されています。
現在の、復元零戦ですね、カッコいい![]()
![]()
アメリカ 上空ってのが いいですね、
富士山![]() との画像が、
との画像が、
あれば …。
贅沢言ってすみません
「あるよ」
って昔あったトレンディードラマの台詞みたいだけど…有るよ。
昭和19年、富士山をバックに飛ぶ零戦二一型(後期タイプ塗装)の古写真をカラー化してある画像。
です。
こりゃ素晴らしい![]()
頂きました、![]()
ありがとうm(__)mです、零戦 は、かっこいいなぁ
私が知っているのは、
例の真珠湾攻撃の、
練習は、鹿児島湾で練習したとか、
真珠湾は浅瀬なんで、
深く沈まない魚雷を開発したとか、
うろ覚えですが、間違ってたら、すみません![]()
![]()
![]() 、
、
先程、『零戦燃ゆ』という、映画ありました
零戦以前の飛行機、
録画して、一時停止して撮りました、![]()
↓↓
追加
↓↓
『零戦燃ゆ』の
1場面、のムービーです
↓↓
零戦燃ゆ のこのシーン良いですね。![]()
パプアニューギニアから回収された残骸を元にアメリカとロシアの会社によって現代技術により復元された零戦二二型の画像を貼ります。
二機復元された中の一機の飛行シーンです。
これら二機は映画パールハーバーにも出演しました。
二二型は零戦各型の中で攻守ともに一番バランスが取れているという意味で最良の型だと言われています。
現在に よみがえる、
零戦 二二型、ですね
晴れた青空に 日の丸 私の心までが、洗われます、
ありがとうm(__)m、
台湾から発進、マニラの米軍クラーク基地に向かう、零戦
『零戦燃ゆ』より
↓↓
つづき
つづきです
↓↓
戦争も生き残った零戦のエースパイロットだった坂井三郎氏監修、主演:藤岡弘氏の「大空のサムライ」という映画は非常に良かったですよ。
今も昔も何の集団にも有り得るエリートと平、エリートだけど志しのある者、平だけど熟練した者、などなどの関係を零戦が活躍した時代を背景に絶妙に画いた実体験者監修によるよる実話の映画です。
坂井三郎氏の実体験によるガダルカナルの日米航空撃滅消耗戦をメインにした映画です。
これを観た時、恥ずかしながら涙が出て来ました。
レンタルで探して観られたら感動というか考えさせられますよ。
標高3776mの富士山上空を編隊飛行する零戦五二型3機の画像を待受サイズで貼ります。
大空のサムライの補足というか、零戦のエースパイロットだった坂井三郎氏は生前このように言われていました。
「戦闘機に望む性能の項目の中で1番大切なのは長く飛び続けていられる性能である。」
「零戦の得意技は色々と言われているが、1番凄い得意技は左反転して急旋回し敵機の後ろに素早く回り込む左捻り込みの技が物凄く俊敏に出来る点だ。」
「世界に先駆け当時としては大口径だった20mm機関砲をいち早く標準装備したのは良かったが、当たれば大爆発だがションベン弾になる特性から命中させるには特別なコツが必要だった。」
「7.7mm機銃は直球で飛んで行くので当て易いが威力が小さすぎる。」
「総合すると威力もある程度あり命中させ易く携行弾数も多く装備出来る12.7mm機銃を多数装備するように統一を図っていたアメリカ軍戦闘機は羨ましかった。」
と。
富士山と零戦 こりゃ素晴らしい![]()
![]()
![]()
![]()
![]() です、これも待ち受けに、頂きますハィ
です、これも待ち受けに、頂きますハィ![]()
実は、私ヘルシアは、万次郎 なんです、
この歴史スレの『万次郎長州へ行く』の20※のトリップ見てください、
このレスのトリップと同じです、![]()
日本史が好きなもんですから、ついついこのカテゴリーに投稿してしまいました
名無しさんの、零戦の知識には、お見それしました、おそらく零戦だけではなく、あらゆる飛行機を勉強なさっていると感じます、
出来ますれば、ハンネを 『零』にしたら、嬉しいです、
『カーブを描くションベン弾』勉強になりました ![]()
![]()
![]()
『大空のサムライ』
必ず TSUTAYAで、DVD借りて見てみます、
私も 感動してみたいデス
スカパーのテレビ番組の中で
60年以上の時をえて、今なお飛び続ける、オリジナルの、零戦がある。
米 プレーンズ オブ フェイム博物館が所有の
『五二型零戦』
↑放送されるようです、スカパーのヒストリーチャンネル、
12月21日(土)19:00〜20:00
ヘルシアさん、私は正直言ってこの いつもチャンネルに定住して良いものかどうかまだ決めあぐねています。
ハンネの話は私なんかには勿体ない名前だと思いますのでお気持ちだけ頂いて…ありがとうございます。
m(_ _)m
『零』ではなく『0』と名乗っておきましょうか。
お気に入りのベストショットの一枚を貼ります。
1995年8月6日、日本へ里帰りしたプレーンズ・オブ・フェイム博物館の零式艦上戦闘機五二型が茨城県竜ヶ崎飛行場で飛行して見せた時の画像です。
パイロットは館長のスティーブン・ヒントン氏でした。
この時はノースアメリカンP-51Dムスタングも来日しており、この零戦と並走しながら同時にスタートし離陸したのですがP-51Dムスタングがまだまだ地上を滑走している最中に零戦は既に十数メートル以上上空を飛行していました。
何だか先人たちの匠の技の結晶を目にした思いでした。
もしも、ヨーイ・ドンでスタートして一対一で勝負する空中戦があったなら間違いなく零戦が世界一強い戦闘機になるでしょう。
おやおや
0一文字では反映されないようですね。
では一先ずは名無しでいきます。
龍ケ崎飛行場の零戦かいな、めっちゃ懐かしいな。
曇り空の中を水平飛行から垂直上昇を経て艶やかに反転する機動にシビれまくったがな。
この零戦はプレーンオブ フェイムでも展示飛行を見学したけど飛行後、格納庫に入った機体は、カウリングが熱を持ちエンジンからピシピシと音が聞こえ、その拍力に圧倒されたがな。
ボランティアのハイスクールの男の子が目を輝かしながらカウリングから主翼に伝わるエンジンオイルをウエスで拭いていたので拙い英語で話しかけると零戦が大好きで是非、操縦したいので飛行訓練を受けてるとの事やった。
Tシャツに漢字で零戦と書いてやったら大喜びして内緒で操縦席に入らしてもらったけど、当時の搭乗員の事を思い感無量になったなぁ。
アメリカの地で宝物のように大事に扱われていた零戦は神々しばかりの格好良さやった。
0さん、素晴らしい画像ありがとうm(__)mです、
胴体に2本線があるのは、なんですか?
私は零戦は、素人なんですみません、
詳しくはわかりませんが部隊の目印になるマークか、部隊長マークか、二番機のマークか、を摸したものだと思います。
権兵衛さん、
アメリカで、いい経験されましたね、
羨ましいです、
今や飛行機は、ステルスなど、はかり知れないほど発達してますが、
昭和15〜は、零戦は
画期的な戦闘機だったのでしょうね、
零戦のスタイルに感動し 古い物好きな私は
どんな新しい戦闘機よりも、零戦が大好きです、
ヘルシアさん、零戦とは違いますが、陸軍の中島(スバル富士重工の前身)製戦闘機ですけど、サービスでこれも貼りますね。
1973.10.10帰国時の入間基地で飛行中の四式戦闘機疾風Ⅰ甲(Ki84Ⅰ甲)
零戦は千馬力級エンジンでしたが疾風は二千馬力級エンジン戦闘機でした。
0さん、![]() ありがとうm(__)mです、
ありがとうm(__)mです、
四式戦闘機疾風Ⅰ甲(Ki84Ⅰ甲)
なんか零戦と似ていますね、
プロペラ機のボディの日の丸、がたまりませんね、
零戦の機体に描かれた二本の白線は編隊長機の印しで味方機からも視認良好ながら、敵機からは格好の目標にされるので熟練指揮官が搭乗する場合が多かったんやな。
写真の疾風はアメリカより購入した後、長い間、宇都宮市の富士重工業に保管され、この時に飛行第47戦隊の整備隊長であった刈谷陸軍大尉が同機を点検したところ、簡単な整備でフライアブリ状態になるとの判断やった。
しかし経年劣化の対策が行われないまま飛行不可となったのは至極残念やな。
権兵衛さん、凄い知識![]() 私は何となく、『零戦燃ゆ』の映画見て、かっこいいなぁ、と感じる程度の知識
私は何となく、『零戦燃ゆ』の映画見て、かっこいいなぁ、と感じる程度の知識![]()
![]()
0さんの画像、四式戦闘機疾風Ⅰ甲(Ki84Ⅰ甲)は低空飛行で、着陸寸前かと思いましたが、機体が傾いているので、地面スレスレで、また上昇みたいで、
たまりませんね![]()
胸がジンジンし 鳥肌が立ちます、
零戦各型のほとんど大半は中島飛行機製の栄エンジンを使用していました。
栄エンジンは複列星型14気筒空冷エンジンで千馬力級エンジンでは信頼性は非常に高いエンジンでした。
太平洋戦争の前半の零戦の敵戦闘機は千馬力級エンジン戦闘機ばかりでしたが、その後続々と現れた敵戦闘機は軒並み二千馬力級エンジンの戦闘機ばかりでエンジンパワーの差という面で非常に苦戦を強いられました。
日本の二千馬力級エンジンとして過度の期待を背負わされたのが海軍の紫電改、陸軍の疾風に使われて有名だった中島飛行機製の誉エンジンでした。
誉エンジンは傑作であった栄エンジンをベースにして作り上げられた複列星型18気筒空冷エンジンでした。
誉エンジンの最大の売りは千馬力級エンジンとあまり変わらない小さな直径なのに二千馬力級の力が出せるエンジンであるということでした。
だから同じ二千馬力級エンジン戦闘機でも誉エンジンを使用した日本の戦闘機はアメリカ製戦闘機よりも前面面積を小さくすることが可能となっていました。
ただ問題点はハイオク仕様だった点です。
日本の技術者たちは軍部に対して誉エンジンが素晴らしい動力性能を出すためにはオクタン価の高い燃料が必要不可欠ですよと散々釘を刺していました。
しかし、技術者たちの説明は良く理解しないままにカタログデータのみに目を奪われ誉エンジンに惚れ込んでしまった軍上層部は造る軍用機、造る軍用機にとにかく誉エンジンを積みたがり誉を積め誉を積めと命令しました。
規定の環境をちゃんと整えた上で正しく運用された場合は誉エンジンは素晴らしい性能を発揮出来るエンジンでしたが、戦局は悪化し燃料は元より物資は急速に不足していく中、規定された環境など整えられるはずもなく誉エンジンを積んだ軍用機は軒並み故障や不調が多発し大混乱となりました。
これはひとえに甘い見識しかなかった軍上層部の責任でした。
いかに高性能な物でも指揮する者が愚かなら台なしになる実例でした。
零戦があまりに万能に何にでも使えて傑作だったことは軍上層部に不必要な安心感を与えてしまい後継機開発が後回し後回しにされる悪循環を生みました。
誉エンジンに対する過度の期待も安心感からでしたが後継機開発後回し現象も零戦に対する安心感からでした。
例によって軍上層部は零戦の後継機 烈風にも誉エンジンを積むように命令しました。
物資不足状態の時期に造られた誉エンジンは本来の高性能を発揮出来ておらず、そんな状態の誉エンジンを積んだ烈風は低い性能しか出せず開発関係者を落胆させました。
そこで三菱側は軍上層部は反対していましたが三菱側が自腹で自社製二千馬力級エンジンであるハ-43(誉エンジンよりは直径が若干大きい)に積み替え烈風をテストしたところ軒並み性能は改善され計画要求値を満たしました。
これを聞いた軍上層部は大喜びし直ちに正式採用されましたが既に終戦は直ぐそばでした。
同じようなことはたくさんあったようです。
浅はかな者を指導者に据えてはいけないという実例であり戒めでもあります。
↑ハンネを0と入れるのを忘れていました。
ごめんなさい。m(_ _)m
誉型エンジンは、栄型エンジンをベースにクランクケースの大きさをそのままで、14気筒から18気筒化した為にエンジンの各部品の配置に多少無理が生じ整備性に難点があり、これが稼働率低下の一因でもあった訳やな。
燃料に関しては開発当時、海軍は100オクタン価のガソリン供給を約束していた為に設計時にその事を前提に開発したけど
諸事情により95オクタン価の燃料しか供給、出来なくなり、機械的にオクタン価を上げる為、水メタノール噴射装置により燃料問題に対応したんやな。
出力アップには加給器のブースト圧を上げる必要があり、これにより燃焼室が高温になりプラグの点火前に異常爆発するデトネーション発生を抑制する為により耐爆性の強い高オクタン価の燃焼が不可欠となる訳やな。
巷の燃焼事情の解説では日本は戦争後半にガソリンの質が低下していった事になってるけど実相は年を追ってオクタン価が向上していき全ての誉型エンジンには95オクタン価の燃料が供給されていたんやな。但し南方からの原油の供給が絶望的になった戦争後半には燃料節約の為に練習機等には低オクタン価燃料を用い、実用機の高オクタン価燃料の温存に努めていたんやな。
必要な燃料は在庫していたけど供給の望みが無い為に小出しに使っていた訳や。 但し航空燃料より遥かに消費量の多い艦船用燃料は枯渇していたけど、日本は艦船が全滅に近い状態であったからまぁ問題にはならんかったんやな。
ほんでや燃料のオクタン価問題は解決方向にあった誉型エンジンの不具合の原因を追究してみると、まずマニホールドに不具合が生じ、これが表面化されないまま用いられた為に燃圧低下の要因となった点とキャブレター方式では、14気筒エンジンへの燃料供給が 限界になりつつあったのに18気筒化した誉型では、更に各シリンダーへの正常な燃料供給に問題が発生化した為、対策として低圧力の燃料噴射装置を開発し、惜しむらくは実用化寸前に終戦となって
その真価を発揮できなかった事やな。
その他では大動員の為、機体やエンジン製造に不可欠な熟練工や経験者が次々と徴兵に取られ、難易度の高いエンジン生産に難点が発生した事で、燃料問題より深刻な状態となったけど、軍の大号令の前にその声は伝わる事は無かったんや。
栄型エンジンより全てが高品質化で額面馬力を達成する誉型エンジンやのに実際は、より悪い条件下で実用化された事も要因のひとつやな。後は点火系統のマグネットやプラグコード、プラグ自体もアメリカ製より品質が劣る事も馬力低下の原因やな。
米軍に捕獲された日本機は米軍規格の高オクタン価燃料を始めとしプラグ及びプラグコード、エンジンオイル等で完全整備され、日本ではブーストを押さえ運用されていたエンジンが本来の性能を発揮したために日本側のデータより遥かに高い性能を記録したんやな。
いよいよ、専門的用語がたくさん出てきました、
私には ちと難しいです、
しかしそのような状態で 敗戦になったわけですね
まぁ一言でいうと戦前の日本の科学技術は高レベルの設計が出来たけど、材料や周辺技術がそれに追従する事が難しかったので額面通りの性能が発揮、出来んかったと言う事やな。 零戦の開発時は日本の航空技術は凄まじい勢いで発展している過程にあり、お手本になるアメリカの航空機技術を必死に学び取り、そこから更に高レベルなものへと発展さしたんやな。
機体に用いられた部材にも超々ジュラルミンと言うそれまでの米軍規格の航空機材料より格段に優れた強度のジュラルミンを住友金属の技術者が開発に成功し、それが零戦の軽量化に貢献したんやな。
エンジンもアメリカのプラット&ホイットニー製を参考に同時期のアメリカ製より先進的な構造と高品質な材料が使われ、アメリカ製を参考に劣化コピーならぬ進化コピーとも言うべき高いレベルやったんや。
また零戦の開発当時、航空機産業に従事する人は極めて優秀な人材で、日本人特有の職人肌とより高度な技術に挑む真摯な姿勢が零戦を誕生させた訳やな。
アメリカの技術を急速に吸収し、一時期ではあるが米軍の戦闘機より優れた性能を誇ったのが零戦の真の姿やな。
余談ながら初期の零戦にはアメリカ製の部品が使われた箇所もあり、機体の構造自体もアメリカの技術を吸収、発展させ更に高いレベルに昇華させたものやな。
燃料もアメリカ製の92オクタン価ガソリンがベストでエンジンオイルに至ってはテキサコ社製オイルを使用する旨が取り扱い説明文に記載されとったんやな。
終戦により零戦の全てが途絶したように思えるけど、実は当時、零戦の重要部品を開発したメーカーや下請け会社は平成の現在に至り未だに操業している所も多くあり、自分達が普段、使っている生活用品に零戦の技術的な系譜が脈々と受け継ぐがれているんやな。
権兵衛さん、よくわかりました、レスを五回ほど繰返し読ませて頂きました、
昨日、NHKで『零戦〜搭乗員たちが見つめた太平洋戦争』があり、
零戦が米空母に体当りする場面、
↓↓
昨日の零戦の番組を見たけどオカンの兄弟が19歳で特攻隊員やった事と重なったがな。
戦闘機乗りになり零戦で大空を駆けるはずが練習機での特攻隊員となり、出撃前に終戦となり復員したけど、戦後は元特攻隊員に対する世間の風当たりは厳しいものがあったそやな。
終戦直後に熟練の搭乗員が「お前達も海軍の戦闘機パイロットなら一度は零戦に搭乗しておけ」と言われ歴戦搭乗員の操縦する複座の零戦に搭乗し、初めて対戦闘機の機動を体験したけれど物凄いGがかかり背骨が折れるかと恐くなり最後は鼻血が出たそうやな。
着陸後フラフラになり機体から降りた姿を同僚達にからかわれたそやけど、その同僚達も着陸後はフラフラになり嘔吐する者もいたそうで、
それでも搭乗希望者が後を絶たず予備学生の少尉達が当時、貴重品だったサントリーの角ビンを手に「願います」と言って搭乗飛行を願い出たそうや。
夕闇が迫るまで飛行は続き、エンジン全開飛行で加熱しパンパンパンと異音を発しカウリングを高温で真っ赤にしながら着艦要項通りの見事な三点着陸で定点接地し全員から拍手を持って迎えられたそや。
叔父に会う度にこの体験談をせがんだもんやけど、零戦には自分の琴線に触れる 言い知れぬ魅力があるねんがな。
日本人の期待を一身に背負い大東亜決戦機とまで言われた二千馬力級エンジン戦闘機疾風。
現存していて過去に飛行展示も行っているのに零戦に比べると公開されているカラー写真が非常に少ない疾風。
飛行展示のカラー動画に至っては探してはみたものの見付けることが出来ていません。
少ないながらも公開されていた疾風のカラー写真を厳選して貼ります。
どれも1973年入間基地でのもの。![]() 前から気になっていることなのですが、出来るだけ大きな画像を提供すべく出来るだけ大きな画像を貼っているのに試験的に自分でダウンロードしてみると小さな画像にしかならないのです。
前から気になっていることなのですが、出来るだけ大きな画像を提供すべく出来るだけ大きな画像を貼っているのに試験的に自分でダウンロードしてみると小さな画像にしかならないのです。
ダウンロードのやり方が良くないのでしょうか?
それともダウンロードする際には必ず小さな画像に変換されてしまうシステムになっているのでしょうか?
ヘルシアさんが最初に貼られていた写真のカラー化版を貼ります。
ソロモン諸島上空を行く零戦二二型の編隊です。
零戦二二型はエンジンを栄二一型にして、主翼は零戦二一型と同じ折り畳み機構付きの翼の長さが長いタイプとして燃料タンクも容量を増やし、零戦本来の機動性重視指向に戻し航続距離の回復も狙った型で零戦各型の中では最もバランスの取れた最良の型だといわれています。
写真の零戦はアメリカ軍との航空撃滅戦という戦力の消耗戦に入った時期のものであるため酷使されていたこともあり、また赤道付近の灼熱の太陽光に曝される毎日だったこともあり各機とも塗装がかなり傷んでいました。
まさにこの時期は特にパイロットも戦闘機も消耗の激しい熾烈な消耗戦でした。
この零戦の勇姿は吉田一報道班員がラバウルからガダルカナルへの進攻時を撮影したもので、本来は一式陸攻の100メートル上空を飛行するのが編隊の定位置で、この時は写真撮影の為に同高度に下がって来たそやな。
搭乗員は一説によると中島少佐とも言われてるんやな。
ラバウルからカダルカナルの航路は晴天時は珊瑚礁や数多くの無人島が途上に点在し、視認で航法が可能やけど天候が悪化すると航法計算をしながら千キロの長駆を飛行して帰還しなければならぬ、数多くの機体が航法を誤って未帰還となりラバウルは搭乗員の墓場と呼ばれたんやな。
パプアニューギニアから回収された残骸を元にリバースエンジニアリングという現代技術の復元手法を使って復元されたあとテストに望む零戦二二型。
その頃の写真です。
復元が済んだばかりで、まだ塗装されていない状態の姿だと、またそれもいいですね。
0さん、権兵衛さん、
解りやすく、コメント
おそれいります、
私は 零戦は、あまり詳しくなく、このスレで、
零戦に深く興味をもつ様になりました、
先日コンビニで
『零戦の真実』と言う本を買ってしまいました、↓↓
恥ずかしながら、初めて知った
この本にかかれてある、
翼内燃料タンク、
五二型は自動消火装置付き
零戦が抱いている、ロケット爆弾かと思いましたが、![]() 予備燃料タンクでした
予備燃料タンクでした
ヘルシアさん、おはようございます。
落下式燃料増加タンクを初めて装備したのは三菱零戦の一代前の先輩戦闘機である三菱の九六式艦上戦闘機だったといわれています。
それはスリッパ型増槽と呼ばれ、まだ洗練された形ではありませんでした。
運用コンセプトを受け継ぎつつ空力的にリファインを図り洗練された物にしたのが零戦でした。
これ無くしては3200km前後という零戦の長大な航続距離は実現不可能でした。
後から開発され出て来たアメリカの戦闘機などでは同じような落下式増槽を備えたものも出て来ましたが、同時期の諸外国製戦闘機の場合は見た目は似ているが落下出来ない固定式も多くありました。
長距離飛んで空中戦直前に落下式増槽を捨てて戦いに挑む運用方法の零戦の落下式増槽はその点では画期的だったといえます。
2013年も最終日なので零戦の戦場写真の中でも一番鮮明に撮れているといわれる写真のカラー化版を貼ります。
飛行中の零戦五二型極初期型と二二型です。
零戦が実戦投入された当時の世界の戦闘機は航続距離わずか600〜700km前後の物が一般的で、3200km前後もの長距離(連続飛行にすると11時間前後もの長時間)を飛んで行き空中戦をするなんて常識はずれもいいところだったので諸外国の軍では信じない者も多くいました。
特にアメリカ本国ではその情報の報告を受けても信じようとしませんでした。
しかし、これは事実だったため太平洋戦争の前半アメリカ軍は太平洋地域での航空戦力をほぼ全て失う手痛い目に遭うことになりました。
それでアメリカ軍は太平洋戦域に散らばる零戦の残骸を探し回り拾い集めては復元して零戦の秘密をあばこうと血眼になったといいます。
そうして得た技術情報を元にして自分たちの国の戦闘機開発に活用しました。
戦時中オーストラリアのイーグルファーム空軍基地のハンガーセブンには新品かと思うくらいに綺麗に復元された飛行可能な零戦があり、この零戦で性能特性の調査をして自国製戦闘機と模擬空中戦をさせたりして研究していたといいます。
アメリカ軍のそのバイタリティーも圧巻ではありました。
0さん、貴重なお話し、ありがとうです
零戦の 搭乗員は
椅子に座ったまま、同じ体勢で何時間も、操縦する際に、かなりの、睡魔に襲われるそうですね、
眠ったまま、海に墜ちて亡くなった方もいるとか![]()
![]()
しかしまいったなぁ![]() 、この『いつもチャンネルに』0さんや、権兵衛さんのように 零戦に詳しい方が
、この『いつもチャンネルに』0さんや、権兵衛さんのように 零戦に詳しい方が
いらっしゃるとは、
まだまだ 知っている事ありましたら、
コメントお願いします、φ(._.)メモメモ
零戦52型以降に装備された翼内タンクの自動消火装置は、当初、搭乗員達には気休め程度にしか思われてなかったそやけど、実際に被弾しガソリンに着火した次の瞬間に消火するのでその機能の高さに驚いたらしいがな。
これはガソリンに着火した場合、0.3秒以内に対策を講じる必要があり、零戦の消火装置の場合は、燃料タンクに熱感知器が装着され、炎により感知器が通電し瞬時に炭酸ガスを噴射する仕組みになってるねんな。
ワイが仕事で使ってる溶接器は、炭酸ガスで空気を遮断した中で鉄を溶かす仕掛けになっとるんやけど、作業中に洗浄に用意してるシンナーが染み込んだボロキレに飛び火して炎が上がっても溶接器のノズルから炭酸ガスを出すと瞬時に火が消えるんやな。
被弾して自動消火装置により撃墜を免れた機体は主翼一面に黒い煤が付着するので、着陸後に他の搭乗員にそれを見られて「地獄の閻魔様に通せんぼをされて良かっの。」とからかわれたんやな。
ヘルシアさん、権兵衛さん、おはようございます。
m(_ _)m
二日に跨がる深夜業務で昨晩から今朝にかけても仕事だったので日にちの感覚が麻痺して一日ズレて勘違いしてました。
今日が2013年の最終日でした。
零戦五二型極初期型と二二型の鮮明な戦場写真のカラー化版は本来なら今日貼るべきでした。
赤道付近の上空での写真のため使い古された実戦使用機なら大半が灼熱の日差しのために塗装が褪色し剥がれかけているのですが、この写真の機体は配備されたばかりの時の零戦みたいで新品そのもののようです。
原版の白黒写真で見てもそれはハッキリ判ります。
今日は1942年7月9日アリューシャンのアクタン島でアメリカ軍に発見され回収されて零戦調査研究の鍵となった空母龍驤の戦闘機隊の一人、古賀忠義一飛曹乗機零戦二一型の画像を貼ります。
回収後、飛行可能状態まで復元され当時のアメリカ海軍戦闘機の塗装とマークに塗られてテスト飛行中の姿です。
アリューシャン攻撃作戦の際にトラブルでアクタン島に不時着してしまった零戦二一型です。
草地と思われていた緊急時の着陸予定地は湿地帯であったためにひっくり返り古賀忠義一飛曹は頭部を強打して亡くなられていたそうです。
北方の海域特有の濃霧に阻まれ日本軍側では発見出来ず、たまたまアメリカ軍側に発見されてしまったようです。
アメリカが大喜びしたのは言うまでもありませんでした。
徹夜明けご苦労はん。
アクタン島で発見された零戦は、オイルラインに被弾しエンジン不調になり、着陸を試みたものの湿地帯に主脚を取られ
機体が横転し搭乗員は即死したんやな。
この零戦を調査したグラマン社の技術者達は機体の設計と製作技術が極めて洗練され、特に薄い外板を全く歪み無くフレームに張る技は、グラマン社の熟練工を上回るもので、加えて沈頭鋲による滑らかな機体表面処理に感嘆したそやな。
海軍の戦闘機パイロットからはワイルドキャットの主脚の操作は、手動による人力操作やのに零戦のそれは、油圧によりスイッチで操作できるのを羨ましく思ったそやな。
また通説では零戦の機体構造は、量産に不向きとされているけどグラマン社の技術者は、零戦の構成部材は大掛かりのプレス機械や精密な金型を用いなくとも簡単な木型等を用いて製作可能で、町工場レベルの所でも機体部材の量産が可能で人海戦術により大量生産可能な事を指摘してるのやな。
この簡単な木型により部材が作れる事によって現在でもリバースエンジニアリング工法により零戦が新造可能な訳やな。
0さん、権兵衛さん、
明けましておめでとうございます、
0さん、貴重な画像ありがとうm(__)mです、
しかしながら零戦の日の丸が、☆マークに塗り替えられた、
むなしくなります、
権兵衛さん ![]()
たしか権兵衛さんの、ご先祖樣は 零戦の搭乗員 だとか、
リバースエンジニアリング工法
↑↑
私には難しいので![]() 意味を教えて下さい、
意味を教えて下さい、
m(_ _)m
明けましておめでとうさん。
まぁ叔父さんは練習機での特隊員で一度だけ複座の零戦に搭乗しただけやけどな。
ほんでリバースエンジニアリング工法とは、原形を保った航空機の残骸から採寸し、形をコピーして構成部材を新たに新規製作する事やな。
勿論これは大変な労力を必要とする作業で一機の機体を完成させるのに五年や十年程、かかる場合もあるんやな。
エンジンは構成部材の復元は困難なんで 状態が良好な場合は分解整備で完璧なオーバーホールで稼動状態にして、状態の悪い場合は同じサイズのエンジンに換装するんやな。
零戦の新規製作の場合はアメリカ製のエンジンを使用する場合が殆どやねんな。
なるほど、
殆どがアメリカ製のエンジンとは…。
しかし しかたないし
何年もかけて、復刻される方々に頭が下がります、
ヘルシアさん、権兵衛さん、あけましておめでとうございます。
飛行可能な復元機となるとコストと消耗部品などの供給体制を含む維持運用コストを考えるとやはり同クラスの普及率の高いものをということに行き着きアメリカ製の千馬力級空冷星型エンジンという流れになるのがほとんどです。
そしてアメリカ製エンジンではあるが組み立ては中国で行うなど費用を極力抑えるようにしている事例も多いです。
零戦の場合は機体表面からリベットの頭が突起しないように頭部分を平らにカットした沈頭鋲を全面的に使用し機体表面を滑らかにするように工夫されていました。
主翼は正面から一見すると胴体から左も右も斜め上に向かって伸びているよう(ただ上反角が付けられているだけのように見える)に見えますが、主翼の中ほどから微妙に下方へ垂れるように造られています。
捩り下げと呼ばれる日本特有の匠の技的な絶妙な造りです。
これにより失速し難く低速域での操縦特性を良くしていたといわれています。
画像は零戦二二型と五二型の飛行シーンを正面側から捉えたものです。
捩り下げが判ると思います。
0さん、こわちわ、![]()
微妙な、捩り下げ
言われて見れば、何となく![]()
上につり上がった主翼は 米海軍戦闘機 F4Uコルセアで、よく見かけますが、零戦が捩り下げとは、知りませんでした、
現存する飛行可能なアメリカにある5機のなかの1機、
零戦21型
米テキサス フライング レジェンド航空博物館所属、
ソロモン諸島バラレ島で回収とか、
復元に4年余りの歳月を費やし 2004年7月初飛行に成功
↓↓
0さん貴重な画像ありがとうm(__)mです、
私の画像は雑誌から携帯で撮った画像です![]()
同じく21型 の復元された操縦席と
飛行中で、アメリカ人が操縦しているのが残念です![]()
今から ブックセンターに行って 零戦の本を見てきます![]() ,
,
このフライアブル(飛行可能)の21型は、ダコタブレイド社で製作された機体で航空ショーに突如として参加しその完成度の高さと相まってセンセーショナルに近い形で雑誌等に掲載されたもんやな。 エンジンはゼロ戦のそれより若干、外径が大きいプラット&ホイトッニーを搭載しながらカウリングと胴体部分の違和感の無い造形は見事の一言に尽きるがな。 ロシアで製作された22型は同じエンジンを用いながらカウリング寸法が大きく、胴体部分と段差があるのが残念なところやねんな。
82※は権兵衛さんですね、
素晴らしい知識、![]() おそれいります、
おそれいります、
私は 本をそのまま、書いてます![]() しかしかなり勉強しましたよ、
しかしかなり勉強しましたよ、
権兵衛さんの言われる、ロシア製零戦22型
ニューギニア西端のバボ飛行場で回収した残骸を基に、ロシア製零戦
バボ飛行場跡に放棄されていた 三菱製零戦22型
第3869号機
と飛行中の零戦22型
コメモラティブエアホース所属
本をそのまま携帯で撮ったので、不鮮明ですみません![]()
![]()
![]()
垂直尾翼に第3航空隊の、『X-133』とあります
Xの機番は第三空で後の202航空隊やな。
鈴木少佐の率いるこの部隊は歴戦搭乗員達で構成された常勝部隊でメドナ基地進出の時は、周辺の歓楽街で若い搭乗員達が派手に遊び回り、これに目を付けた憲兵隊と大立ち回りをする事も度々やったそやな。
昭和18年のポートダウィーン進攻作戦では鈴木少佐率いる零戦隊は一式陸攻の護衛として進撃し、迎え撃つスピットファイアー隊と激しい空中戦を展開してワンサイドゲームで勝利したんやな。
それより以降は、バトル オブ ブリテンで活躍した歴戦のスピット隊の隊長はドッグファイトでは不利と考え、レーダー管制で日本軍の戦爆連合を捉え早期発進し高々度から零戦隊を攻撃したものの難無く矛先を交わされ 執拗にドッグファイトを挑まれる間に燃料切れとなるスピットファイアーが続出する有様やってんな。
ヘルシアさん、権兵衛さん、こんにちは(^O^)/
オーストラリアでのスピットファイアと零戦の戦いで使用されたのは零戦二二型と砂漠仕様の防塵フィルター付きトロピカルタイプのスピットファイアMk.Vcでしたっけ?
私はスピットファイア贔屓ではありませんが、スピットファイア贔屓の人にいわせるとオーストラリアがイギリスに頼み込んで配備してもらったスピットファイアのタイプは最新型とは呼べない旧式タイプで北アフリカの砂漠戦で使用されていたトロピカル仕様そのまんまだそうで、オーストラリアの気候には合っておらず不調でオーストラリアのパイロットたちは戦闘機対戦闘機戦には不慣れな者ばかりだった。
一方、零戦はオーストラリア周辺の気候に合っておりパイロットも戦闘機対戦闘機戦のベテランばかりだったとネット上で主張しているようです。
画像は零戦二二型とスピットファイアMk.Vcどちらも飛行中のものです。
Mk.Vcは機首下面にオチョボグチが突き出たヒョットコみたいな防塵フィルターが付いた特異な姿のスピットファイアです。
これが砂漠の熱帯地方には合っていても湿度の高い熱帯地方には不向きだったのでしょうかね。
当時のヨーロッパ戦では特にそうだったのかどうかはよく判りませんが、離陸したらすぐに急上昇して高い位置に占位する飛び方をしていたらしく、湿度の高い熱帯地域でそれをやると急激に圧縮された湿度の高い空気内に含まれる湿気が霧というか水蒸気になり、それが装備していた防塵フィルターを詰まらせてエンジンが火を噴いたり煙りを吐いたりしてエンジン不調となり辛うじて飛んでいるかのような状態となり本来なら戦えるようなコンディションではなかったのだが健闘したのだという言い分のようです。
確かに日本の空であっても梅雨時とか雨上がりの時とかに飛行機が急機動で空を飛ぶと翼端や翼面の周りの空気が急激に圧縮されヴェイパー(水蒸気による霧のような雲)が発生しますから、有り得る話かも知れませんね。
まぁ戦闘機同士の闘いはルールの無い無差別クラスの殴り合いみたいなもので、機体の仕様云々は眠たい話しやろな。
それにこの時期、英空軍は米軍供給の高オクタン燃料を使用するのに対し零戦隊は指定燃料92オクタンよりやや劣る91オクタン燃料を使用していた点でも英空軍の方に有利やったと思うねんな。
南方地帯の基地では機体の燃料が直射日光により温度が上がったまま高々度に上がるとペーパーロック現象を起こしエンジンストールが発生するので、貴重な井戸水を使って燃料を冷やしたり、燃料タンクに給油する際は鹿皮で燃料を濾過して水分を除去する等の整備員の大変な努力も大切やってんな。
バトル オブ ブリテンでドイツ機を相手に活躍した戦闘機やったので日本軍の零戦なんか何するものとの、過小評価が敗退する原因の一つやと思うなぁ。
さらに長距離進攻の零戦隊にドッグファイトで絡まれたスピット隊がホームグラウンド上空で燃料切れを起こしたて笑える話しやがな。
但しスピットファイアー自体は、傑作と評価されるロールスロイス製マーリンエンジンが出力を上げるのに比例し戦闘力を増して行きレシプロ機の限界にまで進化していったのは基礎工業力の高さを現すものやな。
ポートダウィーンでの迎撃戦に敗れたと言うのは無数の空中戦での一つの事象に過ぎず、最終型のスピットファイアーは零戦より遥かな高性能機やったと思うねんな。
0さんの言われる、
オチョボクチ スピットファイヤ
私はしりませんでしたが、本にありました
イギリス空軍戦闘機
前期型と後期型があり
画像は後期型
ドイツが降伏したあと、太平洋戦争後期にイギリスは、政治的理由からイギリスは空母を太平洋戦線に投入し
零戦とスピットファイヤが空中をした とか、
スピットファイヤ後期型↓↓
0さんと権兵衛さんに、付いて行くには、専門紙がいりますね、
権兵衛さんの言われる
『ドックファイト』
私の本にはありません
教えて下さい、m(_ _)m
ドッグファイトとは文字通り闘犬の事で犬同士がお互いの尻を噛み付こうとする 闘い方で戦闘機の場合は、お互いの機が相手を捉えようと旋回して射撃点に付こうとする機動の事で
戦闘機に興味があったら誰でも知ってる 用語やな。
それと空母に搭載されて日本近海に飛来したスピットファイアーは、シーファイアーと呼ばれるタイプで、高々度を700キロで巡航可能なタイプとは異なり、空母への着艦と言うデリケートな操作が必要とされる為に運動性を重視したタイプやな。
このシーファイアーの飛行性能は零戦52型と均衡し、確か終戦当日の午前中の空中戦でシーファイアーと零戦隊が闘い、お互いに一機の損失を出したんとちゃうかったかいな。
権兵衛さん、ドックファイト知りませんでした、![]()
調べました↓
当時の、栄二一型発動機で飛行する、唯一無二の零戦五二型
米軍が民間に放出した戦時下の捕獲機を完全復元した、プレーンズオブフェイム航空博物館
大戦末期に米軍がサイパン島で捕獲、
非情にオリジナルに近い状態とはいえ、戦後30年近く放置されていたので8本の主柱 と 超々ジュラルミン、電送系、だけみたいで当時の栄二一型は発動機はほぼそのまま、
その鼓動は、70年以上を経ても、今なお健在、素晴らしい![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
↓↓
上記 零戦五二型コックピット
操縦席の造作はほぼオリジナルに忠実、
フットバーは英シーフューリー戦闘機の流用品
とあります、
漢字の数字が たまりませんね、![]()
二枚目の画像は防弾鋼鈑非装備のため 後方視界は良好 背もたれは肉抜き孔座席は大柄な米パイロットに合わせて約15㎝後退できるようにしてある
ノースアメリカンP-51Dムスタングが好きだという人は多く世界的にも第二次大戦の最優秀戦闘機といわれることが多い。
しかしP-51Dムスタングと対戦した敵国の戦闘機パイロットや本人は希望していないのに命令でP-51Dムスタングに無理矢理乗る羽目になった戦闘機パイロットたちの感想(作られた声ではない真実の声)を知ると話はかなり違って来る。
P-47サンダーボルトなどのP-51Dムスタング以外の戦闘機に比べると割と安価な費用でいろいろな用途をそつなくこなし最高速度が早く一応航続距離も長くすることが出来た点を評価したとするならば最優秀戦闘機の評価はピッタリと当て嵌まるということらしい。
つまりP-51Dムスタングという戦闘機は使う側の者(第一線で戦うパイロットたち)というよりは保有する側(軍、ひいては国)にとっての最優秀戦闘機であったというのが真実のようだ。
そこに輪をかけて民間に払い下げられた機体の数が多かったりエアレーサーに改造されて使われたりして人気が更に強化されたというのが正しいだろう。
意外にもP-51Dムスタングと対戦したドイツ軍でも日本軍でもP-51Dムスタングが特に強く優秀だったと語る戦闘機パイロットはほぼいない。
P-47サンダーボルトやその他の戦闘機の名を挙げて苦労したことを語る者が大半だという。
そして更に驚くことにアメリカ軍戦闘機パイロットはP-51Dムスタングに乗るよりは軒並みP-47サンダーボルトに乗りたがっていたらしい。
理由はいろいろなことをそつなくこなし最高速度は速く航続距離も長いが、飛行安定性が悪く挙動不審な動きをする癖があり機体強度が弱く後部燃料タンクに重大な欠点があり操縦の仕方を誤ると空中分解や操縦不能になる危険性をいつもはらんでおり、操縦上いろいろな制約が多くあった。
そういう理由でどの戦闘機パイロットたちも自分の命を預けるには不安感が強かったためだ。
地上攻撃機として使われることになったP-51(A-36アパッチ)が誕生したのは1940年と零戦より僅かに1年後なだけだがイギリスからの様々なアドバイスや技術協力により生まれ変わったP-51Dムスタングが誕生したのは第二次大戦も終わりに近付いた1944年になってからです。
この頃にはドイツ軍も日本軍もかなり軍事力が衰えていたためP-51Dムスタングが大量に撃墜される悲劇が避けられただけなのです。対戦する敵戦闘機がほとんどいなくなっていたためP-51Dムスタングは駅や民家、一般市民などに対して機銃掃射をしてまわり戦争犯罪といわれても言い逃れ出来ないような悪行の限りを尽くしていました。
このようにして機銃掃射された側の生き証人が昨年末ドキュメンタリー番組に出演されていました。
これが最優秀戦闘機と評価された戦闘機の正体でした。
画像は19年前、茨城県竜ヶ崎飛行場から飛び立ったプレーンズオブフェイム博物館の零戦五二型とP-51Dムスタングのデモンストレーション飛行の様子です。
低空で急旋回、2機共お互いにこのまま相手側に旋回して接近すれば飛行性能の違いから(零戦よりP-51Dムスタングの方が大回りになる)ションベン弾になる(遠心力により旋回円の外側へ放物線を描く)20mm機関弾であってもP-51Dムスタングがバラバラに撃墜されそうなポジションです。
でもこれはあくまでもデモンストレーション飛行です。
もう一枚の画像は同じくP-51Dムスタングの後方に付いた零戦五二型です。
これはおまけで貼ります。零戦が搭載していた武装の一つ
・九九式二号20粍機銃の作動の様子を示したGIFアニメーションファイル
・九九式二号20粍機銃各種使用弾と九九式一号20粍機銃弾の画像
です。(参考までに)
大戦中の最優秀機と評価されるムスタングP51も決してパーフェクトな機体では、無かった事が確かやな。
大航続距離を求められた為に燃料を過大に搭載し、これが起因となり落下タンクを装着した場合は機体の挙動が不安定になり常にトリムタブを調整しないと直進飛行が困難な事や、
エンジンの馬力に対し機体重量が重く、低高度域では零戦や特にメタノール噴射装置付きの隼3型などの機動に追従できない点などが挙げられるわな。
エンジンもロールスロイス製マーリンタイプをアメリカのパッカード社でライセンス生産されたけど当初はフォード社での生産が打診されたけど同社の技術陣が量産困難と判定した精密な構造やってんな。
パッカード製のマーリンエンジンは暫し原因不明のエンジンストールを発生し、このため硫黄島から日本本土への長距離飛行では撃墜した日本機よりもエンジントラブルが原因で未帰還となった機体の方が多いとも言われているんやな。
まぁ陸軍戦闘機隊の黒江少佐は捕獲したムスタングを自分の愛機のように乗っていたけど、その高速性と機体の装備や無線及び航法装置の充実ぶりに高い評価をしていたので高性能な機体であった事は確かやと思うな。
権兵衛さんこんにちは。
m(_ _)m
これは今から19年前にプレーンズオブフェイム博物館のP-51Dムスタングと零戦五二型が茨城県竜ヶ崎で飛行した際の映像のワンシーンです。
同時に離陸を開始、この映像の最後のあたりの両機の高度差には驚きでした。
この軽快さだけを指して高性能というのは言い過ぎかも知れませんが、離陸性能だけを見てもこれだけの性能差があるのは動かぬ事実ということでしょうね。
我々日本人の先人たちの技術的功績を見た思いがした映像です。
同時に離陸スタートして、ものの数秒でこの高度差、機体サイズから考えると既に数十メートルは高度差が出来ています。
零戦の舞い上がり易い機体性能以外にも低い着陸速度性能(低速でもバランスを崩さず失速せずにコントロール出来る操縦性能)から考えると極端な話このまま旋回して直ぐにでもP-51Dムスタングを機銃掃射出来そうな感じです。
この映像を見たことない人にとっては驚きだろうと思います。
私も初めて目にした時は驚きでした。
血の滲むような軽量化と捩り下げなどの匠の技の効果なのでしょうか。
ちなみに零戦で使われた沈頭鋲や捩り下げの技術は戦後のジェット機時代になってからは超音速旅客機コンコルドにも取り入れられており、もちろん最新の現代ジェット戦闘機にももう常識であると言わんばかりに使われているようです。
(戦闘機好きの人の間では既に良く知られていることですが)ノースアメリカンP-51ムスタングという名前を聞くとアメリカの代表選手的な戦闘機だと捉えられがちですが設計したのはアメリカに移住したエドガー・シュミュード(対ドイツ戦のさなかということでドイツ的なイメージを払拭したかったのでしょう本当はエドガー・シュミットです)というドイツ人でした。
アメリカに移住する前はドイツのメッサーシュミット社などで戦闘機設計に携わっていた人物でした。
そういう経緯で設計され、アメリカからの援英機の購入を増やしたいと考えていたイギリスからのアドバイスと技術協力ならびにロールスロイスのマーリンエンジンを得たことにより元々取り入れられていた急機動をよく行う戦闘機には不向きながら高速は出し易い層流翼の効果も合間って高い最高速度が出せる戦闘機となりました。
水滴型風防に変更したことで飛行安定性が更に不安定となったため垂直尾翼の前方にドーサルフィンを取り付けて安定性を補いました。
航続距離を長くするため大量の燃料を搭載出来るように作られていましたが後部燃料タンクの燃料が減っていない状態では急な機動は一切行えない、無理して行えば墜落の危険性があるという残念な戦闘機でもありました。
同じような型式で同じような姿をしていた日本陸軍三式戦闘機飛燕でも同様の現象がありましたが日本の場合は後部燃料タンクを使わないようにして取り外していました。
割り切り方の違いでしょうね。
総合して考えるとP-51Dムスタングとはスピード競争機としてなら向いているが戦闘機としては不向きな機体なのに無理矢理戦闘機として大量使用された飛行機であるといえます。
そして運よく大量に撃墜されることがなかったために最優秀戦闘機だなどという称号を頂いてしまった戦闘機だと思います。
それは乗っていたパイロットたちや敵のパイロットたちの感想が物語っています。
あまり良い評判がない。
龍ケ崎の航空ショーは、ワイも行ったけど5月やのに薄ら寒い日やったな。
印象に残ってるのは、良好な零戦の運動性で水平飛行から垂直上昇する機動にはシビレたがな。
一通りの飛行マニューバが終了して観客から質問する時間が設けられていたけど、その中で当時、零戦の整備員やった人の質問で「戦時中の零戦のエンジン音と比較して静かなようですが。」とあったけどその回答として、エンジンを保護する為に全開の六割しかパワーを使ってないとの事やたんやな。
実際に零戦52型から推力排気管になってバリバリと言う排気音がしたと搭乗員の手記に書かれているのに龍ケ崎で垣間見た零戦のそれは割と低めのように思えたんやな。
多分、全開で飛行した更に鋭い運動性を披露してくれると思うで。
ほんでやな最強のレシプロ戦闘機は制空性能のみを特化したグラマン社のベアキャットやろな。
一般的にヘルキャットは零戦を軽くノックアウトしたように思われているけどその実相は、熟練搭乗員が操縦する零戦は、かなり手強い存在感があったようで歴戦搭乗員達が数多いたラバウルでは、カタログデータでは零戦より遥かに優れているヘルキャットやコルセア、P38などの米戦闘機でも低中高度でのドッグファイトで絡まれて苦戦する様が米軍パイロットの手記からでも伺える事ができるねんな。
これは戦闘機は速度性能だけでは、絶対的なアドバンテージを得るのは困難な事を現してるんやな。 グラマン社にもたらされた戦闘機パイロットよりの戦訓がベアキャットの設計に反映され、完成された機体は空中戦で絶対的な優位を保つレシプロ最強の戦闘機やったと思うねんな。
ムスタングとの模擬空中でも圧倒的な高性能ぶりを発揮したそうやがな。
どの時代でも、どの戦争でも、同じ年に完成した戦闘機同士が戦うかといえばそうではないケースが実際の戦闘では往々にして多い。
理由はその時代時代の歴史や国々の御家事情に大きく左右されています。
それはそれとしてアンフェアでない正常対応な対比で考えると日本の海軍の艦上戦闘機とアメリカの海軍の艦上戦闘機を当て嵌めた場合はそれぞれ実機が完成し飛べるようになったのは
零戦が1939年
F4Fが1939年
紫電改が1942年
F6Fが1942年
烈風が1944年
F8Fが1944年
でした。
日本とアメリカの間で実際に行われた戦闘機同士の戦闘のほとんどは1939年生まれの歳老いた零戦と1942年生まれの若いF6Fヘルキャットというものでした。
戦争の時代にあって、いかにアメリカが資源も技術も持ち裕福であったか、一方日本がいかに貧しく貧しいながらも大国に食い下がったかが良く判る図式です。
アメリカとの戦争の結果からいえる事実は零戦とF4Fワイルドキャットとの戦いでは日本の圧勝でした。
しかしその後、日本も紫電改、烈風と零戦の後継機となる戦闘機を何とか開発するところまでは出来たのですが戦いに使えるだけの状態まで数を揃えることに失敗したためアメリカの新型戦闘機と零戦が戦い続けなければならない捩れ現象が発生してしまいました。
要は初戦の戦争に圧勝していた当時の日本人も素晴らしかったが問題点は戦争継続能力が足りずアメリカ合衆国と戦争すること自体に無理があり過ぎたということでしょう。
その先どう収めるかという構想もハッキリしない戦争に踏み切ってはいけないということでしょう。
国の舵取りをする政治家の皆さんはシッカリと頭に焼き付けておかなくてはならない事柄です。
0さん、権兵衛さん、全部読ませて頂きました、0さんムービーありがとうm(__)mです
素晴らしい![]()
権兵衛さん、さすがです、
ここで
『永遠の0』の著者
百田尚樹 ベストセラー誌から、抜粋です↓↓
何故零戦は日本人の魂を揺さぶるのか?
零戦は日本の文化 あるいは考え方を象徴していますと言うのは、名人が造った戦闘機、名人が設計して名人の職工がつくり、
なおかつ、それを乗りこなすのは、名人パイロット、
たとえば、零戦のライバルと言われる、アメリカの
グラマンなんか、プラモデルみてもわかるんですけど、不細工でしょう、
まぁ美意識の問題も多少ありつつ、
日本の零戦と比較すると
よく言われるのは、
零戦は直線が無い ということ、どこを見ても直線が無く 凄く美しい若干のカーブで仕上げています
しかしカーブは飛行機をつくる場合にはかなり厄介です、
鉄板を切るのにも 直線に切るのは簡単ですが
カーブを切るには技術がいります、相当腕のいい職人じゃないと、アールを綺麗に切れない、
零戦の翼を見てください
本当に美しいカーブです
所が、グラマンなんかは直線ばかりでアメリカは、つくり安さを考えているんです、理想的なカーブを描くほど性能はいいのは、解っているけど、その為には一流の職工がいると、直線の方が早く出来るだろう工場単位で考えると より性能の良いカーブを使って、1ヶ月に1000機出来るのと、
もっと簡単に直線を使って1500機 できるんだったら多少性能や 見かけ が落ちても、数が多い方が戦争には勝てる、のではないか、というのが、アメリカさんの考え方、なおかつそういう作り方だったら、一流の職工じゃなくても
普通の職工でも出来るのじゃないか、と
じゃ日本の考え方といえばつねに際高級品のものを
つくろうという考え方なんです、設計者も職工も一流の方を集めて時間をかけてでも作り上げる、
そんな風に造った飛行機ですから、それに乗るのも一流となるし、その零戦に憧れて零戦パイロットになろうとするわけです
零戦は、日本人の国民性が現れています、だから飛行機の性能はグラマンより上、でも 1機に対するコストパホォーマンスを考えた場合
はたして零戦の方が上かどうか、
お値段はと言うと本体価格のみで零戦二一型(三菱製)が約55000円(生産開始当初は約82100円)、中島製で約69000円。エンジンや搭載兵器などのオプションを含めると三菱製が約149787円、中島製が約163787円だったそうです。
勿論これは量産当時の価格なので2007年の価格価値との差で言えば当時の1789倍にもなるようです。
これに基づき換算すると三菱製零戦は約2億7000万円。
当時の軍用機同士で比較すると零戦の前身である九六式艦戦が約84331円。
九九式艦爆が約168950円。アメリカのノースアメリカンP-51ムスタングが約230405円。
4発重爆撃機ボーイングB-29スーパーフォートレスが約2726458円だったそうです。
単純に比較は出来ませんが開発時期は違っても実際に戦闘を交えた戦闘機同士で考えると零戦とP-51、その国家が1機の戦闘機に投入出来た金額の差、アメリカと日本 彼我の裕福さの違いを実感する気持ちになります。
参考までに2007年時点で現在航空自衛隊の主力戦闘機ボーイングF-15イーグルが1機120億円、アメリカの最新鋭ステルス戦闘機F-22ラプターは1機141億円だそうです。
注)2007年時点での換算資料しか持ち合わせていなくて済みません。
それからF6Fヘルキャットの価格についても判りませんでした。
申し訳ありません。
m(_ _)m
只、これらの事実からいえることは戦時中の日本製軍用機は総じてアメリカ製軍用機より遥かに低価格であったということがいえます。
お金の損得でいえば高価なアメリカ製軍用機が日本製軍用機に戦いで勝っても当たり前であり、逆に低価格の日本製軍用機に戦いで負けた場合はアメリカは大損だったということでしょう。
日本製になると高価になってしまう今の日本製軍用機とは全く逆転現象です。
一部間違えました。
ごめんなさい。m(_ _)m
アメリカの最新ステルス戦闘機F-22ラプターの価格は141億円ではなく、241億円でした。
おそらく現在世界一高価な戦闘機がF-22ラプターだと思います。
アメリカ製と日本製の兵器価格の差は当時のアメリカと日本の通貨価値の差だと思います。
太平洋戦争開戦当時のアメリカ合衆国と日本の国力(各種生産能力を含む総合的な国の力)の差は少なくとも20対1以上ありました。
国力の差イコール通貨交換の価値の差といえるでしょう。
人件費も日本人の方が遥かに低賃金だったということになります。
零戦が開発された経緯の一つとして長距離進攻作戦に従事する為の性能要項と言われてるけど実際は、艦隊上空を6時間以上に渡り哨戒し、襲来する敵攻撃機を撃破するもので20ミリ機銃装備もそれに合致した指示やってんな。
つまり空母に搭載するための戦闘機で当初は千機程度の生産と見積もられていた為、コストの高い大型金型を用いる事なく熟練工員達による
手作業に近い工法で
工芸品のように製作されていたんやな。
各工程の要所には神業級の技術を持った職工が腕前を発揮しそれに倣うように熟練工員が従事しとった訳やな。
アメリカと比べあらゆる根幹となる基礎工業力が劣る日本では洗練された設計により、複雑なアールを描こうとも鋭い空力特性を追及するのが必須やったんやろな。
アメリカの航空技術を急速に吸収していった日本の技術者達はアメリカの底力を熟知し、自ずと身を削るような創意工夫
の後に誕生したのが零戦なんや。
余談ながら零戦はレイセンと呼ぶのが正しいとする向きもあるけど、海軍では普通にゼロセンと呼ばれていたんやな。
これは戦前でも一般的に0をゼロと言うのが普通やったからやねんな。
零戦のエンジンを起動する時の掛け声は英語が用いられてるし、英海軍をお手本とする海軍自体が英語を多用しとったんやな。
せやから零戦を正しくはレイセンと呼ぶんやと言うのは、エセマニアっ言うこっちゃな。
まぁ一時期にせよ米戦闘機を凌駕した大空の王者零戦は、老いたり言え質量共に優勢な敵機に善戦を重ねたその勇姿の滅びの美学に琴線が触れるかも知らんな。
しかし滅びの美学で終わらんかったんが零戦の零戦たる所以なんや。
零戦開発に従事した技術者や関連会社が戦後、失われた大切な珠玉を取り戻すかのように日本の復興に尽力し、技術立国として今に至る訳や。
0さん、明らかに国力の差ですね、
権兵衛さん、零戦は素晴らしい工芸品、ですね
ここで、零戦とは関係ありませんが、以前![]() の軍カテゴリーで投稿しましたが
の軍カテゴリーで投稿しましたが
再度
画像は国産の『九四式自動拳銃』です、
他国の自動拳銃ガバメントやワルサーも良いけれど、私は なんといっても、心が奪われます、
見た目はカッコ悪いと思うかもしれませんが
我々日本人の心にジーンと訴えかける、何かを持っている拳銃だと、私は思います、
この銃が開発されたのは、1934年(昭和9年)ということですが、34式という名称にはせず、
皇紀2594年からとった、94式にしたところなんかはさすが日本人です、
また銃左側に『式四九』安全装置に『火![]() 安』と刻印されているのがたまりませんね
安』と刻印されているのがたまりませんね
現在 アメリカのヴィンテージガンショップでは
かなり高値で展示してあるそうです
ヘルシア、0の両氏による零戦談議にワイも引き込まるようにしゃしゃり出たけどなかなか興味尽きることは無い感じやな。
ところで日本軍の小型拳銃の事やけど、サンディエゴ軍港の近くにミリタリーショップがあるんやけど広大な敷地の中に航空機の部品や機体等が野外に置かれ、そこの建物の一角に機関銃や多種に及ぶ火器が展示されてあり日本軍のコーナーも設けられ、38式歩兵銃や南部14式拳銃が飾ってあったけど、親父さんの代からミリタリーショップを経営してるとのオーナーの話しの中で、昔は日本軍の銃器や軍用品は大量に在庫があって価格も非常に安かったそやけど当然、供給が無いので価格が急に上昇しているとの事やったなぁ。
発射機能の損なわれた南部14式があって真剣に購入を検討したけど機能が損なわた状態でも実銃を日本に持ち込むのは、繁雑な手続きが必要
で諦めた事があったんやな。
後はドイツ軍のコーナーには新品のワルサーP38が重厚な宝石箱のような木の箱に入った状態で飾られてあり、功績を上げた将兵への戦功品らしいけどオーナーが気に入って非売品との事やったなぁ。
ワイの拙い英語に身振り手振りで受け答えしてくれたオーナーに好感を覚えたので、ドイツ軍のヘルメットや勲章やハーケンクロイツの旗とかを購入したらSSの刻印が入ったスプーンをオマケに貰ったけど、あの商売上手のオーナーは元気にしとるやろか。
ほな銃器の話が出たところで零戦の機銃に付いてウンチクを言うたろかいな。日本海軍が選定、採用したエリコン20ミリ銃に対しての批判は著名な零戦搭乗員 であった坂井三郎氏による発言が影響しとる訳やな。
低伸弾道で60発の弾丸しか搭載できない20ミリ機銃は戦闘機用としては欠陥品扱いに近い旨の発言が見られたけど、海軍戦闘機の主要兵器として順次、改良されて行き、二号艦戦、則ち零戦32型に搭載された二号20ミリ銃は現地部隊より破壊力大と評価され、より高速化した零戦32型と共にその部隊配備を切望されていたんやな。
防弾強固な米軍機に対しては炸裂弾の装備された20ミリ銃が最適だと思われ又、零戦の開発目的は巷で言われような長距離進攻用では無く実際は艦隊上空を長時間、哨戒及び来襲敵機を迎撃する旨で開発されたのは前回で説明したけど、その要項には高速化した敵攻撃機には破壊力の大なる20ミリ銃を持って要撃するとああったんやな。これは先見の目があり、大戦後半の特攻作戦で防弾装備された特攻機への迎撃で米軍装備の12.7ミリ銃では有効弾を与えてもそのまま突撃するので威力不足が報告されいたんやな。
一方、本家のエリコン社でも実現、出来なかったベルト給弾化を実用化した日本海軍は20ミリ銃を有効な兵器と認識していたので逐次、改良を加え優秀な航空機関銃として育成、正常進化させたんや。
台南空やラバウル基地の専任搭乗員(士官以下の搭乗員の長)であった坂井三郎はガダルカナル進攻作戦で片目失明の重傷を負いながらも辛うじてラバウル基地に帰投したその不屈の精神力は評価に値するも、それ以降の激化する米軍機との死闘は経験しておらず内地で入院加療中の間に零戦は32型、22型、52型と移行しそのつど戦闘力を強化して行ったけど、退院後に再び搭乗員として復帰し零戦52型を操縦した時の所見では、運動性が低下し零戦本来の戦闘力が損なわれたとの事やったんやな。
しかし空戦の実相は高性能化する米軍機に対し21型では抗し難く早期に二号20ミリ機銃搭載の52型の部隊配備を切望するとの意見が部隊から出てたんや。
その後、雷電や紫電改に搭載された99式二号20ミリ機銃は逐次改良を加えられエリコン式では日本海軍だけが実現させたベルト給弾により一門、250発の搭載が可能となり防弾強固な米重爆にとっても、炸裂弾装備の20ミリ4門の射線は脅威そのものやったんや。
ほんでや米軍機の標準装備であるブローニング12.7ミリ機銃は、これまた陸軍から艦艇まで多用に採用された傑作品とも言える機銃でエリコン20ミリ機銃と共に原形誕生から100年近く経つの逐次改良に改良を加え、未だ現役と言う優れものやな。
ブローニング機銃は旋回のGで装弾不良になる事が頻繁に発生する事やエリコン機銃に比較すると重量が重いという点もあったけど、良好な直進弾動性と発射速度の点が優勢で日本機のそれより優れた照準器の装備と相まって防弾性の低い日本機にとっては恐るべき兵器やった訳やな。
まぁブローニング機銃とエリコン機銃は敵味方の双方で多用された一つを見ても歴史的な名機銃という感じやな。
権兵衛さん、![]()
私も三度アメリカに行きました、
国民が拳銃やライフルを持てる国です、
必ずコンビニねレジーの横には、拳銃が忍ばせてある国で、恐ろしい国です、
坂井三郎
『大空のサムライ』
ガダルカナル上空で被弾したあと、1000キロ決死の飛行機
戦後、1987年訪米
ワシントン州航空ショーで、71歳の零戦パイロット坂井三郎が 見事なスタントをやったと関係者を驚かせた、とか
坂井三郎画像二枚と
最後の画像は 極東空軍だったフランクカーツ大佐、 零戦に乗った坂井が、B17を撃墜する様子を目撃した、とあります
ヘルシアさん、権兵衛さん、おはようございます。
m(_ _)m
坂井三郎氏はガダルカナル戦でアメリカ海軍のダグラスSBDドーントレス艦上爆撃機の8機編隊に近付き過ぎて、気付けば後方50mの範囲内に入ってしまったため合計16丁の7.62m旋回機銃の猛烈な銃撃を受けて右ゴーグルから入った銃弾が頭部を掠め重傷を負い右目の視力を失ったそうですね。
出血もひどく手足の麻痺もあったそうですから、よくそんな状態で生きて還れたものだと驚きます。
画像は7.62m後方旋回連装機銃を備えたダグラスSBDドーントレス艦上爆撃機です。
まぁ銃器に興味のあるワイでも市民が護衛の為に拳銃等を所持する国は、衰退の一途を辿ると思うな。
アメリカ文化が好きなワイにとっては、
ホビーとしての銃器が数多くある状況とそれゆえに市民が犯罪の犠牲になるという二律背反的な事象は、決して好ましいとは思わんねんな。
ほんでやな坂井三郎中尉は、海軍戦闘機搭乗員になるべく戦艦勤務の水兵から航空兵を目指した努力な人で、その人間性や理不尽な出来事を甘受しない一途な性格に日本人としての矜持を感じる事ができて、数多くの著書を熟読したものや。
敵兵にも哀れみをかけ、特筆すべきは作戦行動中に遭遇した敵輸送機を見方基地に強制着陸か従わなければ撃墜かの措置を取るべく、その輸送機に接近したところ窓越しに婦人と五歳位の女の子が怯えた表情でこちらを見ているのを確認し、中学時代の英語の先生であった女性教師を思い出して即座に輸送機の機長に行きなさいと指示をして見逃した事例があって、本人曰く軍人とした失格であったけどその時だけは軍紀より人間性を優勢したとの事やってんな。
坂井中尉は、零戦21型が最も優勢を誇った頃のガタルカナル進攻初日に戦傷のため戦列を離れ、それ以降の米軍が新型戦闘機を逐次投入し零戦の優位を脅かす戦況は経験しておらず、零戦21型以降の各タイプの零戦やその武装に付いてての所見は、かなり割り引いて聞かんと零戦とその戦闘方の実相を見誤る場合があるねんな。
また復帰後、紫電改部隊に若年搭乗員の指南役で配属されたけど米軍機との死闘に生き残った歴戦搭乗員との間で意見の食い違いが生じて、煙たがられていた事も確かやってんな。
20ミリ四門を装備した紫電改そのものも
をエンジンの管制が難しく米軍機に対する戦闘力は零戦に及ばない旨の発言をしていたんやな。
しかし史実は、二機の零戦に対し紫電改単機をもって優位に立てる高性能な機体やな。
つまり零戦21型が絶対優位の状況から次第に米軍機が高性能化する戦況の変化を命を的に感じ取り、戦闘方に反映しなければいけない大事な時に戦列を離れた為、新しい空戦方の体系に追従できんかったんやろな。
中支戦線で活躍した歴戦搭乗員が教員時代を経て南方の最前線に配属され米軍機との緒戦で未帰還になる場合が多々あった事がこの事を物語っているわな。
しかし不撓不屈の精神力と戦闘機搭乗員としての矜持には感銘を覚える事があるねんやな。
0さん、権兵衛さん、こんばんは![]()
![]()
![]()
このいつもチャンネルで、
戦闘機の知識人に会って 大変貴重な体験しています、あらためて御礼を申し上げます、
また、そんなに零戦に知識がない私は、
携帯サイトをたまたま見て 投稿しましたが、
こんなに奥が深いとは…。二人に影響されて、とうとう零戦の専門紙を買ってしまいました、
坂井三郎は 権兵衛さんのおっしゃるとうり
帰投後 上官の笹井に対し『敵機を追捕せんとするも雲中に見失えり』
明らかな背命行為 軍率違反で、重罪ですね
坂井三郎は固く沈黙を守ったとか、
戦後もこれについては固く沈黙した、
終戦から半世紀たって、考えを改め、ある講演会で告白した、
すると思いもよらない事起きていた、
ちょうど同じ頃、機内で娘を抱き締めていた、元看護婦の母親が、私達を見逃してくれた日本の搭乗員に会いたい、と
赤十字などを通じて坂井を照会していたそうで、
こうして坂井と彼女は奇跡な再会を遂げて互いの無事を喜びあった
と本にありました、
坂井三郎は時には軍規を破っても、守る何か
正に大空のサムライですね、
余談ですが、![]() の歴史カテゴリーで、私が万次郎ハンネで投稿している時に、
の歴史カテゴリーで、私が万次郎ハンネで投稿している時に、
私を擁護して頂き、大好きな方で
その方のハンネは「下石」さん でした、
雰囲気が何となく、権兵衛さんに似ています![]()
まちがってたらごめんなさい、
ワイは軍カテにしかしゃしゃり出てないので違う人やな。
まぁ零戦を問わず軍事技術が戦後の優れた民生品を生みだす礎になり、その技術の系譜は21世紀の今に至り脈々と続いてるねんな。
50年以上前に各国の鉄道技術者達は200キロの巡航速度は振動問題で不可能とされていたけど、これに挑み新幹線を誕生させた技術者もかっては零戦の振動問題、則ち主翼フラッターを学術的に解明した功績のある人やな。
航空後進国の日本にあって零戦を開発した設計した設計陣と
それを形作った技術 達、そして零戦で駆け巡った大空の若武者達…。我々日本人の中にこれらの研ぎ澄ますた優秀なDNAが流れていると思う時、零戦を見ると何故か誇らしさを覚えるんやな。
権兵衛さん、私の勘違いで失礼しました![]()
戦後半世紀以上たった現在の 我が国の発展は
零戦の技術者達の発想が脈々と引き継がれ、
コンニチに至るわけですね、
私は小学生のころ、
アメリカは 自動車の生産国としては、世界一と
習いました、
「零戦燃ゆ」の映画でもあったように、「自動車も、まともに造れん日本が我々より航続距離の長い戦闘機などあり得ん![]() 、空母が必ず近海にいるに違いない」
、空母が必ず近海にいるに違いない」
とマッカーサーが言っていたのを思い出します、
こんにちは(゚▽゚)/
当時、飛ぶ鳥を落とす勢いといわれた旧大日本帝國海軍台南航空隊零戦パイロットたちの記念写真をカラー化したものを貼ります。
零戦のエースパイロットとして有名な坂井氏、東洋のリヒトホーフェンとも呼ばれた笹井氏も写っていますし、バックには零戦も写っています。
アメリカ軍、イギリス軍戦闘機なんぞ何のその、向かうところ敵無しだった時代の写真。
0さん、いつも貴重な画像ありがとうm(__)mです
台南航空隊、
勇ましいですね、
零戦が最強であった頃の誇らしげな一葉やな。
この頃の零戦は、作りが丁寧で外板の歪み等が一切なくツルツルしていたそやな。 エンジンの稼動率も非常に高く、最初の30分が調子良ければ後は、燃料が切れるまで絶好調やったそや。
後半の52型は戦闘力が向上したけどエンジンの稼動率が低下し、機体の作りも若干、荒くなったのが
21型に慣れ親しんだ搭乗員が違和感を覚えたかもな。
写真は二列目の右から二人目が吉田一報道班員でこの時は飛行服を借りてカメラに収まりセルフタイマーで撮ったそや。
お二人とも、ご存知だと思いますが
第二次大戦、終りごろ
ドイツの戦闘機、
メッサーシュミット製
プロペラ機ではなく、ジェットエンジン、の
「ME・262」が あったそうです、
デスカバリチャンネル で昨日放送されました、
↓↓
最高速度870キロだそうです、
MK108機関砲 4門
世界初実用ジェット戦闘機です、ハィ、![]()
当時のムスタングより
200キロ速いそうです
Me262は、レシプロ戦闘機の速度性能が限界点に達しつつあった時に次世代の戦闘機として実戦配備された機体やな。
エンジンの信頼性が低く、フレームアウト(エンジン停止)により墜落事故が多発したけど、その速度性能ゆえにベテランパイロットが操縦するMe262は、あらゆる敵戦闘機を凌駕する戦闘力を誇ったんやな。
惜しむらくは、部隊配備された頃にはドイツの制空権は連合軍に握られ、一千機に及ぶ戦爆連合の空襲の前には数十機に満たないMe262では、戦局を挽回する事は出来んかったんやな。
ジエットエンジンは基本的に低質燃料(灯油)を用いるので高オクタン価の燃料が精製できなかったドイツにとっては好都合の動力やったんや。
さすが 権兵衛さん、
ジェット戦闘機の燃料が 安価な灯油 だとは知りませんでした、![]()
下のムービーは、デスカバリチャンネルが、
戦後に撮影した
米海軍 グラマン社
F4Fワイルドキャットと
零戦の性能を比較したムービー です
つづきです、
坂井三郎が出て来ます
ヘルシアさん、権兵衛さん、おはようございます。
(゚▽゚)/
自衛隊の航空祭などに行くとジェット戦闘機などがアクロバット飛行している中、石油ストーブのような匂いが終始漂っています。
現在のジェット戦闘機でも使用している燃料は白灯油系の燃料のようです。
世界初の実用ジェット戦闘機といわれるメッサーシュミットMe262ですが、実はこれより若干早く初飛行を終えていたハインケルHe280が世界初の実用ジェット戦闘機だったという話があります。
但し、ヴィリー・メッサーシュミット博士がナチス党員であったのに対してエルンスト・ハインケル博士はナチス党員ではなかったためにナチスドイツの政治的思惑が大きく働いてハインケルHe280は採用されることがなかったといわれています。
似たようなハインケル社への冷遇は他にも多数あったため話の真実味はかなり高いと思われます。
まぁ、そのようなナチスドイツ政府御用達みたいな経緯があり採用されたメッサーシュミットMe262でしたが、ヒトラー総統は昔から戦闘機より爆撃機を好み、折しも連合軍爆撃機によりドイツ本土が爆撃されていることに対する復讐心も強く作用し生産されるメッサーシュミットMe262は戦闘機としてではなく爆撃用戦闘機として完成させ対連合軍用の爆撃に使うようにと厳命されていました。
高速性能が一番の売りだったメッサーシュミットMe262は戦闘機として使うのが最良の策でしたが、遅れ馳せながら戦闘機として使用方法を転換した時には既に時遅し、でした。
さらにつづきです
↓↓
メッサーシュミットMe262の先進的技術としてユンカース社製Jumo004軸流式ジェットエンジン以外にも翼の後退角がありましたが、戦後も後々になって判ったこととして大きなJumo004軸流式ジェットエンジンを搭載することになった関係で機体のバランスが大きく変動したためバランスを取り直す目的から翼を後退させていたことが関係者の証言から判っています。
それは最初の試作機の翼を見るとほとんど後退角の付いていないものが使われていた事実とも合致します。
いずれにせよヒトラー総統よりも戦闘機や航空戦のことを熟知していた戦闘機隊総監のアドルフ・ガーラントがメッサーシュミットMe262は戦闘機として使ってこそ意味があると進言したにもかかわらずヒトラー総統の考えは変わらず認められることはなく、ほとんどが爆撃用として使われたことがメッサーシュミットMe26の本当の能力発揮に対する最大の障害でした。
気付けば↑メッサーシュミットMe26になっていました。
最後の2が抜けてました。
ごめんなさい。m(_ _)m
正しくはメッサーシュミットMe262です。
ちなみにメッサーシュミットMe262が搭載していたのはユンカース社製Jumo004軸流式ジェットエンジン。
ハインケルHe280が搭載していたのはハインケル・ヒルト社製HeS08遠心式ジェットエンジン。
イギリス、アメリカが同時代に開発中だったのは遠心式ジェットエンジン。
現代のジェットエンジンの主流は軸流式ジェットエンジンです。
戦後の世界(アメリカ、イギリス、ソ連)の翼の後退角技術やジェットエンジン技術のほとんどは戦利品としてドイツから奪った技術をもとにしていることは言うまでもない事実です。
零戦のエースパイロットだった坂井三郎氏は戦闘機パイロットとしては敵より高い位置に居ることと太陽を背にした位置に居ることと敵より先に相手を発見することが何より大事だと語っていました。
これらが揃っていれば先制攻撃がかけ易い。
先制攻撃が出来れば勝てる確率が格段に上がる。
始めの二つは環境に応じて変化するが自分なりに準備しておけることとして視力を鍛えておくことを上げられていました。
地上での休憩中も昼間の空に星を見付ける努力を常に欠かさないようにして視力を鍛え上げていたと語られていました。
現代の戦闘機パイロットも視力が良いことは必須条件のようですが、戦後の戦闘機はジェットエンジンやレーダーやミサイルの技術革新により紆余曲折があり一時は戦闘機不要論が出たり格闘能力の必要性の再認識があったりしていますが、実状では戦闘機同士の格闘戦が起きる可能性は低く、いかにして先に敵を発見し先に攻撃するかが最重要視されている現状です。
周辺機器の技術革新の進んだ現状、戦闘機パイロットに必要不可欠だった先に敵を発見するための高い視力は現代のレーダー技術の能力に置き換えられているといえます。
戦闘機パイロットとしての身体能力の高さは今も必要とされますが、勝敗のほとんどの鍵はレーダー技術に代表される戦闘機周辺機器技術の能力差がその国の戦闘機の強さの差となって現れる時代でしょうね。
そういう事実を念頭に考えると機動性をやたらとアピールしているロシア製や中国製の戦闘機は勘違いも甚だしい気がします。
格闘戦をする遥か前の段階で勝敗は決まってしまう時代なのにね。って気がします。
戦後も生き残ったアメリカ軍のリパブリックP-47サンダーボルト戦闘機のエースパイロット(撃墜数31機)フランシス・スタンレー・ガブレスキー中佐の画像を貼ります。
彼は外の様子以外にコクピット内のいろいろな機器類の警報や表示に常に細心の注意をはらっていなければならない(一つでも見逃していたら撃墜されかねない)現代のジェット戦闘機に乗って戦えといわれたら迷わず断りたい。と戦後のインタビューに答えていました。
私も同感だと思いました。
第二次大戦辺りまでのプロペラ機による戦いが「人間が人間らしく人間の能力を最大限に活かして戦い合える限界だった」ような気がします。
現代技術の戦闘機を見ているともう人間の能力を超えている気がします。
人間が乗っていること自体が戦闘機の能力を制約する足枷にすらなっているかのようです。
そんな現代戦闘機には乗るのは嫌だというガブレスキー氏の発言には実感がこもっていると思います。
0さん、素晴らしい![]()
0さんの言われる
↓↓
「第二次大戦辺りまでのプロペラ機による戦いが「人間が人間らしく人間の能力を最大限に活かして戦い合える限界だった」
正にションベン弾ではなく
ミサイル弾、になってしまいました、
フライングヘリテイジコレクションの改造複座零戦二二型です。
第251海軍航空隊の応急迷彩塗装を施してあります。
リバースエンジニアリングという復元手法で復元された零戦二二型の二号機になります。
操縦出来ない人でもこの零戦で後部座席に体験搭乗飛行させてくれたらみんな喜ぶことでしょう。
そんなサービスしてくれないかな(^O^)/
普通の単座の零戦二二型の一機が一号機で↑この複座零戦二二型が二号機で、もう一機の単座零戦二二型が三号機だったと思います。
オリジナルの栄エンジンはさすがに無理なのでプラット&ホイットニーR-1830ダブルワスプエンジンを搭載し外板は若干厚くしてあり強度を上げてあるらしいです。
↑一部間違えてしまいました。
ダブルワスプではなくツインワスプでした。
ごめんなさい。
m(_ _)m
0さん![]() 、画像ありがとうm(__)mです、
、画像ありがとうm(__)mです、
ツインスワプ←意味を教えて下さい、
毎回すみません![]()
![]()
![]()
今もなお、日本に現存する零戦、11機
河口湖自動車博物館、飛行機、
零戦3機
国立科学博物館、東京都
靖国神社 東京都
大刀洗平和記念館
三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所資料室
海上自衛隊鹿屋航空基地資料館
呉市海事歴史科学館大和ミュージアム
航空自衛隊浜松広報館
エアパーク
知覧特攻平和会館
画像が貼れてないのが
あります、すみません
河口湖自動車博物館、飛行機、
零戦3機
国立科学博物館、東京都
靖国神社 東京都
大刀洗平和記念館
三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所資料室
海上自衛隊鹿屋航空基地資料館
私もそんなに詳しいわけではありませんが…
プラット&ホイットニーの最初のエンジンがワスプ(スズメバチの意味)と名付けられていて、その改良型がツインワスプと名付けられているようです。
たぶん、最初は単なる空冷星型エンジンだったものを高出力化するにあたり空冷二重星型エンジンにしたために名付けられた名前だと思います。
貼り直し![]()
三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所資料室
海上自衛隊鹿屋航空基地資料館
また1枚貼れてませんでした、
三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所資料室
↓↓
0さん、ありがとうございます、
「空冷二重星型エンジン」ですね![]()
だいぶ遅くなりました
おやすみなさい![]()
135に貼った改造複座零戦二二型の兄弟機、三号機にあたる普通の単座零戦二二型のオーナーは日本人であるという話があり、近々日本への里帰り飛行が計画されているという話があります。
それからオレゴン州エバーグリーン航空宇宙博物館はマーシャル諸島タロア島で回収した零戦4機分の残骸を元にしてリバースエンジニアリング技法を使って飛行可能な零戦三二型を完成させる予定らしいです。
しかも再生したオリジナル栄二一型エンジンを搭載した機体だそうです。(このオリジナル栄二一型エンジンも回収した複数基から作り上げるようです。)
早ければ2015年の春から夏頃には…という話。
2001年から始まったというこの計画、現在はワシントン州のレジェンドフライヤー社で組み立て作業が進行中のようです。
では![]()
お休みなさい。
ガラ携で
ダコタブレイド社製零戦二一型と入力して検索し、Googleモバイルでそのまま検索を続けると、この「いつもちゃんねる」のこのスレが出て来ますね。
ある意味では凄いね。
>>152さん、深いレスに訪問ありがとうm(__)mです、
いつもチャンネル、かなり宣伝してますね、
あと1年ほどすると、![]() のようになるかもデス、
のようになるかもデス、
今映画で「永遠の0」が上映されてるみたいです私はDvDが出るまで待ちます、
永遠の0は、映画館で見たらアカンど。
ワイの嫁はんは、零戦には全く興味は無いけど、V6のファンやから岡田准一が主演と言うことで、一緒に映画館に足を運んだんや。
零戦の飛行シーンに迫力ある臨場感を感じたけど、それより更なるは、主人公、宮部久蔵の死生観や家族愛、戦友愛などが混然一体となり感無量の境地になって泣けて来るがな。
嫁はんもハンカチで目頭を押さえとったし、周りの人も泣いとったがな。
人前で涙を流すのが嫌なモンはDVDで一人で観賞せなアカンねん。
ほんでやな以前、河口湖の飛行館で零戦21型を見学したけど、実際に稼動する栄エンジンを搭載し、神々しいオーラを放つその機体に魅入られるように時間を忘れて立ち尽くしとったがな。
ちまたでは永遠の0が映画上映中ですが私もDVD販売待ち派です。
実際に飛行可能な零戦自体は希少なものです。
そしてその中にあって更に更に希少な存在になりそうなのがオリジナル栄二一型エンジンを搭載して飛行可能状態にしようと計画されている零戦三二型です。
今現在は飛行可能な零戦三二型は世界中どこを探しても一機も存在していませんからね。
(零戦三二型…栄二一型エンジンに換装し動力性能向上を狙い、主翼端を切り主翼を短くして横転性能と高速性能の向上を狙った型。当時のアメリカ軍は他の型の零戦とはまるで別機種だと思い込んでゼロ/ジークとは違うハンプという別の名称で呼んでいました。)
期待が高まります。
ロシアに送って再生した零戦二二型一号機/二号機/三号機の写真
零戦三二型のカラー化写真
アメリカ軍による飛行テスト中の零戦三二型写真
を貼ります。
零戦三二型は日本や世界中に保存展示されている零戦の中でも数が少なく元々希少。
新しい型のエンジンに換装し主翼を短くしたことにより速力、上昇力、加速性能、横転性能は確かに向上したのですが、その代償として航続距離が短くなり旋回性能が若干低下したため、これを嫌うパイロットも居たそうです。
しかし、他方ではこの零戦三二型の性能の方が良いとして好むパイロットも居たそうですからそこは乗るパイロットの好みの差というか使い方、戦い方の選択の違いなのだと思われます。
敵対していた当時のアメリカ軍戦闘機は軒並み重戦的性格に作られた戦闘機ばかりでしたから軽戦的性格(横の戦闘に強い戦闘機)を好むのか?重戦的性格(縦の戦闘に強い戦闘機)を好むのか?次第で大きく評価が分かれるところです。
当時の日本の戦闘機のものづくりとしての考え方は先ず第一は小回りの利く機動性能ありきでその他の性能項目は二番目以降にされていました。
そのため不思議な話ではありますが当時の軍が審査する際は戦闘機とは全く違う別の用途に使う軍用機でも何故か小回りの利きはどうかというところまで評価の対象とされていました。
そのようにして作られていた日本製戦闘機は横の戦闘に強いため外国製戦闘機と対戦した場合に空中戦を行うと勝つのがほとんどでした。
太平洋戦争の前半戦で外国製戦闘機がバタバタと落とされまくったのはこれが理由でした。
しかし後半戦になると外国製戦闘機は横の戦闘には巻き込まれないように避けて縦の戦闘を仕掛けて来るように全面転換して来たため形勢が逆転し日本は負け戦に転じることになりました。
横の戦闘とは巴戦でありドッグファイトであり俗にいわれる空中戦のこと。
縦の戦闘とは一撃離脱戦法でありロッテ戦法もサッチ・ウィーブ戦法も基本的には一撃離脱戦法の一種。
要は太平洋戦争後半戦アメリカ軍戦闘機は空中戦をしなくなり、上空から勢い付けて高速で迫り撃っては逃げ撃っては逃げを繰り返す戦い方に大転換したというのが事実でした。
日本の当時の戦闘機パイロットの間では昔からの巴戦の性能を重視する人たちが大多数ではありましたが実際に対峙した敵国の戦闘機パイロットの戦い方を目の当たりにして一撃離脱戦法に適した戦闘機が良いと考える者や一撃離脱戦法にも適し巴戦にも適した戦闘機が良いと考える者など昔ながらの戦法だけにとらわれずいろいろと主張する者が現れていたのは確かでした。
それでもその頃にはそれらに十分に応えてやるだけの余裕が日本にはなくなっていました。
そういう苦しい戦局の中にあって計画、開発、生産をする側も只々、手をこまねいていたわけではなく予定は遅れつつも新型戦闘機を作る努力は続けられていました。
そうして陸軍(代表でいえば疾風)でも海軍(代表でいえば紫電改)でもそれぞれに一撃離脱戦法にも適し巴戦にも適した新型戦闘機を送り出し始めていたのですが国力の衰えた日本にとって十分な品質と十分な数を揃えてやるのは至難の技であり敗戦する結果となりました。
しかしそれらの新型戦闘機はアメリカ軍側でテストされそのほとんどが高い評価を受けていました。
総じて品質の良い物資を使い数を揃えられていたらアメリカ軍側に相当な被害があったに違いないと驚愕されていたのが事実でした。
それら諸々のことがあり戦争で日本に勝ったとはいえそういう部分では日本に対する敬意をはらっているアメリカ人もそれなりに居るということでしょう。
日本海軍戦闘機の零戦の後を継ぐものは何だったのか?
それは三菱製 十七試艦上戦闘機「烈風」になるはずでした。
順調にいけばそうなるはずでしたが、零戦の試作機が十二試艦上戦闘機でしたから実に五年のブランクを空けての後継機でした。
戦時下にあっては全ての兵器の技術の進展は平時とは比較にならないほど急速に進みます。
それを考えると敵であるアメリカ軍は次から次へと新型機を開発しては実戦投入していたのに五年もブランクを空けたことは大きな失態でした。
長いブランクが空いた原因は軍上層部の零戦への信頼感の高さもありましたが、具体的には零戦の改良型の開発と対爆撃機用の局地戦闘機「雷電」の開発に技術者がとられてしまい手が回らなかったのが実状でした。
参考までに画像は烈風と雷電です。
「雷電」は十四試局地戦闘機。
折しもアメリカ軍の四発重爆撃機ボーイングB-29による日本本土爆撃の脅威が迫っていましたから、これに対する対抗手段を模索していたのは当然の流れではありました。
しかしエンジン技術分野で弱かった日本には強力で小型な戦闘機用エンジンに適当なものがなく苦肉の策として爆撃機用の大型エンジンを採用したため、それに伴い開発は難航を極め長引きました。
その努力の成果もあってか戦後アメリカ軍にテストされた「雷電」への評価はかなり高いものでした。
大型とはいえ出力の高い爆撃機用エンジン(1800馬力級エンジン火星)を搭載し空力的に洗練された紡錘形の胴体に四枚羽のプロペラ、通常翼と層流翼を絶妙にミックスさせた主翼(内翼側のみ層流翼としていた)を持っていましたからアメリカ製戦闘機お得意の一撃離脱戦法も問題なく行えて日本戦闘機お得意の巴戦にも強いという戦闘機に仕上がっていたからでした。
但し問題は艦上戦闘機としてではなく局地戦闘機として開発されていたため航続距離も短く(短いとはいっても増槽付きでは2520kmは飛べだ)離着陸特性も零戦のようには良くなかったので零戦の後継機には成り得ませんでした。
局地戦闘機「雷電」の現存機は戦時中フィリピンで滷獲されたものがアメリカのプレーンズオブフェイム博物館に屋内展示されています。たぶんこれが唯一の現存機だと思います。
模型による局地戦闘機「雷電」の三面画像とプレーンズオブフェイム博物館にある局地戦闘機「雷電」の画像を貼ります。
「烈風」の開発もエンジン開発(戦闘機用小型高出力エンジン誉)の不調から難航しました。
画像で見る外見からもお分かりの通り「雷電」は戦闘機用には不向きな大きいサイズの爆撃機用エンジンを使うしかなかった関係上、機体設計に相当な苦労を強いられました。
その姿を見れば苦労がヒシヒシと伝わって来ます。
エンジンの前には延長軸を設け、その前には冷却空気を強制的に取り込むための強制冷却ファンを配置し、そのまた前に幅広ブレードの四枚羽プロペラが配置され、それら強制冷却ファンまでを外板で覆い紡錘形に絞り込んでありました。
大きいサイズのエンジン搭載でもどうにかして空気抵抗を減らそうと努力した結果でした。
翼は前述した通り内翼側を高速が出し易い層流翼断面として外翼側は通常翼断面として高性能化を図っていました。
もちろん捩り下げの技術も使われていました。
高速も出せて小回りも利きアメリカ軍が手強い相手だと思ったのも無理もない話でした。
アメリカ側では零戦や雷電などの日本製の軍用機を滷獲して徹底的に調査していましたが捩り下げの技術については判らずに居ました。
この妙技をアメリカがやっと理解出来たのは戦後になってからの話です。
アメリカ軍側でテストされた雷電は高い評価を受けており、日本側で問題になっていた悪い点はアメリカ軍側ではさして問題とされず、当時の我が軍のどの戦闘機でも対戦したら互角か又は負ける可能性が高いとして雷電に対し好評価を与えていました。
日本側での雷電に対する評価はあまり良いものがなく苦労して開発された割には劣等生扱いでした。
当時の日本では零戦が何の任務でもそつなくこなす、あまりにも優等生的な存在だったために新型機を開発する際は何でも零戦の性能が基準となっており、零戦より速いとか、零戦より小回りが利かないとか、という表現で何でも零戦の性能との比較が基準とされていました。
軽戦の代表選手たる零戦に慣れ親しんだ者が大半だったため重戦に分類される雷電はそれだけでも敬遠されました。
エンジン延長軸系から来る振動問題、直径が大きい胴体やファストバック形式の風防から来る視界の悪さ、長い離陸距離や速過ぎる着陸速度など、零戦と比較すると悪い評価のオンパレードで努力の割に不遇な新型戦闘機でした。
しかしアメリカ人にはこれらの問題点は全く問題視されなかったことを見ると当時の日本側はかなり神経質な評価を下していたために有能な戦闘機を持っていながら有効に活用出来なかったという結論になりそうです。
太平洋戦争終結時に日本を占領したアメリカ軍がアメリカ本国に向けて送ったリポートの内容と重なる気がします。
そのリポートの内容には「日本には優れた人材、優れた技術があり、優れた物も作り出せる状況にありながらも、それを十分に有効活用することに失敗した結果がここにある。惜しいことだ。」とありました。
海軍の三菱製「雷電」と陸軍の中島製「鍾馗」を比較した写真。
連合軍によるテスト飛行のひと駒で三菱「雷電」とアメリカ海軍艦上戦闘機グラマン「F-6Fヘルキャット」、イギリス軍のスーパーマーリン・スピットファイア戦闘機が同時に飛行している写真。
を貼ります。
一枚目の写真を見ると入手出来る大馬力エンジンは大きなサイズの爆撃機用エンジンしかないという同じく苦しい環境下の同じ日本にあって同じく大変な苦労を強いられたこの二機種。
海軍の三菱製「雷電」と同じく陸軍の中島製「鍾馗」も良く出来た優秀な戦闘機でしたがテストしたアメリカ軍側からの評価は高く日本側では劣等生扱いでした。
しかし同じような環境で同じような冷遇を受けながらも両機の側面写真を見ると三菱と中島のそれぞれ個性の違いが際立って目立ちます。
二枚目の写真を見ると同じく大きなサイズのエンジンを搭載しデブな機体を作っても日本機とアメリカ機の出来上がりの違いが明瞭に判ります。
国民性の相違なのでしょうか、同じデブ戦闘機でも日本機の場合は身の引き締まったデブマッチョです。
日本機の場合は一心に磨き上げるように造り込むような日本人の性格が表れているようです。
雷電はプロペラの延長軸の起因による振動が発生し、その対策に時間を取られて実用化が遅れたんやな。
根本的な振動係数の解決は、現在の技術を持ってしても解明困難な事例もあって、雷電の開発当時は効率が低下するのを
承知でプロペラ剛性を高くして一応の対策を見た訳やがな。
離陸時の雷電は冷却ファンからは、ジエットエンジンのようなキィーンと言う音が発し急角度で上昇する様子がその高性能ぶりを現しているようやったなぁ。
米軍規格により完全整備された雷電は、日本海軍の公試記録を遥かに凌ぐ高性能を発揮し、米軍のテストパイロットによる飛行レポートでは
それまで操縦した日独、米、英、各国の機体の中で最も優れた飛行性能記録して唯一、ムスタングの高速性に若干、及ばないとの事やったんや。
権兵衛さん、こんばんは。
プレーンズオブフェイム博物館の雷電は是非なんとかして飛行可能なように修復して再び強制冷却ファン特有の金属音を響かせながら飛行する姿を我々に見せて欲しいものです。
結局、雷電も烈風も零戦の後継機とは成れず、実質的に零戦の後を継ぐ戦闘機と成ったのは川西飛行機(海上自衛隊向け救難飛行艇US-1やUS-2を開発生産している現在の新明和の前身にあたる航空機メーカー)製の紫電改でしたね。
強風の改良型が紫電で紫電の改良型が紫電改なのでこの三機種の画像を貼ります。
雷電の実機は見学したけど写真等で見る大きいと言う印象よりは、各部の設計が洗練されている為か全体的に流麗な感じがするねんな。
日本海軍での運用では燃料やエンジンオイル等の質的問題の為に持てる実力を発揮、出来んかったのは残念やったけど、302空 厚木航空隊の雷電部隊は直上方攻撃による背面の機動でB29を攻撃し、暫し戦果を上げているんやな。
紫電はフィリピン方面で運用されたけど誉型エンジン実用化の過渡期に実戦配備された点と、二段式の収縮脚による動作不良による稼働率の低さにより際立った活躍は無かったけど、高速化する米軍機に対しては、零戦より速力があって防弾が施された本機は有用と判断された訳やな。
実際の空中戦の機動では、宙返りを行うとオートローテーションに陥る癖があって、零戦に慣れた搭乗員には敬遠され、実際に紫電に搭乗するのを拒んだ戦闘機隊長もいたんやな。
その後の紫電改では、機体設計を熟成させ主翼を低翼に改めた為、二段式収縮脚では、30秒以上かかっていた脚の収納が本機では、十秒以内に収まった点と、誉型エンジンが実用レベルに達した点や、水銀を媒体に用いた空戦フラップの不具合解消により見違えるよう高性能を発揮したんやな。
紫電改の公試テストでは最高速度は600キロに届かないけど実際はエンジン実用化の途上で出力制限下での数値で、海軍の飛行テストでは優に630キロに迫る速度を記録し、また高翼荷重にも関わらず空母への着艦テストでは零戦より操縦操作が容易であると報告されて一日も早い部隊配備が渇望されたんや。
縦の機動を活かした模擬空中戦では紫電改単機で二機の零戦
に対して優位に立てる事があって、零戦に慣れ親しんだ搭乗員は、初めて操縦する紫電改の操縦性と速度性能が良好に口を揃えて「紫電改さえ有ればグラマンに絶対、負ける気はしない。」とその高性能ぶりを讃えたそや。
紫電改も復元されたものが数機ありますが、いずれもアメリカ。
飛行出来ない展示機ばかりだったと思います。
紫電改も自動空戦フラップ込みで飛行可能なように復元して飛行する勇姿を見せて欲しいものですね。
最後の型の紫電改と最初の型の紫電改の写真と紫電改の透視図解を貼ります。
大戦機を復元する上で一番の障害になるのは大概の場合はエンジンです。
多くの復元機のほとんどはエンジンを復元するのが大変困難なために別の代用エンジンを搭載するか、飛行出来ない状態での地上展示となっています。
(墜落して失われてしまうことを恐れての地上展示オンリーという場合もありますけど)
エンジンやエンジン部品までリバースエンジニアリングで復元出来るようになったら素晴らしいのにと願うばかりです。
最終型となった零戦の改良型の写真を貼ります。
零式艦上戦闘機五四型です。
順調に量産型に移行したら六四型と呼ばれる予定でした。
軍からの命令で長らく自社製エンジンではなく他社製エンジンである中島製 栄エンジンを搭載して来た零戦の各型でしたが、終戦間際まで来てようやく三菱製 金星六二型 離昇出力1560馬力の空冷星型エンジンを搭載した零戦を完成させましたが試作機を二機作ったところで終戦となってしまいました。
中島製 栄二一型エンジンは離昇出力1130馬力だったため430馬力のパワーアップということで度重なる改良による重量増加で各種性能が低下するばかりだった零戦の性能も五二型レベル+アルファまで回復することとなりました。
金星エンジンとほぼ同じエンジンに換装した陸軍の川崎製の五式戦闘機がグラマンF6FヘルキャットやノースアメリカンP51ムスタングと互角に戦っていましたからこの零戦五四型もかなり期待出来る存在ではありましたから惜しいことをしました。
零戦のエンジン選定に当たっては、三菱の瑞星搭載は、あくまでも暫定的なものやったんやな。
一般的に零戦への栄エンジン搭載は海軍側からの一方的な命令によるものと思われてる節があるけど実際には、堀越技師自身、瑞星エンジンでは海軍側の性能要項に合致しない事が
分かっており、もう一つの選択肢であった金星エンジンも機体の大型化への懸念等があったけど、零戦の開発時には戦闘機用の金星エンジンは、実用化されてなかったんやな。
一方の栄型エンジンは先進的な設計によって開発され、零戦の開発中や試験飛行中にも栄型エンジンの出来の良さが堀越技師にも伝わり、技術者の視点から海軍側より伝えられる栄型エンジンの性能に
零戦の要求性能をクリアーするには、栄型エンジンが最適であると判断したんやな。
海軍側も三菱の社員である堀越技師への配慮から海軍の指示により栄型エンジン搭載決定と言う形式的に命令と言う形にものになった訳やな。
惜しむらくは栄型エンジンの最終系は1500馬力達成を計画されていたけど誉型エンジン開発により、その実現化は無かった事やな。
1500馬力の栄型エンジン搭載が真の零戦の理想形やったかも分からんな。
太平洋戦争当時の日本の軍部は技術者がことの真実をちゃんと説明しているにもかかわらず、精神主義ばかりをごり押しして技術者たちの話を聞かず話の本質を捩曲げる悪い癖が横行していたのは事実です。
堀越技師と共に零戦開発に携わって苦労をしていた曾根技師が生前NHKの特集番組で当時のことを語っていました。
その時の話はこうでした。
南方に進出し航空撃滅戦を戦っていた前線部隊の切羽詰まった改善要求の声に応えるべく零戦三二型を開発している時期に開発会議の席上で声を大にして会議の流れを握っていたのはやはり軍部でした。
ご存知の通り零戦各型の中でも三二型だけは角張った主翼の翼端形状をしています。
技術者たちは翼端を丸く整形しないとカルマン渦が発生し速度を出す上で障害になることを知っていたので整形してから完成させて欲しいと訴えましたが、軍部は「最近弛んではおらんか?そんな考えではこの戦争は勝ち抜けない!精神を引き締め軍と民間と一致団結してこの戦争を勝ち抜こうではないか!」と高圧的にいわれ会議は終わり技術者たちの訴えは聞き入れられなかったと回想されていました。
それが原因で零戦三二型は主翼端を整形する暇も与えられず実戦投入されエンジンの馬力は上がっているにもかかわらず速度性能はほとんど向上出来ないままに使用されることを余儀なくされました。
ようやく主翼端整形がなされたのは太平洋戦争末期になってから零戦五二型からでした。
軍部が押すエンジンを開発メーカーに押し付けて失敗した事例は他にもあり零戦の後継機に予定されていた烈風でも軍部は三菱製エンジンの搭載を最後まで認めず中島製の誉エンジンを搭載しろという命令を撤回しませんでした。
その結果、烈風の性能は要求値を下回り開発中止となりました。
しかし三菱が自社の主張を通し勝手に自腹で三菱製エンジンに換装してテストした結果、性能は向上し要求値を達成、結果を聞いた軍部は採用だ採用だと喜びましたが時期既に遅く終戦となりました。
当時の軍部の押し付けは本当にあった話なのです。
開発に携わった人、本人が語っていたのですから。
零戦の開発中は、海軍側と技術者側の意見のすり合わせの余裕もあったけど、対米戦に突入してから零戦の優位が保てないようになると部隊からより速度を向上した新鋭機の要望が矢継ぎ早に届き、海軍も切羽詰まり技術陣側に無理難題に近い要求をしたんやな。
零戦32型も翼端の角ばった型は、堀越技師の静養中に他の技師によるもので、職場復帰後に32型の翼端を見て不本意だと言う思いを禁じ得なかったそや。
烈風は、試作の段階から実現化の可能性は皆無に近い機体やったかもな。
一般的に烈風は海軍側のエンジン選定ミスの事が取り出されるけど、史実は烈風の試作が内示された時にはハ43は試作中で、昭和20年に入っても実用化には今一歩のエンジンで、最初から三菱製のハ43搭載に決定していても決しても早急にな烈風の部隊配備は不可能やったんやな。
烈風試作には実現化になりつつある誉型エンジンを搭載予定とするのは、至極、当然で理に適った事やろな。
ただし烈風試作の段階で海軍側が犯した大きななミスは、翼面荷重を指定した為、その数値をクリアーするには機体自体の巨大化は、避けられず、自ずと誉型エンジンでは馬力不足になる事が堀越技師には分かっており、開発中の自社エンジン以外には要求性能達成は不可能と断定し、執拗に海軍側にハ43搭載を提言した訳やな。
三菱製のハ43エンジンは中島製の誉エンジンに比べると無理をした設計をしていないぶん大きさと重さ的にいえば大きく重かったためハ43エンジンを搭載した場合の方が性能的には不利なはずでした。
しかし結果が逆に出たのは何故か?
それは実際に使われていた誉エンジンがメーカーのいうカタログデータよりいかに低性能であったかを如実に物語っていたわけです。
無理をした設計をせず堅実路線を選んだハ43エンジンの方が悪化した環境下でも確実な性能を出していたわけです。
まずハ43エンジンと誉型エンジンは共に傑作エンジンと評価された金星と栄エンジンをベースに、それぞれ14気筒から18気筒化に改め、更にブースト圧を上げ馬力向上を目指した
もので、ハ43は2200馬力、誉型では2000馬力を目標としたものやったんやな。
但し空冷星型18気筒エンジンはアメリカでも冷却問題等をクリアーするのに手を焼いた代物で、当然、燃料やオイル、プラグ等の全ての質がアメリカより劣る日本では、相当の技術的困難が発生し、それをクリアーして曲がりなりにも実用化に達成したのが誉型エンジンやな。
ハ43は、開発に当たり三菱では中島飛行機で開発中の新型18気筒エンジンが画期的な高性能を目標にしてる旨の情報を聞き、次世代の大馬力エンジンを開発する計画のもとにハ43が設計される経緯となったんや。
当然、ハ43に於いても誉型エンジンと同じような燃料問題や油圧低下の様々なトラブルが発生し、終戦間際になっても技術的問題を抱えたまま試験飛行の機体に搭載されたのがハ43の現状やな。
零戦の次なる艦戦が一日でも早く実戦配備したい海軍と自社の新型エンジン実用化を標榜して開発された烈風は、レシプロ戦闘機としては正常進化した機体で、先々に計画されるであろう大馬力のエンジン換装に合致した機体やったんやな。
惜しむらくは、烈風はエンジンの熟成途中で終戦となった事やな。
実際は中島飛行機の荻窪のエンジン製作工場が爆撃により壊滅して、ハ43供給の目処が絶たれたけどな。
中島製 誉エンジンを搭載した試作機 試製烈風のテスト飛行の結果は操縦性と飛行特性は悪くなかったものの最大速度520km/h程度、高度6000mに達するまでの所要時間は10分もかかり、零戦の再来を望み大きな期待をかけていた海軍ならびに開発関係者全員を落胆させました。
零戦より低い性能では後継機とするのは無意味であり当然烈風の開発は中止と決定されました。
顧客でありユーザーにあたる海軍から強引に決定付けられた誉エンジンの搭載でしたが開発を担当したプライムメーカーである三菱側は納得がいかず、使用していた誉エンジンを下ろして地上テストで出力の再確認を行ったところ中島がいっていたカタログデータである2000馬力はおろかメーカー主張カタログデータの80%(1600馬力程度)しか出力が出ていない事実が証明されました。
これ以前から軍部は新しく開発される軍用機に軒並み誉エンジンを採用するようごり押しで命令していましたから、これらの軍用機は軒並みトラブルだらけとなり大混乱を招いていました。
たくさんの新型機に強制的に採用させたぶんテスト使用する機会は増えたため当然実用化のための実験は進展していました。
しかし軍部から優遇され実用化のための実験が進んでいたといいながら80%の出力しか出せていないのが現実でした。
軍部が特定のメーカーにエンジンの押し付けをしたりエンジンの供給をさせず冷遇するなどの行為は何も日本だけの話ではなくどこの国でも少なからずある話であり昔だけの話でもなく現在でもある話なのです。
臭い話には蓋をしろ的な考え方は良くないと個人的には思います。
良くない話でも本当の話を語った方がいいと思います。
我が身に良い話ばかり語っていると良い未来はありません。
良い悪い関係なく事実は事実として認めていかないと良い未来はありません。
日本の戦闘機好きです。
日本の発動機も好きです。
好きですが、それらには良い部分も悪い部分も当然あります。
零戦開発当初、十二試艦上戦闘機が搭載した三菱製 瑞星エンジンもその後の中島製 栄エンジンも三菱製 金星エンジンも好きです。
中島製 誉エンジンも三菱製 ハ43エンジンも好きです。
たとえていうなら中島製 栄エンジンは良く造り込まれた大量生産車用の使い勝手の良いエンジンだとすれば、中島製 誉エンジンはそれをベースにして気筒数を増やし特別にチューンしたレーシングカー用のハイオク仕様特殊エンジンであり、職人の匠の技に依存し切った美術工芸品のようなエンジンだといえます。
国家の総力戦で戦わねばならない近代戦にあたり職人技に依存するしかないレーシングカー用の特殊エンジンで戦おうと考えたのが日本の軍部だったといえます。
こういう表現で聞けば太平洋戦争当時の日本の軍部の先を見通す目がいかに愚かだったかがよくわかると思います。
兵器というものは高性能なものが望ましいのは当然ですが、先ず第一はいつでも確実に作動する信頼性がなかったらすべては無意味なのです。
真面目に堅実にの精神をいつの間にか忘れ、気がついたら自分が理想とする夢だけを追いつづけ敗戦を迎えていた。
それが当時の日本の軍部の姿だと思います。
国家の総力戦たる近代戦では極々少数の兵器がたとえ高性能であってもあまり意味はないということでしょう。
総力戦なのですから。
兵器は高性能なものが望ましいが、いつでも確実に作動する信頼性がなかったらすべては無意味。というのは零戦のエースパイロットだった坂井三郎氏が生前語られていた戦後の言葉「戦闘機の各種の高い能力も長く飛んでいられる能力がなければすべて無意味だ。」と本質的には同じだと思います。
無理に無理を重ね痩せ我慢して小型高出力のエンジンを搭載しても動かなければ無意味だし、力が出なければ無意味だし、飛べなければ無意味ということと同じです。
それを強引に推し進めたのが太平洋戦争当時の日本の軍部。
我々日本人にとっては良くない話ですが、真実は素直に直視することこそが、より良い未来へと繋がる正しい道だと信じます。
まぁ何やな対米戦に突入した時点で次期高性能戦闘機のエンジンとしては、誉型エンジンしか選択肢が無かったんやな。
誉型エンジンのベースとなった栄エンジンも開発当時は先進的な構造設計で実現は困難と言われとったんやがな。
それでも馬力向上は戦闘機の性能には不可欠なもので次世代へ繋がる技術への挑戦として様々な試行錯誤と失敗を繰り返した後に実用化に成功したんやな。
当然、栄エンジンが熟成したらその次の新型エンジンとして更なる高性能化を模索するのが技術的な正常進化で、栄エンジンをベースに18気筒して誉型エンジンへと繋がった事は自然の成り行きやな。
誉型エンジンの馬力低下はエンジン自体に起因するものでは無く、主だった原因は、マニフォールドの鋳型の形崩れによる形状不可の為と、その他、様々なトラブルによるもので、技術陣はこれを全力で解決し、海軍では紫電改で陸軍では疾風の後期型で誉型エンジンはほぼ実用化の域に達してた訳や。
特筆すべきは陸軍飛行47戦隊の刈谷整備大尉の指揮下で整備された疾風は稼働率100パーセントを誇り
、高性能エンジンに必要手順に従った整備が稼働率の高さに繋がったんやがな。 海軍の343空の紫電改の整備隊でも熟練整備士官の手になる機体は高い稼働率を誇っとるんや。
このように熟成を重ねた誉型エンジンやけど、18気筒と言うシリンダー数ではキャブレター方式では各シリンダーへの均一な燃料供給が困難になりつつあり、これが振動等の原因となったんやけど、対策方としては、低圧燃料噴射装置を持って誉型エンジンの根幹的な弱点が克服されようとしたんや。
終戦により実用化にならんかったんが残念やったのう。
戦争責任を全て潰え去った軍部に押し付け、自分達が被害者面する様は非常に醜いもんや。
対米戦突入も当時のマスコミや国民がアメリカなにするものとの鼻息も荒く、日本全体が対米戦やむなしとの機運が高まっていたんとちゃうかかな。
いわば戦争やそれによる戦禍は日本人全体の連帯責任やろな。
いざ対米戦になったら航空機の性能向上は必至で、実際に部下の命を預かり米軍機と対峙する指揮官達は、軍部に機体の性能向上要求を火のように要求するのは至極当然やろな。
切羽詰まった状況ではメーカー側に理不尽な要求したのも前線からの命を的にした要求があったからこそやな。
メーカーも戦争により多大な利潤を得てるのやから多少の無理な事は成し遂げんとアカンやろ。
NHKの番組での曾根技師による海軍への恨み節もNHK主導による海軍悪玉論が見え隠れして釈然とせんものを感じたんや。
零戦の搭乗員であった人達は海軍の戦闘機搭乗員として零戦で大空を駆けた事に誇りを感じており、防弾装置云々の恨み節は坂井三郎元海軍中尉その人以外には言及する者は非常に少ないのとちゃうやろか。
まぁOさんも 軍部に対して悪玉論を打ってもどうにもならん事やから、かって太平洋洋上を我が物顔で艦艇や航空機を繰り出した海軍の見敵必殺の精神に免じで
暫し、滅びの美学を垣間見てくれたらエエがな。
何も太平洋戦争の責任を軍部に押し付けるということではありません。
変に曲げて受け取らないで下さい。
太平洋戦争についてのことは日本人全体の責任です。
それがあることは念頭に置いた上で日本人の一般個人個人は個人であるだけに個人でやれることには限界があり力が弱かった。
それに引き替え政府や軍部などの大きな組織は力も統制力もあるため、やれることはたくさんあった。
戦争時だからこそ日本人国民をより良い方向へ導く責任があった。
この責任は重大なものであり、これを間違った方向へ強制し導いてしまった責任はごめんなさいでは済まされないということをいっているのです。
何事もおかれた立場次第で責任の重さは天と地ほど違いますからね。
それから人命を重視した防弾装備は絶対必要だと訴えたのは坂井三郎氏をはじめとした前線で戦っていた兵士たち自身であり、いらないといっていた人など聞いたことがないです。
そしてこの兵士たちの叫び声にも似た声に応えることが出来るようにやらせてくれと訴えていたのが曾根技師たち技術者たちでした。
その声を「弛んでる!けしからん!」といいながら黙殺し続けたのが実際には最前線で命をかけて戦うこともなかった軍部の上層部の人間たちだったのです。
これを書いただけです。
実際に命をかけて戦っていた人たちが語っていた生の声です。
悪かった歴史を直視せず、捩曲げる者は将来にも又、同じ過ちを繰り返すでしょう。
反省の出来ない者に物事の改善は無理だからです。
まぁまぁ興奮せんと落ち着きや。
戦闘機の防弾装置もそれぞれ昭和14年と15年に試作の内示があった雷電と強風に防弾装置の必要性が指示されとったんやな。
防弾に関してはノモンハン事変でソ連機と壮絶な空中戦を行った経験が有るだけに隼は、既に燃料タンク防弾がされていてこの点では海軍を一歩リードしとったなぁ。
海軍でも紫電改では実用に耐える防弾装置が施されとるがな。
まおワイはあんまり頭の回転がエエ事、無いよって難しい話を振られても難儀するだけやから気楽な話を頼むわ。
ほなまたな。![]()
0さん、権兵衛さん、
すごく 勉強なりました、
私はエンジンの事は、さっぱりわかりません、![]()
しかしながら、太平洋戦争で、命をささげた、英霊の方々には
深く深く、頭がさがります、
私は戦争に関する 映画やテレビ大好きで、いつも見ております、
ヘルシアさんお久しぶりです。
こんにちは(゚▽゚)/
人それぞれに個性があるのでいろいろな考え方や意見があって良いと思います。
但し、いつの時代でもそれぞれ人たちにそれぞれの立場というものがありますから立場の違いに相応のやるべきことと責任の違いが存在することは誰も否定出来ません。
個人の行いで起承転結まで終わらせられる小さな規模のお話なら当事者たちで上手くいくように適当に行えば良い話です。
しかし、戦争に代表されるような国家間レベルのグローバルな物事を行う場合は国家全体を動かすような大きな組織、政府や軍でしか行えない関係上これに関わる人たちの責任は重大なものです。
このような場合に何かを動かす際には良かった場合の話だけを話ような者は愚か者です。
こういう場合の重責を担った人たちは良かった場合の話だけを考えるのではなく悪い結果が出た場合のことことも考えておくことが必要とされます。
政府や軍の関係者は重責を担っている関係上、勝った場合のことだけではなく負けた場合のことも考えておくことが必須条件だということ。
戦争では相手に被害を与えますが、逆に被害を受けるのも付き物です。
こうした避け難い状況の中にあってリスクコントロールやダメージコントロールを考えることが出来ない者が物事を指揮指導することは国全体にとっての不幸そのものなのです。
不幸にして太平洋戦争での日本はその悪いケースがそのまま実行されてしまったため特攻作戦などが行われてしまったわけです。
戦争を始めた指導的立場の者たちが責任をとらず、その代償として最前線で戦う兵士たちや一般人がどんどん死に行く結果を生みました。
このことを反省せずして勝ち戦の時のことばかりを話すのは如何なものかな?これでは将来にも又同じ失敗を繰り返すだけだなと思ったのでこれらの話を書きました。
責任ある立場の政治家などが責任逃れすることが多い現在ではありますが、責任ある立場の人たちが重い責任を担わなければならないのは時代が変わっても変わることはありません。
おごり高ぶった軍部による兵器開発への細かな数々の横槍やエンジンの選定ミスもいってみれば同じ事柄の中の一つなのです。
おごり高ぶった軍部による兵器開発への細かな数々の横槍やエンジンの選定ミスも同じ事柄の一つ。とはどういうことかといえば、これらの軍部からの兵器開発への細かな数々の横槍やエンジン選定ミスに従った結果、使用する戦闘機が敵に通用しない状態に陥り味方部隊援護も困難になりどんどん守勢一点張りになり命を引き替えにした特攻作戦を行わなくてはならない状態にまでさせてしまった。
軍部=責任ある立場の人間としてこのエンジン選定ミスに代表される判断指導ミスは責任重大なことだったのです。
軍部寄りの人たちはこの件をとかく曖昧にしたがりますが、これは曖昧にして良い物事とは違うのです。
Oさんへ。
現在の自衛隊は米軍と共に切磋琢磨して最も強力な戦術集団を組織してるんじゃないのかな。
昔の軍部の悪口を並べても何を言いたいのか見えて来ないよ。
せっかく権兵衛さんとOさんの専門的なエンジンの話を興味深く楽しんでいたのに
興ざめだね。
権兵衛さんは四つ葉時代から軍カテで相当レベルの高いコメで常連さん達を唸らせていたし、確かエンジン関係の加工やチューニングをやってるその道のスペシャリストじゃ無かったかな。
ここでのコメもそれにふさわしく鋭い内容だと思うんだけど、Oさんのはコピペとイミフな日本軍の悪口を感情的に批判してもロム専の連中から見たらつまんないんじゃないかな。
後ね烈風のエンジンの事も自分は詳しく無いから判断できないけど権兵衛さんのコメには説得力があって分かり易いのかな、まぁもっと勉強してね。
0さん、
私は、当時の軍部の方針は 敗戦したと言う事は、
間違っていたと言う事だと思いますが、
しかし当時の日本国民(軍部も含め)どなたも家族、又は、や日本を守ろう、という目的は、みんな同じですね、
185※さん コメントありがとうございます、
0さんも、権兵衛さんも専門的で、かなり勉強されたと感じます、
私は低学歴だから、コメント読んで解らない事がたくさんあります
二人とも、素晴らしいです、尊敬してます、
ひとつだけ質問です、
真珠湾攻撃
①アメリカは暗号を解読して米軍上層部は 真珠湾攻撃を知っていた、米国民は、戦争にヤル気が無かった為、
上層部は わざと攻撃を受け、反日感情を米国民にうえつけた、
↑↑
正しいのでしょうか?
まちがってたらごめんなさい、
0さんのおっしゃるとうり、
人それぞれ、思い 考えがあります、その個人の思想的な考えは、皆 「良」ですね、
しかし 権兵衛さん、0さん、すごい知識ですね
ヘルシアさんありがとうございます。
前もって軍部寄りの人たちは〜といっていたらやはり確実に出て来られましたね。
186番さんあなたは正に軍部寄りの人です。
今の自衛隊はアメリカ軍と協力して最高の軍事集団を作っている?ですか?
日本の防衛はアメリカ合衆国の軍隊や軍事産業にベッタリ依存して初めて今のような状態を辛うじて維持していることにお気づきではないようですね。
186番さんは外見ばかりで判断し過ぎです。
あなたこそ外見の装備や共同訓練だけにとらわれるのではなく、もっと本当の意味での見識を深められた方がいいですよ。
それから権兵衛さんのことは以前から存じてますよ。四つ葉で好評だったとかいう下りはそれは息のかかった人たちと仲間内だけでの話だと思います。
万人が万人そう思っていたわけではありませんから話は大きくいわない方が良いですよ。
装備だけとって見ても今の日本の防衛装備はキーになる部分は外国(アメリカ合衆国)に握られ依存し切っている。
戦闘機でも艦船でもエンジンにあたる動力部分は国産では強力なものを開発出来ずにいる。
何も変わってないではないですか、太平洋戦争当時の状況と同じく強力なエンジン一つも自国製では作れないままですよ。
国の根幹に関わる重要分野の技術は外国に依存せず国産化する。
これが太平洋戦争の失策から学ぶべきことの一つの一例なのに何一つ改善されていない証拠です。
このままでは、もし戦争が起きたら又、太平洋戦争当時と同じことを繰り返し国民を窮地に立たせると思います。
軍部を悪くいいたくない思いから軍部寄りの人たちはそれを知っていながら知らないふりをする。
だから国のためにも国民のためにもならないのです。
逆に罪悪ですらあるといってもいいくらいです。
もう一度いいます。
反省のない者に改善は無理です。
悪かった部分を悪かったと認識しないのだから改善点を見出だせないでしょ?
だからそんな人たちに改善は無理なのです。
ヘルシアさんの質問に対してですが、
アメリカの上層部は日本が真珠湾攻撃をすることを事前に知っていたというのは本当だろうと思います。
日本を太平洋戦争開戦へと向かわせる原動力となったのはアメリカの態度だけではなくイギリス、オランダも大きな役割を担っていました。
特にイギリスは自国の国益を有利にするため得意の諜報能力を使って実際よりかなり誇張した日本の情報をいろいろとアメリカに耳打ちしていました。
オランダも石油を売ってもらえなくなると日本にとっては死活問題になることを重々知りつつも輸出禁止にするという行動をとりました。
日本が戦争でも始めなければならなくなることを知りながらの行動でした。
近年になっていろいろな諜報活動の資料が公開されわかって来たことですが現在日本と仲良し仲良しといっている国、イギリスもオランダも実は日本を太平洋戦争をしなければならない状況へわざと追い込んだ張本人だったことが知られています。
アメリカの上層部が日本による真珠湾攻撃を事前に知るきっかけとなったのはウルトラと呼ばれる機密情報によってだったと思います。
ヘルシアさんがおっしゃる通りリメンバーパールハーバーという合言葉をもとにアメリカ合衆国国民を日本との戦争に駆り立てるために利用していたということのようです。
当然アメリカの上層部はアメリカ合衆国国民には知らせず長年の間、情報統制していたのだと思います。
0さん、![]() 、ありがとうございます、太平洋戦争に突入する、きっかけはイギリス、オランダが
、ありがとうございます、太平洋戦争に突入する、きっかけはイギリス、オランダが
絡んでいたとは、知りませんでした、![]()
パールハーバーには
米空母がいなかったとか?
186番だけど まぁこっちはロム専なので とても、専門的な知識のコメは無理っぽいんだけどね、あえて言わせてもらうよ。
以前の四つ葉は相当な知識自慢の人がそれ相応のレベルの高さでコメをやり合っていて常連の権兵衛さんもその中の一人だったよね。
凄く面白くネットでは知ることが無理っぽい話を聞けて熟読してたんだよね。
そもそも権兵衛さんって四つ葉のニュース糧でも違うハンネで名だたる論客?を相手に常にあの関西弁で押し気味でコメしてたんだけど、関西弁嫌いの自分が関西弁に親しみを感じるようになったよね。
その頃の軍カテで権兵衛さんと話の噛み合わないようなやり取りをしてた人がひょっとしてOさんなのかな?。
まぁ権兵衛さんのことはこの辺にして、 Oさんの言いたいことはだいたい分かるような気もするけど反面、漠然として雲を掴むようなって感じかな。
軍部が悪い、政治が悪い、教育が悪いって感じの一人よがりの批判だけって感じ。
後は真珠湾攻撃のことも以前に四つ葉で議論されていたけど
日本政府の暗号は解明されていたけど軍部の暗号は解明されていなかったらしいとか、各国の諜報機関が日本の空母部隊の動きを追跡して、その中で真珠湾攻撃の可能性もアメリカ側に伝えていたらしいけど、アメリカ軍は万が一、日本軍が真珠湾攻撃を行っても能力不足でたいした被害は出ないだろうとタカをくくっていたとかね。
でも実際はあの頃の日本の空母部隊に敵う国はいなかったそうかな。
それでさ、Oさんの日本軍批判も一個の意見だから大事だと思うよ。
Oさんって文章からするとまだ若い人だよね、自分も二十代前半で人のことは言えないんだけどね。以前の四つ葉の軍カテは結構、年配者達が中心で長年の知識の蓄積でほぼ専門誌レベルだったよね。
若い?Oさんの軍部批判も興味深いので、以前の四つ葉の常連さんレベルでのコメを期待してるからね。
自分より年上だったらエラソーなタメ口ごめんなさい。
186の人よ
クスッと笑ってしまうな。いや失礼しました。
何々?
よつばでは相当レベルの常連の権兵衛さんがいて好評を博していた?
そしてその権兵衛さんはニュースカテでも違うハンネを名乗って名だたる論客を相手に常にあの関西弁で押し気味でコメしてた?
笑わせてくれるじゃないか。
その関西弁の人と権兵衛さんは同じ人物でしょう?
と質問されたのに対して権兵衛さんではないと否定していたのを見たことがあるよ。
その逆もあった、権兵衛さんに対してあなたはニュースカテにいるあの関西弁の人と同一人物でしょう?
と質問されて権兵衛さんも同一人物ではないと否定してました。
本人が否定してたのに他人がそんなこといいきれるのは摩訶不思議なはなしだね?
正体がバレましたな権兵衛さん?
いやブライアンの代理人さん?(笑)
あなたのコメ見てたらなんだかいつも言い争う喧嘩相手を探し求めているようにしか見えないね。
忠告です。
別人に成り済まして荒らし回るのはやめといたほうがいいよ。
みんなに迷惑だろ?
ああ、ニュースカテの代理人さんの事でしょ?
軍カテでもニュースカテでも権兵衛さんと代理人さんが同一人物ってことはみんな知ってる事だよね。
もっと本人はとぼけて違うって言ってたみたいだけどね。
だって同じ日の軍カテとニュースカテの権兵衛さんと代理人さんのIDが一緒だったからね。
それにあの関西弁でもすぐに同一人物だと分かるでしょ。
まぁニュースカテの代理人さんは敵も多かったけど支持する人も逆に多かったよ
自分はその内の一人だったけどね。
自分が権兵衛さんと代理人さんに間違えられて光栄だけどね。
それにあの人だったらこいつはと思たっら他人のフリなんかしないで速攻に関西弁でズバっと来るでしょ、 それが痛快だったけどね。
多分たけど代理人さんか権兵衛さんにこてんぱんにされた人なのかな。
186さんポロリとボロが出たね。
悪あがきしてるけどもう遅いよ。
よつばでは本人が否定してたことをここで公然と肯定出来るのは本人以外にいないだろ!
しかも自分で自分のことを褒めちぎってる始末。
恥を知りなさい。
見苦しいね。
ハイおしまい。
荒らし回るのはほどぼどにしといてね。(笑)
名無しさん早速だけど自分は193のスレで権兵衛さんと四つ葉のニュース糧の人は同じ人、的なコメをしたけどね代理人さんだとは一言も言ってないのにどうして代理人さんだと特定できたのかな。
それは四つ葉では代理人さんと権兵衛さんは同一人物だと言うのは常連さんだったら誰でも知ってる事だからだよね。
代理人さんはニュース糧では言いたい放題が痛快でファンも多かったと言う事実をコメしてるだけで他にもっと代理人さんを持ち上げる人はいっぱいいたでしょ。
まぁ今回は権兵衛さんの代理人と言うことで話は終了にしとくね。
それじゃ権兵衛さん自分なんかが勝手に代理人を気取ってすみませんでした、痛快で鋭いコメを楽しみにしています。
186さん作り話はやめましょうね。
自分はほぼ毎日よつばの軍カテとニュースカテは覗いてましたが、権兵衛さん=ブライアンの代理人さんという疑惑を抱く人はいましたが本人たちが否定していました。
そして権兵衛さん=ブライアンの代理人さんだという書き込みをする人は全くいませんでしたよ。
IDが云々なんて見え透いた嘘はやめましょう。
醜くって往生際が悪い。
195、197、199番さんありがとうございます。
そう感じていたのは私だけではなかったようですね。
私の場合は数日に一回ペースで四つ葉のニュース糧と軍糧を覗き内容を読んでいました。
結果からいうとあなたが見た内容とほとんど同じような具合でした。
それで186番さん=権兵衛さん=ブライアンの代理人さんなのかなと思いました。
しかしこの話はここまでにしましょう。
汚い手を使う者はそのうち罰が当たりますよ。
なぜか話が権兵衛さんがどうだったこうだったのコメになって脱線してしまっているのでコメするなら少なくともスレのタイトルに関連するコメにしましょうよ。
0さん判りました。
汚いことしてる奴を見ると何かいってやりたい性分なもんですみませんでした。他では聞けないはなしなんて大嘘、誰かさんみたいに戦争ものの本類に載ってるコメばっかじゃないコメと画像と動画を又よろしく。
それじゃ自分はただの閲覧者に戻りま〜す。(笑)
皆さん、こんばんは![]()
![]()
![]() 、
、
軍糧、ニュース糧、![]() の時は、私は18禁に居ました、私の携帯で撮ったオリジナルのムービーや画像を投稿しておりました、
の時は、私は18禁に居ました、私の携帯で撮ったオリジナルのムービーや画像を投稿しておりました、
その後、日本史に興味を持ち 万次郎ハンネで歴史糧で投稿しておりました、
0さんのこのスレの支援画像、ムービーなど、貼って頂き、感謝にたえません、
また権兵衛さんの、零戦に対する、深い知識、
おそれいります、
また軍糧、ニュース糧の古参の皆様、私の大先輩です、
頭がさがるのは、18禁エロ糧では なく、
ここを見てくださっている方々です、
話の流れがこのようになってしまいヘルシアさん並びに好意的に閲覧して下さっていた方々には申し訳なく思います。
186番さんが私のことを若造だろうといいながらコピペばかりしているなどと愚弄しておりましたが、私はそんなに若くはなく二十歳の方々の倍以上の年齢です。
もちろんコピペの多用などしておらず己の記憶を頼りに書いたコメばかりです。
真意を読み取れない人には特に説明までするつもりは更々ありません。
蝦夷富士こと標高1898mの羊蹄山を背景に飛ぶ零式艦上戦闘機五二型(プレーンズオブフエイム博物館所有)の写真を二枚貼ります。
アメリカ海軍艦上戦闘機グラマンF6Fヘルキャットの出現に対し当初、軍の上層部は零戦五二型に水メタノール噴射装置を追加した栄エンジンを搭載した程度で十分対応可能で勝てると思い込んでいましたが、最前線で命懸けで戦っていたパイロットたちの要請に真摯に応えなかった結果は史実の通りとなったのでした。
戦争に負けた理由の根幹にあるものは己の悪い部分を認めず敵の良い部分をも愚弄したおごりの考え方でした。
0さん、ありがとうです
ヤハリ零戦は、カッコいいです、現在のどんなハイテク戦闘機より、心が熱くなります、
しかし この零戦に命をささげ特攻して 行った方々には永遠に敬意を表して、
また「バンザイ攻撃」とかで、
サイパン
硫黄島
ガダルカナル
他
多くの犠牲者を出しました、
0さん、のコメントの中で、水メタノール噴射装置 とは なんですか?![]()
ヘルシアさんこんにちは。
水メタノール噴射装置とはドイツではMW50と呼ばれ当時のドイツから伝えられた技術の一つで一種の出力増加装置です。
これを使うことで燃料のオクタン価を上げたような状態を作りだし燃焼室の異常燃焼を抑え出力増加をさせるためのものです。
しかし長くは使えない一時的な緊急出力増加装置でした。
水メタノール噴射装置のことをもう少しわかり易くいうと普通にエンジンが動いていて燃焼室で燃料と空気の混合気が爆発しているところに適量の水を噴射してやると燃焼室内の爆発の熱により水は気化して水蒸気となります。
その際に水が気化することにより熱を奪い膨張するため結果として異常燃焼の熱は奪われ膨張する力によりピストンはより強く押されこととなり異常燃焼防止と出力増加に繋がるという仕組みのものです。
メタノールを混ぜてあるのは高空では温度が下がり凍結するという現象に見舞われるためそれを防止する目的で混ぜてありました。
しかし各気筒に均一に噴射出来なければ激しい振動が誘発され効果が見込めないため栄エンジンへの搭載試験では不調が続き実用化予定は遅れに遅れました。
軍部の目論みは誤算に次ぐ誤算だったといえます。
エンジンの事は、難しいですが、
まぁ現在の自動車のターボエンジンの一種ですね
まぁ、パワー増加装置だからヘルシアさんのおっしゃる通りその類いということになりますね。
第二次大戦中に航空機用ターボチャージャーを実用化出来たのは豊富な資源と技術力を兼ね備えた数少ない大国アメリカ合衆国のみだったことは皆さんご存知のことと思います。
では日本やドイツではどうであったかというと日本は同じく航空機用ターボチャージャーの開発はしていましたが資源貧乏だった日本では希少金属のニッケルなどの不足により開発のほとんどが上手く行かず終戦を迎えました。
ドイツはというと試験結果は上手く行っていましたが他の兵器類ゲルリッヒ砲などと同様に希少金属類がすぐに枯渇し数を揃えられなくなることを予測して悟り開発を中止する決断を下していました。
そして航空機用ターボチャージャーの代わりにGM-1と呼ばれる亜酸化窒素噴射装置を開発しターボチャージャーと同様の効果を得て使用していました。
亜酸化窒素とは麻酔に使われる笑気ガスです。
なんやちょっと見とらん間にエライいややこしい事になっとるがな。
代理人?知らんがな。ワイは、あんなお下劣とちゃうがな。
ほんで傍観者なるボンクラは、スレタイにある零戦の知識も皆無の癖にいつの間にか湧き出とるゴキブリ兄ちゃんやな。
いつものように見事なアホっぽさは、未だ健在で、かってのよつばを彷彿して懐かしいど。
ほんでや186の兄ちゃん援護射撃、オオキニな。よつばの頃もたまに援軍してくれた兄ちゃんかいな。
さて本題に入るとして、まずヘルシアの兄ちゃんが疑問とする水メタノール噴射装置の事やな。
まぁ解り易くエンジンの燃焼の理屈から説明すると、空気とガソリンの最適な混合比はおよそ15対1で仮にパワーアップのため自然吸気のエンジン(ノンターボ)にガソリンの比率を多くしても空気の量が変わらないので不完全燃焼になり黒煙が出るだけやな。
これに対して排気の力を利用するターボチャージャーとエンジンの駆動を利用するスーパーチャージャーでは、それぞれ
空気を圧縮するので
燃焼室により多くの空気量の供給が可能となり、それ伴い最適混合比のままでより多くのガソリンを燃焼室で爆発させる事が出来て結果、馬力が上がるんやな。
しかし圧縮された空気とガソリンの爆発温度は、自然給気方式より高温となりプラグ点火に関係なく 着火するようになってエンジン損傷の原因になる訳やな。
権兵衛さんには気の毒だがその説明は複雑過ぎて逆に解り辛いね。
もっと他の人みたいに素人が聴いても飲み込み易いように説明してくれないかな?
玄人もしくは玄人気取りの人間同士ならツーカーの内容なのかも知れんがその説明では逆に理解し辛い。
意図的に自分を専門家っぽく見せようとして専門用語をただ並べ立ててるかのような説明は素人には理解し難いよ。
お解り?
ただ数字を並べ立てればいいってものでもないだろう。
ただ専門用語を並べ立てればいいってものでもないだろう。
ってこと。
肝心なのは聴いた人が理解し易いかどうかってことさ。
権兵衛さんの説明ではターボチャージャーやスーパーチャージャーの場合だと馬力は出るが燃料消費量はめちゃめちゃ多くなり燃費はめちゃめちゃ悪くなるってことかな?
それから空気をたくさん押し込めるのはいいけど冷やすための装置がないとトラブルが発生するってことかな?
川崎が作った日本陸軍の戦闘機では冷やすための装置を省いてもそれなりに機能してたらしいよ。
ターボチャージャー付きエンジンがね。
知ってた?
名無しの兄ちゃんな、
ワイが専門家を気取って難解な用語の羅列てか?
まぁそんな悲しい事を言うなよ。
ただただ、大戦中の戦闘機に興味があって、その手の本を読み倒しとるだけやがな。
よつばの軍カテでも零戦や戦闘機の話が出ると夢中でコメをしとったんやがな。
ほんでやインタークーラーの無い排気タービンてか?
陸軍の偵察機で新司令偵とか五式戦やろ。金星のエンジンに水噴射の排気タービンかいな、完璧とはいかんでもどうに実用の域に達したがな。
ほんでやさっきの続きやけどな、エンジンの燃料に付いては現在の燃料工学でも解明されとらん程に難しい事なんや。
それを無い頭を絞って出来るだけ解り易く説明したろと思う訳や。
要するに空気を圧縮すると温度が上がり、その状態で燃料室では、異常高温により、ピストンの位置とプラグの点火タイミングと言う重要なポイントに関係なく混合気が自然着火=勝手に爆発してエンジンが壊れるのやな。 これを防ぐには、より着火点の高いガソリンが必要で、それをオクタン価と言う数値でガソリンの品質を表すのやな。
その数値が高い程、性能の良い燃料となるけど、残念ながら日本ではアメリカ並のオクタン価の高いガソリンは精製、出来んかったので燃料室の温度を下げる必要があったのでエンジンの混合気(ガソリンと空気の混合) の通り道に水と凍結防止にメタノールを混ぜたものを噴射してたと言うこっちゃ。
210番さんご指摘ありがとうございます。
この手の話では説明をしている本人は難しい話をしているつもりはなくても読み手の多くの方々には専門的過ぎるとしてわかり難いというご意見が出ることは良くあることなので出来るだけ噛み砕いたわかり易いかたちで説明していましたが私の説明にもわかりにくいところがあったならお許し下さい。
以後も出来るだけより一層わかり易くするように心掛けますので、ごめんなさい。
訂正やな
↑で燃料室=燃焼室が〇やな。
後なガソリン自体も混合気として燃焼室に吸入される事で冷却効果があるんや、せやからガソリンを濃くするとオーバーヒート防止の効果もあるけど当然、燃費は悪くなるんやな。
オクタン価の低いガソリンでスーパーチャージャーや排気タービンを作動させるにはガソリンを濃いめにセットする必要があって、これはパイロットが任意で混合比やブースト圧をシリンダー温度計でチエックしながら調整する場合もあったんやな。
エンジンの特性として、空中戦なんかのエンジン全開時では、ガソリンの消費が激しく、反対に巡航速度では、シリンダー温度を見ながらガソリンの混合比をオーバーヒート手前まで薄くしてより長い時間、飛行出来る訳で零戦では、熟練搭乗員が操縦するとおよそ12時間以上も飛んでいられたんやな。
そして零戦の水メタノール噴射装置の事やけど飛行実験では、芳しく無かったけど陸軍では、ほぼ同じエンジン搭載の隼3型で水メタノール噴射の実用化に成功しとるのやな。
零戦の場合は海軍用の栄型エンジンは石川島播磨で製造されたけど、プロペラのギアー回りにトラブルが発生し飛行中の零戦がプロペラを飛散させる事故が発生し、この対策に技術者の労力が向けられ水メタノール噴射装置まで手が回らんかったんやな。
零戦の水メタノール噴射は計画倒れや無くてタイミングが悪かったんやな。
0さんの説明も数字がたくさん並んでて解り辛いところありました。
でもそのように真摯な態度でコメント返されるとこれ以上は何もいえませんね。
それにしても権兵衛さんはもの凄く感じ悪いな。
関西弁でいえばどんなことでも自分のいうことが通ると錯覚している人みたい。
それはただの錯覚ですよ。
指摘されても自分を省みるところもないし誰に対しても上から目線。
スレ主さんに対してまでも上から見ている態度だし。
画像の提供は皆無な上に説明は解り辛い。
それを伝えても善処する姿勢すらない。
何でも自分が一番と思い込んでるタイプかな。
解り辛いコメントだけなら読んでもあんまり意味はないって感じです。
いずれにしても皆さん出来る限り解り易いコメントお願いしますね。
それでガソリンのオクタン価とエンジンの関係を簡単に要約すると、エンジン自体は、燃焼室の混合気の自然着火現象が発生するまでは、ターボなりで過給する事で無制限?に馬力アップする事が理屈では可能なんやな。
例にとると、かってのF1の世界でセナとプロストによって連戦連勝やったホンダのV6ターボ時代に技術者達はエンジンの燃焼理論を追究し、1500CCのエンジンでブースト二気圧時に2000馬力を発生したんやな。
勿論これは、戦闘機に例えると時間制限のあるミリタリーパワーと同じで、予選時の短時間だけ用いられる馬力やけどな。
二気圧とは、1472ミリバールの事で、因みに誉型エンジンのブーストは、設計では最大で500ミリやったんやな。
初期のホンダF1開発時には、かって中島飛行機で栄エンジン等の技術者やった中村技師も携わっていたんやな。
誉型エンジンの設計者やった中川技師は、戦後、プリンスと日産でレース用のエンジンを開発して活躍したんやな。
大戦中に頭の中では、高性能なエンジンを企画しても根幹的な技術問題やガソリン等の問題で今、一歩の所で終戦を迎え
た挫折感が後になりレーシングカーの高性能なエンジン設計の大きな原動力になったんとちゃうやろか。
ワイは勿論、専門家と違うけどスバルや日産のターボエンジンを自分でブーストアップを行い、そのエンジンの排気音の向こうに栄エンジンや誉エンジンの吼吠が聞こえような気になるんやがな。
216の兄ちゃん、まぁそう言うなよ。
ワイの関西弁はよつばからのスタイルやがな。
別に上から目線とかエラソーにとかの気持ちはあれへんがな、
って言うかよつばの時から、ストーカーみたいにようワイに絡んどったやろ。
まぁその調子でこれからもワイの相手になってくれや。
楽しみにしてるで。
↑案の定、コメントを読み終わってから何の話だったのかを考えてみると結局は零戦や軍用飛行機にまつわる説明というよりは自分の自己自慢話。
直接指摘を受けてもそんなこというなよでごまかし反省なんて微塵もない。
こんな時の関西弁って便利ですな。
たいがいものごとの本質が軽く聞こえるから悪気はなかったように聞こえるからね。
ちなみにストーカーって何のこと?
自分のことがいつも必要以上に注目されているように思えるのは自意識過剰、っていうか異常。
敵も多かったとか誰かが書いてたが敵は必ず多くなる性格のようですな。
三拍子以上良くないものが揃い過ぎているようですからね。
少しは自分について考え直したほうがいいよ。
210のアンポンタン兄ちゃんな、予想しとった通りの嫌コメやの。
ターボエンジンのブーストアップが自慢てか?アホちゃうか。
そんなもん車がいじるの好きな人間やったら誰でもやっとるこっちゃ。それを自慢としか思わん思考方に兄ちゃんの歪んだ人間性が端的に表れとるのとちゃうか。
あのな兄ちゃん、ワイの事が嫌やったらそれはそれで構わん、しかし嫌コメに終始せんとエンジンの燃焼理論にそった話で反コメをしたらどや。
ワイもエンジン工学の専門家から見たら素人やから燃焼云々のコメに突っ込みどころがあるかも知らん、そっちの方向から反コメしてくれ。 例えば栄12型エンジンのブースト圧とか
最適なオクタン価の数値とか、ここはそんなコメをする所やがな。
ほな210の兄ちゃんな次のコメが、またしても嫌コメに終始して単なるアホと言う事を証明するのか、
鋭いエンジンのコメでワイを唸らしてくれるのか、楽しみにしとるど。
また自慢だ。
栄エンジンがどうだのブースト圧がどうだのこうだのオクタン価がどうだのこうだのと結局自分の自慢話をしてドヤ顔してるだけだよな。
どこからどう見てもそのようにしか見えんよ。
自分が自動車用エンジンを改造しただのチューニングしただのという話を自慢したいだけじゃないか。
自動車の保有率が上がった現在だが様々な事情により自動車を持ちたくても持てない人たちは日本全国にた〜くさんいるんだぞ。
そのた〜くさんの人たちからするとあんたがグダグダ書いてるコメントは自己自慢話じゃなかったら何なんだ!?
零戦のエンジン関連ということばを借りた自分の趣味の自慢話だろうが!
自分のコメントの話の主旨を良く見てみたらいい。
自慢話にしかなっていないから。
人のことを馬鹿だの阿保だのいえばいいさ。
しかしここに指摘していることは権兵衛さんのコメントの真髄を突いた内容だからな。
本当の要点は自慢話をすることにあるのさ。
冷静に考えてみな、零戦のエンジンの話をするのに自分の自動車の改造話が必ずしも必要か?
全く無関係だよ。
本当に何の目論みもなくコメントしているのであれば純粋に零戦のエンジンの話だけをすればいいはずだ。
それが出来ないところに権兵衛さんの自己自慢話を抑えきれないエゴがあるのさ。
なんてったって自分が一番だという性格は隠せないね。
しょせん手前みその自己満足ね。
ご苦労さん!(笑)
権兵衛さんがそんなに自分の自慢話をしたくてしたくてしかたないのなら乗り物の四輪カテゴリーにスレ立てて自動車の改造話やらチューニング話とやらを思う存分自分の自慢話をすればいいんじゃないの?
どうだい正論だろ?
そもそも自動車のF1の話も別のジャンルの話だからね。
四輪カテゴリーで自慢しまくるのが正解だ。
アンポンタン兄ちゃんな、嫌コメに終始して自分のアホの証明をしてどないするねん。
ホンマに難儀なやっちゃのう。
日本のレーシングカーエンジンは、かっての航空機エンジンの技術的な系譜を受け継いとると言う話をしただけやがな。
自慢話がどうのこうのてホンマに頼むで もう少し賢くなったらどや。
ほなまた夜にでもしゃしゃり出るから楽しみにしとれよ。
関係もないのにいろいろこじつけて散々自分の自慢話しておきながら、改造しただのチューニングしただのそんな他人の自慢話誰も聞きたくないだろう。
零戦に興味はあってもどこぞの他人の自動車の改造話なんぞは誰も聞きたくないはずだ。
そもそも零戦の話とは全く無関係なのだからな。
自分の自慢話ではないというのなら証明してみな。
出来ないなら自信過剰な大嘘つきというレッテルを貼られるだけだな。
普通、スレ立てる時も他人様のスレにコメントする時も説明や解説となるコメントと併せてその主張を読む人たちにも各々で本当にそうかどうか確認出来るように参考資料の画像などを同時に貼るのが基本だが、権兵衛さんあんたはわかり難いコメントをただただ書くのみで(その内容はいわば自論の押し付け)コメントの内容が本当かどうか確認出来るような参考資料になる画像などを貼ったことすらないな!
卑怯といえば卑怯だし、言語明瞭意味不明瞭とはこのことですな。
権兵衛さんの主張のしかたなら本当かどうかの確認すら困難なようにわざとしてある。
全くもって透明性がない。
それは同時に信頼性がないと同じで信用しても良いという根拠がないのに等しい。
平たくいえば権兵衛さんのコメントは読む人に根拠の確認もさせず、自分のいいたいことをいうだけいって無責任なコメントを続けているだけにすぎない。
今までよく権兵衛ウザイといわれていただろう?
ちゃんと根拠となる参考資料となる画像などを提示して正々堂々とするべきだろうな。
的を得ているだろう?
図星だからな。
夜にしゃしゃりろかと思たけど、もう一言だけ付け加えとくわな。
アンポンタン兄ちゃんな証明、証明て既に自分のアホの証明を嫌コメでしとるから証明はもうエエがな。
兄ちゃんは、かってのよつばのアホ馬鹿漫才でワイにフルボッコされたバカンチの残党かいな。
あのな自慢云々とか置いとてやな、ヘルシアの兄ちゃんが水メタノール噴射て何かとの問いに、Oさんが学術的に解説したコメの補佐的な感じで、出来るだけ解り易く説明しとるのやがな。
それを難しいて解らんと言うのは、アンポンタン兄ちゃんのオツムのオクタン価が低いからとちゃうやろか。
水メタノール噴射の話、自体が極めて専門的な分野やど、それを解り易く説明するのに自分の経験や様々な事例を用いるのは、至極当然やろ。
アンポンタン兄ちゃん自体もインタークーラーの装備してない排気タービンの話をワイに降るから、自分なりにコメを返しとる。
アホ馬鹿の応酬やったら別のスレでなんぼでも相手にしたるがな。
ここはヘルシアの兄ちゃんのスレやから
スレ題に沿ったコメをして、荒らしのような不様な真似は、エエ加減にしとけ。
ほなスレ主のヘルシアの兄ちゃん、お後よろしい頼んまっさ。
これまで資料画像の一枚も貼らず好き勝手放題のコメントだけしていい逃げしてた弁解はいりませんよ。
弁解は何度聞いても無意味!
大風呂敷広げるならそれ相応の参考資料画像を貼りなさい!
そして自分の自慢話をしていたわけではないとしらをきるなら信用出来るという根拠を示し証明しなさい。
出来ないのならやはり自信過剰なだけの大嘘つきというレッテルが貼られますね。
それからフルボッコだか何だか知りませんが人を自分の都合のいい人物に仕立て上げるのはやめてもらいたいものですな。
相手のことを何も知らず自分勝手に見下して失礼極まりないことばかりいってる愚かさを認識しなさい。
荒らしみたいなことをするのは権兵衛さん自身の裏の姿ですよね。(笑)
権兵衛さんの十八番は盗るつもりなんてありませんよ。(笑)
権兵衛さん、0さん、 そして、みなさん、![]()
![]()
私は、零戦は外観だけしか知らず、大変勉強させて頂きました、
自分の車のボンネットあけても 何が何だか解りません、![]()
私は過去![]() では、軍糧(1回だけ投稿)、ニュース糧は覗いた事もありませんでした、
では、軍糧(1回だけ投稿)、ニュース糧は覗いた事もありませんでした、
しかし凄い方々がいるもんです、
ヘルシアさん、みなさん、こんばんは。(^O^)/
水メタノール噴射装置のことで一ついい忘れていたことがありました。
長所は書いたものの短所を書くのを忘れていまして異常燃焼防止と出力増加は良い点ですが燃焼室内に水を噴射して使うことにより各シリンダーの内壁やピストン自体に腐食が発生し易くなる点が短所である悪い点です。
普通に考えてもエンジンを構成している主な材料である金属は水分により錆びる性質があることはみなさんも良くご存知の現象です。一般的に金属はただ加熱しただけでもそのまま放置しておいただけで周りの大気中の空気の成分や湿気と反応し自然酸化膜(錆)が表面に出来上がります。
そしてエンジンの場合は普通に使っていても加熱と冷却を頻繁に繰り返すことになるためその現象は起こり易くなります。
以上のことを考えると自分の車のパワーアップに水メタノール噴射装置をと考えていた人が居たならやめておくことをお勧めします。
ほなまたウンチクを言うたろか。
市販車の水噴射装置は富士重工(スバル) のインプレッサーなんかにターボの冷却用インタークーラー本体に水噴射装置が標準装備されとったな。
水は、水道水をそのまま使用して確か寒冷地では、不凍液を添加したんやな。
水噴射装置は普通のプッシュ式のスイッチがあって、オンにすると必要に応じ自動で噴射される構造で、かっての中島飛行機として隼や紫電快のエンジンを製作したメーカーである事を彷彿させるんやな。
ほんでやワイのコメを見た、オツムのオクタン価が極めて低いアンポンタン兄ちゃんが脳内デトネーションを起こして、意味不明な事を喚き散らしよるんかの。
ほなお次 アンポンタン兄ちゃんのデトネーション的コメントを期待しとるで。
注 脳内デトネーションとは、普通では見る事の出来ない不可視な燃焼理論等を読むと脳細胞にアドレナリンが分泌され、覚せい剤使用に類似した状態になる事やねん。現在の医学では治療法が見付かっていなく、ネット環境から遠ざかるのが良しとされとるがな。
訂正 紫電快を紫電改に。
ほんでやデトネーションとは、Oさんも説明してたけど燃焼室の異常燃焼の事でピストン、コンロッド等に深刻なダメージを与える現象やねん。
脳内で発生すると暫しクルクルパーになりよるんやな。
私の 一番好きな画像です
零戦が米空母に体当たり寸前、
↓↓
まぁ何と言うか、上の写真は空母エセックスに突入する艦爆発 彗星やな。
二枚目は戦艦ミズーリに命中寸前の零戦で惜しむらくは、爆弾を搭載していなかった為か、戦艦の厚い舷側に跳ね返へされてかすり傷を付けただけやってんな。
ほなまたウンチクな。
特攻攻撃を彗星と零戦の機種別に比較すると艦爆機である彗星は、機体の爆弾槽に 爆弾を収納する事ができ急降下爆撃として的確に米艦船に命中させる機体で、照準器も急降下時に軸線を敵艦に的確に合わせるような微調整可能で、特攻機としては、最も高性能な機体やってんな。
一方の零戦は250キロ爆弾を搭載して急降下の機動を行うとオーバースピードとなり操縦不可能となるので艦爆専門の操縦要項に沿った訓練が必要やってんな。
さすが、権兵衛さん
おそれいります(≧ω≦)
空母エセックスに突入する 彗星と。
戦艦ミズーリに命中寸前の零戦でしたか![]()
戦艦ミズーリと言えば
無条件降伏署名した、戦艦?、
調印式には、かの幕末の黒船来航の時の星条旗(現在よりも☆の数が少ない)
を 戦艦に飾ってあったとか、
皆さんこんばんは。(゚▽゚)/
ヘルシアさんの232番の画像の一枚目はもう少しいうなら太平洋戦争当時の日本の海軍航空技術廠が設計開発し愛知飛行機が生産することとなった艦上爆撃機彗星を三菱製金星空冷星型エンジン搭載に改良した三三型です。
チノエアショー2013での彗星三三型の復元機の写真。
倒立V型液冷式エンジン搭載型の彗星一一型の写真を貼ります。
参考に見て下さい。
艦上爆撃機彗星についてもご他聞に漏れず、当時関わっていた人たちが大変に苦労させられた話はたくさん語り継がれています。
艦爆彗星が掲載されている書籍類を見るか艦爆彗星と入力して検索すればそのことが良く判りますよ。
国からのバックアップを受けて知識を学び、国からのバックアップを受けて購入した設備機材を使うことが出来た海軍の機関である航空技術廠が日本で使い得る最新技術と最新設備機材を使い設計開発した新型機をさあ量産してくれといわれ後の責任を一手に背負うかたちになった民間会社とその関係者はさぞかし大変だったろうことは想像に難くありません。
国防のために最も良い新型機を作ろうとした愛国心は判りますが設計開発した機関が最後まで責任を全うして量産まで行うのであればどこからも文句は出ません。
しかし実際には国の財力に支えられ最新技術で完成させた新型機を何でも自前の費用で行わなければならない民間会社に後を引き継がせる、航空技術廠より古い設備機材しかなく劣勢であることが判りきっている民間会社に後を引き継がせるという無謀さが見えて来ます。
本当ならば海軍の機関と民間会社との大きな環境の差を考慮するのが正しい行いのはずでした。
しかし時代の風潮は物事の分別は後回しにして軍がやれといったらやれという無謀極まりない状態でした。
その証拠として戦争が終わり平和な時代となってから当時の関係者が口々に本当にあったこのような話を話し語り継いでいるわけです。
これは氷山の一角でしかありませんが官(国の役人や軍人)による民間(一般人)への横暴を示す一つの実例です。
このような実話は単にエンジンの話だけに留まらずたくさんありました。
違うと思う人は太平洋戦争関連の書籍類やネット上に記されている書き込み類を見てみられたら大変勉強になるという以上のものが必ず得られますよ。
ほなまぁ軍部への批判は、置いといてやな、彗星自体が敵戦闘機を振り切れる艦上爆撃機として、実験機の性格をも持ち合わせた機体で、設計は海軍の技術機関関である空技厰が担当したんやな。
零戦よりも高速で画期的な性能要求に答える為、メッサーシュミットに搭載されているダイムラーベンツのDB601型 液冷エンジンのライセンス生産を決定し、機体は、油圧方式から電気式に変更され、これまで油圧で操作していた箇所をサーボモーターで稼動する方式に改め、整備の簡素化を計ったものやったんやな。
量産化に当たっては、DB601の液冷エンジンを生産する愛知飛行機が機体製作も担当する事になったんや。
一般的に実験機同様の機体を民間会社にその量産を無理強いしたような印象があるけど、製作の難しい機体を海軍側が技術的に自信がない民間会社に一方的に強制するはずも無く 、打診を受けた愛知飛行機としてもやや困難と思える内容でも会社経営の見地からしたら受注を受けて利益を上げようとするのは、自然の成り行きやな。
彗星の試作機は、所定の高性能を発揮したけど、量産化に際しては、新機軸に付きものの様々な不具合が発生し、また実用化途上でミッドウェイ海戦に偵察機に改修された彗星が敵索任務で活躍したものの母艦と共に失われる事態や、戦局の悪化に伴い実用化への技術指導をすべき空技厰に技術者派遣の余裕が無くなり部隊配備が遅れに遅れたんやな。
さらに実用化され部隊配備された後のバッテリ容量不足に起因した電動装置の不具合や、水冷エンジンの取り扱い不慣れにより稼動率は低くかったものの、愛知飛行機製のDB601型エンジンは、同じく川崎で製作された同型エンジンより比較的、高品質な材料が使用できた為にエンジンの熟成化が計られて行き、川崎では量産に失敗した性能向上型の同型エンジンもどうにか実用域に達したんやな。
部隊配備された当初は新しい機構に慣れていない為に稼動率は低くかったものの愛知飛行機の技術者による担当整備兵への的確な整備要項の教育により稼動率が向上し、その高速性の為、搭乗員にも高性能機として評価された機体やったんな。
航空機に違わず兵器そのものは、常に性能向上をして行くもので試作機の場合は、それまで熟成された技術を土台にさらなる高性能に挑む必然性があって、その為には未知の技術や発展途上の新機軸を追求するのは、当然であり、技術的基盤や、あらゆる物資や人的要素に恵まれた
米国であれば未知なる高性能への挑戦は、日本より遥かに高条件であったんやな。
逆に日本では全てが米国に劣る中で技術者達の優れた資質による骨身を削るような努力で未知なる高性能に挑んでいった訳でここでは純然たる技術的な内容に終始し、軍部の技術的行政の不甲斐なさは別の機会にコメントをしたいとワイ個人としては、そう思うねんな。
最後にスレ主のヘルシアの兄ちゃんのおかげでエンジン等の突っ込んだ話が出来て面白かったわ、
オオキニな。
太平洋戦争当時は何か軍の意向に合わないことをいうと貴様はお国を守っている軍人に盾突く気か!?
とくるのが当たり前の時代でした。
こんな横暴な特権をかざしていたのが日本の軍でした。
ということで当時空軍はなかった日本では特権をかざす勢力として陸軍と海軍がありました。
当然特権をかざすもの同士は自分たちの方が一番だと自負していたため陸軍と海軍は非常に仲が悪い存在でした。
それを如実に裏付ける外国での実話が残されています。
日本は当時同盟国だったドイツからダイムラーベンツDB601倒立V型12気筒液冷エンジンのライセンス生産権を買い国産化したエンジンを戦闘機用エンジンとして使っていました。
しかし国産化されたのは陸軍用は川崎製のハ-40、海軍用は熱田二一型と別々に国産化されていました。
普通に考えるとライセンス生産権を一回買って両者ともそれを参考にして国産化されたのだろうと思いがちですが、そうではなく非常に仲が悪かった陸軍と海軍はライバル心を燃やし陸軍用は陸軍が金を払い海軍用は海軍が金を払い、一つのライセンス生産権を買うのに重複して二つ分の金を払って別々に購入していたのです。
日本の陸軍と海軍は国としては同じ一国なのだから共同購入したらいいじゃないかとドイツからいわれたにもかかわらず両者とも頑として聞き入れず結局一つのライセンス生産権購入にそれぞれが金を払うというバカバカしいことを実行してしまい、ナチスドイツのヒトラー総統からは日本の陸軍と海軍は仇同士なのか?
と笑われたそうです。
現在の話であればマスコミからのバッシングの嵐に曝されるのは間違いない種類の話です。
発動機ではなく彗星の機体の話に話を戻すと生産関係者は大変苦労させられたということは既に書きましたがその中でも大きな実例でいうと生産だけは愛知飛行機に責任を持たされたわけですが軍からの命令を受けて以降も航空技術廠から全部の設計図は届かず長い間一部の設計図しか届いていない状況が続きました。
そして設計図が一式揃った後も空中分解などのトラブルが起きる度に航空技術廠で改設計が行われ、改設計が行われる度に改設計分の設計図がなかなか送られて来ないというにっちもさっちもいかない状況に立たされ生産の責任を持たされた関係上、生産関係者は非常に迷惑したという事実が語り継がれています。
総じていえることとして軍は国防に懸命になった愛国心はあったものの現実問題として見通しの甘い部分が数多くあったということ。
その見通しの甘さのせいで多くの者が迷惑し苦労し最悪の場合は命まで奪われたのでした。
権兵衛さんのいうハ-40や改良版のハ-140より熱田二一型や改良版の熱田三二型の方が順調に推移したという主な理由は陸軍と海軍の差にありました。
陸軍はオリジナルのDB601ではコンロットなどにニッケルコーティングをして作ることとあったにも関わらず希少金属であるニッケルを使うことを禁止しました。
一方陸軍よりはいろいろな物資を保有していた海軍ではニッケルを使うことを許していました。
ニッケル使用を許された海軍用エンジンはコンロットなどにニッケルコーティングを施すことが出来たため焼き付きなどのトラブルが起き難い状況にあったわけでした。
これも陸軍の見通しの甘さが原因でした。
権兵衛さん、0さん、
こんばんは![]()
![]()
![]() 、
、
権兵衛さん、ありがとう彗星、まったく知りませんでした、
零戦より少し先が尖ったイメージですね、
また当時の政治学、軍対民間の争い
零戦は 日本の歴史の1つですが、枝葉がいろいろわかれます、
開発に当たって、軍と製造業者との意見の違い
知覧の特攻の話し
日本、アメリカ、ドイツの飛行機の差
などなど、話はつきませんね、
私にとってはこのスレで 一回り大きくなりました、まだまだ教えて下さい
ヘルシアさんこんにちは。
(^O^)/
水メタノール噴射装置に関連して第二次大戦中のヨーロッパでのドイツ軍機の話を一つ。
第二次大戦末期ともなるとドイツ軍占領地域の領空であっても夜昼問わず連合軍戦闘機が我が物顔で飛び回る状況でドイツ軍機にしてみれば単機で飛行するのは非常に危険でした。
そんな中、フォッケウルフFw190の設計者クルトタンク技師は技術会議出席のために自らが設計開発したTa152H型の試作機を操縦して飛行中にアメリカ軍の二機のノースアメリカンP51ムスタングと遭遇し襲い掛かられそうになりました。
しかしタンク技師がMW50水メタノール噴射装置を作動させるとTa152H型試作機はみるみる間にノースアメリカンP51ムスタング二機を引き離し無傷で無事帰投したという話が残されています。
この時のアメリカ軍パイロットはまたドイツが怪物のような戦闘機を作り出したのかと思い驚いたそうです。
ちなみにMW50水メタノール噴射装置使用時のTa152H型試作機の最大速度は高度12500mで765Km/hというスピードでした。
0さん、こんばんは![]()
![]()
![]()
ドイツの水メタノール噴射装置、Ta152H型試作機知りませんでした![]() 、
、
画像ありがとうございます、
全体的に細身ですね、
ヘルシアさんこんにちは。(^O^)/
ちょっと人聞きは悪いのですけど戦争兵器のことを知ることは全ての道とまではいいませんがほとんど全ての道に繋がる知識を勉強することに近いです。
人は戦争をすることで歴史を積み重ね発展して来ました。
戦争を知ること戦争兵器を知ることはその過程で必然的に世界情勢、歴史、政治、経済、衣食住に繋がる知識にも触れることになります。
以上のことから人聞きは悪いけど戦争兵器を知ることは大変有益です。
私が勉強した限りでいうとドイツの兵器は陸海空いずれの場合も派生型が非常に多く、合理主義に照らしてその中から何かを選び選抜して生産を行う傾向が強いです。
その分、切り捨てられお蔵入りするものも多い。
話をフォッケウルフFw190〜Ta152Hに戻すと設計者のクルトタンク技師は設計技師でありなからパイロットという異色の逸材でメッサーシュミットBf109の補佐役としてフォッケウルフFw190を開発することになった時も希望するエンジンを供給してもらえないなどの政治的嫌がらせにもめげず立派に開発を成し遂げました。
戦争末期になってTaを戦闘機名に付けることが軍から認められたのはタンク技師の功労が認められた結果でした。
珍しいダクテットスピナー装備のFw190最初の試作機の画像と数多い派生型を省略し代表的なFw190シリーズの画像を貼ります。
開発は下から上への順番です。
Fw190をベースにしてここまで変貌させ高性能にしたのは全く驚きです。
おまけに尾部には木製素材を使い幅広のプロペラブレードは多方向から木材を接着した合板を使用していましたからまた驚きです。
0さん、ありがとうございます、
クルトタンク技師、設計技師でありなからパイロットBf109〜フッケウルフFw190へ、政治的嫌がらせ
ドイツ軍マニアには、たまらない画像でしょうね
ここでまた、私の好きな画像です、
空母は、権兵衛さん、0さん、の言われる
エセックスだと思います
画像は、誰だか解りません
2枚目は、よく本にある画像ですね、
上の写真は、第72振武隊の特攻隊員達で子犬を抱くのは、若干17歳の荒木軍曹やな。
回りの隊員達も18歳から19歳までの少年飛行兵達で、昭和20年5月下旬、出撃前の僅かな時間に、写真の子犬の面倒を整備兵に託して機上の人となり 沖縄本島海域に特攻出撃、米駆逐艦に突入し、護国の英霊となられたんやな。
統率の外道と称された特攻作戦やけど、その攻撃により甚大な人的被害を被った米機動部隊のハルゼー長官曰く、彼我の戦力差を考えた場合、特攻作戦は最も効果のある作戦であったとの事やったな。
皆さんこんばんは。
(゚▽゚)/
太平洋戦争の後半戦で日本の若者たちが自分の命と引き換えに体当たり攻撃で敵を倒そうとした神風特攻隊。
これを立案推進した軍の上層部の人たちの中にも無責任なままにしなかった人たちもいました。
今回はこのことについて書きます。
終戦直後、宇垣纏海軍中将は彗星三三に乗りアメリカ海軍の艦艇へ特攻をかけて最期を迎えました。
この件については若い命を従えて同行させ無駄死にさせたなどの批判の声もありましたが多くの若者を特攻させてしまった命令をした指揮官の立場として自分の命をかけてまで責任をとったその行いは他の軍上層部の連中に比べれば天と地ほどの差があり、偉い行いだと思います。
作戦としては外道としながらも特攻隊の立案推進をした大西瀧治郎海軍中将も終戦直後に切腹自殺をしました。
多くの若者を特攻させた責任をとっての切腹自殺であり介錯を拒んだため5時間あまり苦しんだ末に亡くなりました。
太平洋戦争当時、好き勝手放題なことをして特権を振りかざしてばかりの軍部の者たちがいた。
これは誰が何といおうとも事実です。
しかしそんな中にあっても物事を無責任なままにしなかった立派な軍人さんたちもいたことを忘れてはならないでしょう。
参考画像として
昭和20年8月15日、艦爆彗星三三型に乗り特攻して行った宇垣纏海軍中将、その直前写真。
大西瀧治郎海軍中将の写真。
大西瀧治郎海軍中将の切腹自殺を掲載した新聞記事。
を貼ります。
このように特攻にかかわった人たちの命をかけた戦いのお陰で今の日本がある。
そう思うと手を合わせずにはいられません。
ちなみに命を引き換えに体当たり攻撃で相手を倒そうとする攻撃方法の世界的代名詞となった神風ですが、これを行ったのは日本が最初ではなく初めて行ったのはソ連軍でその名は「タラーン」奇しくも神風と似た嵐という意味でした。
権兵衛さん、ありがとうございます、
第72振武隊の特攻隊員達子犬を抱くのは、17歳の荒木軍曹。
写真の子犬の面倒を整備兵に託して機上の人となり 沖縄本島海域に特攻出撃、米駆逐艦に突入し、護国の英霊となられた。↑↑
知りませんでした、感服です、「神風特別攻撃」は、世界では、賛否両論ある中で、我々日本国民は、特攻して逝った方々に対して……。涙が出て言葉がつまります、
0さん、いつも画像ありがとう、
宇垣纏海軍中将の特攻。
特攻隊の立案推進をした大西瀧治郎海軍中将の切腹自殺。
私は零戦の内部(特にエンジン等)
はさっぱりわかりません![]() が、
が、
今回の0さんと権兵衛さんの コメントは大好きです、
日本の真珠湾攻撃は、
目標は、米艦隊と軍用施設で(日本のアジア進行は別として)
アメリカの日本本土の攻撃は 女 子供を含む
無差別攻撃と思います
戦勝国 だから?
戦後の 東京裁判で
映画「私は貝になりたい」では、
悔しい思いしました、
ここで、今まで見た映画の中で、私の好きな映画
ラストサムライ 渡辺謙
ほたるの墓 アニメ
日輪の遺産 堺雅人
明日への遺言 藤田まこと
壬生義士伝 吉村貫一郎
中井貴一
私は貝になりたい
フランキー堺
切腹 仲代達也
レッド・サン 三船敏郎
シンドラーのリスト オスカーシンドラー
眼下の敵 ロバートミッチャム
永遠の0←まだみてません
まだまだたくさんありますが、思い出したらまた書きます、
私は もう年ですから、
古い映画ばかりですみません![]()
![]()
![]() 、
、
ヘルシアさんこんにちは。(゚▽゚)/
戦争映画について、今であれば隔週刊 東宝・新東宝 戦争映画DVDコレクションというのが書店などで販売されていますね。
当然のことながら最新の戦争映画は含まれていませんが過去に公開されたいろいろな戦争映画のDVDが比較的安い金額で手に入ります。
通常のこの手のシリーズにありがちなシリーズ全部を揃えないと意味を成さないということもなく、これはと自分が思った作品の時だけ買っても何ら問題ありません。
ちなみに私は創刊号(創刊号だけは通常号の約半額)の連合艦隊と二号目の日本海海戦は買いました。
後は作品名を見て買う買わないを考えようと思っています。
いずれにしても普通にDVDを買うより安いです。
そして映画解説本も付属です。
こういうのもいいですよね。
0さん、![]()
私も 探して買いたいです連合艦隊、日本海開戦
いいですね![]()
いろいろ所で、探してみます、
ヘルシアさんこんにちは。(゚▽゚)/
零戦燃ゆ、も販売予定のラインナップ内に含まれてましたよ。
それから販売予定ラインナップの中には戦時中に作られた有名な映画も多数含まれているようです。
21世紀の空を飛ぶ零戦小隊の画像を貼ります。
先頭を飛ぶのがプレーンズオブフェイム博物館の零戦五二型(世界で唯一オリジナルの栄エンジンを搭載して飛行可能な零戦)、二番目がロシアで新造再生された零戦二二型の一号機、三番目がその三号機です。
ロシアで新造再生された零戦二二型はオリジナルの栄エンジン1130馬力(排気量27.3リッター)より直径が7.4cm大きく重さが118kg重く排気量は約29.9リッターあるプラット&ホイットニーR1830ツインワスプエンジン1200馬力を搭載しています。
機体外板もオリジナルの零戦より厚くしてあり強度が上がっているといいます。
この三番目を飛んでいる零戦二二型は日本人がCEOを勤めるゼロ・エンタープライゼスというアメリカの会社が所有しており、今年中にも日本への里帰り飛行プロジェクトを計画していてその後日本へ移管し動態保存も計画しているらしいです。
この新造再生零戦二二型三号機の日本里帰り飛行プロジェクトは予定では三月に一旦日本へ里帰りし、その後アメリカへ戻ってから夏頃に再び日本へ里帰りして、その後は日本各地での航空ショーなどで飛行する姿を披露してまわり寄付金や興行収入などで機体の維持管理をしながら日本で動態保存していこうという計画なのだそうです。
アメリカのゼロ・エンタープライゼスという会社はこのプロジェクトのために設立された会社なのだそうです。
尚、もしも日本やアメリカの政府や行政機関などからの圧力により計画がダメになった場合は集めた寄付金は寄付者へ全額返却するとう予定まで決めてあるそうです。
運良く運べば日本各地の自衛隊の航空祭やエアフェスタなどでこの零戦の飛行シーンを何度も見られるかも知れませんね。
楽しみです。
ジェット戦闘機の飛行シーンの撮影に比べたらプロペラ機なら確実に良いシーンが撮れますよ。
カメラ、ビデオカメラを用意しておかないと。
スピードが遅いといっても零戦の場合はこれがまた持ち味であり艦上戦闘機であることから考えると優秀な戦闘機ということになります。
軽量化や空力形状の優秀さや翼端捩り下げの妙技の結果、型にもよりますが離陸滑走距離は179〜200m以内であり着陸速度は119〜138km/hでも失速せずに着陸が出来るという性能でした。空母の狭い飛行甲板上で使用される艦上戦闘機としては極めて優秀でした。
馬力があり高いスピードが出せたため優秀だと評されたアメリカ陸軍のノースアメリカンP51ムスタングはこの使用条件には適合させることが出来ず艦上戦闘機としては失格となりました。
アメリカ海軍のチャンスボートF4Uコルセアも馬力があり高いスピードが出せるとして優秀だと評されていましたが空母の飛行甲板上での運用にはなかなか適合させることが出来ず長い間てこずり後々やっとのことで艦上戦闘機として採用されることになりました。
その間、チャンスボートF4Uコルセアがモタモタしている間にグラマンF6Fヘルキャットにアメリカ海軍の主力艦上戦闘機の座は奪われていました。
これらを考え合わせると艦上戦闘機としては短い距離で離着陸出来ることと低い速度域でも墜落せずに飛んでいられる能力は非常に重要な項目でした。
零戦の優れた性能は空戦能力だけが特別視して語られがちですが艦上戦闘機としての基本性能もかなり優秀であり他の戦闘機が同じように真似ようとしても簡単なことではなかったようです。
高いスピードを出せる戦闘機はとかく着速が速すぎる速すぎるとよくいわれます。
その原因は高い馬力のエンジンは大半が重い。
重いエンジンを搭載したことで翼面荷重が高くなるため着速を下げると墜落し易くなる。
墜落しないようにするために着陸速度を速くせざるを得ず結果的に離着陸距離も長くなるという悪循環なのでした。
ふわりと浮かんだような画像はプレーンズオブフェイム博物館の零戦五二型です。
0さん、ありがとうございます、
日の丸 プロペラの零戦、画像見ると、胸が熱くなりますね、
素晴らしいです
私はまだ 零戦が飛んでいる、姿は見たことありません、
楽しみですね、
映画
「連合艦隊司令長官、山本五十六」
TSUTAYAで借りました、
戦艦大和 の雄姿
連合艦隊←×
聯合艦隊←〇
訂正です、
おお〜
いいですね〜
ヘルシアさんこんばんは。
(゚▽゚)/
電波探信儀(レーダー)が未装備だし、最上級重巡洋艦改装に伴い撤去、大和級戦艦に移設した15.5cm三連装砲が四基装備された状態のようですから初期の頃の大和級戦艦の勇姿ですね。
大和級戦艦が最もシンプルな姿をしていた時期のものです。
その後は航空機が優勢だという戦闘事例が次第次第に多くなり、装甲板が無いに等しい重巡洋艦の主砲塔を艦橋構造物の前後左右に設置しているのは被弾時は被害の危険性が非常に高いとして左右の15.5cm三連装砲塔は撤去され、代わりに対空機銃類を針ネズミのように装備するように改装されて行くこととなりました。
これも時代の流れでしょうね。
今では世界中どこを見渡しても戦艦を建造する国も使用する国もなくなってしまいました。
現代ではミサイル類が急速な発達を遂げていますから、もうそろそろ現代版の戦艦の復活があってもいい頃なんですが、どこの国も建造しませんね。
大和級戦艦の二番艦、武蔵を艦首方向から撮影した写真を貼ります。
就役前の公試運転時の撮影です。
↑世界最大の艦載砲である46cm砲の砲塔がドデェーンと腰を据えています。
現在でも世界最大というのは変わっていません。
当時の軍事機密保持の努力が凄まじかったためアメリカ軍もこれが46cm砲であったことを知らず、戦後になって初めて真実を知ったようです。
大和級戦艦は最大の武装を出来るだけコンパクトな船体に搭載することを主眼に設計されました。
実際は満載排水量72000tもある世界最大の戦艦でしたがアメリカ軍は何度も偵察写真などを撮影していたにもかかわらず満載排水量40000t程度の戦艦だと見誤っており、これも真実を知ったのは戦後になってからのことでした。
当時の日本人の努力により敵はことの真相を掴めずにいたことになります。
大和級戦艦であっても数百機もの航空機攻撃の前には遠からず沈められたであろうことは確かですが、敵の装備の真相を知らないままに交戦していたアメリカ軍は一歩間違えば大損害を被っていた可能性はありました。
天候が良い状態で戦艦同士の撃ち合いをしていたらアメリカ海軍の戦艦は多数が撃沈されていたでしょう。
何せ、アメリカ軍は大和級戦艦が世界最大の主砲を搭載した世界最大の戦艦だなどとは思ってもいなかったわけですから。
一歩間違えば大損害だったわけです。
さすが0さん、
大和の画像は、ミッドウェー海戦で、途中から引き返す 所を 撮りました、
装備で、いつ頃の大和か わかるのですか、
おみそれいたしました、おそらく0さんの家は
戦争の本でいっぱいでしょうね、![]()
大和級の、46センチ砲を
全部、真横(90度)に向け同時一成に発砲したら
大和はひっくり返ると
聞いたことがあります、
本当でしょうか?
日露戦争時代だと、
大和は 天下無敵だったでしょうね、
ここで、ミッドウェー海戦、 大東亜戦争の分岐点ですね。携帯サイトに在りましたので↓↓
日本本土を爆撃された日本の海軍は、ハワイ諸島の西、アメリカ海軍の中継基地になっているミッドウェーを攻撃することでした。
当時太平洋にいた日本とアメリカの海軍の戦力は以下の通りでした(あくまでも太平洋にいた数だけ)。
日本ー アメリカ
空母 8 ー、3
戦艦 11ー 0
重巡洋艦 17ー 7
軽巡洋艦 7 ー1
駆逐艦 70余 ー11
戦力は圧倒的に日本のほうが上回っていた。この戦力差をミッドウェーに差し向けて普通に戦えば楽勝だった。ところが、結果は日本の連合艦隊は赤城、加賀、飛龍、蒼龍の航空母艦4隻を撃沈されて完敗を喫し。それどころか優秀なパイロットを三百数十名も失ってしまった。
空母は攻めるのは強いが攻撃されると弱い。だから空母には戦艦以下を張りつけて護衛に当たるのが常識ですが、日本がミッドウェーに向かわせたのは空母4隻とおざなりの護衛艦隊だけでした。
また、空母4隻だけでなく、そのはるか後方500キロを戦艦大和などにミッドウェー方面に向かわせてました。なぜ、4隻の空母に張りつけて護衛させずに、500キロ後方を航行させていたのか。
戦艦大和は世界最大だけでなく、設備も装備も世界最新鋭だった。アメリカが空母4隻からなる日本の機動部隊を発見し、迎撃せよという命令を発する無線を日本はいち早く傍受していた。ところがその内容を4隻の空母には何も伝えていない。
500キロも離れていたため当然ミッドウェー海戦には間に合わず、空母4隻が全滅したという知らせを聞いて空しく引き返すという間抜けなことをやっている。もともと戦艦大和はミッドウェー海戦に参加するつもりなどまったくなかった。ではなぜ500キロもの後方でミッドウェーに向かうような航行をしたかといえば、一応戦闘に参加したという格好をつけるためだった。瀬戸内海にいては、階級が上がるキャリアにもならないし、戦闘参加手当ても出ない。そこで昇進の機会と戦闘参加手当てを得るために、そんな工作をしていたというわけです。
ミッドウェーはアメリカにとって勝てるはずのない戦いだったが、この海戦がアメリカが勝利するための分岐点だった。ミッドウェーでアメリカが負けていたら、ハワイは持ちこたえられないから、アメリカは全軍をカリフォルニアに集結して防衛に当たるしかなかった。そうするとヨーロッパには手が回らないからイギリスはドイツに降伏する。となるとアメリカはヨーロッパでも太平洋でも勝てず、講和を結ぶしかなかったかも。
日本海軍のマヌケな行為により大東亜戦争の勝利が消えてしまった。
こんな大失態を演じたにもかかわらず、機動部隊司令長官も連合艦隊参謀長も失脚すらしなかった。日本の官僚の無責任は今に至るまでまったく変わっていない。
ミードウェー開戦と同時期に行なわれたアリューシャン列島作戦で、アメリカは零戦をほぼ無傷のまま手に入れた。撃墜された飛行士は戦死したが、飛行機はほとんど完璧な姿のまま着陸していたのだ。
それまで零戦は無敵だった。制空権が勝敗を分けるといわれたこの戦争で、零戦はいつでも日本軍を有利に導いていた。その零戦をアメリカはくまなく研究し、新鋭機器の開発と大量生産に没頭することになる。零戦の優越性が失われるのも時間の問題となってしまった。
ミッドウェー海戦で熟練した飛行士が多数戦死し、さらに零戦がアメリカに研究されたことで相対的に日本の戦闘機の性能が劣ってしまった。この状況が、悲劇の神風特攻隊を生むことになる。
↑上記 は 携帯サイトの コピペです、
日本海軍の判断ミスがあったかもしれません、
亡くなった 英霊の方々 またミッドウェー海戦後に亡くなった日本人約300万人の方々(非武装民間人も含めて)
手を合わせて頭を下げざるをえません、
真横に向けて主砲を一斉射撃したらひっくり返るかどうかはわかりませんが映画などでよくある一斉射撃シーンは海上に浮かぶ艦船対艦船の対戦では実際にはほとんど行わないと思います。
行うとしたら角度を考慮した上での陸地に向けた地上攻撃シーンに限られると思います。
海上に浮かぶ艦船という限られた小さな目標に対しては実際には一斉射撃はあまり行わないというのは一斉射撃すると各主砲の発砲の爆風がお互いに悪影響を与え合い着弾位置にズレが生じるため、(主砲射撃の爆風がお互いの弾道に悪影響を与え合うのを防ぐために時間差発砲をさせるための装置が備えられていたはずです。)たくさん砲撃されたという恐怖感を敵に与えることは出来ますが命中しない弾が多数という結果となり得られるメリットは多数の砲弾による威嚇のみとなります。
おまけに檻に入れた小動物を甲板上に置いておき主砲の射撃をするとその際の爆風の圧力により死んでしまうという実験結果もあるので自艦の搭載機材や搭載機や搭載艇が壊れる危険性も十分ありました。
それを防ぐために大和級戦艦の場合は艦尾部分に工夫を凝らした作りを採用していました。
主砲射撃を行う際には特異な作りの艦尾部分に搭載機や搭載艇を収容してそこを爆風シェルターとして活用するように考えられていたほどでした。
大和級戦艦というのは世界的にみても戦艦建造時代の最後期に建造された艦であるためシンプル且つ様々な工夫を凝らしてあり良く出来た艦となっていました。おそらく光学測距装置が活用出来るような良い天候で戦艦同士で主砲の撃ち合いをしたらアメリカ、イギリスの戦艦でも装甲が厚く射程距離が長く威力の大きい46cm砲弾を持った大和級戦艦に勝てる艦は無かったであろうと思います。
日本が大艦巨砲主義に走ったきっかけは日清戦争を目前にした時期に日本より優勢な戦艦群を持ち日本への牽制をしていた中国海軍(当時の清国海軍)の脅威になんとかして対抗しようという切羽詰まった状況がありました。
しかし大和級戦艦という世界的にみても究極の大艦巨砲主義にまで辿り着いた日本でしたが実際の戦争で大艦巨砲主義の艦艇が大成功をおさめた事例は残念ながらありません。
どの戦争の時も勝敗を左右する働きを演じたのは他の兵器でした。
艦橋上から艦首方向を撮影した写真
・大和級戦艦の二番艦である武蔵。
・アメリカ海軍の戦艦ミズーリ。
・イギリス海軍のネルソン級戦艦。
を貼ります。
ヘルシアさんが書かれた内容それもその通り正しいと思います。
確かに心血を注いで研究開発し作り上げた大艦巨砲主義の艦艇を温存しよう温存しようという考えが軍の上層部の中に根強くあったのは事実です。
温存しておいた虎の子兵器(大艦巨砲主義の艦艇)で大国ロシアを破った日本海海戦の時のような華々しい戦闘で戦争の勝敗を決定着けようと夢見ていたのは確かです。
しかし軍用機でも軍艦でも戦闘車輛でも共通なこととして速度の遅い種類の仲間が一緒に行動している場合、遅いものに歩調を合わせるしかなく結果として戦闘部隊の機動能力を落としてしまうこととなります。
近代戦争というのはいろいろな機種の連携による作戦が必要不可欠です。
空母という軍艦は基本的には自艦の速力により合成風を作り出し艦載機の発艦を助けなければならない関係上、建造当初から高い速度性能を与えられているケースがほとんどでした。
戦艦という軍艦は元々は速度が遅くてもそれが普通と思われていた艦種であり空母と同等レベルの速度を持った高速戦艦は数的には少数派でした。
その高速戦艦に分類される戦艦たちはいずれの艦も巡洋戦艦と呼ばれる戦艦の装甲を薄くした分、高速度が出せるようになった艦でした。
速度の速い空母に随伴して護衛することは出来るが敵の戦艦と主砲の撃ち合いをした場合は命中弾を受けると非常に弱く直ぐに倒されてしまう程度の装甲しか持ち合わせていませんでした。
アメリカ海軍のアイオワ級戦艦ミズーリは速度が速く高速戦艦でしたが装甲面ではさほど強力ではなく、もしも大和級戦艦と直接主砲の撃ち合いをして被弾していたら非常に脆かったはずです。
実際にはアメリカ海軍の空母戦力が多数あり大和級戦艦と戦艦ミズーリが砲撃戦をするほどの距離に近付くことはありませんでした。以上のことも作戦計画に影響を与えた可能性は非常に高いです。
高速○○と呼ばれる軍艦を除いて考えると軍艦というものは基本的には駆逐艦や軽巡洋艦や重巡洋艦や空母はその任務遂行上の必要性から高速であり二十数ノットから三十ノット前後出せるのが普通でした。
それに比べ戦艦は二十数ノット前後が普通で三十ノットを超えるものは数的には少数派でした。
潜水艦は更に遅く水上でも十八ノット程度、水中では十ノット程度しか出せませんでした。
現在の潜水艦は水上と水中の速度が逆転し全般的に速度性能も向上し水中でも二十数ノットから三十数ノット出せるものまであります。
その各種軍艦の艦種による世界的な当時の常識を逆手に取った独特な戦略が第二次大戦中のドイツにありました。
第一次大戦に敗戦し負けたドイツにはいろいろと不利な制限が課せられていました。
新生ドイツ海軍には当然持っていいとされる軍艦の総排水量の割り当てが少なく制限されていました。
戦争に勝った国々の都合のいいように制限を課せられていたわけでした。
そこでドイツが考えたのが俗にいわれるポケット戦艦の建造でした。
ポケット戦艦とは多数の小型の潜水艦Uボートを使用した戦略と同じく通商破壊戦を展開し敵(主に永遠の宿敵イギリス)を兵糧攻めに遭わせるための装備でした。
ポケット戦艦とは重巡洋艦よりは遅いが重巡洋艦より大きな主砲を持ち、戦艦よりは小さい主砲だが戦艦よりは速い速力を持った特異な小型の戦艦でした。
要は普段は武装を持たない敵国の輸送船を見付けては撃沈し、敵重巡洋艦と遭遇した場合は敵重巡洋艦より大きな主砲の力で敵を撃沈する。
敵戦艦と遭遇した場合は戦艦より速い速力を利用して逃げるという使用方法をコンセプトとして計画建造された小型戦艦でした。
当事者のドイツ人にしてみれば真剣に取り組んでいたことなのですが、一見すると滑稽にも見える種類の戦艦でした。
0さん、初めて見る画像です、ありがとうm(__)mです、私でも書物読むより、分かりやすくありがとうございます、
0さんの言う 刻々と変わる、新型兵器 新型戦艦
当時日本は 大和や武蔵が日本の誇りであり、日本の象徴として、温存したかったみたいですね、
何かの本で読んだのですが、
世界三大無用長物
(でかいばかりで役にたたない)
①ピラミッド
②戦艦大和
③6気筒直列エンジン?
とか、
無用の長物というのも努力を注ぎ保有して持っていた当事者とただ外部から見て知っただけの部外者からすると受け取り方は大きく異なるので押しなべて一律とはいかないでしょう。
立場の違いで受け取り方は様々なのでどれが一番正しいというのはないのかも知れません。
大和級戦艦に代表される大艦巨砲主義の艦艇ですが当時は世界中の常識が大艦巨砲の戦艦をたくさん持っていることが現在でいう核ミサイルをたくさん持っていることと同じだったため、その国の国力と威信を示すバロメーターだったのです。
世界中の有識者の大半が有り得ないと主張していた航空機による攻撃で戦艦を沈めるという方法を世界に先駆けて実証した日本海軍でしたが当の日本軍内部にも大艦巨砲主義を崇拝する勢力が多く存在していました。
軍上層部の大多数の人々には未来のビジョンが見えていなかったため、たとえ正しいことを主張していても風変わりなことを主張する者は変人扱いされて邪険にされていたわけでした。
日本軍内部では全体の兵器体系でいうと大艦巨砲主義が有力で戦闘機でいうと一撃離脱方式の戦闘機よりも巴戦オンリーの戦闘機が有力とう凝り固まった考え方の状態でした。
改革派より保守派が牛耳る世の中だったということでしょう。
艤装中の戦艦大和
昭和十六年九月二十日
呉軍港
の写真を貼ります。
よく見ると艦首方向までよく写っています。
艦首方向の向こうがドックの出入口ですが何かカーテンのような物で仕切られています。
戦艦大和関連の書籍類に事あるごとによく出て来る棕櫚縄で編まれた巨大カーテンの目隠しです。
外から大和の船体を見られないように隠し、周辺の高台や山々には憲兵などを多数配置し警備して機密保持に心血を注いでいたらしいです。
当時、このために棕櫚縄を大量に買い付けたため棕櫚縄が希少な物になり市場から棕櫚縄が消えうせてしまうという現象も引き起こしていました。
ちょっと感の鋭い人なら一般人でも今何か起こっているようだなと気付いたでしょうね。
戦争の前触れとはそういう日常生活の些細な変化から読み取れるといいますから。
予算の消費や物の買い占めや大量の人員の動員など大和建造に費やした全ての労力を考えると無駄遣いといわれても仕方ないところもあるかも知れません。
しかし当時はそんな時代だったとしかいえませんね。
戦艦大和の場合は広島の呉でしたが二番艦の戦艦武蔵の場合は長崎、長崎でも同様にして機密保持に心血を注いでいたそうです。
近くを通る列車も造船所の近くを通過する際は常時乗車していた憲兵の命令で造船所側の窓はカーテンを下ろし見えなくするように徹底されていたそうです。
棕櫚縄の件など直接その地域に住んでいなくてもちょっと頭を働かせれば何か普通ではないことが進行中なことが想像できるくらいですから近隣地域の人たちは公な場では口には出さないけど知っていました。
書き忘れていました。
↑の添付写真の画面右側に写っているのは空母鳳翔の艦首部分です。
空母鳳翔は日本初の空母であり世界初ともいわれています。(掲載書籍次第で書かれ方が違い世界初ではないとするものもあります。)
いずれにしても世界的に航空母艦が誕生し始めた初期に建造された実験空母的性格の空母です。
日本海軍はこの鳳翔を使って船体や甲板や艦上構造物や艤装品などなどどういう物をどういうかたちで装備するのが一番最良なのかを試行錯誤しながら実証実験してその後の空母建造に役立てたのでした。
艦橋や煙突もどの場所にどんな風に設置したら一番良いのかもこの実証実験結果から決定されていきました。
そういう歴史の流れがあり空母の艦橋や煙突は右舷艦首寄りに設置するというのが常識化しています。
それは現在でも世界的な常識となっています。
空母開発の過渡期に建造された空母は左舷に設置している艦も存在しますが極めて少ない稀な艦といえます。
0さん、![]()
画面右側、空母鳳翔、言われるまで気づきませんでした、日本初の空母であり世界初ともいわれています。掲載書籍次第で世界初ではないとするかも?
↑
初めて知りました、
戦艦大和は今もなお、沖縄の近くに海深く沈んでいるようで、
なんとか 今の日本の技術で引き上げられないのでしょうか?
戦艦三笠の記念艦が
あるとききます、
ヘルシアさん、おはようございます。(゚▽゚)/
鳳翔でいろいろな改造を施してはまた改造し直して実験を繰り返し日本の空母は進化して行きました。
そして巡洋戦艦から改造された空母赤城や改長門級戦艦から改造された空母加賀は最初は重巡洋艦の主砲用の20cm連装砲を二基搭載した三段空母として造られ後に通常飛行甲板の空母へと大改装されました。
これも三段式飛行甲板の使い勝手を試す大いなる実験でした。
世界的にも空母開発の過渡期に建造された日本の空母、赤城、加賀、蒼龍、飛龍、翔鶴、瑞鶴などはそれぞれいろいろな艦橋配置、煙突配置になっています。
この時期も日本独自に考え出した方法で船体側面から下方へ湾曲させた煙突を出し排気ガスに海水を混ぜて放出し排気ガス温度を下げ煤煙を抑え着艦する艦載機の妨げにならないようにする工夫を凝らしてありました。
同じ時期に商船や他の艦種から改造された空母も概ね同様(飛行甲板上には艦橋を設けず飛行甲板下に艦橋を設けた艦も少なくありませんでした)。
そしていろいろと試行錯誤を重ね、やがて日本空母独自の形が定まり造られたのが煙突と艦橋を一体構造物として右舷艦首寄りに設置し煙突を26度外側に傾斜させ煙突トップが飛行甲板上から17mの高さになるようにしたものでした。
この型式で完成した空母には飛鷹、隼鷹、大鳳、大和級戦艦からの改造空母である信濃がありました。
この型式は日本独自なものでした。
飛鷹と隼鷹で実験的に試し、その後大鳳と信濃に導入されました。
大鳳と信濃はどちらもあっけない最期を迎えましたが新機軸を盛り込んで期待を背負った空母でした。
どちらも従来から空母という艦種の最大の弱点だった木製だけの飛行甲板をやめ、敵機からの爆弾命中の爆発にも耐えられるように主要範囲だけながら装甲化した飛行甲板を装備し航空攻撃に撃たれ強い空母となっていました。
これはミッドウェイ海戦で被った四空母喪失の時の反省点を反映した結果だったのかも知れません。
運用構想としては最前線でも装甲化した飛行甲板により敵機の爆撃に耐えて艦載機の離発着を敢行し攻撃を続行、ミッドウェイ海戦の時のように不幸にして母艦を失った友軍機がでてもその友軍機をも収容して攻撃を続行させるという運用用途を想定して建造されていました。
太平洋戦争当時の建造でしたが大鳳はエンクローズドバウと呼ばれる艦首の形をしており現代のアメリカ空母のような艦首形状でした。
ちなみに当時イギリス海軍でも同じような形状をしたハリケーンバウを採用していました。
イギリス海軍では大鳳と同じく飛行甲板の装甲化も図られており、装甲化によって大鳳と同様に格納庫容積は減少していましたが日本軍機の特攻機が飛行甲板に命中してもたいした被害を受けず残骸を排除して直ぐに戦線復帰出来ていました。
同じように日本軍の特攻機が飛行甲板に命中した場合に修理が必要な状態になっていたアメリカ海軍の空母とは歴然とした差がありました。
戦艦大和の引き揚げは残念ながら難しいでしょうね。
何故かといえばアメリカ海軍は二番艦戦艦武蔵を沈めた際に何百機もの攻撃機を使って世界の戦艦史上最大の被害が出るような攻撃をしましたが、なかなか沈まないこの一隻の戦艦に舌を巻いていたといいます。
この時のことを教訓にして戦艦大和を攻撃する際には左舷側ばかりに魚雷や爆弾を集中させ攻撃して傾斜を復元させる大和級戦艦の注排水機構の能力を奪い沈めました。
そして沈む際には弾火薬庫の誘爆と水蒸気爆発が起こり船体中央付近から二つに折れて分離して沈んでいるので引き揚げは難しいといわざるを得ません。
仮に出来たとしても費用が途方もない額になるでしょうね。
0さん、こんばんわ〜![]()
![]() 、
、
空母の「煙突」考えた事ありませんでした、![]()
おかげで かなり勉強しましたよ![]() 、
、
戦艦の時代は終わり、
空母の時代、ですね
まさに 日本の江戸末期の刀、槍 の時代が終わり、鉄砲の時代に変わる、と同じです、
旧日本海軍が誇る、「戦艦大和」
大和に搭載された 九四式45口径 46センチ主砲
三連装砲搭を3基
3万メートル先の40センチ装甲板を貫く、しかもバランスよく配置、
口径 460ミリ
径長 45口径
砲身長 20、7メートル砲身重量 165トン
弾丸重量 1、46トン
最大仰角 45度
最大射程 4万1852メートル
↑↑
私の本から抜粋です
しかし凄い世界最大戦艦、ですね米軍が見た時はビックリしたでしょうね、
ヘルシアさん、こんばんは。(^O^)/
戦局の悪化により結局は中止となったのですが、大和級戦艦の主砲を上回る主砲の開発も予定されていて50.8cm砲を開発して連装砲塔で三基搭載し長10cm連装砲を対空対艦両用砲として複数基搭載、船体規模は大和級戦艦とほぼ同じに据え置く新型戦艦を建造しようと考えていたようです。
紀伊という艦名まで考えてあり次の艦の名前まで尾張と予定されていたようです。
大艦巨砲主義支持派の方々は大和級戦艦では満足していなかったようです。
試射でひびが入りダメでしたが、既に大正時代には48cm砲の試作を行っていましたから技術的素地はある程度あったようです。
一方アメリカ海軍もモンタナ級という大和と同規模排水量で40.6cm三連装砲塔四基を搭載する戦艦を計画していましたが時既に戦艦の時代でもなかろうという判断から計画は中止されました。
0さん![]()
大正時代に既に48センチ砲、試作とは 凄いですね、
紀伊、尾張、ならあとは 水戸で 徳川御三家ですね
ヘルシアさん、こんばんは。(゚▽゚)/
現在の海上自衛隊での艦名の名付け方は旧日本海軍からすると違ったりしていますが紀伊や尾張のようなそんな名前も将来また使われるかもですね。
外国の海軍では人の名前を付けたりしますけど日本では人の名前は付けませんね。
沈んだ時に縁起が悪いし国民の士気も低下しますから。
戦艦紀伊と尾張は大和級戦艦と同規模の船体に50.8cm連装砲三基と長10cm連装砲を多数搭載と書きましたがこの長10cm連装砲がまた高性能でした。
最初に防空用の秋月級乙型駆逐艦の主砲として使用され迂闊に近付いたアメリカ軍の爆撃機コンソリデーテッドB24リベレーターだったかB25ミッチェルだったかをいきなり三機も撃墜したため、アメリカ軍から特に警戒対象とされていました。
この長10cm連装砲は口径が60口径か70口径ほどもあり長い砲身によって対空用にも対艦船用にも使える両用砲でした。
その良い評判から搭載を予定されたのだと思います。
戦艦紀伊が実現されていたらこんな姿という模型の画像を貼ります。
実現出来なかった計画艦大和級戦艦の発展型→戦艦紀伊とくればアメリカ海軍の計画艦戦艦モンタナの資料も貼っておきますね。
戦艦モンタナの完成予想模型と二面図です。
モンタナ級戦艦は50口径40.6cm三連装砲を四基、合計十二門搭載でそのぶんアイオワ級戦艦より大型化し日本海軍の大和級戦艦に匹敵するサイズの排水量となる予定でした。
日本海軍の46cm砲や50.8cm砲に対するアメリカ海軍は40.6cm砲と劣勢に見えますが50口径という長い砲身と搭載砲門数の多さ、そしてスーパーハードシェルとよばれる新型の砲弾で日本海軍には十分対抗出来ると踏んでいたようです。
モンタナ級戦艦は全般的に見るとアイオワ級戦艦(アイオワ級戦艦はアラスカ級大型巡洋艦に近い考え方で造られており戦艦と対決することも望まれながらも速い速度性能を利して空母機動部隊の護衛任務もこなすことを望まれていた巡洋戦艦に近い戦艦でした。)の拡大発展版ですがアメリカ海軍戦艦の長年の伝統を初めて破りパナマ運河の幅を超える艦幅になるよう計画されていました。
それでも大和級戦艦の艦幅よりは細身でした。
アイオワ級戦艦は一般的には大和級戦艦のライバル的戦艦であったように表現されることが多いです。
しかし実際にはアイオワ級戦艦というのは33ノットという空母と同レベルの速い速度で空母機動部隊に随伴してまわり空母を護衛することが主目的の戦艦であり仮想敵に据えていたのは大和級戦艦ではなく高速戦艦に分類される日本海軍の四隻の金剛級でした。
元々は巡洋戦艦であり後に戦艦へと艦種変更された金剛、霧島、比叡、榛名でした。
この四隻の内、一番艦の金剛だけはイギリスのビッカース社に発注して建造され、その後の三隻は日本で建造された金剛級の姉妹艦でした。
明治以来長らくイギリスに依頼して建造してもらっていた輸入戦艦もこの金剛が最後でその後日本は独り立ちして自前の力で戦艦をはじめとした軍艦を建造して行くことになりました。
この金剛級戦艦群は30ノットを超える高速度が出せたため大切に温存される傾向の強かった日本の他の戦艦とは違い非常に重宝がられて酷使され太平洋を縦横無尽に活動してまわることとなりました。
アメリカ海軍はこの金剛級戦艦群に自分の空母機動部隊が狙われることを恐れ対抗出来る空母護衛任務用戦艦を建造することを急務としていたのでした。
とどのつまりがアイオワ級戦艦が仮想敵に定めていたのは27ノット程度の速度しか出せない大和級戦艦ではなく30ノットを超える高速度で空母機動部隊に迫ることが出来る金剛級戦艦群だったのでした。
戦艦は古い種類の軍艦だといわれるのが一般的になってしまいましたが、戦艦が持つ大口径主砲の大きな火力にものをいわせ島にある敵の飛行場に延々と艦砲射撃を加え破壊してしまう運用方法を世界で初めて実践して見せたのも日本の海軍でした。
当時これは戦艦の新たな利用方法でした。
この時も移動速度の速い金剛級戦艦群は重宝がられ多用されました。
金剛級戦艦群は本当にお疲れ様な船たちでした。
頭が下がります。
0さん![]() 、
、
戦艦紀伊、まるで大和そっくりですね、
大口径砲の場合は、
弾頭と薬嚢(ヤクノウ)での発射で、薬莢(ヤッキョウ)は存在しないようで、別々なんですね、発射まで大変だったでしょうね、
マシンガンや高射砲のように、連発しない
アメリカは 50口径
とは驚きです、
画像は 二種類の弾頭と
薬嚢(ヤクノウ)です、
ヘルシアさん、こんにちは。(゚▽゚)/
ほとんどの戦艦の主砲はヘルシアさん言われた通り砲弾と薬嚢と呼ばれる袋に入った発射用火薬を砲身に詰めて発射していました。
薬嚢の量を増やしたり減らしたり砲身の俯仰角を変えたりして射撃で飛ばす距離を変更していたようですね。
私も昔は全ての戦艦の主砲はそうなのだと思っていたのですが一部には薬莢を使うものも存在していたことを数年前にはじめて知りました。
先日お話した第二次大戦中のドイツ海軍のドイッチュラント級ポケット戦艦がそれで基準排水量11700t(あくまでも表向きだけだと思われます)の船体に主砲として52口径28.3cm三連装砲を二基搭載していてこの主砲の砲弾が薬莢式でした。第一次大戦で敗戦国となったドイツは戦勝国に都合良く作られたベルサイユ条約を突き付けられ保有してもいいとされる軍艦に細かな制約を加えられており、この艦を建造する時も旧式の退役する軍艦の代わりの艦として建造してもよろしいとされたものの排水量は1万トン以下で搭載する主砲の大きさも口径28cm以下でなければならないなどという軍備抑制策を課せられていました。
それでドイツが考えに考えて出来上がったのが通商破壊戦に特化した通称ポケット戦艦と呼ばれるドイッチュラント、アドミラル・シェーア、アドミラル・グラーフ・シュペーの三隻でした。
ドイツはベルサイユ条約に従い排水量は1万トン以下に抑えたと公表していましたが、ぱっと見ても1万トン以下には見えませんし1万5千トン前後はゆうにいってるようにしか見えません。
当時みんなもそう思っていたことでしょう。
その二番艦アドミラル・シェーアの52口径28.3cm主砲の砲弾の薬莢の写真とジブラルタル海峡での二番艦アドミラル・シェーアの写真を貼りますね。
当時直接遭遇する可能性があったのはアメリカ海軍の軍艦ではなく、敵となるのはほぼイギリス海軍の軍艦のみでした。
当時のイギリス海軍の戦艦は22ノット程度のスピードしか出せなかったため、ばったり出くわしても26ノットという優速を利して易々と逃げることが可能で、逆に重巡洋艦に出くわした場合は敵は最大でも20cm砲しか持っていないので楽に敵重巡洋艦を圧倒し撃沈することが可能でした。
誠に「自分に課せられた不利な制約を逆手にとった」素晴らしいドイツ独特の戦略でした。
ドイツのポケット戦艦の戦略は↑に書いた通りですが、いろいろな海上航路の近辺をうろうろうろつき邪魔者が居なくなれば本来のお仕事である通商破壊活動に専念し武装を持たない輸送船を探しては沈めまくり永遠の宿敵イギリスを兵糧攻めに遭わせるという日常でした。
それを可能とするために船体にはアルミなどの軽金属を使い軽量化して航続距離を長く出来るディーゼルエンジンを動力とし当時としては斬新な技術を惜しみなく投入した小型戦艦となっていました。
大和級戦艦も計画当初は長大な航続距離が得られて敵弾を被弾した時にも火災になり難い機関であるディーゼルエンジンを動力にしようと考えられていました。
しかしこれらの長所を持ちながら大和級戦艦の船体という巨体を十分に動かせるだけの大出力のディーゼルエンジンを作るのは当時の日本にとってはかなりハードルが高く動力の不調という不安材料を抱えるよりはここは手堅く従来型の機関を採用しようということになり結果として優秀とはいい難い最大速力や航続距離になりました。
その点を考えると当時としては大型艦用のディーゼルエンジンを実用化出来ていたドイツはさすが技術立国という感じです。
単純な比較の一例として同じ従来型の機関を使っていても実用的に使用出来るエンジン内部の燃焼温度の高さの違いを見較べれば日本とドイツでは歴然とした差が存在しました。
燃焼温度を高く設定して使っても問題が発生しないということはそれだけ基礎技術レベルの水準が高いということでありそれだけエネルギーを引き出せる効率が高く高出力エンジンにもなるということです。
ドイツよりも低い燃焼温度で運転しないと直ぐに異常をきたしたということは残念ながら日本の技術レベルがドイツよりも低かったという証です。
構成部品の材質や加工精度が技術的にも劣っていたということでしょうね。
当時の日本の細かな基礎工業技術レベルの水準がドイツよりかなり劣っていた端的な事例としては潜水艦がありました。
ドイツは第一次大戦の時代から第二次大戦に至るまで世界中に名が知れ渡っていたUボートという潜水艦で世界中を震え上がらせたことで有名です。
基本的にドイツの潜水艦は小型高性能で大量生産型の潜水艦、日本の潜水艦は大型で大量生産向きとはいえない潜水艦でした。
大きさだけでいえばこの二国の特徴は現在でも同じ傾向を継承しています。
当時違っていた二国の差は基礎技術力の差による基礎的な性能差でした。
太平洋戦争当時秘密裡にドイツに派遣された遣独派遣団の日本の潜水艦は途中で連合軍に沈められたものも多くやっと辿り着けた潜水艦もありました。
日本の潜水艦は元々は第一次大戦でドイツから戦利品として譲り受けた潜水艦、ゲルマニア造船所で造られたUボートの研究から発達した大型の外洋型潜水艦で当時ドイツで主流だったUボートの倍以上の大きさでした。
船体が大きいということはたくさん物を搭載出来るため遠くの海まで進出して活動するのには有利でした。
しかし当時の日本の基礎工業技術レベルはドイツより劣っていたためネジ一つから船体に至るまで質が良くありませんでした。
ドイツ占領下のフランスの軍港にやっとのことで辿り着いた日本の伊號潜水艦は出迎えてくれたドイツ軍のスタッフに後から「これでは海中に潜航しながら大声でここに居るよ〜と叫びまくっているのと同じだなあ」とわれたそうです。
それだけ日本の潜水艦が出す海中ノイズは酷かったそうで闇夜の提灯状態(敵に直ぐに狙い撃ちされるような状態)だったそうです。
そしてドイツと取引した品々を搭載して日本へ帰国する際にはこのままの状態ではあまりに酷すぎて直ぐに敵に居場所を探知され沈められてしまいますよというアドバイスを受けドイツの技術スタッフによりノイズ防止の対策を施してもらい帰国したそうです。
艦内にある架台へのエンジンのマウント方法から何から何まで様々な部分に改良とアドバイスをしてもらうほど基礎的技術レベルに大差が存在していたようです。
昔、潜水艦の多くの技術を教えてくれた先生の母国を訪問してまた再び先生からいろいろと教えてもらったという感じですね。
0さん、素晴らしいコメント
感服しました、
ポケット戦艦、←これも勉強しました![]()
ここで
第二次大戦中 の拳銃及びライフル、マシンガン
(代表的な)
ドイツ
ワルサーP38
ワルサーP08
モーゼルK98(ライフル)
シュマイザーMP40
ワルサーPPK
アメリカ
ガバメントM1911-A1
トンプソンM1A1
M1カービン
日本
南部14年式自動拳銃
94式自動拳銃
38式歩兵銃
↑
だいたいの各国の使用銃 です、
まだまだたくさんありますが、
訂正
ワルサーP08←×
ルガー P08←〇
拳銃はあまり詳しくありませんが、画像を貼りますね。
南部十四年式拳銃です。
南部十四年式拳銃は大正十四年採用だそうで実に21年間も現役として使用されていたようですね。
0さん、![]()
一枚目の画像は
南部14年式 の前期型と
後期型ですね、
後期型は トリガーガードが 少し前に膨らんでいます、手袋したままで、人差し指が入れやすい、引き金を引きやすい
零戦から 話がそれてしまいました、![]()
零戦を誕生させた
堀越二郎ですが またその部下の技術者たちによる、
堀越は群馬県出身
東京大学 航空学科 昭和2年卒業
同級生5〜6人理系の秀才と共に、三菱に入社
2年後ドイツ、アメリカと渡りました、航空設計の勉強、当時の技術者としては最優秀、この時零戦の主務者で30代半ば、
チームとしては、計算担当、機体構造、動力装置、兵装、降着装置の各2名この中の一人東条輝雄は戦後、我が国で唯一開発された旅客機YS11の、
主務者を務め、その後
三菱重工の社長、
ちなみに彼は東条英機首相の ご子息だとか、
ヘルシアさん、おはようございます。(゚▽゚)/
海軍の三菱零戦にならび活躍した戦闘機として陸軍の中島一式戦隼がありますが、その中島飛行機㈱で一式戦闘機隼や二式単座戦闘機鍾馗の設計に携わっていたという糸川英夫技師のコメント映像を見たことがあります。
糸川英夫技師は日本のロケット開発の父とも呼ばれた人で太平洋戦争後はロケット開発で日本の宇宙開発に多大な貢献をしたことで知られた人物でした。
つい何年か前に探査機を使って移動している小惑星上に着地し小惑星の砂を回収して地球へ持ち帰るという世界的快挙を日本のJAXAがやってのけましたが、糸川氏の日本の宇宙開発における多大な貢献からその惑星探査機にハヤブサという名前が付けられたり、探査する小惑星がイトカワと名付けられたりしています。
そのコメント映像の中で糸川氏は隼や鍾馗の開発をした時期前後の話から当時の苦労話までいろいろと語られていました。
そしてその中には零戦を開発した三菱の堀越二郎技師の話や零戦の話も出て来ました。
糸川氏がいうには同じ戦闘機設計技師という同業者として見ると堀越氏は非常に真面目でキッチリやらないと気が済まない性格の人だったと。
堀越氏が設計した零戦はドイツのゲッチンゲン大学のプラントル教授の翼の理論というのをキッチリ守って設計されていると。
堀越氏は非常に真面目な人だから優等生的にキッチリ守って設計されてますねぇ。
といわれていました。
無理難題ばかり命令して来る軍側と渡り合いながら隼で苦労し、また隼とは真逆の性格の戦闘機鍾馗でも苦労した糸川氏は私だったら真面目にキッチリ理論を守って設計するというのは出来ませんといわれていました。
糸川氏は隼の前の陸軍主力戦闘機である九七式戦闘機でも陸軍側から無理難題の命令を突き付けられて大変苦労したことも語られていました。
とにかく技術的な理論だけを守っていたら軍側から突き付けられて来る無理難題の命令には対応出来ないといわれていました。
技術者たちが「やっちゃダメよ」ということは必ずといっていいほどいうことを聞かないのが軍でしたと。
禁止されたことは守らないのに何か問題が起きると技術者たちを呼び付け「お前たちの会社が作る戦闘機は不良品じゃないか!」と怒り付ける人がほとんどだったというお話で、今でいうところのモンスタークレーマー(執拗に文句ばかり付けて絡んで来る客)みたいな存在だったようです。
時は折しもノモンハン事変から太平洋戦争と戦争の続く時代真っ只中でしたからたとえ正論であっても一言でも口答えすると「貴様はお国を守る兵隊さんに歯向かう気かあ?」となるのがごく当たり前の時代だったそうです。
上から順番に中島一式戦闘機隼、二式単座戦闘機鍾馗、晩年の糸川英夫氏の画像を一枚貼りますね。
中島飛行機㈱は現在のスバル自動車の前身の会社。
中島飛行機㈱は中島知久平という人が社長だった会社。
陸軍の一式戦闘機隼は九七式戦闘機の後継機で海軍の零戦に近い設計思想で造られ零戦に類似した性能を示した巴戦に強い戦闘機でした。
隼が搭載していたエンジンは八-25といい零戦が搭載した栄一二型エンジンの陸軍バージョンでした。
二式単座戦闘機鍾馗は海軍の三菱雷電と同じ用途を目指して造られた対大型爆撃機用の迎撃用戦闘機でした。
鍾馗も雷電と同じく高い最高速度と高い上昇能力を第一優先に設計されたため爆撃機用の直径の大きな空冷エンジンを搭載した割に主翼面積が小さい作りの戦闘機でした。
陸軍も海軍もスピードを最重要視した迎撃用戦闘機を要求しながも高い空戦能力も同時に要求したため鍾馗は蝶型フラップを装備、雷電はファウラーフラップを装備して小回りを効かせられるように設計されていました。
同じような条件、同じようなコンセプトで造られた両機でしたが、中島の鍾馗は大きな機首から後ろに向けて急激に絞り込んでいく設計、対する三菱の雷電は大きな機首を紡錘形に整形した設計で、どちらの設計も設計技師たちの独自な個性が滲み出ていました。
結果的には終戦後に両機ともアメリカ軍にテストされ、鍾馗も雷電も迎撃用戦闘機としては最高な戦闘機だと高い評価を得ていたそうです。
世界中にその名前を知らしめた日本の零戦。
それは良くも悪くも日本人の歴史と国民性を代弁している存在だといえます。
零戦に代表される日本の軍用機の特徴は今なお日本に日本人に受け継がれている。
その証拠に現在に至るまで日本人が作る様々な製品は同じような傾向を持っています。
一例として上げるなら車でも家電品でもタフとは言い難いが軽量小型な割に燃費や消費電力が少ないものを作るのが得意。
そのような日本を代表するような零戦のことを語るならば当然、当時日本海軍の零戦と双璧を成していた日本陸軍の一式戦闘機隼を語らないわけにはいかないので中島飛行機㈱の一式戦闘機隼そして次いでに二式戦闘機鍾馗についても書きました。
しかし、そもそも一式戦闘機隼のことを書くならその前作の九七式戦闘機から始めなければなりません。
中島飛行機㈱で開発されたキ27九七式戦闘機は同時期の三菱九六式艦上戦闘機(零戦の前作にあたる)と共に空前の成功作機となり、これらの成功により日本は世界水準を超える戦闘機を自分で作り出せるようになりました。
日本はこの時期を境に研究用サンプル機以外の外国製戦闘機は一切輸入しなくなりました。
輸入しなくてもよくなったといった方が正しいでしょう。
その陸軍のヒット作戦闘機中島キ27九七式戦闘機の写真を貼りますね。
ノモンハン事変でうようよ湧いて出て来る大量のソ連製戦闘機ポリカルポフI-15やI-16をバッタバッタと叩き落としまくりました。
この時の陸上戦闘では日本が劣勢でしたが航空戦の空中戦では日本が優勢で圧勝していたといいます。
太平洋戦争直前から終戦までの間の主立った日本陸軍戦闘機は傑作機といわれた中島飛行機㈱の九七式戦闘機から始まり終戦間際の川崎飛行機のキ100五式戦闘機までとなります。
これは試作段階のものを除く実際に使われた戦闘機だけでこれだけになります。
僅か十年間で陸軍の戦闘機だけでもこんなにたくさんのものが開発され使用されました。
平和な時代に比べると戦時中は技術が加速度的に急激な進歩を遂げるといういい実例です。
敵と戦う毎に兵器を実戦使用するため不具合点が直ぐに浮き彫りとなり日々改良が繰り返されるため技術が急激な進歩を遂げるという流れです。
今のような平和に溺れた時代では想像もつかない目まぐるしさだったと思います。
参考資料として一連の陸軍戦闘機の写真を貼ります。
上から中島飛行機のキ43一式戦闘機隼、キ44二式戦闘機鍾馗、川崎飛行機のキ61三式戦闘機飛燕、中島飛行機のキ84四式戦闘機疾風です。
液冷式エンジン搭載機のため三番目の飛燕を除いて眺めると一式戦、二式戦、四式戦と中島飛行機製の戦闘機の発達の流れが良く見て取れると思います。
軽量化に徹した一式戦、極端に大きなエンジンと小さな翼で一撃離脱戦法に適するよう苦心して作られた二式戦、大東亞決戦機と呼ばれエンジンの大馬力化と小型化の両立により巴戦にも一撃離脱戦法にも強い戦闘機を目指して苦闘しなが作られた四式戦。
一見したところどれも同じように見られがちですが、よく見るとそれぞれの個性が輝いていて全くの別物同士でした。
0さん![]() 、こんばんわ
、こんばんわ
中島飛行機㈱が現在のスバル自動車の前身の会社とは知りませんでした、![]()
テレビ映画「連合艦隊」がありましたので、
録画して、いちぶ部分ですが、
昭和19年、最後の日本空母、
「ずいかく」
の船内で、
「瑞鶴」
失礼しました、
沖縄へ出撃する 大和
零戦のライバル
F6Fヘルキャット(グラマン社製)が大和に襲いかかる 発砲する戦艦大和
F6Fヘルキャットで正解かなぁ![]()
ヘルシアさん、おはようございます。(゚▽゚)/
日本が太平洋戦争に敗戦した後、日本を占領したアメリカは日本への戦後政策として「再び日本が好き勝手に戦争を始めないように」という策略から
・日本が持っていた兵器の破壊。
・日本の兵器に関わる工場や生産設備の破壊。
・日本の優れた技術者や権威のある有識者の公職からの追放。
・日本の大手メーカー、財閥の解体。
・アメリカによる現在の平和憲法の押し付け。
を行いました。
これにより様々な制約を受けたため戦闘機などを作っていた技術者たちも職を失い仕方なく鍋や釜を作って生活を食いつないでいました。
アメリカから禁止された物以外でと考えスクーターや自動車(最初の頃の開発車としてはスバル360ccが有名ですね)を作り始め、それを足掛かりに富士重工やその関連会社が出来、また寄せ集まって富士重工グループが出来上がったというところですね。
富士重工は現在では航空機開発から宇宙開発まで手掛けておりスバルは富士重工の自動車部門にあたる会社になります。
戦時中に中島飛行機㈱が戦闘機を量産していた跡地に現在のスバルの自動車生産工場もあります。
話変わって空母翔鶴の二番艦が瑞鶴ですが、翔鶴は武勲艦と呼ばれていた一方で瑞鶴は不運なことが多く被害担当艦などと呼ばれることもありました。
そして敵艦隊の目を逸らす目的で囮部隊として出撃する羽目になり沈んで行きました。
まだ幼顔の若い兵士が片道切符で敵艦に体当たりなんてとても悲しいですね。
ヘルシアさんの動画、戦艦大和の主砲発射シーン、これは主砲による対空射撃なので三式焼霰弾による敵機編隊への射撃だと思いますよ。
46cm砲弾の中に内蔵した無数の焼夷弾子による霰弾攻撃です。
密集体系で飛行して来る敵航空機編隊に効果的だとして日本海軍の巡洋艦や戦艦の主砲に採用された装備でした。
その三式焼霰弾の写真と三式焼霰弾の炸裂の様子を記録した資料写真を貼りますね。
それからこの時期(大和の沖縄特攻時)のアメリカ海軍空母の主な艦載機の写真も貼りますね。
上からグラマンF6Fヘルキャット艦上戦闘機、グラマンTBF/TBMアベンジャー艦上攻撃機、カーチスSB2Cヘルダイバー艦上爆撃機です。
0さんの おっしゃるとうり、ですね、
日本は昭和20年の終戦を迎えて、
ポツダム宣言受諾.無条件降伏により 日本にある、あらゆる
武器が廃棄されましたね
そのなかにも、日本刀もありました、
日本軍が持っているって事で刀剣は武器と言うことで進駐軍に没収、
で、軍隊が所有刀剣だけでなく、民間人の持っている刀剣も含むとポツダム宣言にあるそうで、
美術品であるか?
武器なのか?議論され
またそのどさくさ紛れて神社仏閣にある、文化財級の刀剣も、GhQが戦利品として持ち帰ったとか、
刀剣ファンの私としては残念でなりません、
私の趣味![]()
刀剣
日本史
戦争映画
ゴルフ
熟女![]()
皆さんはじめまして。『連合艦隊』私も好きです。中井喜一さんのデビュー作品です。写真は江田島市の海軍兵学校の『雪風』のアンカーです。
ヘルシアさん、こんばんは。(゚▽゚)/
先日行き着けのセブンイレブンで珍しく日本刀の特集本が売ってあったのでヘルシアさんの立てられていたスレのことを思い出し、つい買ってしまいました。
日本刀については曖昧でおぼろげなことしか知識がない私なので少しは勉強しようかなという前向きな思いです。
太平洋戦争で日本が敗戦した後、アメリカ人は日本からの戦利品をアメリカ本国に持ち帰り家族や知人にお土産としてプレゼントするのが流行ったようです。
中でも高い人気だったのが日本刀や旭日旗、日の丸の旗でした。
どの国でも戦争はしないのが一番です。
しかし戦争不可避なのであれば絶対に負けてはならない。
負けるような戦争は最初からしないのが一番です。
負けたら戦利品として何でも持ち去られてしまう。
そのことを歴史の実例で証明しているような事柄です。
きんたさん![]() 、
、
コメントありがとうございます、
中井貴一、かなり若いですね、デビュー映画でしたか、 「雪風」知りませんでした![]()
太平洋戦争直前から敗戦までの日本陸軍戦闘機の流れを説明した中で一旦、三式戦闘機と五式戦闘機のことだけ割愛していましたのでこれらについての画像を貼りですね。
上から
・三式戦闘機飛燕の兄弟みたいな試作機キ60
・キ61三式戦闘機飛燕一型
・キ61-Ⅱ三式戦闘機飛燕二型
・キ100五式戦闘機
全て川崎飛行機の戦闘機です。
日本の陸軍でも同盟国ドイツでの戦闘機開発の進化には敏感になっており世界の趨勢が巴戦重視の戦闘機から一撃離脱戦法重視の戦闘機へと移行しつつあることをうすうす感じてドイツのダイムラーベンツDB601液冷式エンジンのライセンス購入に動き、これを国産化して搭載した一撃離脱戦法重視の戦闘機を模索していました。
そこでDB601装備のメッサーシュミットBf109E戦闘機をドイツからサンプル機として輸入し研究、DB601の国産版の川崎八40を装備した試作機キ60とキ61を試作(キ60とキ61の主な違いは主翼の長さと面積を全く別物にして飛行特性を変えていました)、Bf109Eとキ60とキ61とキ44二式単座戦闘機鍾馗の試作機これらを性能特性比較を行っていました。
それぞれ模擬空中戦もしていました。
その結果Bf109Eは一撃離脱戦法用戦闘機としてドイツが開発しただけあって一撃離脱戦法に徹する限りは優れていて、キ60は翼面積が類似していたこともあり最もBf109Eに近い飛行特性を示しました。
Bf109Eにほぼ近い飛行特性の戦闘機をわざわざ日本で作って日本陸軍が使用してもあまり意味がなく、結局は日本伝統の小回りが効いて巴戦に強く尚且つ一撃離脱戦法をも難無くこなす飛行特性を併せ持ったキ61が三式戦闘機飛燕一型として採用されキ44も二式単座戦闘機鍾馗として採用される結果となりました。
次に八40を更にパワーアップした八140を飛燕の機体に搭載して三式戦闘機飛燕二型が作られたました。
しかし以前お話した通り日本陸軍の見通しの甘さが起因してDB601の国産化版八40は失敗しており、その改良版の八140も失敗作となって故障とトラブルの連続でした。
そのため川崎飛行機の工場ではエンジンのない首なし飛燕の機体だけが大量に並ぶ事態にまで陥りました。
その後に開発された救世主的戦闘機がキ100五式戦闘機でした。
工場に並んだ大量の首なし飛燕の機体を改造して1500馬力級空冷式エンジン金星の陸軍版を搭載して生まれ変わったのがキ100五式戦闘機でした。
850km/hのスピードにも耐えられる飛燕の頑丈な機体に故障やトラブルが少なく整備もしやすい1500馬力級空冷式エンジンを搭載したものだから若干の最高速度の低下はあったものの扱いやすく高性能な新型戦闘機の誕生となりました。
キ100五式戦闘機は第二次大戦最良の戦闘機だと評価されているアメリカのノースアメリカンP51ムスタングとも対等に戦える戦闘機として生まれ変わったのでした。
戦争も終わりに近い時期の誕生だったため約半年あまりの活躍でしたがキ100五式戦闘機の終戦間際の活躍に対し陸軍大臣賞が出されたということもありました。
改良版試作機には中間冷却器(車のターボエンジンでいえばインタークーラーにあたります)を省略した簡易版ターボチャージャーを搭載したキ100-Ⅱ五式戦闘機二型があり結果は難航を極めていた他のターボチャージャー研究機とは異なり概ね良好な性能を発揮しました。
しかし登場が遅きに失し日本は敗戦となってしまいました。
0さん![]() 、
、![]() の歴史カテ に
の歴史カテ に
まだ私の投稿した スレがまだ 残ってます
学問歴史カテゴリーを開き「刀剣シリーズ」と 書いて、検索 して下さい、
あと
「剣豪シリーズ」
「幕末シリーズ」
「戦国シリーズ」
などなど、投稿が残ってます、![]() の時は 万次郎のハンネでした、
の時は 万次郎のハンネでした、
きっと面白いと思います、
きんたさん、初めましてm(__)mこんばんは。(゚▽゚)/
幾多の困難で危険な戦場をくぐり抜け沈められることなく戦争を生き抜いた武運艦、あの駆逐艦雪風の錨ですね。
ヘルシアさん、了解しました。
後でまたよつばの方も拝見させて頂きます。
それでいろいろと参考にさせて頂きます。
自分で好きに学ぶのもいいですが、自分が知らなかった人の知識に触れるのもまたいいものですよね。
って私は思います。
さすが0さん、素晴らしいです![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
零戦以外の戦闘機、
詳しく 画像付き
おそれいります、
勉強しました![]()
日本が太平洋戦争に負けたのは普通に使える航空機用ターボチャージャーを作れなかったからだという人が居たりしますが、私としては何かちょっと違う気がします。
戦争に勝つためにはターボチャージャーが絶対必要だったとも思えませんが…
太平洋戦争初期にはターボチャージャーを装着した重い機体のアメリカの戦闘機を指してまるで蛙を喰った蛇のようだと馬鹿にしていた日本の陸海軍上層部でしたが、戦争が進むにつれ、しきりにターボチャージャーを装着した航空機を試作しては失敗し試作しては失敗しを繰り返していましたね。
無理もないことです。
資源に乏しい貧乏国日本には希少金属である熱と圧力に強い金属材料自体が少なかったわけですから大半がうまくいっていませんでした。
当時ターボチャージャーを実用化して大量生産出来たのは技術面でも資源保有面でも裕福な富める国アメリカ合衆国だけでした。
しかし、ここに紹介した陸軍川崎キ100-Ⅱ五式戦闘機二型や他にも陸軍三菱百式司令部偵察機四型や陸海軍共同開発三菱キ83双発遠距離戦闘機などターボチャージャーを装着して良好な性能を出していたものも複数存在していました。
だからといっても戦争の勝敗を左右することは出来ていません。
日本陸軍の太平洋戦争最後の実用戦闘機、川崎飛行機製のキ100五式戦闘機。
戦争も末期だったためか普通なら日本陸軍の場合はキ番号を付けて○○式戦闘機の後に名前が名付けられるのですが、これには名前が名付けられませんでした。
名付ける余裕がないくらい日常的に街や工場など日本全体が敵の空襲に曝され戦況が相当逼迫していたことが感じ取れます。
同盟国ドイツでは国全体が日常的に敵の爆撃に曝されていたため地下に工場を作りそこで戦闘機や戦車などの兵器を大量生産していたらしいですが。
キ100五式戦闘機は元々は前面面積が小さい液冷式エンジンを搭載するのに合わせて作られた細い胴体の機体でした。
そこに前面面積の大きな空冷式星型エンジンを装着しようとしたのだから単にエンジンを積み換えるといっても簡単ではありませんでした。
エンジンと胴体機首接合部分と排気管の処理や全体的な外形の処理にはドイツからサンプル機として輸入していたフォッケウルフFw190A戦闘機の機体各部の処理方法が大変参考になったといわれています。
こうして急降下速度850km/hでも空中分解しない頑丈な機体でアスペクト比の高い(縦横比が高く細長く翼幅は広い)主翼という飛燕譲りのタフな機体に馬力も高く信頼性も高い空冷式星型エンジンを組み合わせたことにより最優秀戦闘機と呼ばれたあのノースアメリカンP51ムスタング戦闘機をも鴨にしてしまうような傑作戦闘機 キ100五式戦闘機が生まれたのでした。
今でもイギリスのダックスフォードにある博物館には世界中で唯一1機だけキ100五式戦闘機が保存屋内展示されています。
飛行はさせないそうですが、エンジンは定期的に動かしていて稼働可能に保たれているそうです。
0さん、そんな昔から
ターボチャージャー、なるものが、あったんですね、
話は変わって、明治の
日露戦争の 日本海海戦で
「皇国の興廃此のー戦に在り、各員一層奮起努力セヨ」
と言う言葉が思い出します、
秋山実とも だったかなぁ?
ヘルシアさん、こんばんは。(゚▽゚)/
ターボチャージャーの元になった技術は民間船の低出力ディーゼルエンジンの出力向上のためのものとしてかなり前から存在していたようですよ。
以前何かで読んだことがあります。
第二次大戦初期、ドイツ軍は非武装のユンカースJu86Rという双発の偵察機を使いイギリス軍戦闘機が上がって来れないような高高度を飛行しながら悠々とイギリス本土の写真偵察(これが世界初の戦略偵察であり戦後からつい最近に至るまでのアメリカ軍はこのドイツ軍のコンセプトを模倣して発展させ戦略偵察を行っていました)を行っていましたが、当時はまだ航空機用ターボチャージャーが作られていなかったため動力用エンジンに送るための空気を別の空気圧縮用エンジンで圧縮して使っていました。
これで空気が極端に薄くなる14800m前後の高さまで上がり飛行していました。
とてもじゃないが当時の戦闘機が上がって来れる高さではなく手をこまねいて見ているしかない状況でした。
さすがは技術立国ドイツでした。
航空機用ターボチャージャーがないならないで何とかしていた、転んでも只では起きない。
第二次大戦当時で 高度
14800m前後の高さ とは 凄いですね、、
ここで、ベストセラー
「永遠の0」の著者
百田尚樹 氏 のなぜ零戦は日本人の魂を揺さぶるのか?
名人の名人による名人のための戦闘機、
優れた叡智と緻密な技術を備えた
サムライ精神が息づく
日本の歳高級品、零戦、
↑↑
本に在りましたので、
またゆっくりした時に書きます、
何故か?エラーが出て画像一枚以外は他の画像も文章も反映されませんでしたのでもう一度貼ります。
少し脱線します。
申し訳ありません。
m(__)m
通常、空の高さも高度3000mを越えると空気が薄くなり始め、高度6500m前後を越えると自然吸気のピストンエンジンでは馬力が急激に低下し力が出なくなるそうです。
その苛酷な現象を逆手に取り、より高く更により高く高い高高度を飛べば同じ高さまで上がって来れる敵の戦闘機は居ない、高ければ高いほどに敵の高射砲の弾も当たり難くなるという発想から武装は装備していなくても敵にやられる可能性はほとんどないため低速で悠々と飛行して敵本土の偵察写真をじっくりと撮影して帰って来れるというドイツの戦略でした。
この賢い戦略をそっくり真似たのが戦後のアメリカ軍でした。
ジェット機としては速度は約800km/h(マッハ0.8)と遅いが25000mもの高高度を飛べるグライダーのような細長い主翼を持ったロッキードU-2ドラゴンレディという戦略偵察機を作り長年に渡りソ連領土内を写真撮影偵察を繰り返していました。
アメリカはソ連への領空侵犯はしていないとしらをきっていましたが、ミサイルが発達して以降SA-2ガイドラインという対空ミサイルによってアメリカのU-2が撃墜されパイロットが捕らえられるという出来事により領空侵犯の事実を認めざるを得なくなりました。
ソ連は撃墜したU-2数機の残骸を機体の形通りに赤の広場に並べ報道公開し、乗っていたパイロットを裁判にまでかけました。
その後パイロットの身柄はお互いが捕らえていたスパイ同士の交換引き渡しによりアメリカへ帰国出来ることになりました。
次にアメリカはU-2戦略偵察機の後継機として高度25929m前後の高高度で約3529km/h(マッハ3.2)もの高速度で飛行出来るチタニウムを機体に使用したロッキードSR-71ブラックバードという戦略偵察機を開発し近年まで使用し戦略偵察をしていました。
このSR-71は高性能を極めていただけに一機も撃墜されることなく退役しました。
現在では人的損害、軍用機の損害のリスクを考え戦略偵察活動は軍事偵察衛星が後を引き継いでいます。
添付画像一枚目はドイツのユンカースJu86R戦略偵察機。
二枚目上はアメリカのロッキードU-2ドラゴンレディ戦略偵察機、下はロッキードSR-71ブラックバード戦略偵察機です。
話がついつい脱線してしまいましたが、元々書きたかったのはこちらです。
対比出来るように日本陸軍戦闘機の流れを書いた後に零戦開発の流れ。
(零戦の前々作→零戦の前作→零戦→零戦の後継機。)でした。
三菱では九試単座戦闘機という試作機が開発され、これが素晴らしかったためにその流れが続くこととなりました。
九試単座戦闘機を元に開発され日本海軍に採用されたのが九六式艦上戦闘機でした。
この時期に日本陸軍では中島飛行機製の九七式戦闘機が採用され、どちらの戦闘機も素晴らしいと絶賛され、この時期から以降日本はサンプル機以外の外国製戦闘機は輸入する必要がなくなりました。
添付画像一枚目と二枚目は傑作と絶賛された堀越二郎技師作の試作機、九試単座戦闘機。
三枚目は九試単座戦闘機から続く九六式艦上戦闘機の各型の側面図。
陸軍も海軍も次の戦闘機を開発する際には九七式戦闘機や九六式艦上戦闘機が要求性能の基準とされました。
その影響で海軍の零戦も陸軍の隼も機動性を良くするために相当な苦労を強いられることとなりました。
良くいいますよね、素晴らしいものを世に出した後、それを超える次の作品を世に出すことが最も難しいと。
乗っていたパイロットたちの多くと設計者の堀越二郎技師自身は零戦よりも九六式艦上戦闘機の方に思い入れが強く九六式艦上戦闘機の方が良かったと語っていたようです。
三菱では九六式艦上戦闘機の後継機として十二試艦上戦闘機という試作機が作られ、これが海軍に採用されて零戦一一型となりました。
零戦一一型に翼端折り畳み機構(両主翼端50cmのみ)と着艦用拘束フックと無線帰投用方位測定器などの本格的な艦上戦闘機仕様を施したのが零戦二一型です。
添付画像一枚目と二枚目は九六式艦上戦闘機。
三枚目は零戦二一型。
0さん、よくわかりましたよ。三菱九試単座戦闘機、試作機九六式艦上戦闘機。
陸軍の中島飛行機製九七式戦闘機。
そして↓
三菱十二試艦上戦闘機、零戦一一型。
零戦二一型。
とつづくんですね、![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
またここで、百田尚樹の「永遠の0」から抜粋
↓↓
当時米軍の教え、
1930年代の当時、戦闘機は、国をあげてつくりあげるのが、飛行機、最先端テクノロジーを集めた 世界最高のもの、
当時の軍部と三菱スタッフでは、
軍部のとうてい無理難題の要求、
それを少しでも近いものをと堀越二郎。
確かに飛行機をつくるって大変な事で、
また機械工業、テクノロジー、科学に関して当時は、ヨーロッパが圧倒的に優れていて、アジアの国なんて全く認められていなかった、
アジアとヨーロッパでは大人と子供くらいの差があったようで、
でも、日本はヨーロッパアメリカの飛行機がかなわない戦闘機を突然つくり上げた、
最初アメリカ軍なんかは零戦にボコボコに墜とされる![]() んですけど、もうこれは日本の戦闘機をなめていたとしか言いようがない、
んですけど、もうこれは日本の戦闘機をなめていたとしか言いようがない、
「自動車もまともに造れない国が、アメリカの戦闘機に敵う戦闘機を造れるはずがない」と
スピード重視で戦闘機を造れば、空中戦能力が落ちる、小回りが利かない小回りが利く設計を重視すると、スピードが出ないと、矛盾が出てくる
各国がどちらに重視するかによって、その国が持つ戦争感、文化が現れる
日本は最高の戦闘機を追及した、
海軍省が、のちに零戦になる十二式艦戦と言う
試作機つくれと、三菱に要求、
三菱側は「え"〜絶対無理」と
①世界のあらゆる戦闘機を凌駕するスピードの戦闘機、
②世界のあらゆる戦闘機と戦って、空戦能力を上回る戦闘機、
当時の技術で考えると、矛盾を越えていた、
それを三菱の堀越二郎という天才設計技士が、軍部の無茶苦茶な要求に応えて仕上げたのが、
零戦、
戦闘機は2機がお互いに最後尾を取り合う(権兵衛さんの言うドッグファイト?)前に固定された機銃で、巴戦?、
当然小回りが利く方有利 速さを重視したアメリカの戦闘機はすぐに後ろをつかれ、堕ちる![]()
![]()
仮にアメリカの戦闘機が零戦のうしろにつけば、零戦はそのまま下にすぅーっとさがる、アメリカ戦闘機が追いかける、零戦は上に向かって宙返りアメリカ戦闘機は当然追いかけるが、重くて小回りが利かない、これで撃墜です、
零戦は後ろにつかれても、クルッと一瞬に、アメリカ戦闘機の後ろにつく
百田尚樹
↓
アメリカ軍は
零戦にしてはならない、 「3つのネバー」を指示してます、
①ゼロと格闘してはならない
②ゼロと300マイル以下で、ゼロと同じ運動をしてはならない、
③低時速に上昇中のゼロを追ってはならない、
このネバーを犯せば必ずゼロから撃墜される、
しかし同時にゼロの弱点も見抜いていたと
それが防御力、
零戦は、世界最速のスピードと世界最高の空戦能力持つ飛行機ですが、
このため犠牲にしたのが (0さんの言われる)防弾装備、パイロットを守る背中の鉄板も無、翼にある燃料タンクも1発でも当たったら火を吹きますし零戦は墜ちる、
同時の戦闘機は500キロぐらいしか飛べないが、零戦は、3000キロ。
それだけ燃料が必要だから翼の中も利用するしかない、翼は最も撃たれやすい、
同時日本の零戦がなかなか墜ちなかったのは、
パイロットが超一流だったからで、
零戦は一流のパイロットが操れば、世界最高の戦闘機ですけど、普通の技量のパイロットが乗ったら 危険な戦闘機 まさに棺桶の飛行機ですね、
海軍省の(三菱に発注)
十二式艦戦試作機
後の零戦
↑↑
0さんのコメント
を抜粋、
もう少しでお彼岸ですが、3月21日は野中五郎少佐の命日ですね。一度の出撃での航空特攻での戦死者数が一番多いのでは?
きんたさん、こんばんわ
野中五郎少佐←
しりませんでした![]()
![]()
今から調べます、
コメントありがとうございます、
こんばんわ〜![]()
![]()
きんたさんのいわれる
野中五郎少佐、
調べましたぁ、また勉強しました、![]()
凄い将校さんですね、
画像は
一枚目 野中五郎少佐
2枚目 特攻機「桜花」
3枚目 一式陸攻が桜花を 抱いている、
太平洋戦争末期
沖縄へのアメリカ軍上陸を、阻止しようと、
沖縄を守ろうと、命を捧げた軍神、ですね、
間違ってたらすみません
上記 サイトより抜粋
18機の一式陸攻に12機の桜花を搭載して出撃をして全滅してしまいました![]() 野中少佐はそうなる事を予見して意見具申をしましたが、受け入れて貰えなかったそうです。
野中少佐はそうなる事を予見して意見具申をしましたが、受け入れて貰えなかったそうです。
きんたさんから、教えてもらってから、サイトより、です、→▲桜花(おうか)というのは、大東亜戦争の末期に実戦に投入されたロケットエンジンを搭載した特攻専用機です。
大東亜戦争の時代に、ロケットエンジン搭載の飛行機があったというのはすごい話ですが、この時代、「桜花」は、まだ自力で離陸することができませんでした。
なので一式陸攻の下に吊るされて敵地まで飛び、上空で親機から切り離されたあと、ロケットを噴射して、一直線に敵艦に向かって突撃したのです。
搭載する爆弾は、1200kg爆弾です。
通常の航空機による特攻の5倍近い威力の爆弾を搭載していました。
そして1040km/hという、音速に近いスピードで、一直線に敵艦に体当たり突撃しました。
成功すれば、その破壊力はすさまじいものです。ところが桜花の搭載したロケットエンジンは、一瞬で燃料を燃やしつくしてしまいます。
つまり、航続距離がありません。
桜花の航続距離は、わずか37kmです。
30キロというのは、上空と海上とでは、最早目と鼻の先です。
すぐそこに見える距離です。
そこまで近づいて、切り離されて、まっすぐに敵艦に向かいました。
桜花は、2トンを超える重量があります。
ですから、さしもの一式陸攻も、桜花を懸吊すると「飛ぶのがやっと」という状態になります。
つまり一式陸攻は速度が出ず、小回もきかなくなります。
ですから敵の戦闘機に襲われたらひとたまりもありません。
桜花を懸吊した一式陸攻は、戦闘機であるゼロ戦に警護を固めてもらって、敵艦隊に近づきます。
この頃の米艦隊は、特攻対策として高射砲の砲弾に「近接信管」を搭載しています。
「近接信管」というのは、砲弾を中心に半径15メートルに電波が発射されていて、その電波が飛行機を察知した瞬間に爆発するというものです。そして砲弾の中には、無数の鉄片が仕込まれていました。
近接信管を搭載した砲弾が、特攻する桜花の近くで炸裂した瞬間、パイロットは大怪我をし、あるいは即死し、機体は穴だらけになって吹き飛びます。
こうした近接信管を搭載した砲弾を、米艦隊は突入してくる桜花めがけて、一斉に何百発と撃ち込みました。
小回りを利かせ、敵砲弾をかいくぐらなければ、とても敵艦に近づけるようなものではありません。
けれど桜花は、速度が速いかわりに、一直線にしか飛べません。
米軍の間では、桜花は、「BAKA BONG(おバカ爆弾)」とあだ名されたといいます。
私達は航空戦の素人ですが、そんな素人でも、以上の説明を聞けば、桜花の出撃がいかに危険なリスクを負ったものかがわかりますね。
当時のパイロット達は、航空線のまさにプロフェショナルです。
しかも、航空兵に採用されるような人たちは、とびきり優秀なパイロットたちです。
プロであるがゆえに桜花作戦の危険性、無謀性は、私達より何十倍も承知しています。
それでも彼らは飛び立ちました。
桜花の最初の出撃は、戦局押し迫った昭和20年3月21日のことです。この5日後には、沖縄戦が開始されています。
まさに米艦隊が、沖縄めがけて続々と押しかけてきていたときです。
日本としては、なんとかして敵の沖縄上陸を阻止し、遅らせ、民間人の避難を促進したいけれど、すでにこの時点で、帝国艦隊は最早壊滅し、空母もなく、沖縄近郊の制海権、制空権は、完全に奪われていました。
飛ばせる飛行機もない。飛行機を飛ばすためのガソリンも、残り僅かです。
この時期、日本の航空隊は、練習機に摘んだガソリンは、まともな石油ではありませんでした。
ひとことでいえば、いまでいうサラダ油をガソリンの変わりに積んで飛んでいました。
(↑↑↑本当かなぁ?)
戦後のことですが、米軍が日本陸軍の四式戦闘機「疾風(はやて・ゼロ戦の後継機にあたる)」に、米国製のオクタン科の高いガソリンを入れて飛ばしたところ、当時世界最強といわれたP51ムスタングよりも高い性能を示しています。
特攻する際は、それなりのガソリンを入れたものの、いまで言ったら、ハイオク使用の車に、軽油を入れて飛ばすようなもので、そもそも充分な性能を発揮させることができないという状況でもありました。
けれど、それでもなお、帝国は沖縄を守るために全力を尽くそうとしたのです。
圧倒的な兵力を持った敵に対し、わずかばかりの兵器で戦わざるを得ない。
かくなるうえは、問題点山積みの兵器とはいえ、「桜花」出撃やむなし、と判断せざるを得なかったという事情も背景となっていました。
万にひとつでも、攻撃を成功させれば、あるいは攻撃が成功しなくても、敵は日本本土から飛んでくる特攻隊への防戦に注力せざるを得ない。
そのために敵は、相当数の兵力を防備に割かざるを得ない。
そうなれば、米軍の沖縄上陸は遅れ、遅れた分、沖縄内では米艦隊からの艦砲射撃対策のための掩蔽壕や、民間人避難のための防空壕をほんのわずかでも強化できるし、戦場となりうるエリアから民間人を避難させることもできる。
だから「桜花」は飛び立ちました。
太平洋戦争当時に日本の技術力が最低でもドイツと同レベルにでもあれば特攻隊で若い兵士たちの命をたくさん失うこともなかったのにと大変悔やまれます。
合掌。
ドイツは確か敗戦間際にヘンシェル社製フリッツXという誘導滑空爆弾をハインケル社製双発爆撃機から切り離しイタリア海軍の戦艦ローマに命中させ撃沈していました。
イタリア軍の方針転換で連合軍側に寝返ろうとしているその時の撃沈だったと思います。
人間が乗って操縦しなくても使用出来る誘導技術が日本にも確立されていればと惜しまれます。
太平洋戦争末期の昭和19年11月29日に大和級三番艦の改造空母信濃が未完成のまま横須賀から呉へ回航中にアメリカ海軍の潜水艦の雷撃により潮岬沖に沈みましたが、この時に信濃は桜花を50機搭載して運搬中だったそうです。
信濃が沈められていなかったら少なくともあと50人プラスアルファの若い兵士たちの命が失われていたことになります。
これは幸といっていいのか不幸といっていいのか、これもまた戦争の現実でしょう。
特攻専用兵器桜花の開発に携わった日本海軍航空技術廠の三木忠直技術少佐は自分が開発した桜花によって若い命をたくさん失わせてしまったことを悔いて戦後は戦争に直接使われないであろう鉄道車輛開発に力を注ぎ初代の新幹線0系新幹線のデザイン設計を手掛けたそうです。
添付画像は一枚目は三木忠直技術少佐が開発した特攻専用兵器桜花の透視図解。
二枚目は桜花50機を運搬中に沈められた改造空母信濃の写真。
三枚目は上から戦後の三木忠直元技術少佐、0系新幹線の木型模型、0系新幹線の写真です。
時間がある方々は 読んで下さい、サイトからのコピペです
↓↓
沖縄戦では、多数の民間人が犠牲になられました。
このことがいまだに沖縄に暗い影を落としているといわれています。
けれど、よく考えていただきたいのは、本来、軍が戦闘をするとき、民間人がいては、軍はその機能を存分に発揮することができないということです。
ただでさえ、少ない兵力、乏しい戦力で戦わなければならない日本軍にとって、戦場に民間人がいたら、正直困ることになります。
ですから、軍は、沖縄戦に先んじて、沖縄の民間人の本土への疎開を遂行しようとします。
しかし、これに反対し、沖縄県民を戦地という危険に晒したのは、ほかならぬ沖縄県知事でした。
ともあれ、沖縄には、まだまだ多数の民間人が残っていたのです。
沖縄県民をひとりでも多く救うためには、本土に残るわずかばかりの兵力をもって、米軍に挑み、米軍の注意を本土側にそらしておく必要があります。
そのために「桜花」は出撃しまています。
それは昭和20年3月21日のことでした。
この日出撃した部隊は、桜花を懸吊した一式陸攻18機と、護衛のためのゼロ戦30機です。
部隊は、敵艦隊のはるか手前で、進撃中に敵艦隊にレーダーで捕捉されました。
そして上空で待ち構えたグラマンF6F戦闘機28機の待ち伏せにあい、迎撃されまています。
一式陸攻を守ろうとゼロ戦部隊が対空戦を挑み、一式陸攻がまる裸状態になったところに、別なグラマン部隊が襲いかかる。
そうして陸攻隊は全機が撃墜され、ゼロ戦隊も、30機中10機が撃墜されました。
無理をして一式陸攻から飛び立った桜花もあったけれど、飛距離が足らず、海中に没しています。
この戦いで後ろを取られ、必死で機体を左右に滑らせて射線をかわしながら、ついに被弾して一瞬で火を噴き爆発、桜花を吊ったまま墜落する一式陸攻の姿を記録したF6Fのガンカメラ映像が残っています。
翼をもぎ取られ落下する一式陸攻には、一機につき10名の歴戦の搭乗員が乗っていました。
そして全員が還らぬ人となりました。
この特攻について、後世の人たちからは、特攻を意思決定した宇垣纏中将に対し、たくさんの非難が寄せられました。
命を犠牲にして特攻を行うことを前提に出撃した桜花の搭乗員だけでなく、運搬役の一式陸攻まで全機未帰還となっているのですから、責任者の責任を追及する声が上がるのは仕方がないことだと思います。
しかし、上に述べたように、他に沖縄戦を阻止する効果的な方法がない中で、なにがなんでも敵の沖縄上陸を阻止することを至上課題とした当時の状況にあって、他にどういう判断のしようがあったのでしょうか。
防備のために同時に出撃した戦闘機ゼロ戦隊にしても、攻撃隊指揮官の野中五郎少佐が、護衛機70機を要求したのに、30機しか付けれなかった、という人もいます。
しかし、実際には、このときゼロ戦は、なけなしの飛行機のなかで、55機が出撃しているのです。
この時点では、整備できている飛行機「ありったけ」の戦力です。
ところがその戦闘機も、途中でエンジン不調となり、25機が途中で引き返しました。
結果、護衛が30機となったのです。
上空を飛行中の一式陸攻の機体の中から、下に吊るされている桜花に飛んで乗り移ったのです。
飛行中の機体に吊るされた桜花は、それこそ上下左右に激しく揺れ動いています。
その揺れ動く小さな桜花の小さな狭いコクピットに、パイロットは上から飛び乗るのです。
上空何千メートルという航空です。
そこに、パラシュートも付けずに、飛び降りる。一歩間違えば、そのまま転落します。
転落すれば死あるのみです。
ようやく桜花に乗り込むと、一式陸攻は、桜花を機体から切り離します。切り離された桜花は、その瞬間、数十メートル、猛烈なスピードで落下する。
落下しながら、桜花はエンジンに点火します。
それは恐怖の瞬間です。この時点で意識を失ったら、それも即、死亡を意味します。
そしてまっすぐに目標に向かって飛ぶ。
しかし、翼の小さな桜花は、低速では着陸しません。
猛スピードです。
0さん![]() 、桜花は
、桜花は
三木忠直少佐 と言う方でしたか、空母信濃←かっこいい![]()
後の新幹線も
画像ありがとうm(__)mです、
つづきです↓↓
国内着陸訓練でも、桜花の搭乗員は、何人も命を落としています。
その過激な訓練を経由して、生き残った最強の兵士だけが、死ぬことを目的とした特攻作戦に参加しました。
彼らはそこまでして、私達の国を守るために、沖縄を守るために出撃し、散って行かれました。
そのことの意味を、私たちはもういちどよく噛みしめてみる必要があるのではないかと思います。
繰り返します。
上空で、一式陸攻にぶら下がっている桜花に飛び移る。
それがどんなに危険なことか、考えなくたってわかろうと思います。
出撃しても、敵艦隊に30キロまで近づくことが、何を意味するか。
そこまで近づく前に、桜花は一式陸攻ごと撃墜されることが、彼らプロには痛いほどわかっていたことと思います。
その一式陸攻には、一機につき10名の搭乗員が乗っています。
撃墜されれば、桜花の特攻が不首尾に終わるだけでなく、乗組員全員が死ぬことになるのです。
このことについて、戦後、指揮官がバカだったとか、日本軍は人の命を粗末にしたとか、いろいろ書いている人がいます。戦争が終わり、自分は安全なところにいて、現に不首尾に終わった作戦には、好きなことが言えます。
ののしりたいなら、ののしれば良い。
しかし、これだけは言いたいのです。
彼ら搭乗員たちは、指揮官も含めて、誰より命を大切にする人たちでした。そして桜花の出撃が、どれだけ危険なことかを、プロである彼らは、後世に安全なところにいて、いろいろごちゃごちゃ批判している誰よりも、その危険をよく知っていた男たちでもありました。
それでも彼らは出撃しました。
無理とわかっていても出撃しました。
何のために?
沖縄を守るためにです。
祖国の大地を敵に踏ませないためです。
それは、かげがえのない思いやりの心です。
いろんなご意見もあると思いますが、サイトよりコピペです、
↓↓↓
このときの作戦で攻撃隊指揮官となった野中五郎少佐は、「激戦の中で、部下を死なせない」ことを誇りとした指揮官です。
けれど、彼はひとりだけ部下を失ったことがありました。
夜間攻撃で、敵の船に魚雷を撃ち込むために海面すれすれに飛行したところ、いきなり横から割りこんできた敵の別の船にあやうく衝突しそうになったのです。
彼は、急上昇してこれを避けようとしました。
けれど、そのとき一式陸攻の尾翼が海面を叩き、後部銃座にいた部下がその衝撃で吹っ飛んでしまったのです。
数多くの航空線を戦いぬいた野中少佐の、それが唯一の部下の損失でした。
彼はそのことにずっと悩み、二度と部下を、絶対に死なせないと誓っていました。
彼は最後の突撃で、自らの命を失う日まで、その一時以外、いっさい部下を失うことはありませんでした。
その彼が、最後の出撃のとき「湊川(みなとがわ)ですな」という言葉を残しました。
「湊川の戦い」というのは、建武3(1336)年の足利尊氏と楠木正成の戦いですね。
いったん九州に疎開した足利尊氏が、3万5千の大軍を率いてやってくる。
迎え討つ楠木正成は、わずか7百の手勢です。
勝てる見込みはありません。
楠木正成は、このとき「正成存命無益なり、最前に命を落すべし」と語り、5月25日、湊川で両軍は激突し、多勢に無勢ななか、六時間におよぶ激しい戦いの後、正成軍はわずか73人になってしまいました。
最期をさとった正成は、生き残った部下とともに民家に入り、七生報国を誓って全員自刃しています。
野中大佐が「湊川」に例えたということは、彼がこのときの出撃がどういうものであるかを充分に悟っていたということです。
野中五郎少佐は、明治43年、東京・四谷のお生まれです。
子供の頃から明るく、周囲を笑いの渦に巻き込む天賦の才があったそうです。
学生時代は、クラシック音楽が好きで、レコード屋に入り浸ってレコードを買い求める音楽青年でもありました。
大東亜戦争の開戦と同時に、当時大尉だった野中は、一式陸攻の分隊長として、フィリピン、ケンダリー、アンボン、ラバウル、ソロモンと転戦しました。
そして、巡洋艦、輸送船合わせて四隻を撃沈しています。
ラバウル時代には、草鹿任一第十一航空艦隊司令長官から武勲抜群として軍刀を授与されてもいます。
昭和18年11月のギルバート戦では、彼が発案した「車がかり竜巻戦法」で、米軍を悩ませもしました。
これは、薄暮、単縦陣で海面すれすれに飛行し、敵艦船を遠巻きにして、その周りを回り、最後尾の機に先頭の隊長機が迫って輪のようになる。
そして照明弾を落とすと、敵が光にさらされて姿を現す。
そこを全機で魚雷攻撃するというもので、多数の米艦船がこの攻撃で沈みました。
野中五郎大佐の趣味は茶道でした。
南方では出撃前にも翼の影で野点に心を鎮めていた方でした。
彼は新任の部下に、
「若え身空で遠路はるばるご苦労さんざんすねぇ。
しっかりやんな。お茶でも入れようか」と声をかけ、面くらわせたりもしています。
言葉づかいはべらんめい調だけれど、飄々とした味があり、とにかく部下思いの優しさから多くの部下たちに慕われ、彼の部隊は、いつしか「野中一家」と呼ばれるようになったそうです。
その「野中一家」に、桜花部隊が配属されたのです。
「死ぬ」とわかっている部隊です。
下士官たちはくたびれ、若い兵士たちの気持も沈んでいる。
野中隊長は、そんな彼らを見渡し、朝礼台で挨拶しています。
どいつもこいつも不適な面魂をしている。
誠に頼もしいかぎりである。
この飛行隊は日本一の飛行隊である事は間違いねぇ。
何となれば隊長が日本一の飛行隊長だからであ〜る。
かく言う俺は何を隠そう、海内無双の弓取り、海軍少佐中野五郎であーる。
かえりみれば一空開隊当初より、大小合戦合わせて二百五十余たび。
いまだかって敵に後ろを見せたことはねぇ!
講談調でたたみかけるように話す野中に、いつしか兵たちは ニヤリと笑い、表情に力強さが戻ったそうです。
この様子を見ていた人の談によると、野中五郎少佐の訓示は、なにやら勇者の魂が乗り移っていくような不思議な魔力があったといいます。
ヘルシアさん、どうもです。![]()
信濃は大和級戦艦の三番艦でしたが日本海軍が次々に空母を失ったため空母戦力拡充の一環として建造途中に空母へと改造されました。
戦局が逼迫して何もかもが簡略化、簡略化で通常ならば行わなくてはならない就役前の各種テストも省略に次ぐ省略に終始したため本来なら行うはずの水密試験や注排水設備のテストも省かれ行われていなかったために潜水艦の雷撃程度であっけなく沈んでしまいました。
当時、空母信濃は世界最大の大きさの空母(戦後アメリカで原子力空母エンタープライズが出現するまでは信濃が世界最大の空母だったと思います。)で飛行甲板も装甲化されていて航空攻撃にも潜水艦からの雷撃にも強い空母として最前線へ進出し、その打たれ強さを利して浮かぶ最前線基地として活躍することを期待された空母でしたが、ろくなテストもしていなければあっけなく沈んでもしかたのないことでした。
ここにも技術者たちのいうことを聞き入れず精神力、精神力を連呼した軍上層部の見通しの甘さが悪しき風習として実行されていたのでした。
特攻隊も根底には同様なことがいえるのです。
下っ端の兵士たちが作戦を決定するわけはないのですから軍上層部の戦争の計画や指揮のとり方が悪く戦局が逼迫したのにその尻拭いを特攻隊というかたちで若い兵士たちに背負わせ、自分たちは特攻して行く立場ではないのだから、命令を下すだけの立場なのだからという無責任でずさんな行いが悲劇を生んだということでしょう。
今でも国のリーダー、地域のリーダー、会社のリーダー、学校のリーダーにあたる人たちの中にもそんな連中は必ず居ます。
そんな人たちが重要なことを推し進める立場に就くと悲惨な結果が待っています。
そうならないように物事には目を配っておかないといけませんね。
0さん、おっしゃるとうり、
日本のリーダー、
会社のリーダー
私は20年務めた 会社が倒産しました、
まさに リーダーと呼ばれる方々の、失態が原因です、
私は愛社精神に燃えて、働いてましたが、
残念でなりません、
空母信濃はきいた事あります、戦艦から空母に改造された空母でしたか
その内プラモデルでも
買って みたいですね、
やはり 野中五郎少佐に
指示したトップクラスの上官、
また「桜花」を造れと
指示した軍上層部、
日本を守るとは言え、
むなしく思えてなりません、
まぁ今の平和な世界にいる私が言えるのかな?、
日本軍の悪いところがでた、ミッドウェー海戦も、
日本軍は、情報を軽視し 作戦を重視、
国力の判断の誤り
組織の不統一
だったようです
戦争のことを語るのに漫画やアニメというと不謹慎だと受け取られる方もいるかも知れませんが、そういう意図は一切ないことを事前に断っておきます。
特攻隊がどのようなものであったかを少しでも知る上では理解しやすいと思いますのでこのアドレスを貼ります。
YouTubeでの松本零士氏の代表作ザ・コクピットの
『音速雷撃隊』です。
他にも同じページの中で
『鐵の竜騎兵』
『成層圏気流』
もありますのでよろしければご覧下さい。
戦争の世界がアニメで判りやすく描かれています。
これは昔、雑誌やコミックスで出版されていた戦場漫画シリーズで後にザ・コクピットシリーズとしてリニューアルされていた松本零士氏の作品です。
数あるストーリーの中から松本零士氏が厳選した上記三作品だけがアニメDVD化されたものです。
架空の部分もありますが、国や歴史、戦争兵器のことを良く勉強した上で描かれた作品なので戦争映画に勝るとも劣らないものです。
http://m.youtube.com/watch?v=J4d8Y0MaBbg&guid=ON
参考までにガラケーを使っている人はMy Tube (読みはまいつべ)というのを検索してタイトルを入力して動画検索すればダウンロードも可能ですよ。
スマホを使っている人は動画ダウンローダーを持っていればダウンロードも可能ですよね。
頂いておきたい人はこれらを参考に。
ミッドウェーの大敗戦の責任は 山本五十六、南雲忠一中将、で、もしアメリカなら責任とって更迭左遷かも?
確かに空母どうしの戦いは、日本は初めてかもですが、
二人を責めるのは酷かな?
しかしなぜ敵空母を発見できなかったのか?
0さん、
松本零士氏の代表作ザ・コクピットの
『音速雷撃隊』。
『鐵の竜騎兵』
『成層圏気流』
↑↑
時間があるとき、是非みて見ます、0さんいつもありがとうございます、
少し見ました![]() 、
、
「桜花」がでてました、
0さん![]() 、
、
あらためて、世界最大級 空母信濃、を画像探しましたが、みつかりません![]()
![]()
短命で張りぼて、だったみたいで、
0さんの貴重な.当時の空母信濃画像
本当にありがとうございます、
空母信濃が戦艦だったら、戦艦信濃だったかも知れませんね
一号艦 大和
二号艦 武蔵
三号艦 信濃(紀伊?)
ヘルシアさん、おはようございます。(゚▽゚)/
あの空母信濃側面のカラー化写真の元写真(良く見ると船体規模と艦種を敵に誤認させるための欺瞞迷彩塗装を施した空母信濃のモノクロ写真)と側面スケッチと空母信濃と戦艦大和の対比図を貼りますね。
戦後長い間、空母信濃の写真は残されていないとされていて唯一詳細に描かれた側面スケッチがあるのみという状態でした。
しかし、2000年代に入った直ぐだったか、その前後あたりで唯一の写真が一枚発見されたということで公開されたのがこのモノクロの側面写真でした。
だから公開されているものとしては現在のところこの写真以外に空母信濃の写真は存在していないはずです。
元来、軍艦というものは艦内を無数の部屋に仕切り、それぞれの部屋の気密化を図り防水区画化してもしもの時でも沈み難くしてあるのが普通です。
特に戦艦はその防水区画数が多く設定される艦種です。
戦艦は基本的には大事な部分を出来得る限り強靭かつ分厚い装甲板で覆い敵の攻撃から守りますが、これと併用するかたちで防水区画数を多くして防御力を高めているものです。
どこかのある場所が敵弾を被弾して破壊された場合はその区画との境になる扉を閉鎖してそれ以外の区画への浸水を防ぎ沈没しないようにする。
いわゆる、ダメージコントロール(戦う上で自分の艦だけ無傷でいられるということは現実的には有り得ない、なにがしかの損傷は受けるものと割り切り、損傷を受けた場合にも出来るだけその被害を極限させようという考え方)の一つの手段です。
そこに注排水設備を併せて備え水平バランスをとれるようにしてありました。
空母信濃も元々が大和級戦艦の船体を使用していたので空母化により防水区画数は減らされていたとしても基本的には大和級戦艦につぎ沈み難い軍艦であるはずでした。
しかし、前述の通り水密試験や注排水設備のテストが省略され行われておらず乗っていた乗員も不慣れな人が大多数だったために魚雷4本程度の命中であっけなく沈んでしまったのでした。
戦闘機用エンジンとして過度に期待された誉エンジンと全く同じで、やっぱり仕様はいくら高性能でもちゃんと作られていることを確認出来ていなければ絵に描いた餅と同じということですね。
海軍も陸軍も当時の日本の軍上層部の見通しの甘さに起因する不手際は残念な話ばかりです。
全ては重責を担っているはずのお偉い方々の無責任なものの考え方から来ていると思います。
今後の日本では同じようなことは繰り返されないよう望みたいものですね。
信濃は110号艦、紀伊は111号艦とされていました。
111号艦も起工はされましたが、ほどなくして建造は中止されました。
それから大和級戦艦の三番目の戦艦になる予定だった信濃用の46cm主砲は準備されていて、これは試作中だった50.8cm砲と共にアメリカが戦利品として持ち去ったそうです。
そして信濃用に用意されていた46cm主砲の砲塔の一番分厚い装甲板、前楯(厚さ650mmの特殊装甲)をアメリカの40.6cm砲弾で貫通させたものがアメリカ国内に現在でもモニュメントととして屋外展示されているそうです。
あの狭い面積に穴を空けてあるところを見ると遠距離から命中させたものではなく、かなり近い距離から据え撃ちしたのは間違いないでしょう。
実際の戦場では近くに近付く遥か前から撃ち合いは始まりますから戦艦同士が敵艦の直ぐ目の前で据え撃ち出来る環境は事実上有り得ません。
自分が戦争で負かしたはずの相手である日本の兵器の技術がたとえ一つでも自分たちより優れていたことを当時のアメリカ人はぜがひでも認めたくなかったのでしょうね。
駄々をこねる子供みたいな行いです。
その証拠にみせしめモニュメントを作るための射撃はしても日本から持ち去った46cm砲や50.8cm砲の性能をテストするための試験射撃は行われていないようです。
真珠湾攻撃のことを騙し討ちだとして日本をアンフェアだと言い続けて来たアメリカ、しかしアメリカのこの実際有り得ない環境で無理矢理モニュメントを作り出すやり方こそアンフェアだと私は思います。
これら日本から持ち去られた46cm砲、50.8cm砲その他の周辺機材は今もアメリカ国内のどこかに眠っているのでしょうね。
私も松本零士さんのファンです。スタンレーの魔女から好きになりました。『責任の所在』は難しいですけど、『誰かが』取らないと同じ失敗をくりかえすだけかと![]() それが『原因究明』につながり、『対策』につながり、『成功』につながるかと
それが『原因究明』につながり、『対策』につながり、『成功』につながるかと![]() プロセスを『精神力』にむりやり置き換えたら
プロセスを『精神力』にむりやり置き換えたら![]() あと『適材適所』も大切だと思います
あと『適材適所』も大切だと思います![]()
0さん![]() 、
、
空母信濃←凄いですね、まさに圧巻です、プラモデルは見てましたが、知りませんでした、
降板でサッカーが出来るみたいです![]()
昔(明治)の戦艦対戦艦は お互い敵同士、見える敵の戦いでしたが、
空母対空母戦のミッドウェー戦では 見えない敵の戦い、だから情報が唯一 勝敗を決めました、
日本海軍の上層部は大敗戦を日本国内に、漏れないように隠します、現にミッドウェーに参加した兵士の口を塞ぐため国内のどこかに閉じ込めてしまうと いう有り様です、
きんたさん![]() 、
、
画像は戦艦大和カナ?
ミッドウェーの敗戦は、軍部が勝利と国民に伝え 海軍上層部は、皆、仲よしこよしだったから、
誰一人敗戦の責任をとりませんでした、
日本の空母4隻を失った 責任は、大 です、
訂正です![]()
空母どうしの史上初の、海戦は 1942年5月
日本と連合国で行われた 珊瑚海海戦、がありました、![]()
![]()
当時日本は戦訓をドイツから学びますが
イギリスとドイツの戦いは空母どうしの戦いは
なかったようで、
>>361 写真のプラモは『比叡』です。今回のは、零式の32型です。 ミッドウェー海戦の損害は陸軍にさえ秘密にしてたみたいです。そしてガタルカナル戦へ![]()
きんたさん 画像ありがとうm(__)mです、
零戦三二型 たまりませんね![]()
零戦特有の、翼 黄色いライン、これぞ零戦ですね。
きんたさんは、プラモデルたくさん 持ってらっしゃるようですね、
戦艦比叡は元々は巡洋戦艦であったため通常の戦艦に名付けられる旧国名ではなく山の名前である比叡山の比叡という名前が名付けられています。
一応、姉妹艦になる金剛も榛名も霧島も同様です。
金剛はイギリスのビッカース社に建造を依頼して輸入した艦でこれを最後に日本は外国からの輸入をやめ国産艦建造に乗り出して行きました。
二番艦の比叡はその最初の国産建造艦となりました。
しかし後々、各艦近代化改装を何度となく行う際に他の三隻には問題は起きなかったのに一番艦の金剛だけは穴を空ける時に使うドリルが折れて使い物にならなくなるということが発生しました。
師匠であるイギリスが造った一番艦金剛を真似て姉妹艦を造ったつもりでしたが特殊鋼の装甲板を作る際の日本とイギリスの技術力の差が如実に表れた事例でした。
二番艦の比叡は大和級戦艦建造の事前テストケースとして艦橋部分は大和級戦艦のような艦橋に改装されました。
だから良く似ている(大和級戦艦の艦橋が比叡の艦橋に似ているといった方が正しいかも知れませんね。)ヘルシアさんが見間違えたのも無理もないことです。
同じような事前テストケースは他にもあり空母大鳳や信濃の煙突一体型島型艦橋は客船改造空母隼鷹や飛鷹で事前に実用テストされていました。
戦艦比叡と大和級二番艦武蔵の艦橋が良く判る画像を貼りますね。
大和級戦艦建造の事前テストケースを務めた関係上、戦艦比叡だけは他の姉妹艦三隻とは違う姿の艦橋シルエットとなっていました。
大和級戦艦の艦橋の事前テストケースだったため姿が似ているのはもちろんながら光学式測距装置やレーダーの配置や機能に至るまで機能的な配置も似ていました。
いわば戦艦比叡を使って大和級戦艦の光学式測距装置やレーダーによる敵の探知、敵へのレーダー射撃なども研究していたようです。
よく日本はレーダー射撃なんて到底無理だったといわれることが多いですが、テストもせっせと行っていたのが事実でした。
只、惜しまれるのは当時の日本の電子部品は現在とは全く逆で壊れ易く信頼性という点では絶対とはいえなかったことです。
大和級戦艦では射撃用レーダーとして二号二型電探(よく22号レーダーと呼ばれ紹介されることが多いラッパを二段重ねにしたような小型レーダーです。)を使っていたようです。
ヘルシアさん、0さん今晩はです。 大和型や金剛型も好きなんですが、最近は西村提督と壮絶な最後をとげた『山城』『扶桑』に興味があります![]() 良く旧式戦艦に分類されておりますが
良く旧式戦艦に分類されておりますが![]() 写真は『山城』のプラモです。
写真は『山城』のプラモです。
0さん、戦艦比叡と戦艦武蔵の画像を
何度も見させていただきましたが
いまだにわかりません![]()
![]()
![]()
![]()
大きさでいうなら 下の画像が武藏カナ?
きんたさん、西村提督と 言えば、レイテ沖海戦の 勇者 ですね、![]()
しかし0さんは、日本の軍艦、飛行機、めちゃくちゃ
勉強してますね。
まいったなぁ、
そういえば 権兵衛さん どうしてるかなぁ。
戦艦扶桑と山城は第一次大戦中の建造ですから旧式艦に分類されるのもしかたのないことかも知れませんね。
それから改装をたくさん行ったため、この二艦は艦隊で過ごした期間より改装のためにドック入りしていた期間の方が長いことで海軍内部でも知られていました。
この二艦は早い時期から重点的に改装をたくさん行っていたため、いざ戦闘をする際には他の艦より全ての装備品が旧式化していたのも旧式艦に分類されてしまう理由となっていました。
毎度毎度タイミングが悪かったともいえるでしょう。
最期はアメリカ軍からの多数の魚雷攻撃とレーダー射撃を受けて弾火薬庫の誘爆を起こし沈みました。
やはり日本はレーダーの技術が劣っていたのは相当痛かったですね。
日本ははじめは八木・宇田アンテナなどを作り出し世界的にも進んでいたのに軍上層部の先を見通す力のなさから早期開発を促進出来ず逆に阻害してしまい欧米諸国に追い越されてしまったことは返す返すも残念なことです。
陸軍などは戦利品の移動式レーダーの使い方を尋問中にイギリス軍捕虜から日本人なのにヤギアレイを知らないのか?
と逆質問され教えられる始末でしたからね。
全くあきれます。
0さんがおっしゃるように、当時の日本海軍は、作戦を重視、情報を軽視し、アメリカの戦力を過小評価、組織軽視、でした、また軍上層部の敗北の隠蔽、
太平洋戦争のレーダーの 暗号解読の重要性を日本海軍は軽視したと言わざるをえません、
日本海軍はイギリスから 「ジェントルマンシップ」を学び
相手の通信を盗むということは、紳士のすることではない、諜報活動は泥棒行為と、
正々堂々と作戦で打ち破る、と言うのが、日本海軍の伝統であり サムライの信念でした、
しかしながら、時代はそれを受け付けてくれません、
かの幕末の戊辰戦争も
徳川幕府軍は、サムライ精神で刀と槍(旧式銃含む) かたや薩摩、長州、土佐は、新式連発銃でした結果はご存知のとうり、「やあやあ我こそは○○いざお相手いたぁす」
の時代が終わってました
話がそれましたが、
真珠湾の責任をとって、更迭された
米連合艦隊司令長官
ハズバンド・キンメル
新任のチェスター・ミニッツ連合艦隊司令長官が最も力をいれたのは、情報であり、日本軍の暗号解読ですね、
当時ハワイにある
太平洋艦隊司令部暗号解読班は、150人、24時間体勢で日本軍の暗号を解読してました、
ヨーロッパでは既に1941年のビスマルク追撃戦の時点でイギリス海軍、ドイツ海軍、共に戦艦にはレーダーを装備していてレーダー射撃で撃ち合っていたそうですから同じころ一方の太平洋戦域で戦い合っていた日本海軍とアメリカ海軍にはまだ出来ない芸当でした。
新型装備を一年早く使えるのと一年遅れて使えるようになるのでは雲泥の差で、戦時下であれば尚のことその僅か一年の間に遅れている側の国はズタボロにされてしまうことを意味します。
これは正に技術力の差です。
直接的な攻撃兵器には熱心だった日本軍上層部、反面間接的な防御兵器にはほとんど無関心。
というかそんな間接的な防御兵器の開発に熱心になっていたら、軍上層部からどやされ迫害される始末でした。
この考え方がよくなかった一大要因だと思います。
特攻をしなくてはならないようになったのもそうですが、持ってない技術を精神力でなんとかしろというのは現実離れし過ぎでした。
メンタル面を高く保つのは良いことですが、出来ることと出来ないことの分別はつけないとダメです。
特に戦争遂行の計画指揮をとる軍上層部にはそれがないとダメでしょう。
その昔(第一次大戦頃)、飛行機が戦争に参加し始めた頃からしばらくの間はその活動は天候によって大きく左右されるものでした。
しかし、時代が進むにつれて世界の国々は二度の世界大戦を経験し、徐々に近代化して行き天候にあまり左右されることなく活動が出来るようになって行きました。
そのように発達した戦闘機のことを全天候型戦闘機と呼びます。
昼夜天候変動の気象条件にほとんど左右されず活動出来る戦闘機という意味です。
戦艦に於いてレーダー射撃が出来るようになるということはそれに近い状態まで進化したということを意味します。
昼夜関係なく濃霧に囲まれ視界がきかなくなっても敵の位置を把握して射撃、命中させることが出来る能力を獲得したということです。
逆の言い方をすればレーダー射撃の出来ない戦艦は昼夜天候変動に左右される盲目状態の戦艦だといえます。
どっちが圧倒的に有利か判ると思います。
暗視装置付きの戦車と暗視装置なしの戦車が闇夜で撃ち合う状況と全く同じなのです。
いくらサイズの大きな大砲を持っていても敵に命中弾を与えることが出来なければ無用の長物ということです。
テレビで随時放送されリアルタイムなお茶の間の戦争報道、テレビゲームのような戦争と呼ばれた湾岸戦争。
イラク軍がズタボロに負けた大きな一大要因の一つに夜間暗視装置がありました。
イラク軍のほとんどが夜間暗視装置なんて装備しておらず、仮に贅沢な装備を与えられた部隊があったにしても古い世代の夜間暗視装置だけでした。
対するアメリカ軍を中心とした多国籍軍は戦闘機パイロットやヘリコプターパイロットから戦車兵、末端の歩兵に至るまで最新世代の夜間暗視装置や携帯型GPS装置などを普通に装備して戦いに従事していました。
陸でも海でも空でもイラク軍の兵士たちはあっけなく敵にやられてしまうはずでした。
視界が遮られる砂嵐や夜間の闇夜で敵には見られているが自分たちは見られていることすら判っていなかったわけですから無理もない。
盲目がゆえに自分がどの敵から撃たれたのかすらも判らないままに死んでいったイラク軍兵士がほとんどだったといいます。
本来撃つべき敵戦闘機や敵戦車が破壊し尽くされて居なくなった後のアメリカ軍兵士は他にターゲットが居ないものだから戦闘機やヘリコプターや戦車の中から夜間暗視装置越しに覗いたイラク人一人一人に照準を合わせ撃ち殺していっていました。
本来、人に向けて撃つものではなく軍用機や軍用車輛に向けて使う大口径機関砲や誘導弾を人に向けて撃っていたのでした。
その時の夜間暗視映像が公開されていました。
技術力の違いから圧倒的な戦力差が生じるとこんなことも起きるという実例でした。
太平洋戦争末期の日本本土でもアメリカ軍の戦闘機パイロットたちは民家や駅や列車や民間人に向けて機銃掃射を日常的に行っていました。
その当時のカラー映像とそこに居て運よく助かった人が出て来る本人証言の番組が去年末だったか今年始めだったかテレビで放送されていました。
九州の福岡近辺の映像でした。
アメリカ軍は正義の味方なんてことはいえない現実を突き付けた番組でした。
イラクでの話を考え合わせるとアメリカ人は現代でも太平洋戦争末期当時と変わらない相変わらずの行いを今尚続けている証拠といえるでしょう。
アメリカ人の頭の中と人殺しを楽しむ考え方は何も変わっていないということでしょう。
0さん、おっしゃるとうりです、![]()
攻撃兵器には熱心だった日本軍上層部、反面間接的な防御兵器にはほとんど無関心。被害の対策など日本の辞書にはないのですね、ミッドウェーで攻撃重視で、空母は丸裸でしたね、
0さんの言われるとうり、防御兵器の開発に熱心になっていたら、軍上層部からどやされ迫害される始末でした。←![]()
持ってない技術を精神力でなんとかしろというのは現実離れし過ぎでした。←![]()
![]()
![]()
第二次大戦以後、戦闘機、ヘリコプターも含む
反動の少ない自動銃、
武装、発達しましたね、
航空機による爆撃は
一般市民に与える災害、被害は、第一次大戦から行われてました、
1923年オランダのハーブにおいて、開かれた、
『爆撃は、軍事的目標に対して行われた場合に適法とする』と定められたが、
1937年4/26 ドイツ空軍による無差別爆撃、スペインの小さな町は、ピカソの絵によって有名ですね、
日中戦争では、日本軍による、南京、勧降、重慶 ルーズベルト大統領は、非武装都市の一般市民を空中から爆撃をする、
非人道的 野蛮行為はさけるよう、アピールすたが全く無力でした、
その後、ドイツはロンドンを無差別爆撃、
イギリスもドイツのベルリン、ドレスデン、ハンブルグ、の無差別爆撃、でした、
昭和20年、米軍サイパン司令官のハンセル司令官は、日本の軍事のみの爆撃を支持した方、転属になり、
ルメール少将に交代したことにより、
東京の空襲、夜間の焼夷弾爆撃が中心になり、
2000トンの爆弾![]()
![]()
![]()
を積んだ 334機が
夜の東京を無差別爆撃、
新任司令官は、『東京のすべてを爆撃せよ』と命令する
それにより10万人近い一般市民の屍が町や川を埋めた、
名古屋の無差別爆撃もしかり、最も犠牲の大きかったのは、5月14日の焼夷弾爆撃で、B29 486機
投弾量256トン、
この日撃墜されたB29から搭乗員数名がパラシュートで降下し、名古屋方面で捕獲され、
散々爆弾で人を殺しておいて、自分だけが助かろうとは 虫がよすぎると
当時の市民のいつわざる感情と日本の東海軍です、
その後、広島、長崎ですね、
東海軍といえば、スガモプリズンで絞首刑になった
岡田タスク中将←漢字ワカラズ![]()
岡田中将いわく
「なにもかにも悪い事は敗戦国が背負うのか!」裁判で、岡田中将は米軍の無差別じゅうたん爆撃.夜間爆弾、焼夷弾使用だけでなくその爆撃方法を非難した、爆撃予定地区を連続爆撃し炎上させ更に市民がその地区から逃げ出せないように全員殺戮ね方法をとった残虐な方法を指摘した、明らかに非合法と、言うが絞首刑となる、
映画「明日への遺言」から抜粋です、
アメリカの主張
日本の真珠湾攻撃は、開戦前、
広島、長崎、原爆投下は 戦争を終わらせる為、
と主張
B級戦犯として スガモプリズンで、拘留されていた
岡田 資(タスク)中将は、 B29パイロット(無線技士含む)を、略式裁判で死刑を命じたのは、自分であり、上官の命令は絶対であるから、実行したのは部下はなんの罪もない、(実際は斬首とか)と主張し、すべての責任は自分であると、部下をかばった、
裁判中、無差別爆撃を非難した、と言うアメリカの面目もあり 絞首刑されましたが
私ヘルシアは、無期刑が相等と感じました、
妻宛の遺言、に涙がでました、
画像は岡田資中将を演じた、藤田まこと、
ヘルシアさん、こんばんは。(゚▽゚)/
日本の広島に落とされたウラニウム型原子爆弾と日本の長崎に落とされたプルトニウム型原子爆弾についてはアメリカ人の間でも意見が分かれています。
アメリカ政府が一貫して世界に言い続けている主張は当時そのままの状況でアメリカ軍が日本本土へ進攻すれば大量のアメリカ兵が死傷することが判っていた、それを出来るだけ減らすために事前に日本が降伏するように仕向ける目的で日本本土に原子爆弾を投下した、アメリカ軍による日本本土への原子爆弾投下によって太平洋戦争は早く終わらせることが出来たしアメリカ軍兵士の死傷者も減らすことが出来た。
原子爆弾投下は必要だったのだ。
という主張です。
これを信じて支持するアメリカ人が大多数です。
しかし、アメリカ政府の主張はプロパガンダであり原子爆弾の投下自体が人類の一員としては最大の大罪だと考えるアメリカ人の人々も居ます。
アメリカ人の中にはアメリカ政府の主張する太平洋戦争早期終結とアメリカ軍兵士の被害低減という目的は理解出来るが、二発を投下したのは何故か?二発目は不必要だったのではないか?
一発目の原子爆弾と二発目の原子爆弾はタイプが異なるため日本本土を使って実戦で実験をしたかったから二発目の原子爆弾を投下したのだろう?
それなら大きな大罪になる。
というアメリカ人の人々も居ます。
しかし、いずれにせよアメリカ政府の主張を信じて支持するアメリカ人が大多数です。
そういう意味では自分の国の政府がいうのだから間違いないと安易に信じ込む人々ばかりではないのがアメリカ人、周囲の人々のいうことに流されるのではなく細かな事柄まで事実を学び知った上で自分自身の頭で考えて物事の良し悪しを判断する人々が比較的多く居るのがアメリカ合衆国だということがいえそうです。
だからアメリカ合衆国では事実関係に基づいてお偉い方々が糾弾されるということが時折起きます。
太平洋戦争日本敗戦後の極東軍事裁判では戦勝国が一方的に敗戦国を裁くという関係上、その裁判のほとんどが戦勝国に非常に都合良く不平等でアンフェアな裁判が行われました。
これは第一次大戦でドイツが敗戦した時も同様に戦勝国に都合良くドイツにとっては不条理な決定がなされさまざまな制限を受けたり多額の賠償金を課せられたりして苦しんだのと同様でした。
『勝てば官軍』という考え方の表現はありますが、事実は世界中の人々が知っているのだから時代が進み考え方が変われば現在正しいとされているアメリカ政府の主張も、それは違うだろうと言われる日が来るかも知れません。
去年だったかアメリカが同盟国の大きな国の一つドイツのメルケル首相の電話をかなり前から盗聴していたことが発覚し問題視され国際的なニュースになっていました。
アメリカもドイツのことを友好国友好国といいながらも本心の奥底では最も警戒すべき国の一つだと認識していた証拠でしょうね。
国連内部では現在でも今だに敵国条項というのがあり日本はその敵国になったままだそうです。
日本に対しても同盟国同盟国、仲良し仲良しといっていながらも本心の奥底ではドイツと同様に最も警戒すべき国の一つだと認識しているのは間違いないでしょうね。
アメリカ自身は口ではいろいろなことをいっていてもアメリカ自身がドイツにも日本にも第二次大戦中に必要以上に酷いことむごいことをした事実を自覚しているだけに、いつか仕返しされるのではないかという恐怖心があるからこそ戦後は荒廃し疲弊しきったドイツと日本に経済援助や物資援助という手を差し延べるかに見せ掛け、ドイツ国民、日本国民の骨抜き政策(贅沢な快楽主義の退廃文化を輸出し愛国心を無くさせ自分の自由や権利を主張するだけに熱心で果たすべき役割は逃れようとする無責任な国民を増殖させる政策)に力を入れたわけでした。
しかし、アメリカがしてきたことを知っている人々は知っている人々でいるのですから全員をそんな(骨抜きに)状態に仕向けるのは無理でしょうね。
ドイツは第一次大戦で敗戦した後、フランスなどが中心になってドイツに突き付けたベルサイユ条約の厳しさに反発するが如く、ドイツがベルサイユ条約の決定条件をのむ調印式に使われた客車を引っ張り出して来て撮影しながら爆破し、ベルサイユ条約を破棄すると宣言、ドイツの戦時映画にも記録され公開されていました。
ヒトラーがとったこのアピール的行動は当時連合国から一方的に押し付けられていたベルサイユ条約に苦しむドイツ国民の心情を代弁していたため国威発揚に大いに役立ちました。
こういうことも伴いながら第二次大戦という戦争が再び世界中を取り巻いて行きました。
こんなこともあったという事実をアメリカは知っているだけに、いつか仕返しされる日が来るかも知れないという気持ちは捨てきれないのです。
当然でしょうね。
アメリカは原子爆弾投下や民間人への絨毯爆撃による大量殺戮をしているのですから仕返しされるかも知れないという恐怖心は消えないでしょう。
私はアメリカへの9.11同時多発テロが起きた時、偶然その時のニュース報道をテレビで最初から見ていました。
最初はいったい何が起きたんだ?と思って見ていましたが、今でもはっきり覚えていることがあります。
最初の映像だけは報道していたアメリカ人が『カミカゼアタック!カミカゼアタック!』と連呼していました。
しかし、それは最初の報道だけで、直ぐにそれ以降は『カミカゼアタック!』と言わなくなりました。
ドタバタしていたはずの緊急事態だったにもかかわらず、直ぐさま報道管制をしき表現を規制したのが物凄く伝わって来ました。
アメリカ人が太平洋戦争末期に日本人がとった決死の行動『カミカゼ特攻』についていかに過敏に反応しているかが物凄く伝わって来るリアクションでした。
『カミカゼ特攻』に触れたくないし、『カミカゼ特攻』のような攻撃は受けたくないという心理的トラウマがあり、ましてや日本人に『カミカゼ特攻』をするしか方法がない状況に追い込んだ張本人は誰だ?と思い出されるのを嫌ったためでした。
アメリカ人は戦争で日本人に対して悪いことはしていないと主張しつつも、アメリカ人は完全なる加害者である事実を自分では認識しているのです。
こららの異常な反応がそれを如実に物語っているのです。
382に書いた列車の爆破ですが、少し前後してしまい済みません。m(__)m
正確には第一次大戦敗戦後に無理矢理受け入れさせられたベルサイユ条約で恨みがあったフランス(第二次大戦前半戦では陸海空軍装備でも兵力でもドイツ軍より優勢といわれていたはずのフランス)を戦略の巧みさによりドイツがコテンパに打ち負かしフランスを占領した後に行った列車爆破です。
この出来事もしかたなかったといえばしかたなかったことですね。
フランスはドイツが第一次大戦で戦争に負けたことをいいことにベルサイユ条約でドイツに賠償金も課した上に保有兵器制限も課し小さな軍事力しか持てないようにしておいて自分は新型装備をたくさん開発し、たくさん装備してドイツ軍に差を付けておいたのに、その圧倒的に有利な環境にあまりにアグラをかき過ぎて弛みきっていてこちらには鉄壁のマジノ要塞があるからドイツ軍は攻めて来ようにも攻めて来れないさなどと思い込み、ドイツ軍の巧みな戦略(ドイツ軍が始めた電撃戦と呼ばれる陸空軍一体のエアランドバトル、空軍の急降下爆撃機ユンカースJu87スツーカに補佐された軽量級戦車と機械化された兵員輸送車を主体とした陸軍による協同作戦での早いスピードによる進軍)の前に大敗する結果を自分で招いてしまいました。
当時はフランス軍の方が戦闘機でも新しいものを持ち、厚い装甲と強力な砲を搭載した戦車を大量に持っていたため、仮にドイツ軍とフランス軍が戦う事態になったとしてもドイツ軍に勝ち目はないというのが世界各国の大方の見方でした。
この状況で大敗を喫したフランス軍はかなり弛みきっていたといわざるを得ませんね。
当時フランスには在仏英軍の戦車部隊がおり、もしもドイツ軍に攻め込まれた場合でもこれがフランス軍に加勢してくれるものと期待され足りない場合にもこの兵力が持ちこたえている間にイギリス本土から追加の増援部隊が来てくれるものと考えられていました。
誠に他人頼みなだらし無さ。
当時のイギリス軍にはマチルダMk.Ⅰという歩兵直協戦車が装備されていて、これは砲はたいしたことはなかったのですが装甲板が分厚く当時のドイツ軍の37mm対戦車砲では貫通することが出来ず苦戦を強いられました。
しかし、この時もドイツ軍の巧みな戦闘方法(本来は高い空を飛ぶ軍用機に向けて使う用途である通称アハトアハトと呼ばれる88mm高射砲の水平撃ち)で分厚い装甲板を貫通させ撃破、結局在仏英軍部隊は追い詰められて行き残存部隊は命からがらダンケルクからイギリスへ逃げるはめになりました。
0さん、素晴らしいですコメントです、![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
今から20年程前、私は仕事でアメリカに行きました、
見るからに私は日本人 アメリカ人は、私達を見て、嫌な顔したりして、 嫌な思いもしたことがありました、
例えば自分の祖父が真珠湾で、日本人から殺された、と、根深く思っている方かも知れませんね、しかし日本人に対して友好な方々も居ます、朝鮮半島や中国もそうです、戦争の爪跡が未だに残ってます、
アメリカは一般市民が、 銃を持つことが出来る国です、
例えば、アメリカのコンビニに行って、「これを下さい」とレジーに差し出し、お金を出そうと胸ポケットに手を入れるとレジーにいたオヤジは、レジーの下に拳銃を取りだし、撃ってくるかも知れません、
何度も強盗にやられているコンビニかも、です、
まぁほとんどの車の運転席のグローブボックスには拳銃が、置いてあると思いました、
アメリカは怖い国です、
0さんの、専門用語
また勉強 しました。
イギリス軍のマチルダMk.Ⅰ歩兵直協戦車装甲板が分厚く,またドイツ軍の37mm対戦車砲では貫通することが出来ない、。
通称アハトアハト88mm高射砲の水平撃ち
↑↑初めて知りました。
ドイツがベルサイユ条約の決定条件をのむ調印式に使われた客車を引っ張り出して来て撮影しながら爆破、
↑↑
知りませんでした![]()
ヘルシアさん、おはようございます。(゚▽゚)/
アメリカは建国当初からのポリシー、開拓者精神があり自由主義で個人主義の国だとよくいわれますね。
そこに自分の身は自分で守る、そのためには銃の所持と使用の合法化…という流れがあり、大成功の可能性と大失敗の可能性を秘めた国であるといえるでしょう。
大成功をおさめた人にとってはこの上なく良い国であり、しかしそれを守るのも自分で守って下さいという自己防衛主義の国。
逆に大失敗となってしまった人にとっては最悪の国になる国でしょう。
世界屈指の多民族の集合体であり良い悪いに関係なく最善と最悪が同居する国それがアメリカ合衆国だと思います。
ということはうまく付き合えば非常に有益な国であり、一方付き合い方を間違えば最悪の敵となる国です。戦死された旧大日本帝國海軍連合艦隊司令長官山本五十六元帥は日本を知りアメリカ合衆国を知った上で日本はかくあるべきだと主張されていましたが、それを聞き入れず彼我(日本とアメリカ合衆国)の差をよく理解出来ていなかった軍上層部と不甲斐ない政治家があまりに多過ぎたのが災いして太平洋戦争開戦へと繋がり、やがては日本の疲弊、荒廃そして敗戦へと誘導する結果を招きました。
このようなことを二度と起こさないためには何が何でも戦争反対!戦争反対!を子供たちに教え、戦争反対!戦争反対!を叫んでいくのが一番だという人たちはたくさん居ますが、私はこの人たちちょっとズレてて違うよと感じます。
この人たちは上辺だけを教え戦争は悪い戦争は悪いという呪文をまる暗記するように強制しているだけなのです。
本当に過去のような戦争を再び起こさせないようにするためには山本五十六長官が主張されていたように己を知り敵のことも知っておくこと。(自分たちと自分たちの国、相手の国の人たちとその国の国力を含むいろいろなことを知っておいた上で身の振り方を考える)このことこそが最重要課題であり、戦争反対!を唱えるかどうかはその次に考えるべきことなのです。
私は日本の戦後の平和教育は完全に間違っていると考えます。
歴史や戦争、戦争兵器を知らずして戦争反対は語れないからです。
なぜ悪いかを本当に理解出来ていない子供たちに『戦争は悪い』という言葉だけまる暗記させているだけなのが戦後から現在までの平和教育であり全くナンセンスそのものだと常々感じています。
マチルダというイギリス軍の戦車は模型化販売された戦車のプラモデルやアニメの登場人物名(機動戦士ガンダム)の影響で知った人が多いと思われますがマチルダMk.ⅠよりもマチルダMk.Ⅱの方が知名度が高いです。
第二次大戦前半戦でドイツ軍が撃破するのに苦労したマチルダMk.Ⅰは元々当時のドイツ軍が持っていた戦車より装甲板が分厚く防御力には定評がある戦車でした。
その後、北アフリカ戦線でもこのマチルダMk.Ⅰの発展改良型であるマチルダMk.Ⅱがドイツ軍の前に現れ、また苦戦を強いられることとなりました。
マチルダMk.Ⅱも装甲板が分厚く防御力が強力だったのでした。
この時もドイツ軍は88mm高射砲の水平撃ちの貫通力に助けられ、なんとかマチルダMk.Ⅱを撃破することが出来ました。
蛇足ですが、この頃のイギリス軍戦車は徹甲弾しか使っておらず、ドイツ軍戦車は徹甲弾と徹甲榴弾を使っていました。
徹甲弾とは敵戦車の装甲板を貫通させるのが目的の砲弾、徹甲榴弾とは敵戦車の装甲板を貫通した後に炸裂し内部を破壊する目的の砲弾。
その関係上、ドイツ軍に破壊されたイギリス軍戦車は再利用が出来ない。
一方、イギリス軍に破壊されたドイツ軍戦車は装甲板に穴が空き乗員が死傷しても再利用が可能だという変な現象が起きていました。
なんだか間の抜けた話のようですが、これで両軍の戦力バランスがちょうどとれていたようです。
第一次大戦で世界初の近代的戦車を戦場に送り出したイギリスも第二次大戦のほとんどの期間は戦車開発に関しては良いものに恵まれず失敗作続きが長く続きました。
伝統を重んじるイギリスでは陸軍の場合は兵士が主役であり戦車は兵士を助ける協力者であるとする保守派が根強く、まともな対戦車戦闘用戦車はなかなか生み出されませんでした。
だから当時のイギリス製戦車の大半は歩兵直協戦車や巡航戦車などという名前が付く戦車ばかりです。
戦闘の主役を演じる本格的な対戦車用戦車を誕生させてしまえば歩兵の仕事が奪われてしまうという考え方が保守派勢力に働いた結果、兵器開発の進歩を邪魔する結果を生み出したのでした。
この現象は同じ頃の日本の陸軍内部にもあり日本製戦車の開発発展を大いに邪魔し貧弱な戦車しか作れない状態を生み出してしまっていました。
当時のアメリカ製戦車と並んだだけで子供みたいにしか見えない貧弱な日本製戦車はブリキの棺桶とあだ名される始末となりました。
今の社会でもどこの集団でも大いにいえることとして新しいものが入って来る際にスムーズに導入されるかどうかはその集団が革新派が多いか保守派が多いか次第に左右されるということです。
文章だけでは面白みに欠けるでしょうから参考資料となる画像も貼っておきますね。
【イギリス軍】
マチルダMk.Ⅰ
主砲12.7mm重機関銃、装甲は最大部で65mm
マチルダMk.Ⅱ
主砲52口径40mm砲、装甲は最大部で78mm
【ドイツ軍】
88mmFlak18
56口径88mm高射砲18型
です。
北アフリカでロンメル将軍率いるドイツアフリカ軍団の地上設置された88mm高射砲に撃破された後のイギリス軍戦車部隊の兵士は「高射砲で戦車を撃つなんて卑怯だ!」といったそうです。
これを聞いたドイツ軍兵士は「高射砲以外では貫通出来ない装甲の戦車で攻めて来る方がもっと卑怯だ!」といったそうです。
水掛け論ですね。(笑)
0さん、こんばんわ〜![]()
![]()
引っ越してました![]()
![]()
戦車とバズーカ、どんどん進化してますね、
以前テレビでヒストリーチャンネルで、やってました、
戦車の装甲板を厚くしてもバズーカ砲が当たると戦車の中のビスが乗組員を直撃し死傷者が出たそうで、
また バズーカ砲対策として、
日本の戦国時代の鎧のような 板を何枚もぶら下げその板は爆薬が仕掛けており、
バズーカの砲弾を、戦車に当たった瞬間に、砲弾を瞬時に爆発させると言うものでした、
またそれに対向する砲弾がまた 開発され、
きりがありませんね、
高初速の鉄鋼弾があたり装甲を貫通出来なかった時に内側のビス、又は装甲の一部が剥離して、乗員を殺傷したそうです。バズーカの弾や、ドイツのパンツァーファスト等は成型炸薬弾と言い低速でノイマン効果を利用して内部に高温高圧のガスで焼き殺すものです。
鉄鋼弾の防御策のひとつにアクティブアーマーがあります。本体装甲の外側に爆薬付の予備装甲を付けるものです。成型炸裂弾の防御策は隙間をつくる事です。あとチョバムアーマーとかもありました。
皆さん、こんばんは。(゚▽゚)/
その成形炸薬弾頭を装備したバズーカや対戦車ロケット弾に対抗するために使われるという外付けの板のような爆薬入りの箱はイスラムが開発したブレザーというERA(エクスプローシブ・リアクティブ・アーマーの略称です)です。
中東戦争でシリア軍の歩兵携帯型ロケット弾により戦車部隊が壊滅状態にさせられたイスラム軍が研究に研究を重ね世界で初めて実用化したものでした。
その後世界各国が真似て作るようになり現在に至っています。
ERA開発以前の話ですが、戦車の発達でいうと第二次大戦中のドイツ軍のⅣ号戦車を見ていくと非常に興味深いですよ。
元々Ⅳ号戦車はⅢ号戦車を補佐する役割で短砲身の75mm砲を装備して登場しました。
火力支援の補佐役といった位置付けでした。
結果的にはⅣ号戦車はドイツ軍の軍馬的使われ方をしました。
時期毎の様々な脅威に随時対応しながらたくさんの改良型が登場しました。
長砲身化を図ったりスペースド・アーマーなど様々な追加装甲を施したりしてA〜J型まで、その後もソ連がドイツ軍から捕獲したⅣ号戦車をパレスチナ側の国に与えたため中東戦争の時代にまでも実戦使用されていた息の長い戦車でした。Ⅳ号戦車の発達を見ていくと面白いです。
非常に勉強になること間違いないです。
そのERA=エクスプローシブ・リアクティブ・アーマーは日本語に訳すと爆発反応性反動装甲といいます。
成形炸薬弾頭のメタルジェットが戦車の本装甲を突き破る前にERAの爆発の爆風によって吹き飛ばすことを目的にしています。
395、396の中で文字入力を間違えていました。
イスラム、イスラム軍は間違えで正しくはイスラエル、イスラエル軍です。
ごめんなさい。m(__)m
0さん今晩はです。いつも勉強させてもらっています。私も四号戦車シリーズが大好きです。
鉄鋼弾間違えてましたね![]()
イスと入力して出て来た文字をよく確認せずに入力してしまい気付いたらイスラエルと入れたつもりがイスラムとなっていて、イスラエルのことをイスラムと表現したらまるで違う内容になってしまいます。しかし後の祭りでした。
申し訳ないです。
訂正してお詫びします。
ごめんなさい。m(__)m
シリア軍が大量使用してイスラエル軍戦車部隊を壊滅状態に落とし入れた歩兵携帯型ロケット弾も、現在世界各国で大量装備されている歩兵携帯型ロケット弾も元を正せば第二次大戦中ドイツ軍が使用していたパンツァーファウストの子孫のような関係です。
きんたさん、そうです
まさに そのとうりの事がヒストリーチャンネルでやってました、![]()
![]()
さすが0さん、詳しくありがとうデス、
Ⅳ号戦車ですね、
調べて勉強します![]()
サイトよりコピペです![]()
戦車と言えば、「きゅらきゅらきゅら」と音が聞こえますね、画像は冬のロシアで戦うⅣ号戦車F2・G型
しかし東部戦線ではT−34に、西部戦線ではM4に撃破された
「角張って、ちょっとカッコイー戦車
タイガーじゃぁないなぁ
75mmKwK40L43
威力!!」
75mm?そう言えばこのタイガー、ちょっと小さいような気が・・・・・」
ドイツが誇る
Ⅳ号戦車ですね
アミー共は本車をティーガーと勘違いしている。パンター
でさえティーガーと呼んでるほどのレベルしかないのですが。」
いわばドイツの代表戦車ですね。」
Ⅳ号戦車と言えばA〜jカナ?
「Ⅳ号戦車はそもそも75mm砲搭載の20t級支援車両として開発されたもので。当初の名称は7.5cm砲装甲車で、1937年から
Ⅳ号戦車と名称が変更された。量産型のA型は1937年から35両生産され、ポーランド戦から参戦している。
エンジンはマイバッハHL108、時速は31km/hである。砲塔旋回は電気式。」
短砲身はやっぱり弱そうですが
今でこそ75mmKwK37L24は威力が弱いと思えるが、 当時のレベルでは最強の戦車砲
当時は戦車戦など考えもされていなかった。」
日本の97式中戦車もそうですね。ノモンハン事変で最新鋭であったのにBT5にぼろ負け・・・・・」
「イワン共だけは当時37mmが主流の戦車砲に対して、45mm45口径を採用していたとか。」
「当時は貫徹力より榴弾威力が重視されてましたね。戦車は戦線突破用でしたから。Ⅳ号戦車は防御も優れてたのかな?」「装甲厚は全面15mm
。小銃弾・弾片防御
しか考えられてなかった。」
増加試作的なものだからB型からは前面30mmに増加している。」
「いくら短砲身とはいえ、ドイツ戦車はカッコイーですね。」
「B・Cともあまり変わらない。エンジンが排気量の大きいマイバッハHL120に換装されたため、時速40km/hを誇った。」
ドイツの誇る、Ⅳ号戦車
Ⅳ号戦車
砲身が長いけど
Ⅳ号戦車カナぁ?
↓↓
四号戦車はA型B型C型までは、試作もしくは増加試作。D型E型F1型が短砲身型。F2型43口径75㎜砲。G型H型は48口径75㎜砲。最終型の簡易生産型のJ型。それ以外にも、四号突撃砲。パンテルと同じ70口径75㎜砲を搭載した四号駆逐戦車。88㎜砲をオープントップで搭載したナースホルン。150㎜榴弾砲を搭載したフンメル。20㎜四連装機関砲を搭載したメーベルワーゲン、ヴエルヴィルウィンドウ。37㎜機関砲を搭載したオストウィンドウ。等々バリエーションは世界一ではないでしょうか?
あとイタリア戦線で活躍したブルムベアもありました。
第一次大戦に敗れ敗戦国となってしまったドイツは戦争に敗れたがゆえに戦勝国から様々な制約(一部領土を奪い取られ、兵器開発の禁止や僅かな軍隊しか持ってはいけないなど)を課せられ多額の賠償金も課せられ辛く厳しい時代におかれることになりました。
戦勝国からの様々な制約を受けながら国としては頑張っては賠償金を払い頑張っては賠償金を払いを繰り返していましたが、その辛く貧しくいつまでたっても良くならない生活にドイツの全国民は嫌気がさしていました。
そんな報われない時代を背景にドイツ国家社会主義労働者党=ナチスドイツが熱狂的な国民の支持を受けて台頭することになりました。
第二次大戦後は一般的にはナチスドイツは悪の塊であるという宣伝活動が氾濫し、それが一番正しいことのように広められています。
この活動は世界中に拡がって住むユダヤ人資本家によるものです。
昔々からユダヤ人資本家は国の違いなど問わず世界中に力を及ぼしていますからね。
ナチスドイツはその正式名称が示す通り戦争で負けることさえなければ常にドイツ国民の事を真剣に考えている党でした。
それは既得権益や賄賂に大きく左右される現代の政党に比べれば段違いに真剣でした。
ナチスドイツは国家ぐるみでの労働の場の提供からインフラの整備やモータリゼーションの推進、それらによって得られた収入をより多く国民へ還元し経済を活性化させるために役人の天下りを禁止し、役人たちや各会社の上層部が収益金をピンハネしないように常に監視して見張るということまで実行していました。
現代の腐敗しきった政党の政治家には彼らの爪の垢でも煎じて飲ませたいくらいに真剣そのものでした。
歴史、政治の話が長くなってしまいましたが、ナチスドイツの台頭と共にドイツは理不尽なベルサイユ条約破棄を宣言し再軍備を始め次々と破竹の勢いでヨーロッパの大半を占領下におく快挙を達成しました。
そこでやめておけばよかったのですが、ヒトラー総統は膨らむドイツの人口を支える領土を拡張する目的で軍隊を東へソ連の領土へと進攻させたためソ連製戦車と戦うはめになりました。
最初は敵は旧式戦車ばかりだったので苦戦することなく進攻しました。
しかし、その後は新型戦車(T-34中戦車、KV-Ⅰ重戦車、KV-Ⅱ重戦車など)が現れ苦戦することとなりました。
中でも大量に進撃して来る高い次元でバランスの取れたT-34中戦車にはドイツ軍戦車も圧倒され「T-34ショック」と呼ばれる一大衝撃を受けています。
この衝撃によって、その後開発されたドイツ製戦車はシルエットからして変貌を遂げ更に強力な戦車へと進化していきました。
T-34中戦車の良い部分をドイツ人なりに理解して出来るだけ取り込み開発されたのがⅤ号戦車パンターやⅥ号戦車ティーガーⅡでした。
T-34中戦車自体は数値的には圧倒的に強力な戦車というわけではなかったのですが、新しい考え方がたくさん盛り込まれており全ての項目が比較的高い数値で完成されていました。
1942年レニングラード付近を行く増加装甲付きT-34中戦車76mm砲搭載1941年生産型の写真を貼ります。
正面からの眺めはまるで山のような姿であり戦車としては正に理想的な外形で造られていたことが一目見ただけでも良く判ります。
私は昔から自分独自に世界三大ショックというものを考えていました。
その三つとは…
・ゼロショック
・T-34ショック
・ミグショック
です。
ゼロは日本の零戦のこと。
T-34はソ連のT-34中戦車のこと。
ミグはソ連のMig-15ジェット戦闘機のこと。
いずれの場合もこれらと戦場で遭遇した敵軍があっけに取られるほどにやられまくりショックを受けてその後の自国製兵器には影響が現れたものばかりです。
人間というものは失敗を繰り返すことによって成功を勝ち取り進化して行くものです。
その人間が作り出す戦争兵器も敵にやられる経験を積むことにより次に改善改良され高性能化して行くものです。
敵と戦うと必ず敵の優れた部分の影響を受け、次に作る兵器は敵の良いところを取り込んだものになります。
アメリカ軍は太平洋戦争で日本の零戦にやられまくった苦い経験から零戦に対する戦闘方法や零戦を凌駕する性能の戦闘機を作り出そうと躍起になりました。
その後アメリカが作った戦闘機は日本の零戦に影響されたものばかりでした。
第二次大戦の東部戦線でソ連製T-34中戦車にやられまくった苦い経験からドイツ製戦車もその後開発されたものは皆ソ連製T-34中戦車の優れた部分の影響を受けたものばかりでした。
朝鮮戦争でソ連製Mig-15ジェット戦闘機にやられまくった苦い経験からアメリカ軍は第二次大戦で手に入れていたナチスドイツのジェットエンジンと後退翼の技術を急遽アメリカ製ジェット戦闘機に取り入れて作り出したノースアメリカンF86Fセイバーを実戦投入しました。
一足先に同じく奪い取っていたナチスドイツの技術を取り入れていたソ連製Mig-15ジェット戦闘機とそっくり瓜二つの姿でした。
アメリカ人もロシア人も最初から戦争兵器開発に優れていたわけでもなんでもない、こんな感じでしょうね。
最新兵器では注目されることの多いイージス艦も元を辿れば日本人によるカミカゼ特攻隊の必死の体当たり攻撃に曝された苦い経験が元になっていることはあまり語られることはないようですね。
0さんおはようございます。 過去の教訓を取り入れて進化しているのですね?機雷と潜水艦による海上封鎖によって苦しめられたから、対潜能力が飛躍的に向上したのですね?掃海部隊は、戦後から実戦が始まったような? 今瀬戸内が安全なのは、彼等のお陰なのですね。朝鮮戦争のインチョン上陸作戦の露払いをしたのもたしか日本でしたよね?
こんばんは。(゚▽゚)/
太平洋戦争に敗戦し戦勝国アメリカから押し付けられた現在の平和憲法というものがありながらも半ばアメリカ軍に騙され強引にやらされた感じが否めない朝鮮戦争時の日本による機雷掃海活動でした。
そんな経緯もあったため死傷者まで出しながらも確実な成果を残した日本の部隊に対し評価する旨の報告書は残されていますが、経緯が経緯だけにおおっぴらに公表することは避けられているようです。
日本の部隊に白羽の矢がたったのは当時極東地域にはアメリカ軍の掃海艇も熟練者も少なく大半はアメリカ本土にあったのと戦争当事者である韓国海軍自身が未熟なため確実な掃海作業を求めること自体無理だったからでした。
それからアメリカ軍は太平洋戦争末期に港湾を含む日本周辺の海に一万数千個に及ぶ各種タイプの機雷をB-29の数百機編隊で敷設していました。
中には戦争終結予定の時期には機能を停止する時限式機雷もありましたが、それは一部の機雷だけでした。
戦後日本の掃海部隊はそれらの膨大な数の各種タイプの機雷をシラミ潰しに掃海していきました。
おっしゃる通り、現在私たちが港湾を含む日本の海を安全に利用出来るのはそんな日本の掃海部隊の皆さんの尽力のお陰なのです。
それにしても腹が立つのは国際的にも今だに日本の悪口しか言わない韓国人どもの役に立たない不甲斐なさです。
日本に対しては言葉では言い尽くせないほどの様々な恩を受けていながら(今現在でも恩恵を受け続けているのに)大統領や国連事務総長という責任重大な立場にいる者までが礼儀知らずの恩知らずですから韓国人には空いた口が塞がりません。
誰も来ないようなので、スレのタイトルに近いジャンルの写真を一枚貼ります。
個人的にはレアな写真だと思います。
編隊飛行中の陸軍三式戦闘機飛燕Ⅰ型の写真の復刻カラー版です。
飛燕は川崎飛行機製の戦闘機で液冷式エンジン(ドイツのダイムラーベンツ製DB601倒立V型12気筒液冷式エンジンを日本の川崎が国産化したハ40)を搭載した戦闘機で究極の軽戦であった海軍の三菱零戦とは対極に位置する重戦に近い性格も併せ持った中戦とでも呼ぶべき戦闘機でした。(重戦と軽戦の長所を併せ持った戦闘機という意味です。)
先の尖ったスリムな胴体とアスペクト比の高い主翼(縦横比が高く細長く主翼幅の広い翼)が特徴のスマートな戦闘機でした。
エンジンさえ信頼性が高ければ…
低中高度、低中速度域での格闘戦には小回りが効き無敵を誇った零戦もそれらを生み出す重要要素となった軽量化のつけから最大速度が遅く機体強度が弱いという欠点を抱えていました。
零戦もアメリカ軍に捕獲され詳しい調査を受けた後の太平洋戦争中盤戦以降は最大速度が遅く機体強度が弱く防弾装備らしきものは皆無なことを知られてしまい、そのウィークポイントを突かれ苦戦の連続を強いられました。
太平洋戦争前半戦でいとも簡単に撃墜出来ていたアメリカ軍のカーチスP-40キティーホークやグラマンF4Fワイルドキャットにもてこずる始末。
理由は調査で判明した零戦の弱点を突く戦闘方法をとるようになったからでした。
機体強度が貧弱だった零戦は急降下制限速度も630km/hと低く、これを越えて飛行すれば空中分解してしまうためアメリカ軍戦闘機は零戦の急降下制限速度より速い速度で急降下して逃げる術を身につけていました。
日本側もこの欠点は理解しており零戦も改良が重ねられる度に機体強度の強化が図られ最終的には740.8km/hまで引き上げられましたがアメリカ軍新型戦闘機グラマンF6Fヘルキャットなどの急降下制限速度は840km/h前後と更に高い速度でした。
陸軍の三式戦闘機飛燕の急降下制限速度は速度計を振り切り1000km/hを越えるほどに高いものでした。
三式戦闘機飛燕をエンジンだけ空冷式の金星エンジンに換装して成功した五式戦闘機の急降下制限速度は850km/hまでは問題なくかなり頑丈な機体でした。
0さん、![]()
こんばんわ〜![]()
![]()
久しぶりの零戦の話し
ありがとうm(__)mです、
お隣の国に関しては
0さんの主義主調と 全く同じです。![]()
久しぶりの零戦談話
嬉しいです
皆さんお久しぶりです!!三週間休みが無い!ただ疲れております。三式戦『飛燕』大好きです。
0さん、きんたさん
画像ありがとうm(__)mです、
陸軍三式戦闘機飛燕Ⅰ型の写真
まさに、0さんが以前言われた、「オチョボクチ」ですね、
きんたさんは、プラモデルをそれだけたくさん
つくって らっしゃる
と言う事は、
かなり勉強されてますね
私は、チョイかじっただけ の零戦でしたが、
深い所まで、勉強しましたよ、
当時の零戦の ガソリンはレギュラー?
ハイオク ?
アメリカのグラマンF4F
のガソリンは?
もし当時のアメリカのガソリンを、零戦に給油してたら?
私は自分の車(マークX)
レギュラー入れてましたが ここ最近ハイオクにしました![]()
やはり 低速時からの加速、
エンジン音が靜
若干の燃費向上
と感じました、
こんばんは。(゚▽゚)/
三式戦闘機『飛燕』、飛ぶツバメと書いて飛燕。
スマートさではやはり一番カッコイイ戦闘機でした。
第二次大戦当時ヨーロッパ諸国では空冷式エンジン搭載の高性能な戦闘機は非常に少なく、空冷式エンジンより技術力も手間もかかる液冷式エンジンの方が一流のエンジンだと考えられていた節がありました。
だからイギリスもドイツもフランスも軒並み液冷式エンジンを主力戦闘機に採用していました。
一流の高性能戦闘機を作るなら一流のエンジンを搭載しなくては…という発想でしょうね。
しかし、一流の高性能なエンジンは良いのですが、開発と生産と運用は空冷式エンジンよりも難しいため戦争に使用するならそれなりの技術力と運用知識が必要不可欠でした。
ちなみに私が以前「オチョボグチ」と表現していたのはイギリス軍のスピットファイアMk.Ⅴの熱帯地域仕様のことです。
スピットファイアMk.Ⅴの熱帯地域仕様は防塵フィルター付きの空気取り入れ口が機首下面に付いていたため、同じ先の尖った液冷式エンジン搭載戦闘機でも機首下面が大きく膨らみ空気吸入口はヒョットコみたいな極端な形をしていました。
太平洋戦争当時日本が使用していた航空燃料は87〜93程度のオクタン価でした。
アメリカ軍は太平洋戦争全期間を通して100オクタン価の航空燃料を使用しており、高級な燃料ではグレード130オクタン価の航空燃料すら使用している場合もありました。
ちなみに日本の現在のレギュラーガソリンは90〜91オクタン価です。
日本の現在のハイオクガソリンは100オクタン価です。
しかし、ハイオクガソリンを使えば高い性能が出せると単純に思われがちですが、ハイオク仕様のエンジンなら設計仕様に近い性能が出せます。
一方、ハイオク仕様ではないエンジンにハイオクガソリンを使用しても性能が上がることはありません。
元々の仕様が違うため、調整でもしない限り吹け上がりは悪くなり良い結果は得られません。
良い結果があるとすればエンジン内部の清浄効果があるかないかくらいです。
エンジンの仕様に合った燃料を使うのが一番最良だと思われます。
マークXに乗られているのならプレミアム仕様(ハイオク仕様エンジン搭載)なのでは?
現在の日本のハイオク仕様車はハイオクガソリンよりオクタン価の低いレギュラーガソリンを使用しても車の側で自動調整されるため実用上問題を発生させないようになっています。
そして、ハイオクガソリンを使用した場合は設計仕様に近い本来予定通りの高性能を出せるようになっています。
その逆のケース、ハイオク仕様ではない車の場合は高い値段のハイオクガソリンを入れて使用しても得られるメリットはほとんどありません。
昔、日本でハイオクガソリン販売開始が盛んに宣伝されていた頃に中型のオートバイに入れて試してみましたがバワーが上がることはなく何だかかぶり気味で吹け上がりは悪かったです。
その後レギュラーガソリンに入れ換えたらかぶり気味だったのも解消し吹け上がりもよくなったのを覚えています。
エンジンは当時としては超高回転エンジンでしたが(18500回転からレッドゾーンが始まる超高回転エンジン)当時ハイオク仕様のエンジンを搭載したオートバイなんて存在していなかったので当然の結果だったのかも知れません。
0さん、ありがとうございます、
なんせ 中古車を買って、レギュラーを入れてました、スタンドの方が
車の為、ハイオクがいいよ、と言われ、
ハイオクにしました![]()
ガソリン吸入口を開くフタに、無鉛プレミアム・と書いてありましたが、わけわからず、レギュラー入れてました、
零戦は、ハイオク仕様ではなかったみたいですね
もしハイオク仕様の設計であれば、すごいでしょうね、
第二次対戦当時の軍艦はまさか、石炭かなぁ
第二次対戦←×
第二次大戦←〇
失礼しました<(_ _)>
ヘルシアさん、こんばんは。(゚▽゚)/
意味は判るので全然OKですよ。(^O^)
続きです。→ハイオクガソリンとはレギュラーガソリンより点火しやすい燃料だと思っている人は意外に多いのですが、実は逆であり引火点を高くするためにいろいろな添加剤を配合して点火する温度を上げている簡単には点火し難くしてある燃料なのです。
引火点を高くした燃料でより多く圧縮して点火時期を遅らせて点火すると同じ量の燃料でもより大きなパワーが発生する、これを求めて開発されたものなのです。
そして高圧縮と点火時期を遅らせることをしていない状態では簡単には点火しない性質を持つということは異常燃焼や異常爆発を起こさないということですからノッキングなども起こらなくなるということなのです。=エンジンの調子が良くなるということです。
だからこれらのチューニングが出来ていないエンジンにハイオクガソリンを入れてもパワーが上がることはないのです。
日本陸軍の三式戦闘機川崎飛燕Ⅰ型はドイツのダイムラーベンツ製DB601倒立V型12気筒液冷式エンジンを川崎で国産化したハ40を搭載していました。
国産化の元になったDB601エンジンはドイツ空軍主力戦闘機だったメッサーシュミットBf109Eの搭載エンジンでもありました。
そして、このDB601エンジンはイタリアでもアルファロメオRA1000RC41として国産化されてイタリア製戦闘機の改良版高性能化戦闘機の製作に大いに貢献しました。
このエンジンを使い誕生したのがイタリア空軍のマッキMC202フォルゴーレ(フォルゴーレとは稲妻の意味)でした。
したがってこれら三機種の戦闘機、ドイツ空軍のBf109と日本陸軍の飛燕とイタリア空軍のMC202は心臓部に同じ系列のエンジンを持つ戦闘機であり母なる国は違えども兄弟みたいな関係の戦闘機でした。
これら三機種の参考写真を貼ります。
同じ系列のエンジンを搭載しながらも完成したものはご覧の通りそれぞれのお国柄や国民性を色濃く反映させたものとなりました。
性能や性格もかなり違っていました。
アメリカ軍は戦場で目にした日本の三式戦闘機飛燕のことを最初はドイツかイタリアから輸入したメッサーシュミットBf109EかマッキMC202フォルゴーレだと思い込み日本がこの手の液冷式エンジン搭載の戦闘機を自力で作れるはずがないと見下していました。
しかし、次第にそれが誤りであることに気付くと飛燕に対しイタリア製MC202に似ているということからでしょうかトニー(当時のイタリア系移民のアメリカ人に最も多かった名前)というコードネームを付けて呼ぶようになりました。
どうしても日本人のオリジナル開発の戦闘機である事実を認めたくなかった当時のアメリカ人の日本人に対する差別的感情が物凄く伝わって来ます。
飛燕同様、日本人が作り出した零戦の存在を認めようとしなかった太平洋戦争初期のアメリカ首脳陣、いや認めたくなかったというのが偽らざる真実だと思います。
それだけ日本人のことを見下していたのは事実だと思います。
0さん、こんばんわ〜、
ハイオクのガソリンの事は、よく解りましたよ、 ありがとうございます、
零戦と三式戦闘機飛燕の 違いがわかりません、![]()
ヘルシアさん、お早うございます。(゚▽゚)/
ヘルシアさんが零戦と飛燕の違いが判らないということでしたので零戦二一型と飛燕Ⅰ型の同一縮尺での比較三面図と零戦二一型透視図解と飛燕Ⅰ型透視図解を貼りますね。
両機ともそれぞれ全く違う特徴が一目瞭然だと思います。
どちらも全幅、全長はほぼ同じですが機体形状、胴体の太さ、主翼の広さ、正面面積の狭さがまるで違い、これに重量とエンジン出力の違いが合わさり飛行性能と飛行特性はまるで違うものになりました。
そもそも艦上戦闘機と陸上戦闘機というだけでも要求される性能や特性が異なるため出来上がるものに違いが出るのは自然な流れでした。
0さん、画像ありがとうm(__)mです、
画像は一目瞭然ですね、
航続距離とか、旋回機能、機銃の違いとか?
すみません![]()
![]()
![]()
世界的にもいち早く一撃離脱戦法に特化した戦闘機のご本家メッサーシュミットBf109Eはラジエーターを両主翼下に各一カ所、合計二カ所配置していました。
一方、日本の川崎飛燕Ⅰ型とイタリアのマッキMC202は両機とも共通して胴体中央の操縦席下斜め後方に配置していて日本人設計技師とイタリア人設計技師の考え方は近かったようです。
同じく液冷エンジン搭載戦闘機でドイツからアメリカへ移住した移民設計技師(エドガー・シュミット)が設計した第二次大戦期のベスト戦闘機だと世界的にも評されるノースアメリカンP51ムスタングも同様のラジエーター配置でした。
ちなみにイギリスのスーパーマーリン・スピットファイアはドイツのメッサーシュミットBf109Eと同様のラジエーター配置でした。
どちらが優秀だったかといえば冷却効率と空力特性や整備性、被弾時の耐久性などを総合して考えるとムスタングや飛燕やMC202の方式だと思われます。
イギリスとドイツは昔から常にライバル意識が強くどちらも複雑な造りでも高級指向の高性能なものを敢えて好むようなところがあったようです。
この両者は主脚の収納方法までそっくりでどちらも外翼側に引き込む方式でした。
わざわざそのようにした理由は機銃などの主翼内収納スペースを出来るだけ確保したいという考えからでした。
面白いものでライバル意識の強かったこの二国、ドイツとイギリス。
Bf109もスピットファイアも期せずして同じような主脚引き込み機構にしたお陰で主翼内の機銃収納スペースは確保出来たのですが左右の主脚の間隔(自動車でいえばトレッド幅)が必然的に狭くなり安定性が悪くなり離着陸が難しい戦闘機になってしまいました。
ここを良くすれば、あそこが悪くなり、という具合でまるでパズルゲームみたいな状況でした。
Bf109は翼面積を小さくとって加速性と速度性能重視の一撃離脱戦法を得意とするように作られ、スピットファイアは翼面積を広くとって小回りの効く巴戦を得意とするように作られた戦闘機で、性格は違っていましたが、使用する地域もヨーロッパで同じであり大きな意味での運用の考え方が似通っていたこともあり航続距離が短くどちらもせいぜい650〜700km前後しかありませんでした。
アジア太平洋地域を作戦活動範囲としていた日本の零戦(11時間近く飛び続けられる航続距離の長いタイプでは破格の距離3325km前後もありました)に比べると雲泥の差でした。
これも運用の考え方の違いからくるものだと思います。
ドイツのメッサーシュミットBf109は直線的な角角した翼で構成されたいかにもドイツ的、武骨なイメージの戦闘機。
イギリスのスーパーマーリン・スピットファイアは零戦の前作である九六式艦上戦闘機の翼にも似た葉っぱのような楕円翼で構成されたお上品な貴族的イメージの戦闘機でした。
と私は思います。
しかし、お上品な戦闘機とはいえスピットファイアは度重なる改良に次ぐ改良に耐え高性能なロールスロイス・マーリンエンジン→グリフォンエンジンに支えられ英国を守り抜きました。
これもひとえにマーリンとグリフォンという高性能なエンジンがあったからこそのお話でした。
そう考えると零戦を筆頭に日本の戦闘機は信頼性ある高性能エンジンがなかった故に軒並みどの飛行機も改良すれども性能上がらずばかりの繰り返しで苦汁を舐め引いては太平洋戦争に敗戦する結果に結び付きました。
日本よりはエンジン技術が進んでいたアメリカも当時はイギリスに比べれば未熟なエンジン技術でしかありませんでした。
イギリスからのマーリンエンジンの技術供与によりエンジンを換装し世界的な最優秀戦闘機に生まれ変わったノースアメリカンP51ムスタング戦闘機も当初はマーリンエンジンをアメリカでライセンス生産する前段取りで話を持ちかけられた際アメリカのエンジン製造メーカーはとても自分たちの技術力では手に負えないと尻込みしたそうです。
それくらい液冷式エンジン技術分野ではイギリスとアメリカの間で技術格差があったようです。
今の日本人はアメリカは凄いアメリカは凄いと只単に思い込んでいる節が多分にありますが、レーダーにしてもジェットエンジンにしても様々な兵器分野ではイギリスにたくさん教えてもらい戦後はナチスドイツから奪った技術を元にして学び今現在のアメリカになっているのでした。
元を辿ればジェットエンジンも後退翼もロケットやミサイルもミサイルの誘導技術もステルス技術さえも第二次大戦後にナチスドイツから奪った技術が元になっています。
宇宙開発技術も同じです。
アメリカが元々持っていた技術ではありません。
>>422
しかしながら
ダイムラー製エンジンのあまりの緻密で繊細なエンジンを
日本の技術では均一性をもって量産することも整備する事も出来ませんでした
「飛燕」の低い稼働率は遅れた技術と体制そのものを如実に表しており
欧米、とくに当時世界最先端の工業力を誇ったドイツは雲泥の違いでした
大戦中に日本に寄港したドイツ潜水艦にたいして
日本側が技術を習得したいという思いもあって、整備させてほしいと申し出ましたが
ドイツ側はそれを激しく拒絶して、いっさい触らないでほしいと返答しました
自分たちの命を預けるものに日本の遅れた技術で整備してほしくないという
当時のドイツ潜水艦の乗組員の気持ちが痛いほどわかります
当時の日本の技術を過大評価してはあまり意味がありません
欧米とは歴然たる、超えられない壁があったのです
412で書いておいた通りです。
エンジンさえ信頼性が高ければ…と。
但し、エンジンの信頼性が低かった要因は当時の日本の技術力不足もありますが陸軍の場合は必要不可欠な金属材料の使用制限があったことも大きな要因です。
たとえ仮に技術力があったとしても本来必要な金属材料を使ってはいけないと禁じられたら作れるものも作れるはずがない話でした。
それから潜水艦の技術にしても基礎的な技術からしてドイツと比較したら日本の方が技術力が低く運用知識も低かったのは周知の事実です。
エンジンのマウント方法なんていう基礎的な部分から違いがありました、それも周知の事実ですよ。
日本から遥々ヨーロッパのドイツ軍占領下のフランスのロリアンまで行って再び日本まで戻ることが出来た遣独隊の伊號潜水艦は帰りはノイズが静かになって帰りました。
エンジンのマウントから何からノイズ発生源低減のための手直しをドイツによって行ってもらったからでした。
という具合にこのような基礎的部分から日本とドイツの技術力の差は歴然でした。
他の多くの分野でも同様でした。
しかしそれは皆さん知っている話です。
その上で敢えて関連話を書いている話なのです。
何でも始めからダメダメといってしまえば話はそこでおしまいでしょう?
ビックリしてました、
↓↓
ジェットエンジンも後退翼もロケットやミサイルもミサイルの誘導技術もステルス技術さえも第二次大戦後にナチスドイツから奪った技術。
宇宙開発技術も同じです。
アメリカが元々持っていなかった。
ドイツと言う国はすごいなぁ、
今でも、madeinジャーマニィ、は高級品ばかりですね、
ナチスドイツもよくよく突き詰めていくと正しくは全てがナチスドイツだけの力ではありませんでした。
ナチスドイツは第二次大戦が始まってからというもの最初は十分に強力な軍事力は持っていなかったにもかかわらず他の国にはなかった様々な巧みな戦術の甲斐あって破竹の勢いでヨーロッパ全域をほぼ手中におさめました。
もちろんドイツ自体が屈指の技術力を持った国であったことは疑う余地もありませんが、そこに占領地域の国々が開発していたものを取り込み更に強力な技術大国に成長していったためドイツ以外の先進国より十数年から二十年近くも先を行く断トツの技術立国になったのでした。
第二次大戦の終わり頃になると進攻していく連合軍のその先に発見されるのはアメリカもイギリスもソ連も目を見張るような先進技術の開発物の数々でした。
そのため戦争も終わり間際に近付くと連合軍の各国はお互いにナチスドイツの先進技術による試作品の争奪戦の様相をていしていました。
そして戦後はアメリカもソ連もナチスドイツから我先に接収した先進技術+ナチスドイツの科学者たちを基礎として兵器開発と宇宙開発を達成しました。
現在のジェットエンジンの主流は軸流式ジェットエンジンですが、この軸流式ジェットエンジンは元を辿ればナチスドイツが開発の主軸に据えていたジェットエンジン。
他の国々が開発の主軸に据えていたのは遠心式ジェットエンジンでした。
スプートニクもアポロも月面着陸もナチスドイツからの技術流出がなければ当分の間実現出来なかった可能性が高いです。
アメリカとソ連のジェット軍用機はどちらもナチスドイツから奪い取った技術を基本にして発展したため、不思議なくらいに似通った部分だらけです。
一方そんな世界の流れを横目に見ながらちょっと冷めた目をしていたのがイギリスでした。
人一倍プライドが高いイギリス人はアメリカやソ連のように露骨にナチスドイツの技術の真似をしようとはしなかったためイギリスが戦後開発した軍用機はスマートなものが少ないです。何だか野暮ったい系が多いです。
しかしイギリスにはジョンブル精神というものがあるため頑なだけど独自に技術はしっかりしています。
第二次大戦が終わり、つかの間の平和が訪れるかに思われましたが、自由主義諸国と社会主義諸国との間では既に対峙が始まっていました。
そして朝鮮戦争が勃発しました。
この戦争は社会主義国のソビエト連邦と中華人民共和国に後押しされた北朝鮮と自由主義国のアメリカ合衆国とイギリスに後押しされた韓国が戦争をするという代理戦争でした。
時は折しもプロペラ機からジェット機へと移り変わろうとする過渡期でした。
まだまだ登場したてのジェット機の信頼性の低い部分は長年の使用実績があるプロペラ機が補うような両用の時代でした。
しかしジェット機より信頼性のあるプロペラ機でも有用性が見いだせないものは退役へと追いやられました。
この戦争の時の社会主義側(東側陣営)の主役的戦闘機はミコヤン・グレビッチMig15、自由主義側(西側陣営)の主役的戦闘機はノースアメリカンF86Fセイバーでした。
どちらもジェットエンジンを持ち後退翼を備え性能的にも拮抗したそっくりな新世代戦闘機でした。
理由はソビエトもアメリカもナチスドイツから奪った先進技術を元に開発を行っていたからでした。
ソビエトはナチスドイツのフォッケウルフTa183フッケバインを手本としてMig15を開発し、アメリカはナチスドイツのメッサーシュミットMe262やメッサーシュミットP1101を手本としてF86Fセイバーを開発していました。
あっぱれナチスドイツの先進技術はその進んだ技術により第二次大戦後になって戦勝国同士を戦い合わせるという芸当を引き起こしたのでした。
参考写真として
・Mig15とF86Fセイバーの飛行写真。
・フォッケウルフTa183フッケバインの透視図解。
・アメリカに運ばれたメッサーシュミットP1101の側面写真。
を貼りますね。
第二次大戦中、連合軍ではイギリスがグロスターミーティアを開発しアメリカがベルP59エアラコメットを開発している程度でいずれも旧態依然とした直線翼に低出力の遠心式ジェットエンジンのジェット機でしかなくプロペラ機程度のスピードしか出せない低性能機だったためナチスドイツの先進的技術によるジェット機の技術は喉から手が出るくらいに欲しいものでした。→連合軍によるナチスドイツの先進技術の奪い合いへ。
参考写真のフォッケウルフTa183フッケバインの透視図解を見ても判るようにナチスドイツでは第二次大戦中に既に現代の世界のジェット戦闘機が定番として装備するような装備のかたちを確立しようとしていました。
機銃ももちろん装備していましたが有線誘導式のルールシュタール・クラマーX4誘導ミサイルを通常装備。
現在よりも交戦時のお互いの距離が遥かに近かった当時の状況から考えるとかなり有効な兵器だったといえます。
この手の有線誘導ミサイルは現代では陸上装甲車輛を破壊するための兵器(アメリカのTOWミサイルやフランスのHOTミサイル、ソビエトのサガーミサイルや歩兵携行式のRPG-7など)として世界中でベストセラーとなっており今現在でも大量に使用されています。
開発の元になったのはナチスドイツのルールシュタール・クラマーX4有線誘導ミサイルの仕組みでした。
第二次大戦終結直後までのアメリカの兵器開発技術は他国より抜きん出ていたわけではないという事実を如実に示す象徴的な写真があります。
添付写真は1952年アメリカ海軍ジェット艦上戦闘機FJ-1フューリーと並んで飛行するアメリカ海軍ジェット艦上戦闘機FJ-2フューリーです。
FJ-1フューリーは来るべき日本海軍の新型艦上戦闘機に対抗する目的で太平洋戦争末期に開発が始められていたもので胴体はジェットエンジン搭載用に新しく作られそれにノースアメリカンP51ムスタングの主翼と尾翼を組み合わせた直線翼のジェット艦上戦闘機でした。
朝鮮戦争の当初は敵である北朝鮮軍が空軍力らしい戦力を持っていなかったため西側陣営は直線翼ジェット戦闘機と第二次大戦中のプロペラ戦闘機で戦っても十分な状態でした。
しかしソビエト連邦から大量に供与されたMig15戦闘機を装備した中華人民共和国軍が北朝鮮軍の援軍として飛来するようななると様相は一変し西側陣営は苦境に立たされることになりました。
そのためアメリカは東側陣営のMig15戦闘機に対抗出来る戦闘機の実戦投入に迫られ、急遽FJ-1フューリーにナチスドイツから奪い取った後退翼の技術を大幅導入した大改造を施すことになりました。
こうして生まれ変わったのがFJ-2フューリー(F86Fセイバーの海軍版)でした。
アメリカ陸軍→アメリカ空軍でも同時進行的にほぼ同じものを採用していたため、取り急ぎF86FセイバーはMig15の対抗馬として朝鮮戦争に実戦投入されました。
この対応により西側陣営は戦局を盛り返すことに成功し南北朝鮮は現在のラインで休戦状態になっています。
↑この添付写真を見ても判る通りナチスドイツから奪い取った先進技術を大幅導入する前のアメリカオリジナル技術による戦闘機はたとえ動力だけがジェット化していても低性能で見た目もダサかったのでした。
これらの事実から歴史を見ていくと物凄く技術力のある国というのは例外なく戦争をして敵国を打ち負かした後は敵国の技術を奪い取り吸収して更に高い技術力を身につける。
これを絶えず繰り返しているといえます。
世の中、理由もなく特定のある国だけ技術力が強大になるなんてマジックみたいなことはないのです。
手品(マジック)にも必ず種があるように理由や原因が存在するということですね。
アメリカ空軍はナチスドイツから奪い取ったメッサーシュミットP1101をベル社に命じてデッドコピーさせX5を作りました。
メッサーシュミットP1101は元々は可変後退翼の実験機として作られていたため地上で主翼の後退角を変更することが出来るジェット機でした。
アメリカはこれに独自の改良を加え飛行中でも主翼の後退角を変更出来るようにして可変後退翼の実験機としてデータを収集し後の戦闘爆撃機ジェネラルダイナミックスF111アードバークや艦上戦闘機グラマンF14トムキャットの開発に役立てました。
参考写真として
・メッサーシュミットP1101とベルX5の側面写真。
・ベルX5の可変後退翼の様子が判る写真。
・下から上へ順番にアメリカ海軍グラマンF10Fジャガー可変後退翼艦上戦闘機、アメリカ空軍ジェネラルダイナミックスF111Aアードバーク可変後退翼戦闘爆撃機、アメリカ海軍グラマンF14Dトムキャット可変後退翼艦上戦闘機の写真。
を貼りますね。
みんなナチスドイツの先進技術の恩恵によるものばかりです。
他にもあります、もう退役しましたが宇宙と地上との間を頻繁に往復する唯一の乗り物として世界中に名を馳せたアメリカのスペースシャトルも元を辿ればナチスドイツの先進技術の恩恵の賜物でした。
ナチスドイツのアレキサンダー・リピッシュ博士(彼は人類史上最初で最後のロケット戦闘機メッサーシュミットMe163コメート〔彗星の意味〕の機体設計にも大きな役割を果たした人物)が作ったDM-1という無尾翼の実験飛翔体とその設計を受け継ぎ作られる予定だったP.13aジェット戦闘機。
アメリカはこの先進技術を元にリフティングボディと呼ばれる滑空飛翔体の実験機などを作り研究を重ねスペースシャトルを実現しました。
それからスペースシャトルの構想自体、第二次大戦終結後にドイツからアメリカへ渡ったヴェルナー・フォン・ブラウン博士の発想そのものであり彼なくしては実現出来ないものでした。
アポロの月面着陸も実は彼がアメリカに居て協力したからこそ実現出来た偉業でした。(事実アメリカ人だけのプロジェクトチームでは失敗を繰り返していました)
参考資料として
・DM-1の写真。
・DM-1とP.13aの模型。
・P.13aの模型(後部)。
を貼りますね。
P.13aは画像を見ても判る通りこの時代に既にラムジェットエンジンと二次元式ジェットノズルを使い最大速度1650km/hを目指して開発されようとしていました。
アメリカではオリジナルのジェットエンジンは一つも持っておらず、辛うじてベルP59エアラコメットがイギリスのパワージェットW.1遠心式ジェットエンジンを手に入れ少改良を施したものを使いやっとのことで690km/h前後の最大速度を出したばかりの時代でした。(ジェット機なのにプロペラ機のノースアメリカンP51ムスタングにも負ける最大速度でしかありませんでした)
第二次大戦当時と第二次大戦直後の世界各国での初のジェット軍用機開発状況は以下の通りです。
ドイツではメッサーシュミットMe262がユンカース製Jumo004B軸流式ジェットエンジンを2基搭載して1942年4月に初飛行。
アメリカではベルP59エアラコメットがイギリスのパワージェットW.1遠心式ジェットエンジンを少改良したジェネラルエレクトリックJ31-GE-3を2基搭載して1942年10月に初飛行。
イギリスではグロスターミーティアがロールスロイスW.2B/23C遠心式ジェットエンジンを2基搭載して1943年3月に初飛行。
日本では中島飛行機 特殊攻撃機(体当たり攻撃に使うものではなく500kgもしくは800kg爆弾を搭載し670km/h前後の高速を利して攻撃を行う用途の攻撃機)橘花が唯一の資料ドイツのBMW003Aの断面図だけを参考に→空技廠/石川島重工業が協力して独自開発したネ20軸流式ジェットエンジンを2基搭載して1945年8月に初飛行。
(橘花はMe262の模倣版だといわれることがありますが正しくは全くの別物、運用用途も違えば機体サイズも一回り小型で形状も別物、Me262の技術情報がほぼ手に入らなかったため、日本独自の設計となっています。)
ソ連ではミコヤン・グレビッチMig9がドイツのBMW003軸流式ジェットエンジンをコピーしたRD-20を2基搭載して1946年4月に初飛行。胴体内に2基のジェットエンジンを搭載していましたが機首部分の左右の空気取り入れ口の真ん中に機銃を装備していたのが災いして失敗作になっていたようです。
ソ連では政治的理由によりMig9が初飛行するまで初飛行は許されませんでしたがヤコブレフYak15がドイツのユンカース社製Jumo004軸流式ジェットエンジンをコピーしたRD-10を1基搭載して1946年に初飛行。
第二次大戦で大量使用されたプロペラ戦闘機Yak3の液冷式ピストンエンジンを撤去し替わりにジェットエンジン1基を無理矢理取り付けた構造のジェット機でした。
こうして見るとジェットエンジンとジェット軍用機の開発ではドイツが最も早く尚且つ進んでいました。(ドイツでは実際にはもっと早くに1941年3月30日にハインケル社がHeS8a遠心式ジェットエンジンを2基搭載したHe280というジェット戦闘機を初飛行させていましたが政治的理由に〔ハインケル社の社長だったエルンスト・ハインケル博士がナチス党員ではなかったのが原因〕より冷遇され後から遅れて初飛行したメッサーシュミット社製Me262ジェット戦闘機が優遇され〔メッサーシュミット社の社長だったヴィリー・メッサーシュミット博士はナチス党員だったため優遇された〕正式採用されていました。)
尚、進んでいたドイツでは軸流式ジェットエンジンと遠心式ジェットエンジンをミックスしたような高性能ジェットエンジンHeS 011がハインケル・ヒルト社で開発中でもありました。
連合軍の中では唯一イギリスだけが独自開発のジェットエンジンを持ち世界的にはドイツの次に進んでいました。
アメリカはイギリスのパワージェット社製W.1遠心式ジェットエンジンをイギリスから供与してもらい、これに少改良を加えて使っていましたから独自開発のジェットエンジンは一つもなく技術的に進んでいるとは言い難い状況でした。
日本はドイツからの技術情報を携えて帰るはずの潜水艦があと一歩のところで沈められ唯一日本に伝わったのはBMW003A軸流式ジェットエンジンの断面図のみとなり、ほとんどの部分は空技廠と石川島重工業の協力により独自開発され終戦直前に特殊攻撃機橘花を初飛行させるところまでは出来ました。
ソ連の場合は終戦から一年後の1946年にMig9、Yak15、Su9Kと各設計局のジェット戦闘機が初飛行しましたが、どれもドイツのユンカース社製Jumo004軸流式ジェットエンジンをコピーしたRD-10かドイツのBMW社製BMW003軸流式ジェットエンジンをコピーしたRD-20というコピージェットエンジンを搭載したものばかりでした。
ジェット軍用機開発で他国に遅れをとったという焦りから急げ急げと命令された結果スホーイ設計局のSu9Kなどはジェットエンジンもドイツのコピー、機体もドイツのメッサーシュミットMe262にあまりにもそっくりだったため時の権力者ヨシフ・スターリンの逆鱗に触れ怒りをかったともいわれています。
参考資料として
・上から下へ順番に日、独、英、米の最初のジェット軍用機(特殊攻撃機中島橘花/メッサーシュミットMe262A/グロスターミーティア/ベルP59エアラコメット)・ソ連最初のジェット軍用機(ミコヤン・グレビッチMig9/ヤコブレフYak15/スホーイSu9K)
の写真を貼りますね。
ソ連のスホーイSu9KはドイツのメッサーシュミットMe262Aに驚くほど瓜二つでしょう。
急げという上からの命令によほど慌てたのでしょうね。
しかし独裁共産主義国家だけに権力者の気分を損ね怒りでもかえばたとえ設計者でも粛清に遭う時代、運が良くても投獄、強制労働でしょうから今の北朝鮮とあまり変わらない理不尽な国。
0さん、![]()
すごいなぁ、しかしドイツという国は、進んでましたね、
私の家庭のもめ事がありましたのて、しばらくコメント出来ませんでした、m(_ _)m
しかしこのスレの0さんのレスは、読んでましたよ、![]()
ムービーはディスカバリーチャンネルの、
戦闘機のベストテンをやってましたので、
携帯でテレビを録りました、
FA-22 ラプター
↓↓
かなり高価な ラプター
つづきです、
↓↓
冷戦時代の
イギリス軍機
ハリアーFA2
↓↓
ハリアーFA2
↓↓
ソピースキャメル
第一次大戦
レッドバロンの時代カナ?
↓↓
0さんが言われる
ドイツが誇る、
ME 262ジェット戦闘機
第二次大戦末期
↓↓
しかし 私はなんといっても 零戦がたまりません
ムービーは
零戦五二型 と
グラマンF4F
↓↓
F-22ラプターは第五世代戦闘機と呼ばれる最新鋭の戦闘機。
性能もかなり高く、高価なF-15イーグル戦闘機(F-15イーグルは値段が高価なためアメリカ、日本、イスラエル、サウジアラビア、後に韓国などの高いお金を払える国しか持っていない高性能戦闘機)6機を一度に相手にすることも可能で、しかもこのF-15イーグル6機を圧倒し全機撃墜する能力があるそうです。
その分、値段も更に高価で40機揃えることが出来たとしても約10兆円はかかるといわれる超高級戦闘機です。(しかし今のところアメリカはたとえ同盟国であっても売らない方針を表明しています、軍事機密技術流出懸念だと思います)
第五世代戦闘機に関しては他にもロシアや中国でも開発しているぞという意図的情報公開(他国に対する牽制の意味のプロパガンダ)もありますがどこの国もまだ実戦配備までは至っていないためアメリカの一人勝ちの様相をていしています。
現実問題としてF-22ラプターで戦わなくてはならないような敵の高性能戦闘機は世界中に存在しないではないかという図星な発言もあり当初予定していた機数の調達は議会での承認が得られず総生産機数は大幅削減されているようです。
(超高性能なため国外輸出も禁止されているので値段は下がることもない)
超高性能が故に超高額となり、それが起因してF-22ラプターの敵は国外にはなく、むしろアメリカ国内の議会が最大の難敵となっている皮肉な結果です。
F-22ラプターはステルス性能があるから強いとよくいわれます。
しかし強い理由はステルス性能だけではありません。
第五世代戦闘機と呼ばれる最新鋭戦闘機に求められる能力を全て備えているから強いのだといえます。
ステルス性能、アクティブフェーズドアレイレーダーの装備、撃ちっ放し式ミサイルの装備、高機動性能、スーパークルーズ性能などがそれです。
ステルス性能は電子的に敵に探知され難くなる能力。
アクティブフェーズドアレイレーダーとは機械的な首振りを必要としない新型高性能レーダーです。
撃ちっ放し式ミサイルとは発射した後は誘導する必要のない高性能ミサイルのことです。
高機動性能とは噴射方向を可変出来るジェットノズルを備え急機動が出来るということです。
スーパークルーズ性能とは新型ジェットエンジンで可能になった性能で、従来のジェットエンジンではアフターバーナーを使わないと超音速飛行出来なかったのに対し燃料をバカ喰いするアフターバーナーを使わずに超音速巡航出来る能力のことです。
これら全ての相乗効果で圧倒的に強くなっているといえます。
特に敵には見付かり難いのに敵より遥かに遠くの距離から敵を探知出来る部分がかなり有利に働いています。
だから撃墜される敵はほとんどの場合はF-22ラプターの接近を気付かないままに撃墜される結果となります。
在来型の戦闘機とF-22ラプターが戦う場合を判り易く例えるなら、ほとんど視力のない盲目に近い人と超視力の優れた人が殴り合いをしているようなものです。
F-22ラプターの側は良く見えているから何時でも何処でも攻撃出来るのに対し敵はほとんど見えていないから無力に近い状態。
このような能力を獲得しようとロシアも中国も努力しているようですが、ロシアの場合はもう出来上がっています、実戦配備までは出来ていないだけです。
中国の場合は世界に向けて盛んに宣伝はしていますが外側は出来ていても内部の各重要部分に関して自力生産するにはまだまだ相当年月がかかるでしょう。
公開されている機体の姿を見ても判るように盛んにアメリカやロシアのステルス戦闘機の技術を真似て盗もうとしています。
いつも拝見させていただいております。0さんの知識の多さには驚いております。大変勉強になります。最近のミサイルも高性能なんですね! サイドワインダーみたいな赤外線ホーミング。あとスパローやフェニックス等。最近の誘導システムはどんなんですか?
最近の空対空ミサイルはサイドワインダーミサイルのような熱源に向かって飛んで行く赤外線誘導ミサイルも開発当初とは見違えるほどに性能が良くなっているようです。
当初は敵機の熱排気以外の熱源に騙されて飛んで行ったりして信頼性は低いものでした。
今では精度が良くなり敵機の正面に向かって発射しても有効打を与えられるほどに命中精度と信頼性がアップしているようです。
センサーの高性能化が一番の原因でしょう。
長い有効距離と確実な信頼性の高さでいうとレーダー誘導式ミサイルが一番ですが、これも当初は母機からの誘導が必要で使い勝手の良いミサイルとはいえませんでした。
しかし今ではミサイル自身がレーダー誘導をして行く、いわゆる撃ちっ放し式レーダー誘導ミサイルが主流となり、そこに推力偏向式ノズルやステルス性能を併せて盛り込んだものまで現れているようです。
あまり語られませんが日本の自衛隊が装備するミサイルの場合はたくさん発射しても同じ標的にダブって何発も命中しないようにする機能まであるらしいですよ。
話によると命中させる部分すら選んで設定可能なようです。
当然国家機密でしょうから詳しい話は公にはされないようです。
戦闘機にしても誘導ミサイルにしても一つ一つを構成する素材技術が精度と信頼性を支える鍵ですから素材技術に定評のある日本の技術はこれまでのように中国や韓国にパクられないように注意しながら日本の国防に役立てていって欲しいものです。
様々なレアメタルも数年前に中国による嫌がらせ輸出規制が行われて以来、日本では官民協同で研究を重ね従来比の1/3の使用量で済むような研究成果を出し中国からの輸入量が増えないような成果を出しているようです。
0さん、きんたさん、
こんばんわ〜、
撃ちっ放し式ミサイル
すごいですね、
超高性能 戦闘機、があっても、実戦できなければ、宝の持ち腐れ、ですね
昔は戦闘機の最大速度の速さを利して追って来るミサイルを引き離し逃げ切ったという事例(使われたのは初期のサイドワインダーミサイルだと思います、逃げ切ったのはソ連製Mig25フォックスバットだったと思います)がありますが最近のミサイルは更に高速なミサイルも出て来ていますから最大速度で逃げ切るのは難しいでしょうね。
ミサイルから逃げ切るにはチャフやフレアを放出してミサイルを撹乱するのが一般的です。
そのため妨害に対する対抗力の強い目(精度と信頼性の高いセンサー)を持ったミサイルは大敵ということになります。
アメリカの大手軍用機メーカー三つが集まって開発したF22ラプターに使われているレーダーは日本の三菱が開発したF2戦闘機用レーダーの技術を使い拡張発展させたものです。
当初日本独自開発で完成させようとしていたF2戦闘機はアメリカが首を縦に振らず結局はアメリカからの圧力により日本単独開発は中止となり無理矢理日米協同開発にさせられてしまいました。
契約内容はアメリカ側からは新たな技術の提供はないものの開発のベース機体として既に古くなっていたF16を使えという無理矢理な内容で、しかも開発に必要な飛行特性のソースコードはアメリカ側から提供されないという理不尽なものでした。
それなのにF2開発に使われた技術は日米協同開発技術としてアメリカ側が利用出来るという非常に一方的な条件となっていたためF2用レーダーの技術はF22ラプター用レーダーに転用されることとなったのでした。
アメリカも大国にしては似合わないセコい行いでした。
F2戦闘機の日米協同開発(三菱とロッキードマーチン)の内容がそのようなアメリカ側に一方的にお得な内容だったため、他にもF2開発に使われた日本独自の主翼の一体成形技術やCCV技術もアメリカのF22ラプター開発に使われている可能性は非常に高いです。
アメリカは凄い凄いといわれていますがよくよく注意深く見ると意外にセコいのが現実なのです。
なるほど、
アメリカは、日本やドイツの、いいどころ取りで つくったのを、隠し
我々が知らないもっともっと、高度な戦闘機(公表しない)を 作っているかも知れませんね、
アメリカは凄い部分も確かにあります。
世界中の大半の人々はアメリカは凄いものばかり持ち合わせた凄い国と思っています。
確かに半分は正しいですがアメリカのその物凄い部分も他国からパクった技術や発想の上に成り立っているのも事実。
ここでアメリカによるパクり話から少し離れてロシア、中国、アメリカのステルス戦闘機の比較資料を貼ります。
上から下へ順番にロシアのT-50、中国の殲20、アメリカのF22、アメリカのF35です。
ソ連→ロシアもアメリカも第二次大戦でドイツから奪い取った先進技術を元にして研究開発した技術によりこれら最新鋭のステルス戦闘機を作り上げているため姿形から何から何まで酷似した部分が多いです。
第二次大戦当時のドイツでは驚くことに既にステルス技術が存在していました。
当時はまだ初歩的なものでしたがドイツ以外の国々にはなかった考え方と技術でした。
当時の世界のレーダー技術も初歩的な段階でした。
中でも最先端のレーダー技術を持っていたのはイギリスでした。
当時のドイツのステルス技術が大々的に実戦投入されていたならレーダー技術で最先端をいっていたイギリスに対してかなりの有効打になったであろうことが近年アメリカの大手軍用機メーカーの手によって実証されています。
それはさておき、中国の殲20に注目してみると一見形だけは立派なステルス戦闘機に見えますがロシアとアメリカをあの手この手で必死に真似ようとしているのが見て取れます。
しかし必要なパワーを持ったエンジンを持っていなくて苦労している様子が機体の姿からよく判ります。
エンジンのパワーが足りず尚且つ飛行制御技術が未熟だという現状が露呈したような外形。
ステルス戦闘機には適さないカナード翼、これを付けなければならない理由がエンジンパワー不足と未熟な飛行制御技術にあります。
今の中国の技術ではこうでもしないと飛行させること自体が出来ないという表れです。
中国が中国初のステルス戦闘機のテスト機として公表した(2011年1月)殲20(YouTubeにも動画公開されていますね)の後に更に公開した別機、殲31を追加した写真も貼っておきます。
左側から右側へ順番に中国の殲20、殲31、アメリカのF22、F35です。
そしてアメリカのロッキードマーチンF35の開発データがハッキングにより1年あまりの間盗まれ続けていたこともアメリカ政府から公表されていました。
殲31は殲20より小型で更にアメリカのF35にそっくりです。
各部や全体の姿もそっくりですが空気取り入れ口の形を見れば全く同じ特有の新形式です。
写真で比較するとそのそっくり度合いは一目瞭然です。
中国って本当にたちの悪い国ですね。
ステルス機として世界で大々的に有名になった最初のものは皆さんご存知アメリカのロッキードF117ナイトホークです。
頭にFと付いていますがロッキードのスカンクワークスが開発したステルス性能を持った攻撃機です。
元々アメリカはステルス機を保有しているのではないかと世界中から疑われており、これをモデルとして憶測で作られたステルス戦闘機のプラモデルがイタレリ社などから販売されたりして物議を醸していましたがアメリカ自身は認めていませんでした。
しかし実際にはこのような話が出る遥か以前の1981年には初飛行が済んでいました。2008年には退役。
結局アメリカは後々になって保有していることを認めました。
F117が一番華々しい活躍を見せたのは湾岸戦争の時でした。
露払い役を見事に果たし開戦初っ端の重要な任務(敵の発電施設、通信網、防空網の確実な破壊)を行いました。
この任務の成功により開戦直後早々に敵の敗北は確定的になり中枢神経をズタズタにされた敵は個々に潰滅させられていきました。
F117はステルス機であったためレーダーに映り難く(後々出て来た話で機体全面の電波吸収材には日本のTDKの技術が使われていたそうです。TDK自体は言葉を濁していたようですけど)敵の直接攻撃に遭い難いため護衛や支援のための軍用機が不要でした、そして赤外線誘導爆弾による精密爆撃が可能だったためほとんど目標を外すことがなかったため必要最小限の少数機で任務が可能でした。
このように良い事ばかりのようなF117でしたが唯一撃墜されたものも1機だけありました。
コソボ紛争の際にセルビア軍のSA-3ゴア中低高度対空ミサイル2発の内1発が命中し撃墜されました。
残骸を調べると木製素材も使われていたことが明らかとなりました。
そしてこの時、裏取引によってF117のステルス技術情報がロシアと中国に流れたという話も知られています。
後にロシアと中国が作ったステルス機にはこの時の技術が利用されたのは確実でしょう。
ロッキードF117ナイトホークの写真を2枚貼ります。
F117開発に使われた高品質な日本の磁性体技術は世界の兵器の様々な材料技術分野に於いて日本が下支えしている事実を垣間見たような印象でした。
日本の企業にしてみれば太平洋戦争に敗れて以降は二度と悲惨な戦争はするまいと考え、より高品質な民生品を作り経済的利益に繋げようと思い、たとえばTDKなどはより高品質なミュージックテープやビデオテープを作る努力をしていただけなのでしょうが…
他国が作る同じものより格段に高品質に仕上がってしまっただけなのでしょうけれど。
外国人の目には「日本には兵器に使える良い材料がたくさんあるではないか」という具合に映るのでしょうね。
ICや撮像素子やファイバーケーブルから炭素繊維までそんな具合なのだと思います。
世界屈指の優れた材料技術は持ちながらもそれをバランス良く組み合わせて兵器化するのが苦手で下手なのが日本人でもあります。
しかしこれから先はそんなこともいってはいられなくなるでしょう。
日本は今のところは相変わらず中国や韓国に技術を流出させたり人材を流出させたりで何でもかんでも盗まれっ放しですが、これからは厳しくしないといけないと思います。
日本の技術は国の宝、日本の人材も国の宝、そういう意識を国のトップも日本企業のトップも強く持たないといけません。
技術を流出させないこと、人材を流出させないことは自動的に日本が持つ外向的に有力なカードを増やすことに繋がります。
外国に対していいたいこともいえず我慢してペコペコする時代はそろそろおしまいにしないといけません。特に中国や韓国に対しては強気で立ち向かえる環境を整えないといけないです。
このままではずっと舐められっ放しです。
0さん![]()
第二次大戦時に、ステルス戦闘機、をドイツが開発していたとは
(=°ω°=)ビックリ、
F117 がズラリ、
アメリカは凄いなぁ、
ヘルシアさん、お早うございます。(゚▽゚)/
第二次大戦中にナチスドイツで作られていた全翼機の写真を貼ります。
上から下へ順番に
・ホルテンHoⅨV1(エンジン未搭載型の試作1号機)
・飛行中のホルテンHoⅨV1(エンジン未搭載型の試作1号機)
・ホルテンHoⅨV3(ジェットエンジンを搭載した試作3号機)
・進攻して来たアメリカ軍に捕獲されたホルテンHoⅨV3(ジェットエンジンを搭載した試作3号機)
です。
ドイツにはホルテン兄弟という飛行機作りに才能のある兄弟がいて彼らがこの全翼機を作り出しました。
しかし彼らには大量生産する力はなかったため彼らの優秀な才能を認めたドイツ空軍のはからいで量産はゴータ社で行われることになっていました。
したがって名前はホルテンHoⅨはゴータGo229と呼ばれることになっていました。
空気抵抗が非常に少ない全翼機だったため最大速度は970km/hと速く同じくジェットエンジン2基を搭載していたメッサーシュミットMe262より100km/hも速いものでした。
当時の連合軍の戦闘機との比較であれば300km/hも優速な戦闘機でした。
更にゴータGo229を大型化した爆撃機も作られる計画となっていました。
機体全体が翼の役割を果たすようにブーメランのような姿になっているのが全翼機の特徴です。
非常にシンプルな形であり、このようなシンプルな姿で尚且つ前面投影面積を極力小さくすることとボディに炭素素材を積層させることがステルス性能を発揮するキーポイントであることを当時のナチスドイツの科学者たちは知っていました。
一番下の写真が示す通りアメリカはこういったナチスドイツの最先端技術をたくさん奪い取ってアメリカ本国へ持ち帰り今現在でも分解保管して持ち続けています。
自国で開発する兵器に役立てるのが目的です。
アメリカのスミソニアン航空宇宙博物館やその保管倉庫にはナチスドイツや日本から奪い取った戦闘機などがたくさん分解保管されています。
今でもです。
湾岸戦争で アメリカの
F117ステルス戦闘機が
活躍したのは テレビでみてました、![]()
軍事基地をピンポイントで爆撃してましたね、
0さんの画像の ナチスドイツのステルス戦闘機
翼に![]() マークがはっきり見れますね、
マークがはっきり見れますね、
全く知りませんでした![]()
アドバンスト大戦略でホルテンはよく見ました![]()
0さん、きんたさん、こんばんわ
先日、TSUTAYAから
DVDを借りました、
「戦場のピアニスト」
です、
映画の最後で ドイツの敗戦寸前、ドイツの将校が、ユダヤ人のピアニストを 助ける と言うストーリーでした、
やはりドイツの将校の軍服、カッコいいですね![]() またドイツ人独特の
またドイツ人独特の
ヘアースタイル、
金髪に刈り上げ、オールバック、
そのうち私も同じヘアースタイルにしょ![]()
第二次大戦当時にアメリカ軍がドイツから奪い取りアメリカ本国へ持ち帰ったホルテンHoⅨ(ゴータGo229)は現在も尚、アメリカのスミソニアン航空宇宙博物館の倉庫に分解された状態で保管されています。
その現物写真を貼ります。
胴体中央(前からの写真)、胴体中央(後ろからの写真)、左右の翼の写真です。
このようにして進んだ軍事技術を持った国の兵器をかき集めて持っていればアメリカが軍事兵器先進国になれたのも納得出来る話でした。
それからもう少し資料写真を貼ります。
一枚目は上二つがドイツから奪い取ったホルテンHoⅨ(ゴータGo229)の設計図と先程紹介したアメリカに分解保管されている現物を元に忠実に再現したレプリカの写真、下一つはアメリカのノースロップ・グラマンとボーイングが協力して1980年代に開発した現在のところ世界で唯一のステルス爆撃機B-2スピリットの写真です。(あまりに高価になり過ぎたため裕福な国アメリカ合衆国といえども21機しか生産出来ていません)
二枚目はホルテンHoⅨ(ゴータGo229)の透視図解。
三枚目はノースロップ・グラマンとボーイングのB-2スピリットの透視図解。
アメリカのノースロップは1930年代から全翼機の開発をしていたという人もいますが、これらの事実を見て皆さんはどう思いますか?
感じ方は人それぞれですが、他の多くの模倣事例を見るとドイツの技術を模倣した可能性は否定出来ません。
同様のことはアメリカだけではなく旧ソ連(現ロシア)にもいえることです。
特に第二次大戦末期のこの二ヵ国はドイツの技術の争奪戦を繰り広げていましたから。
第二次大戦当時ではなく近年になって完成したアメリカのノースロップ・グラマンとボーイングのB-2スピリットステルス爆撃機の場合は外形の角度とパネル類の繋ぎ目の角度が一定の決まった角度に揃えてある部分は違いがありますが、これはステルス技術の研究が進み後から判った特性を付け足したためで飛行機としては本来は飛ばすのには適さない形です。
しかし、第二次大戦当時とは違い現代ではコンピューターがあるため、それでも飛行させられるようになったということです。
1930年代にアメリカに
全翼のステルス戦闘機
があったとは、
考えられませんね、
スミソニアン博物館の![]() ←マークが、ハッキリ見れますね、
←マークが、ハッキリ見れますね、
このような、全翼ステルス機 が 先端部にプロペラだったら、( ´艸`)
面白いですね。
ドイツのホルテンの全翼機もアメリカのノースロップの全翼機も初期のものはプロペラ機でした。
但し、どちらも機体前部にプロペラが付いた牽引式ではなく、機体後部にプロペラが付いたプッシャー式でした。
他にこれは厳密には全翼機とは異なりますが、ドイツ(アルグス社製)にもアメリカ(ノースロップ社製)にも円盤型の機体の前部にプロペラを付けたものも存在しました。
どちらも変わり種の奇形機のジャンルになります。
ちなみに基本的にはプロペラやジェットエンジンのファンは形状的にはステルス性能を悪くする一大要因の一つです。
電波を反射し難い素材にする、前方から見た時に見えないような位置に隠す、などの対策をとればステルス性能は格段に上がります。
現代の本物のステルス機はみなこれらをクリアしたものばかりです。
訂正があります。
476で書いたアメリカの円盤型の軍用機はノースロップ社製ではなくヴォート社製でした。
申し訳ありません。
ごめんなさい。m(__)m
XF5Uフライングパンケーキという軍用機でした。
あまりにも奇抜だったため変わり者扱いされ2機しか作られず試作機のV-173は初飛行に漕ぎつけましたが開発中止になりました。
完全なるホバーリングではないもののホバーリングに近いことが出来たらしいですが万人が万人にそんな特異な操縦が出来たかというとそうではなかったため高く評価されることはありませんでした。
開発中止の理由はジェット機が実用化され始めていたため、どんな高性能なプロペラ機を作ってもジェット機には及ばないという判断と牽引式プロペラ機であるためロケット弾などの前方投射がやり難いという点から開発中止となりました。
試作機V-173の飛行中の写真を貼ります。
いろんな戦闘機があるんですね、ビックリしました、よくよく考えてみれば、冗談で言ってみた、全翼機のプロペラ、実在したのがビックリです。そういえば、現在の輸送機の
オスプレイもプロペラ機 ですね、
アメリカのベル社が開発したMV-22オスプレイはチルトローター輸送機。
ちなみにオスプレイの試作機では何故だか三菱製のビシネス用ジェット機の胴体が使用されていました。
熱排気の噴射もしながらプロペラも回すターボプロップエンジンを使用していたと思います。
エンジン前部にはプロペラがありますが、エンジン後部には排気口が空いています。
だからオスプレイを艦船で発着させて使う場合は発着スポットの飛行甲板は耐熱仕様にしておかないと甲板が排気熱で焼けてイカレてしまいます。
垂直離着陸が出来るオスプレイはヘリコプターのように狭い場所で発着が出来てヘリコプターよりも有利な双発機並のスピードと航続距離を併せ持つ新世代の輸送機として期待がかけられています。
しかし、荷室の幅が若干狭いためにハマー(現代版ジープ)は搭載出来ないなどといわれています。
その証拠にハマーを運ぶ任務を見ているとワイヤーで吊して輸送しています。
アメリカは金銭的にも苦労的にも人命の喪失的にも血の滲むような努力の末に開発した便利な輸送機なので、せっかくだからもう一声改良が欲しいところです。
現在のところはどこの国も持っていない(ロシアも中国もヨーロッパ諸国も持っていない)新ジャンルの有益な輸送機なのだからアメリカにはそれを活かしせるようにして欲しいですね。
最近のアジア情勢を見ているといずれは日本も購入しないといけないです。
世の中の反対は置いといて個人的には今の中国やロシアの動きやこそこそしている韓国など見ていると日本は出来るだけ早くMV-22オスプレイとF-35BライトニングⅡは持っておくべきだと思います。
抑止力になるし、もしもの時には有力な防衛手段になるからです。
オスプレイに関する資料を貼ります。
マスコミの片寄った報道によりオスプレイは危ないというイメージだけが強烈に印象付けられ信じ込まされていますが、人間が作り出した飛行する物は必ずいくらかの割合で故障もすれば墜落もします。
従来から使われている在来機でも新型機でもそれは同じです。
それを踏まえて在来機とオスプレイを比較して現実を見るとオスプレイがいかに魅力的な新ジャンルの航空機であるかが良く判ります。
ボーイング・バートルCH-46シーナイト輸送ヘリコプター(在来機)とベル・ボーイングMV-22オスプレイの比較資料。
ベル・ボーイングMV-22オスプレイの透視図解。
ボーイング・バートルCH-46シーナイト輸送ヘリコプターの写真。
です。
オスプレイ配備を中国が異常に嫌がる訳も見えて来る内容です。
オスプレイが福岡の築城基地から活動したとすればその活動可能範囲は朝鮮半島全域までカバーされることになります。
中国や北朝鮮から嫌がられる訳がズバリ納得でしょう。
異常に嫌がっているからマスコミを使ってみんなが反対するように誘導したくもなるというのが中国や北朝鮮の立場なのです。
0さん、こんばんわ
いつもありがとうございます、
F-35BライトニングⅡとはどんな飛行機ですか?
すみません![]()
空挺部隊と違ってある程度重武装の歩兵部隊を短時間で展開出来るのですね?又より少ないコストでより広い範囲をカバー出来るのですね?
皆さん、こんばんは。
(゚▽゚)/
F-35ライトニングⅡとはアメリカのロッキード・マーチン社が複数の資本主義先進諸国と国際協同開発をしているステルス戦闘攻撃機です。(近年、日本も協同開発国の一つに入りました)
大きく分けて3タイプを開発し世界各国が現在使用している戦闘機や攻撃機の更新用の後継機にしようという世界屈指のビッグプロジェクトとなっています。(世界各国で使用中の戦闘機と攻撃機ともなれば合計数でいえば相当な数にのぼることが予想されるため、めったにないビッグビシネスということがいえます)
F-35Aは通常離着陸型。
F-35Bは垂直離着陸型。
F-35Cは艦上戦闘攻撃機型。
A型は主に陸上航空基地から使用されるステルス戦闘攻撃機です。
B型は主に強襲揚陸艦などの艦船から使用される垂直離着陸が出来るステルス戦闘攻撃機です。
C型は主に空母の飛行甲板から使用される通常離着陸型ステルス戦闘攻撃機です。
資料を貼りますね。
一枚目はF-35ファミリーの上面透視図で、左上がA型、左下がB型、右上がC型となっています。
二枚目は垂直離着陸時を示すF-35Bの透視図解。
三枚目は実際に垂直離着陸をしている時のF-35Bの写真です。
きんたさんのおっしゃる通りオスプレイは大変魅力的な使い方を現実のものに出来る新種の航空機です。
F-35ライトニングⅡは一つの共通機体をベースに各部を一部専用設計のものに入れ換えて、たくさんの用途に合うように考えられた統合型ステルス戦闘機であるため、そのぶん新機軸もたくさん導入されているので開発は難航しています。
しかし、結果が順調に達成されれば世界中の多くの戦闘機や攻撃機がF-35に入れ代わることになりそうです。
アメリカの攻撃機のほとんどとアメリカ海軍の艦上戦闘攻撃機とアメリカ海兵隊の戦闘攻撃機は大半がF-35ばかりになってしまうでしょう。
将来的には無人攻撃機かF-35が大半を占めるようになるはずです。
0さん、今晩はです。B型なら海自が装備して、『いせ』『ひゅうが』に搭載できますかね? 『おおすみ』にはどうでしょうか?
きんたさん、おはようございます。(゚▽゚)/
ひゅうが型にオスプレイが離発着出来るのは日米合同演習の時に確認されているようです。
おおすみ型には専用の耐熱板を使用して着艦していましたのでそのままでは普通に発着艦することは出来ないでしょう。
また、F-35Bの場合だとターボプロップの熱排気ではなくジェットエンジンの熱排気ですからもっと強力な耐熱仕様への改造が必要かも知れません。
F-35Bの排気は前部と左右はクールエアーで後部はホットエアーであり、この後部の排気がジェット噴射なので高温なため耐熱仕様になっていない甲板だと離着艦出来ないということになります。
ヘルシアさん。0さんおはようございます。『いずも』に同型艦はできるんでしょうか?昔みたいに航空戦隊を編制しますかね?現代には、合いませんかね?
22DDH護衛艦いずもの同型艦24DDHは既に建造中らしいですよ。
22DDHと24DDHは護衛艦しらねと護衛艦くらまが退役した後の代艦とする予定で作業が進められています。
日本側の従来からの発言通り使用用途はDDHの名前が示す通り対潜哨戒用ヘリコプター搭載の護衛艦ということになります。
しかし、近年全国ネットのニュースでも日常茶飯事報道されるようになって来た中国の横暴な行動を考えると使用方法の見直しもせざるを得なくなるのも時間の問題でしょう。
要は日本が空母型の艦船を従来通り保守的な対潜哨戒用に用いるか、周辺装備を変更してより攻撃的空母として使用するようになるか、は今後の中国の態度と行動次第でしょうね。
その現実を本当に理解出来ている中国の上層部の人間が何人居るのかについては果たして疑問です。
今の中国軍を取り仕切る世代は戦争をしたことのない人間ばかりになっており、捏造も含めた反日教育を受けて育っており、一人っ子政策の影響で贅沢に甘やかされて育ったわがまま世代がほとんどです。
共産党一党独裁国家という仕組み上個人の勝手な行いは基本的には許されない国家体制です。
しかし、反日活動に限っては日本に対して損害を与えることは英雄的行いとして賛美される風潮にあります。
だから身の程知らずで只単に手柄を立てて英雄扱いされたい者はたくさん潜んでいるといえます。
そう考えると今の中国には危険な人間が十何億人もいると考えられます。
0さん、きんたさん、
こんばんわ〜、
いよいよ 専門的になってきました![]()
なかなか解らないところが多々ありますが、
とても勉強しましたよ、近代兵器や近代戦闘機
近代戦艦、空母、
興味が湧いてきました、
皆さんお早うございます。(^O^)/
第二次大戦で制空権を握った者が戦いに勝利するという図式が確定的になったことにより今では戦艦を新たに建造する国も戦艦を戦いに使用する国もいなくなって戦艦という艦種は事実上なくなりました。
一方、戦いの主役に踊り出た航空機、海軍ならば空母が重要視されましたが、幸いにして大きな世界大戦もなかったために空母が兵器体系の中では重要な位置付けのまま来ているのが現代です。
現代の兵器体系の中では核ミサイル、空母、これが最も重要な柱となっています。
しかし、核ミサイルはあまりにも破壊力がありすぎるのと除去が非常に難しい放射能汚染の問題があり、使った国は世界中から非難されるという厄介さから実際には使えない兵器となっています。
そうなると敵国への牽制にも使え、いざとなったら実際の攻撃にも使用出来る通常兵器である空母の存在がクローズアップされるという流れになっています。
そういう理由でどこの国も空母を持ちたがる。
実際に小型艦であっても空母らしき艦船を保有する国は昔に比べ増加しています。
近年日本で空母のような艦船が複数建造されたのは特に日本が軍備を強めたわけではなく世界の国々のそういった動きに対応して相応な対処をしているだけなのです。
中国や韓国が「日本は軍備を増強している」と大袈裟に報道していますが、これは全くの言い掛かりなのです。
なぜなら、日本がヘリ空母を建造する前に誰あろう外ならぬ中国と韓国こそが空母を手に入れたり空母のような強襲揚陸艦を建造しているからです。
日本を非難しながら実はそれより先に言い出しっぺの中国や韓国こそが非難されるべきことをやっているのです。
第二次大戦中の空母は搭載機がプロペラ機だったので現在のジェット機より大きさも重量も小さかったため排水量20000t前後の空母であれば70機前後は搭載出来ました。
しかし、現在では搭載機のジェット化により大きさも重量も大きくなったため排水量20000t前後の空母の場合はせいぜい20機前後しか搭載出来ません。
ひゅうが型やいずも型のような直線式飛行甲板ではなくアングルドデッキにして搭載機の一部を露天係留などすればもう少し搭載機数を増やすことは可能でしょう。
あと本格的な空母にするならカタパルトは絶対に必要です。
ちなみに現在、実用的なカタパルトを作れる技術を持っているのは世界でもアメリカ一国のみです。
この技術を持っていないためにソ連→ロシア、中国の空母は実用化がかなり遅れて最終的には見ての通りあのような姿になっています。
現代の空母でカタパルトがないということは搭載機の迅速な発艦も遅くなりますし搭載機の燃料や武装も少ししか積めないことになり総合的には戦力としての能力が劣ったものになります。
比較して解り易いような上面図の資料を見付けましたので参考までに貼ります。
先ずは戦艦「大和」とヘリ搭載護衛艦「いずも」とヘリ搭載護衛艦「ひゅうが」のサイズ比較。
「ひゅうが」がいかに小規模であるかが良く解ると同時に「いずも」の規模がいかに大きいかが良く解ります。
次に世界各国の主立った現代空母(空母らしき艦船を含む)を並べた資料です。
国旗表示もありますが、形式表示もあります。
左側から順番に
・カタパルト発艦→拘束フック着艦出来るもの。
・スキージャンプ台発艦→拘束フック着艦しか出来ないもの。
・カタパルトも無く主に垂直離着陸出来る航空機のみしか使えないもの。
に分けて並べてあります。
ちなみに一番右端が日本の海上自衛隊のヘリ搭載護衛艦「ひゅうが」、その左隣が韓国海軍の強襲揚陸艦「独島」です。
世界の趨勢を知る上で非常に参考になる資料です。
各国が持っている空母らしき艦船の形や規模を見れば中国や韓国が盛んに騒ぎ立てている「日本は軍備増強して軍国主義に走っている」というマスコミ報道が真っ赤な嘘であることが良く判ります。
22DDH「いずも」や24DDHは規模が大きくなっているのは確かですが、これは世界各国の空母らしき艦船の増加に対応しているだけのことなのです。
イラストの『ひゅうが』にオスプレイが描いてあるのがいいですね![]()
日米合同演習の際のひとこま。
・DDH-181「ひゅうが」に着艦したオスプレイ。
・LST-4002「しもきた」に着艦したオスプレイ。
の画像を貼ります。
「ひゅうが」には普通に着艦しています。
「しもきた」に着艦する際にはエンジンの真下にあたる場所に移動式耐熱板を敷いています。
ここから判ることは「ひゅうが」の飛行甲板は既に耐熱仕様であること。
「しもきた」の甲板は日本が当初より主張し続けていた通り真っ正直に耐熱仕様は施されていない甲板であったという事実です。
↑こういうところが正に日本人です。
真っ正直すぎるくらいに律儀。
当初、輸送艦「おおすみ」「しもきた」「くにさき」が建造される際には中国と韓国はこれは空母だ日本はまた軍備を増強して軍国主義に突き進もうとしていると盛んに報道して悪口を世界に向けて発信していました。
それが中国と韓国の人間性の悪さが露呈した結果ですね。
中国のネットに掲載されていた資料を貼ります。
日本の海上自衛隊の「ひゅうが」「いずも」と採用される可能性がある「F35」についての資料です。
中国は日本が再び空母を建造し保有することと、これに併せて「F35」を戦闘機兼攻撃機として採用し搭載運用することを恐れています。
それもそのはず、昔(太平洋戦争の時代まで)の日本はイギリス、アメリカと肩を並べるレベルで空母機動部隊を自前で建造し搭載航空機も自前で作り作戦運用出来ていた世界三大海軍国の中の一国だったことを中国は覚えているからです。
空母機動部隊、搭載航空機の開発と運用は奥が深くたくさんの技術と経験とノウハウが必要なため他の国々は行うことが出来ませんでした。
恐れるのも至極当然でした。
近年は中国も空母を購入し改造して保有し、新たに中国国産の空母も建造しているらしいですが、技術、経験、ノウハウの蓄積がほとんどない国なのでその能力のほどは未知数です。
韓国は日本が「おおすみ」型輸送艦を建造した時に中国と同様に「これは空母だ!日本は軍備増強をして軍国主義に戻ろうとしている」と報道し騒ぎ立て、後々日本が建造した「ひゅうが」と同じ規模の強襲揚陸艦「独島」(韓国が不法占拠している日本領竹島の韓国側の呼び名)を建造しました。
しかし、当然にして技術、経験、ノウハウの蓄積がない韓国の場合も後々いろいろな部分で不具合が続出しています。
おまけに搭載するヘリも予算不足で装備出来ていません。
それなのに(当初予定では三番艦まで建造予定でしたが予算不足により一旦は同型艦建造全て中止)二番艦の建造を予定しているそうです。
搭載するヘリの予算もないのに韓国という国は懲りない国です。
韓国の場合は日本のイージス艦に対抗して保有したイージス艦もセウォル号沈没事故じゃないけど搭載ミサイルの量が多すぎるためトップヘビーになっており、いつ転覆してもおかしくない状態です。
経験の浅い国が背伸びすると危ないことだらけです。
ははぁ、一般に 「イージス艦」ですね、
名前は わかりませんでした![]()
0さんときんたさんは
その道のプロ ですね
イージス艦開発のきっかけは太平洋戦争末期の日本人による命を引き換えにしたアメリカ海軍艦船に対する爆装零戦などを使った体当たり攻撃「神風特攻隊」であったといわれています。
命をいとわず体当たりするために飛来する多数の特攻機をどのようにして防止するか、それは太平洋戦争末期のアメリカ海軍にとって切実な課題でした。
現場に直面したアメリカ人が受けた精神的な衝撃もそうとうなもので初めて目の当たりにした敵国日本の戦い方(神風特攻隊)に無理もない話でありノイローゼに陥るアメリカ人兵士も出たといわれています。
その後、戦後はソ連との冷戦がありソ連爆撃機からの対艦ミサイルの飽和攻撃を防がないとアメリカ海軍艦隊の存続が危ぶまれる事態となりイージス艦開発の研究は更に進み、やがて完成しました。
初期の頃はミサイル巡洋艦にイージスシステムを搭載して使用していました。
やがて改良が進みミサイル駆逐艦にイージスシステムを搭載して使用出来るようになり現在に至っています。
状況に応じていろいろ変動はありますがイージスシステム搭載艦の最大の利点は基本的には同時に二百数十機の敵航空機を探知して、その中から脅威度合いの高いものを即時に判断し同時に二十数機の敵航空機に対しミサイル攻撃して命中させることが出来るという多数同時探知同時攻撃能力の高さです。
しかし、これが可能なのは前面投影面積が比較的に小さくない航空機に対してのみです。
ミサイルに対する迎撃能力はありません。
後にそれを解消するためにミサイル迎撃能力を付与するための弾道ミサイル防衛開発が日米協同で行われアメリカのイージス艦の一部と日本のイージス艦の一部にはそれが搭載されています。
開発した本家のアメリカ海軍のイージス駆逐艦はアーレイバーク級といいます。
日本のイージス艦はアーレイバーク級駆逐艦をベースにしながら日本が独自に建造しイージスシステムはアメリカから買って装備しています。
韓国のイージス艦はアーレイバーク級駆逐艦をベースにしながら韓国が独自に建造しイージスシステム(値段を安くするために一部のシステム、対潜システムはアメリカからは買わず別の国のもので代用)はアメリカから買って装備しています。
アメリカと日本のイージス艦は搭載ミサイルなどほぼ同数を積んでいますが、韓国のイージス艦だけは船体サイズはほぼ同じにもかかわらず搭載ミサイル数をたくさん増やして搭載しているため排水量(船の重さに比例して増えます)が増加し世界最大のイージス駆逐艦になっています。
要約すると韓国のイージス艦はアメリカや日本に比べ船体サイズはほぼ同じなのに安い値段でより多くのミサイルを搭載した攻撃力と排水量が世界最大のイージス艦であるといえます。
そして、このことは韓国自身の自慢にもなっています。
が、韓国人は尽く尽く頭が悪い者揃いだなあと感じるのは私だけではないでしょう。
自慢げに思っているのは韓国人だけで、これを見ている世界の国々は「安物買いの銭失い」だと無能な韓国人を笑っていると思います。
その理由は船の大きさが同じものに対し、よりたくさんミサイル類を大量搭載すると排水量が増え一見すると、より大規模で攻撃能力が高くなったように見えます。
しかし、実際には船の安定性が悪くなりひっくり返り易くなっており、搭載しているミサイル類が多いということは敵から攻撃された場合には内部から爆発し易くなっているという負の部分には目が全く向いていないからです。
要約すると韓国人が世界一になろうと目論み改良した部分は結果的には改善にはなっておらず、安定性低下とダメージコントロール能力低下を招いているのが現実で、おまけにミサイル迎撃能力は元々なく、対潜システムをケチって別の国のものに代替えしたためにシステムの連携性の悪いイージス艦となってしまっています。
軍と民間では関係ないですが、何故だか韓国の旅客船セウォル号沈没事故の時の話とダブって見えて来ます。
参考資料としてアメリカのイージス艦(アーレイバーク級駆逐艦)と日本のイージス艦(護衛艦あたご)と韓国のイージス艦(駆逐艦 世宗大王:セジョンデワンと読みます)の写真を貼ります。
同じような機動をしているにもかかわらず韓国のイージス艦だけは心なしか傾いているように見えます。
ちなみに日本も韓国も搭載するイージスシステムはアメリカから買って装備しているといいましたが、日本が「あたご」と「あしがら」用にイージスシステムを発注する際にタイミングを同じくして韓国も「世宗大王」用のイージスシステムの発注を行っています。
目的は値段を安く済ませるためです。
文句を言わなかった日本は表向きにはあまり語られないこんな部分でも韓国に対し便宜を図ってやっています。
アメリカでのイージス駆逐艦の価格は一隻約1300億円です。
そんなこんなで韓国のイージス駆逐艦の価格は209億円ほど安く買えたといわれていますが、アメリカからは買わなかった対潜システムなどをヨーロッパのメーカーから買って装備した費用を足せば結局一隻約1400億円は超えているだろうといわれています。
日本のこの時のイージス艦は一隻約1475億円かかっています。
日本の初期の頃のイージス艦「こんごう」級は一隻約1245億円ほどだったといいます。
話は少し変わりますが、戦艦「大和」の建造費用を現在の価値に換算すると一隻約3000億円だといわれます。
ということは日本の最新イージス艦は約ニ隻で戦艦「大和」一隻分の費用がかかっているということになりますね。
高価な船です。
イージス艦の価格はその半分がイージスシステムにかかっているといわれますからシステム自体が高価なシステムです。
故に経済的に資金を持たない国は持つことも叶いません。
たとえ持てたとしても電子的な部分が強味な艦船だけに頻繁なアップデートによる維持管理経費も高いので長く持ち続けることは経済的な国の体力を奪う結果になります。
空母もそうですが、イージス艦も保有するにはかなりのお金が必要とされることを覚悟しなければなりません。
0さん 画像ありがとうございます、
おっしゃるとうり、
韓国の旅客船セウォル号沈没事故
船長や乗組員は乗船客を とどめて、
私服に着替えて、我先にに救助され。
まったくひどい話しです韓国人は当たり前かも、![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
イージス戦の詳しい話し ありがとうm(__)mです、勉強しましたよ、
先程ディスカバリーチャンネルのテレビで
超音速ステルス戦闘機
『F-35』
がありました、マッハ1。6ハリアーの欠点を補うとか、9ヶ国のエンジニアが2000億円かけて
0さんの言う 費用は戦艦大和と同じですね
900㌔級誘導爆弾を
機内に2個搭載
バンカーバスター弾 も
未來の戦闘機ですね、
F35のムービーです
↓↓
F35 の追加ムービー
です
↓↓
F-35 また追加です、↓↓
ヘルシアさん、こんにちは。(゚▽゚)/
昔から個人的にはハリアー戦闘攻撃機のようなものこそ緻密な物作りが得意な島国日本が開発して持つべき防衛装備品だと思っております。
東洋の島国日本では実際にはそうはなっておりませんが…
西洋の同じく島国イギリスでは二十数年もの長い開発期間を経て不屈のジョンブル精神でもって世界初の実用垂直離着陸戦闘機ハリアーを完成させ自国防衛に使用していました。(かつて当初は世界各国で垂直離着陸機の開発が流行りのように行われていたのですが、どの国も開発の難しさとかかる経費に負けてしまい開発中止となり断念していました、最後まで開発を続けたのは粘り強いイギリスと会社の倒産などのない社会主義国家ソ連だけでした)
ハリアーが成功したポイントは四つの推力偏向ノズルを持つ一つのエンジン(コンコルドのエンジンと同じものをベースに改良したロールスロイス製エンジン)と狭い空き地に垂直着陸し思い立った時に他からの支援なしで、また飛び立てるセルフサービス性でした。(現代のジェット戦闘機の大半は高性能だけど地上スタッフの支援なしには再び飛び立つことは出来ません)
ハリアー開発の元々のコンセプトが核攻撃を受けた後も地上支援部隊の支援がなくても各自独自に反撃が可能なこととなっていたためにこのような機能を持っていました。
ハリアーは特殊な飛行が出来る戦闘機だったため超音速飛行は出来ませんでした。
しかし、エンジン的には改良発展型ではマッハ2.0のスピードまでは出せるめどは立っていましたが、現代戦闘機に求められる機能としてステルス性能も加わって来たためその後かかるであろう開発費の高騰を考慮してイギリスは発展型開発を断念しました。
そしてアメリカ主導の国際協同開発の統合型戦闘機(ジョイントストライクファイターJSF→後のF35A/B/C)の重要な開発パートナーとなる道を選びました。
昔は山口県岩国の在日アメリカ海兵隊基地にハリアー戦闘攻撃機が配備されていたため日本でも実際に見に行くことが出来ていました。
・垂直離陸して行くアメリカ海兵隊のAV-8BハリアーⅡ
・夜間、垂直離陸して行くアメリカ海兵隊のAV-8BハリアーⅡ(夜間暗視画像)
・ホバーリングからバック飛行するアメリカ海兵隊のAV-8BハリアーⅡ
の参考画像を貼ります。
四つのメインノズルの中でも後部の二つだけがジェット排気であることが判る画像です。
イギリスは統合型戦闘攻撃機F35A/B/Cの国際協同開発の重要な開発パートナーとなる道を選択し、これが完成したらイギリス海軍もイギリス空軍もハリアーの後継機として採用する予定となっています。
ハリアーに比べF35Bは超音速飛行が出来、ステルス性能もあるため性能アップした点が多いですが、メインエンジンとは別にリフト専用ファンを搭載しているので重量的なロスが大きい点とセルフサービス性がないであろう点はむしろ性能が退化しているともいえます。
ただ、たくさんの機種の後継機となれる可能性を持ったF35の幅広い汎用性を考えるとそこまで求めるのは無理な要求かも知れません。
ハリアー開発当初の時代の他の国の垂直離着陸機はみなメインエンジンの他にリフト専用エンジンを別に同時搭載しているものばかりでした。
この形式だと垂直離着陸の時しか使わないリフト専用エンジンは通常飛行の時には使わない重量物になってしまうため性能を低下させる非常に大きな足枷となっていて実用機としての発展を妨げていました。
イギリスのハリアーは一つのエンジンで全てを行えて通常飛行の時も使わない重量物がないという点でパワー効率が非常に高く実用化を後押しする要因にもなりました。
当初F35の開発は構想だけが先行しなかなか実機の開発が進みませんでした。
理由はやはりエンジンをどのようにするかで難航していました。
結局リフト専用には別のエンジンは搭載せず専用ファンだけを設け、その動力はメインエンジンから取り出した回転力を伝達し回転させる方式を選びました。
残った問題点はメインエンジンの推力をどうやって真後ろから真下に偏向させるかでした。
そしてソ連のヤコブレフYak41(後にYak141に改名)垂直離着陸戦闘攻撃機が使っていた推力偏向ノズルの技術をソ連崩壊後にライセンス購入して活用することで問題点が解決され実機の開発が進むことになりました。
予定では日本の山口県岩国の在日アメリカ海兵隊基地に再来年の2016年にはF35Bが配備されることになっています。
そう考えると今後の日米合同軍事演習ではF35Bが参加することは当然現実的になりますから海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦「ひゅうが」級に離着艦するということも当然ある話だと思われます。
そこから更に考えると昨年の日米合同軍事演習の際に「ひゅうが」級にオスプレイを離着艦させて実演したのもそういう意味での試金石だったのだなあと理解出来ます。
・大西洋上の強襲揚陸艦ワスプ艦上で行われたF35Bの垂直離着艦テスト
・夜間、垂直着陸するF35B(夜間暗視画像)
の画像を貼ります。
この画像でもF35Bの場合も後部のメインエンジンノズルだけがジェット排気であることが判ります。
このようなことが実際に進行中であることを考えるとF35Bの日本導入化も絵空事ではないということが実感されます。
一時期国際的な話題の論点になった海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦の飛行甲板が耐熱仕様なのかどうなのかについて重要な点、搭載する航空機の排気温度ですが、オスプレイの場合は269度であることが公表されています。
F35Bの排気温度は軍事機密ということで残念ながら公表されていません。
それから「おおすみ」級輸送艦の飛行甲板の耐熱仕様化を含めた改装計画もあるようです。
中国と韓国が異常な剣幕で恐れていたこと(日本が空母とF35Bを併せ持つこと)が現実問題として只今進行中のようです。
しかし、このような動きを加速させている最大の原因は中国と韓国の日本に対する悪い行いなのですから自業自得であるといえます。
自分で撒いた種だろうということです。
昔 岩国市の海兵隊基地(海上自衛隊も同居)でこどもの日に解放された日にハリアーのデモを見ました。着陸時に高度が割りとあるのにエンジンカットしたのには驚きました。
岩国基地のフレンドシップデェーのオープンハウスは私も二回ほど行ったことがありハリアーの飛行展示も見て来ました。
きんたさんのお話はもしかしたらハリアーの造りに関係しているのかも知れません。
ハリアーは垂直離着陸時のエンジン冷却用に脱イオン水を搭載していて、それがある間だけ垂直離着陸飛行が可能なのです。
30年前の話しです![]() 当時 広島の第13師団(今は旅団)の特車大隊の方が『やっと61がまわってきた』とよろこんで(ぼやいて)のが印象的でした
当時 広島の第13師団(今は旅団)の特車大隊の方が『やっと61がまわってきた』とよろこんで(ぼやいて)のが印象的でした![]()
61式戦車ですか、これまた懐かしい戦車ですね。
日本の道路、架橋の事情と地形を考慮して既存のアメリカ製戦車を装備するという選択は敢えて行わず、戦後は兵器開発製造を禁止され技術的空白の年月があったにもかかわらず独自に開発した主力戦車の第一号でした。
昔は東西冷戦のさなかでしたから日本の防衛のかたちは北方重視だったので「61がやっとまわってきた」といわれたその意味は重い実感を感じますね。
北方から来襲するであろうソ連の軍事力をどう食い止めアメリカ軍が来てくれるまで持ちこたえるかが重要課題でしたから。
61式戦車→74式戦車→90式戦車までは強力なソ連製戦車の攻撃にいかにして耐え、逆に強力なソ連製戦車の装甲をいかにして破壊しソ連軍の進攻を食い止めるかが一番の最優先課題でした。
ソ連崩壊後の現在では国産戦車に求められる性能要求値も様変わりして次に開発された10式戦車では対ゲリラ戦能力や融通の利く全国展開能力が主眼とされ軽量化しつつ攻撃、防御能力を高めるという相反する要求をなんとかクリアして配備が進められているようです。
進出地域の脅威度合いに応じて装甲の着脱により車重を増減が出来て、スラローム走行しながら射撃しても命中弾を与えられる戦車になっています。
10式戦車は装甲の装着状態により車重を40t→44t→48tと変えることが可能で対峙するであろう敵戦車の強力さに応じた装甲装備にすることが出来ます。
また、新たな新装甲が開発された場合は着脱装甲の中味を換えるだけで姿は同じでも装甲の強化された戦車にバージョンアップすることも可能です。
世界各国の主力戦車は新型になる度に重量が増加し、今や63tを越えるものも珍しくありません。
そういう意味でも日本の10式戦車は世界最先端をいっている戦車といえそうです。
ざっと考えても
日本の主力戦車の重量は太平洋戦争時の
九七式中戦車(18t)
試作車輛のみ四式中戦車(25t)
試作車輛のみ五式中戦車(35t)
太平洋戦争後の
61式戦車(35t)
74式戦車(38t)
90式戦車(50t)
10式戦車(40t〜48t)
といった流れですから日本製の戦車というものはいつの時代も概ね軽量なものばかりです。
長い間戦車の強さは重量であらかた判るといわれ重いものが強いという考え方が支配的でしたが、装甲に使用される素材が金属だけとは限らなくなった現代ではそうともいえなくなって来ています。
造り方、構造技術と装甲素材技術次第では10式戦車のような事例も今後は増えるでしょう。
昔は鉄道の幅で戦車の幅もきまるとか? 三式中戦車と ドイツの2号軽戦車の幅が同じです![]()
きんたさんのおっしゃる通り昔は大きな重量物の輸送力の要が鉄道と船だったため陸上兵器である戦車は鉄道輸送に大きく依存していました。
鉄道はレール幅が広軌路線と狭軌路線があり日本の場合は狭軌路線でした。
欧米列強国の考え方でいえば広軌路線の鉄道は支配国の本国サイズ、狭軌路線の鉄道は欧米列強国に支配されていた植民地サイズということになります。
こんな部分にも欧米列強国による植民地差別の歴史の痕跡を垣間見ることが出来ます。
欧米列強国にとっての日本はアジアで唯一富国強兵をいち早く実行し急速に力をつけた国だったとはいえ植民地レベルでしかない差別の対象に外ならなかったのは事実でした。
昔は必然的にどこの国の戦車も自分の国の鉄道のレール幅の範囲内でしか造れず極少数の例外的戦車以外のほとんどの戦車の幅はそのレール幅に制限を受けていました。
今ならどこの国にもたくさんの広い道路があり戦車を積載して走れるトレーラーがあるため昔ほど制限にとらわれなくて済むようになりました。
それでも日本の現代戦車と諸外国の戦車を比較すると日本の戦車は今なお幅が狭く長さが長めの造りになっています。
現代の日本製戦車とアメリカ製戦車を比較するとアメリカ製に比べ日本製の方が極端に細長い車体になっていて対称的です。
日本は諸外国に比べ道路の幅も狭い道が多いということなのかも知れません。
冷戦時代の西ドイツ国防軍の演習を見てみると、アスファルトの上を全力走行するレオパルドⅡの後に三メートルぐらい巻き上げられてました![]()
0さんも きんたさんも すごいなあ
頭が下がります、
皆さん、こんにちは。
(゚▽゚)/
文章を読むだけではおもしろくないでしょうから参考資料となるような写真を貼ります。
・ドイツのクラウスマッファイヴェグマン社がプライムメーカーとなり造り上げたレオパルド2
写真は右側車輛がレオパルド2A4、これをベースに改良された最新版の種類の一つレオパルド2NGが左側車輛(NGとはニュージェネレーションの略です)(一般の車と同じく人気車種は純正/社外品含め改造パーツがたくさんの種類造られますので世界的人気車種の戦車であるレオパルド2の改良版はたくさん存在します)
・既に退役して屋外展示してある61式戦車の写真(プライムメーカーは三菱)
・2011年の富士総合火力演習の時に並べて展示された74式戦車と90式戦車と10式戦車の写真(いずれもプライムメーカーは三菱)
こうして三世代並んでいるのを眺めるとその時代その時代の戦車開発の流行が目で見て判ります。
昔とはガラリと様変わりして今では被弾経始を重視した鋳造の装甲だけでは防御力が全く足りないことを如実に物語っています。
新しい装甲がなく鉄だけの装甲の戦車ではもう通用しない時代になったということでしょう。
現在の日本の戦車がドイツの戦車に似ているのは同じ系統の複合装甲を採用しているからです。
いろいろな素材を組み合わせた拘束セラミック複合装甲を採用していて素材や製法は機密扱いです。
イギリスやアメリカも複合装甲を使用していますがドイツや日本のような拘束セラミック複合装甲ではないようです。
たぶんイギリスが最初に開発したチョバムアーマーを基本にして改良を重ねたものでしょう。
イギリスとアメリカの現在の戦車が姿が似ているのはそのためです。
世界的に最初に複合装甲を開発したのはイギリスの兵器廠でチョバムアーマーだということになっていましたがソ連崩壊後明らかになったところによるとソ連の方がイギリスよりも早く複合装甲を開発していたらしいです。
しかし、能力的には複合素材の積層の厚みが厚くなく強力な装甲とはなっていなかったようです。
ソ連で最初に複合装甲を取り入れ開発されたのはT-64戦車でガスタービンエンジンと同時に導入されましたが、どちらもかんばしくなくコストだけが高くつき主流派にはなれませんでした。
ソ連の場合の複合装甲はガラス繊維やアルミナや金属板をプラスチックで積層して固めたようなもので、半球形状鋳造砲塔の前面部分をくり抜きそこへその複合素材を収納し装甲板で蓋をして溶接するという製造方法であり、元々複合素材の収納部分の奥行きが深くなく厚みが足りなかったのが失敗の原因ではなかろうかと思います。
ソ連の戦車は被弾率を下げるために背を低くして正面面積を小さくした姿ばかりであり伝統的に砲塔内も車内も狭く外装式ではなく内装式にしたところに無理があったのでしょう。
旧ソ連の戦車は中が狭すぎて戦車兵に身長制限があったのは本当なの?またウォッカは食糧ではなくて燃料で計上されていたん?
イギリス、アメリカの現代戦車は積層式複合装甲を傾斜させて装備しているためお互い似通った姿の戦車になっています。
ドイツ、日本の現代戦車は基本的には複合素材をライナーで圧迫して締め付け六角柱のようなものを作りそれを敷き詰めた分厚い箱のような複合装甲を作り垂直に立てたような状態で装備していて、外側を覆うようなかたちでスペースドアーマーを追加装着しています。
現代戦車を脅かす敵弾は大きく分けると高速徹甲弾とヒート弾(成形炸薬弾)になります。
複合装甲の能力としてはこのどちらにもコンスタントに防御力が高いという意味に於いては積層式複合装甲より拘束セラミック複合装甲の方が優秀だといわれています。
このこともさることながらドイツや日本が傾斜装甲にしなかった理由は進化して強力になった現代の対戦車砲弾に対してはもはや装甲を傾斜させてもほとんど意味はないという割り切りからでした。
いずれにしてもどこの国もより防御力の高い複合装甲を作れる素材を絶えずさがして研究しています。
例えばアメリカのM1エイブラムス戦車でも外見は変わっていなくても初期のものと現在のものでは中に入れてある複合素材が変わっており強力になっています。
例えば同じセラミックでも酸化アルミ系→沸化ボロン系や劣化ウラン系などなど。
いつ何に変更したなどと公表はしませんし逆にどの国もこの手の話は軍事機密扱いとして他国には教えません。
韓国はどうにかしてこの先進国の技術を真似ようとしていますが、韓国の国産複合装甲の耐弾実験写真を見るとわらってしまいます。
砲弾が命中したら白い粉が吹き出し複合装甲としてはうまく機能しなかったようです。
もう古くなった技術ならいざしらずそんなものそう簡単に教えてくれる国があるはずがないです。
外国製の複合装甲や何やらかにやら買って来て寄せ集めて作った実験車輛ならある程度うまくいくでしょうが、真似て作った韓国国産品に変えた途端にトラブルや故障続出、今韓国が一番悩んでいることでしょうね。
それでも韓国国産兵器は世界一だと言って一歩も引かない厚顔さ。
ウォッカの話は良く知りませんが、ソ連のマッハ3出せる迎撃戦闘機Mig25フォックスバットは冷却用に純度の高いアルコールを必要としていてそれを搭載していたのでアルコール運搬機と冗談でよくいわれていたそうで、ソ連兵はMig25フォックスバット用のその純度の高いアルコールを酒代わりに飲んでいたという話は聞いたことがあります。
ソ連の戦車兵には身長制限がある話は聞いたことがあります。
ソ連戦車の操縦手の乗車ポジションなんてF1マシーン以上に仰向けですね。(笑)
なんでも 小型化するのは日本の得意とするところ
ソ連の戦車は、寝た状態のような、形で操縦ですか、![]()
ソ連は昔からドイツと並ぶ陸軍大国、戦車の開発という分野では第二次大戦が始まる前は世界には秘密にしながらドイツとソ連は戦車の協同研究をしていた仲でした。
結局どちらも仲たがいして第二次大戦で戦い合うことになりました。
ソ連製戦車は敵弾が当たらないようにするため前面投影面積の縮小に努力しました。
その結果、車高は次第に低くなり車内は狭くなり戦車兵の体格を小柄な人間に限定しなくてはならなくなりました。
弊害はこれだけに留まらず防御装甲のスペースが狭くなり防御力が低下、狭い車内での取り回しを良くするために戦車砲弾の長さも短めにするしかなく砲弾の破壊力も低下しました。
それが世界に向けて大々的に露呈したのが湾岸戦争でした。
イラク軍の装備していた戦車はほとんどがソ連製だったからでした。
ソ連製のT-72戦車が多国籍軍戦車に一方的にコテンパに撃破されたのは記憶に新しいところです。
これによりソ連製T-72戦車は弱いというイメージが世界各国に焼き付けられたため湾岸戦争後のソ連→ロシアは改良版のT-90戦車を造りイメージ回復に躍起になりましたが、いまだに払拭出来ていないようです。
数は多いお金はあまり持っていないが戦車が欲しい国々の間ではソ連製の戦車は好評だったためこのイメージダウンはソ連にとってかなりの経済的痛手となりました。
そこに拍車をかけるようにソ連製戦車をパクりコピーした中国製戦車が更に低価格で売り込み始めたため状況は更に深刻化しました。
自分の兵器市場を食い荒らされたソ連→ロシアは実は中国に対しハラワタが煮え繰り返っているのでした。
表向きではプーチンが中国と握手していてもロシア国内の軍事関連企業は笑顔ではないのです。
中国はソ連→ロシア製のものをミリタリー服や拳銃から戦闘機まで相当な種類と数をパクりコピーして世界中の貧乏国に大量販売していますからソ連→ロシアは世界最大の中国によるパクりコピー被害国なのです。
冷戦が終わるまでの時代は資本主義諸国から中国への技術的アプローチはほとんど皆無であり中国に入って来る技術的な知識や物のほとんど全部がソ連からのものでした。
ほとんど全てに近いくらい中国にある技術的文明的なものはソ連のものをベースとしています。
ソ連は自国のものを中国へ供与するにあたり中国や中国軍での使用に限ると限定する条件を付けていたのですが、中国自身はこのソ連との約束事を公然と簡単に破りパクりコピー生産したあらゆるものを安いよ安いよと宣伝しながら世界中の貧乏国の紛争当事国に売りさばき始め、いまだにそれをやめず、むしろ更に拡大させている現状です。
そしてあろうことか中国が開発したものだと大嘘までついて平気な顔をしているのです。
どこかの国、韓国と行動パターンが恐ろしく似ていますよね。
自分のものは自分のもの、他人のものも自分のもの的な普通の人の頭では理解出来ない習性は中国人も韓国人もそっくりです。
世界中から嫌われる条件を十二分に満たしています。中国などはいくら人口が多くても領土が広大でも尊敬に値しない人間の集まりだから世界中の人々から尊敬されるわけはないのです。
中国は自分たちは中国四千年の歴史があり長い歴史を持つ国なのだから敬意を払えと事あるごとに諸外国に要求しますが、長い長い間尊敬されないことばかり繰り返しているのだから尊敬を要求しても無理な相談でしょう。
諸外国はそんなに馬鹿じゃない。
中国は他国より長い歴史がある国なのだという自負があり、おごりがあるため海洋進出政策による他国との紛争や一方的な防空識別圏の宣言などが如実に示すように国際的なルールに従うのが苦手で自分勝手なマイルールを他国に押し付ける悪い癖が治せない困った隣国です。
もうちょっと人々の自由や権利を尊重し統制がうまく取れる程度に何ヶ国かに分裂すれば良いのにと思います。
頭の悪い乱暴者は周りの国に迷惑です。
0さん、おっしゃるとうりです。
東京や大阪で 列をつくって並んでいると、
いきなり横から割り込んでくると、聞いたことあります、![]() 中国風な日本語で、
中国風な日本語で、
竹島も 相変わらず です 中国も韓国も なんでもパクリが専門ですね、
↓↓
この人は 何を考えてるんでしょうね、
/ ̄ ̄ ̄Y ̄ ̄\
| |
L_/ ̄ ̄ ̄ ̄\ノ
|:: |
|: __ _|
(6 \●> <●∧
| )・・( |
ヽ (三) ノ
/\ /
/⌒ヽ  ̄ ̄ ̄ ̄\
`| | ヽo ヽ
北朝鮮は付き合い方次第によれば日本にとって有益な存在にもなる可能性はありますね。
但し、接し方を誤れば気違いのような行動をとる可能性もありそう。
北朝鮮と韓国を見比べると大半の人々が北朝鮮は立ち遅れていて韓国の方が圧倒的に近代国家だと思っていそうですが、局部的な比較をすればロケットや宇宙開発技術を見ると北朝鮮の方が遥かに上をいっているようです。
最近の韓国社会を見ていると急げ急げで外国製技術をパクりまくって上辺だけ先進国を装っていたメッキがあちらこちらの分野で剥がれ出し韓国社会全体自体の信用そのものが根底から崩れ出しています。
韓国は衛星も持ち先進国のような振る舞いをしていますが、その真実の姿は一度たりとも自前の技術で打ち上げに成功したこともない宇宙開発技術に立ち遅れた国なのです。
アメリカに打ち上げてもらい、フランスに打ち上げてもらい、日本にも打ち上げてもらい、使用している衛星は全て先進諸外国に打ち上げてもらったものばかりです。
韓国が自前の技術だと鼻高々に宣伝して世界中に輸出している工業製品もそれに必要不可欠なキーになる部分は全て先進国から輸入した部品に大きく依存しておりスマホでも車でも日本に対する依存度はかなり高いものがあるのですが、それを公表はせずに隠しているだけなのです。
地道な努力や苦労もろくにして来なかった国が短期間のうちに高性能な工業製品を量産出来るようになったというのは虫のいいお話であり現実には有り得ないというのが隠された真実なのです。
>>530 皆さん今晩は。 ラッパロ条約でしたかね?戦車開発が禁じられたドイツがソ連と結んだのは。国際政治は複雑怪奇![]() 先日のノルマンディに集まった方々も
先日のノルマンディに集まった方々も![]()
私は条約名までは知りませんでしたが、内容的には第一次大戦に敗れたドイツは戦車開発や軍用機開発を禁じられており秘密で行われたソビエトとの密約により他国からの監視の目の届かないソビエト領内のカザン戦車学校で戦車開発や軍事演習などを行っていたという素地があったためベルサイユ条約を破棄し再軍備宣言をした後もスムーズな再軍備が可能となっていたということですね。
ドイツとソビエトどちらも西側諸国からしいたげられ孤立状態になっていて当時の現状に不満を持っていたためその状態を解消しようとして協力関係を持つに至りました。
ドイツは兵器開発の空白と軍事力の弱体化を嫌い、ソビエトはロシア革命の影響で弱体化したソビエト軍を再度強化したかった。
カザン戦車学校に送り込まれたドイツ軍将校はドイツ軍ソビエト軍の区別なく教育を施したといわれています。
両国ともに利害が一致していたということ。
しかし、ソビエト嫌いのヒトラー総統がドイツの政権をとりドイツが疎遠だったイギリスやフランスと接近するようになるとドイツとソビエトは疎遠となりやがては関係の解消へとなりました。
昔も現在も根底にあるものは変わらないと思えるのがやはり国際関係は表向きの顔とは別に利害の一致というものによって複雑化し予想外の関係をももたらすということでしょう。
最近の動きとして中国はアメリカを牽制する目的で下手な動きはするなよと言わんばかりにロシアとの親密さをアピール。
ロシアはウクライナ問題であれこれ口出しされたくないのでアメリカを牽制する目的で中国と親密な関係であることを演出。
しかし、この二ヵ国、本当に相思相愛かといえば実はわからない。
親密そうに見える関係も上辺だけ。
今のところは利害の一致をみているが、いつまで続くのかは極めて不透明。
現代社会に生きる私たちにとって今の世界情勢、特に緊迫の度合いを強める最近のアジア情勢は大事な事柄です。
しかし、話がちょっとスレタイトルから離れてしまったので零戦関連に戻って零戦の戦場写真を二枚貼ります。
まだ真夏でもないのに最近は暑い日が続いていますので皆さん水分補給はこまめに行って下さいね。
ということで
・南方の恵み椰子の実で水分補給をする南方進出零戦部隊。(写っている零戦は二一型)
・南の島の波打際で燃料補給中の中島製二式水上戦闘機。(飛行場を設けられないような点在する小島の防衛を目的に零戦二一型をベースにして中島飛行機が作り出したのが二式水上戦闘機でした)
日本海軍はこの目的のために川西飛行機に対し水上戦闘機「強風」を作るよう指示しており、これが完成するまでの繋ぎとして作られたのが二式水上戦闘機でした。
繋ぎのはずの二式水上戦闘機でしたが、優秀だったため少量生産の予定に反してたくさん生産されました。
川西飛行機の水上戦闘機「強風」は後に改良されて局地戦闘機「紫電」になり、それを更に改良して局地戦闘機「紫電改」が作られ零戦の後継機「烈風」を実用化出来ずにいた太平洋戦争末期の日本海軍戦闘機部隊を支えました。
↑一部間違えてました。
二式水上戦闘機のベースとなった機体は零戦二一型ではなく零戦一一型でした。
ごめんなさい。m(__)m
略して二式水戦、通称:下駄履き零戦こと二式水上戦闘機はフロートが付いているので滑走路がなくても海上がどこでも滑走路代わりに使える点が最大の利点であり飛行場が造れないような地形や小さな島々での防空や海上交通路での輸送船団の上空援護などに使用されました。
幅広い汎用性があった半面、フロートが付いているぶん戦闘機単体としての性能ではフロートなしの戦闘機と比較すると不利なところもありました。
しかし、フロート付きの水上戦闘機としては性能が高く水上戦闘機としては世界最多の327機も生産され南方海域から北は極寒のアリューシャン列島まで幅広い範囲で使用されました。
そのぶん台風や嵐やおおしけなどの激しい気性環境により失われた数が多かったといいます。
アメリカやイギリスでも水上戦闘機は造られはしましたが、いずれも日本の二式水上戦闘機ほどの性能は出せず、テスト機レベルでおわり採用されるところまでは行きませんでした。
参考写真を貼ります。
・飛行中の日本の中島二式水上戦闘機
・水上滑走中のアメリカのグラマンF4F-3S水上戦闘機
・飛行中のイギリスのスーパーマーリン・スピットファイアMk.Ⅴb水上戦闘機型(Mk.Ⅴb=bウィング仕様の五型という意味)
ぱっと見てもアメリカ機、イギリス機には工夫がほとんど見られず、日本機には独創的な工夫がありありと見て取れます。
在り来りのことをしていては高い性能は得られないことを体言しているようです。
大きなフロートを二つもぶら下げていたら性能が急低下して元のベース機体がどんなに高性能でも低性能機になるのは当然なのでしかたない結果です。
なんといっても、
零戦は、我々日本人の
誇りですね、
胸が熱くなります、
余談ですが、先程タイムスクープハンターというテレビを
見ていたら
世界最古の眼鏡(鼻にかけるタイプ) ドイツで発明者ひ不明ですが
ドイツのウィーンハウゼン修道院 所蔵
14世紀後半だそうで、
日本に眼鏡が持ち込まれたのは
1551年 フランシスコザビエルによって日本に持ち込まれたようです、
余談失礼しました
現在の眼鏡の鼻に当たる部分の造りは日本人によって付け加えられたもので眼鏡が日本に入って来た時、西洋人に比べ顔の彫りが深くなく顔が平たい日本人が使うにはちょっと使い辛かったために改良を加えたそうです。
それが今では眼鏡の普通の姿になって世界中に普及しているということのようです。
世界中には日本人と同じように顔が平たい人たちがたくさん居ますからこの形で世界中に普及し今に至ったのも納得です。
0さん、おっしゃる その事も 言ってましたよ
鼻が低い為、鼻にあたる部分は 日本人が発明したとか、
余談の余談ついでに日本に入って来た眼鏡の話からレンズ繋がりでお話をすると無駄だったといわれることもある大和級戦艦。
明治以来我々の先祖が努力に努力を重ねて自国開発により造って来た軍艦、その中でも持てる技術の粋を総動員して造られたのが大和級戦艦でした。
華々しい活躍の場には恵まれませんでしたが、太平洋戦争敗戦後すべてが荒廃しきってボロボロだった日本が見違えるような急速な戦後復興を成し遂げた得た陰には大和開発までに習得して来た様々な技術と経験が有ったからこそでした。
一つ挙げるとするなら大和級戦艦に搭載されていた世界最大の15.5m測距儀です。
現在のニコンの前身である日本光学製でした。
ニコンは現在でも世界トップレベルの技術を活かし半導体(IC、LSI、C-MOSなどなど)を作るための製造装置の分野で世界トップクラスであり続けています。
これはやはり戦時中からのしたずみの苦労の積み重ねのなせる技でしょう。
韓国や台湾、中国などの新興工業国が急速に経済発展して来たとはいえ全てについて根幹に関わる部分については自分では作れず今だに日本の技術に依存しっ放しの現状を見れば彼我の技術力の差は歴然としていることが判ります。
参考資料として
・大和級戦艦の艦橋部分の模型の写真
・15.5m測距儀の写真と図解
を貼ります。
戦後の日本メーカーが光学機器やカメラ、デジカメ、半導体で世界の上位のメーカーであり続いていることと戦艦大和に代表される戦時中の兵器開発とは無縁ではないのです。
今は世界でトップとはいえませんが、かつて造船の分野でも戦時中の兵器開発で培われていた力が発揮されていました。
日本から盗んだ製鉄技術を元にして中国、韓国が大型船舶を造れるようになったため労働者の賃金の違いにより日本の造船業は世界でトップではなくなりました。
しかし、たとえ建造費が高かったとしても信頼性あるものの造りと安全性を考えると日本製を選択するのが賢いでしょう。
イギリスなどは大型客船を韓国や中国には頼まず日本に建造依頼して来ていますが、賢い国は良く判ってくれているのです。
戦艦大和の 上の方にあるアンテナ みたいなの
ですね、Nikonでしたか、
明治の 乃木希典大将の
望遠鏡は、たしか
ドイツの、カールツワイスだとか、
ドイツは確かに名品揃いですね、
Nikonは、我日本の優秀メーカーですね、
戦後日本の技術はこれだけに留まらず、繊維や複合素材や金属など様々な素材技術分野でもトップをいっています。
ただ、戦後の日本では兵器開発をあまり良く思わない人たちが増えたため、持てる素材技術を兵器に活かすということがスムーズにいっていません。
どこの国でもいえることですが、技術力とノウハウ(例えるなら何を何回どのようなあんばいでどうすれば一番良いかなどというやり方)は国の宝ですから絶やしてはならないですね。
ソニーのハンディカムではドイツのツァイスレンズを搭載していることを売りにして販売していましたが、あれはツァイスレンズをドイツから購入して組み込んでいたのではなく、ライセンスを購入してレンズの製造方法や研磨方法を教えてもらい自負たちで造ったレンズを組み込んで販売していました。
そういう意味に於いてもノウハウというものは技術力と並び重要であり国力や企業力の両輪のようなものですね。
↑自分たちと入れたつもりが自負たちとなってました。
ごめんなさい。m(__)m
中国や韓国では日本や欧米先進諸国の技術をよく盗み近年の発展に繋げています。
しかし、技術は技術資料などを盗むことで手に入れられますが、ノウハウというものは実際に自分で実行して体験しないと得られないものです。
実際に自分たちで実行するとなると事故などで人的被害も発生します。
古くは日本刀などの材料の作製や焼き入れや研磨の方法など聞いただけの話や見ただけでは真似たつもりでも同じものは造れません。
現代でいえば装甲板の焼き入れや各種素材の精製方法やレンズや金属の研磨方法などなど。
中国製や韓国製の製品や兵器が日本や欧米先進諸国のものとそっくりに出来上がっていても、とかく精度が悪かったり信頼性が悪かったりするのは技術資料だけを盗み真似ているからです。
そこには大切なはずのノウハウが欠落しているということでしょう。
レシピだけ盗んで作っただけの料理は一流の味は出せないのと同じだと思います。
中国では旧ソ連から未完成空母を購入し改造して使えるようにしていますが、大型艦船のエンジンすら自分では作れないところをみるとどこまで使える空母なのかは奇しいところです。
韓国は空母に似た強襲揚陸艦「独島(韓国が不法占拠している日本の領土島根県竹島の韓国での呼び名)」を建造し配備していますが、このような大型の軍艦の建造や運用の経験がなかった韓国では早速ノウハウのなさを内外に露呈しています。
欧米先進国から購入したレーダーなどを搭載したにもかかわらず有りもしない敵(ゴースト)を映し出したりしていて今も解決出来ていないのかも知れません。
理由は設置位置や建て付けなんだとか。
やはりノウハウの欠如が原因。
見よう見真似では本物は造れません。
正に仏作って魂入れず。
いや、
仏作って魂入れきれず。
がぴったりです。
ノウハウの欠如が原因。
見よう見真似では本物は造れません。
↑↑
まさにそのとうりです
日本刀は 他国では
造れません、
日本刀は、日本独自の物 しかし 現在の刀匠が
平安、鎌倉時代の刀に
挑戦してますが、
当時の刀には、なれません、
それに近い刀は造ってますが、
西洋や中国の剣は、ただの鉄の棒ですね、
まさにノウハウがないとまねしても
造れませんね、
私はざっくりした理解のし方ですが、
・西洋の剣は刺すもの、
・中国の剣は力押しでぶつ切りにするもの、
・日本刀は刺すこともぶつ切りにすることも出来て何より引いて鮮やかに切ることが出来る。
という感じで認識していましたがどうでしょう?
遥か昔の時代の武器ですが、そんな昔の時代から既に日本人が作るものづくりには独特の賢さがあったのだと理解しています。
日本人、韓国人、中国人、いずれもアジア人として見た目は似ていますが中身は全く別種ですね。
ものの考え方が根本から違う気がします。
だから結果として作る物にも大きな違いが生まれるのだと思います。
早く近代化したとか近代化が遅かったから劣る物しか作れなかったとかいうのは間違いであり単なる言い訳だと思います。
日本刀がそれを証明しています。
昔は日本より中国や朝鮮のほうが何でも全般的に進んでいたはずなのに日本刀に勝る剣を持たず造れず日本から輸入品として買っていたという話もありますから近代化云々の話は現在の中国人、韓国人たちの都合に合わせた只の言い訳です。
0さんの、コメント
まったく同感です、
過去の 日本の匠の、もの作り
世界にも ひけをとらないです。
日本人が精魂込めて作り出したものは数々ありますが、その中でも頭の中にいつも思い浮かぶものはといえば、やはり日本刀、零戦、戦艦大和といった具合です。
いずれも日本人らしさがこもるものばかりです。
零戦の写真を一枚貼ります。
今から35〜36年ほど前、日本へ里帰り飛行するために帰り日本各地の上空を慰霊飛行してまわった時の零戦五二型の写真です。
写真が古いせいなのか、飛行時間帯が夕暮れだったせいなのか、全体的にセピアがかっています。
手前には零戦の飛行に見入る人々の姿と零戦歓迎の文字が見えます。
この零戦は今も世界で唯一オリジナル中島製栄エンジンで飛行可能なアメリカのプレーンズオブフェイム博物館の零戦五二型です。
こりゃ素晴らしい画像
おそれいります、
感無量です、
ハイテク戦闘機が現存する中で、
日本の誇りである零戦、
当時で、1万機 零戦を作りました、
0さんは ↑の画像見て
零戦五二型と わかるのですか?、
零戦の里帰り飛行当時の他の写真(もっと近くでの撮影写真もありました)を含めて掲載されていたものをネット上から拾って来た写真です。
なので他の写真から確認した限り零戦五二型でありこの写真だけが作り物であるという可能性はまずないと思います。
その度ごとに宣伝もされていますし一連の里帰り飛行をした零戦がアメリカのプレーンズオブフェイム博物館の零戦五二型であることは世界中の零戦好きの人たちの間では良く知られた話ですし。
ということです。
同じ零戦五二型が後の1995年に再度里帰り飛行をした際の写真、茨城県の竜ヶ崎飛行場での模様の写真を一枚にまとめたものを貼ります。
この時、一緒にアメリカのノースアメリカンP51Dムスタングも来日しており一緒の飛行する姿を披露していました。
零戦五二型とP51Dムスタングが同じラインに並び同時にスタートして離陸するところを披露していました。
左端の写真は同時スタート離陸後わずか数秒後の状態です、P51Dムスタングはまだまだ地上滑走中ですが、零戦五二型は既に高く舞い上がっていて両機の高度差は既に30mは優に超えています。
真ん中の写真は上空でP51Dムスタングの後方に着いた零戦五二型の写真。
右端の写真はP51Dムスタングの後方に着き低空飛行で飛んで行く零戦五二型。
零戦はどのアメリカ軍戦闘機に後方に着かれても一周旋回すると敵戦闘機との同時旋回であっても一周し終わる頃には逆に敵戦闘機の後方に着くことが出来、形勢を逆転出来たといいます。
最大速度での競走ではアメリカ軍戦闘機に負けていましたが、零戦はアメリカ軍戦闘機よりも身軽で旋回性能が桁外れだったことを如実に物語っています。
太平洋戦争の後半はアメリカ軍戦闘機が速い最大速度を利用して急接近し撃っては逃げる急接近し撃っては逃げるを繰り返し、まともな空中戦を挑まなくなったため零戦の特技は活かせなくなりました。
太平洋戦争当時の価格で零戦一機の価格は装備品一式含めて14万円から16万円程度だったといいます。(現在の価値に換算すると約2億円程度)
それに対してアメリカ軍のP51Dムスタング一機の価格は装備品一式を含めて27万円程度だったといいますから、もしも零戦一機にP51Dムスタング一機が撃墜された場合は金銭的にはアメリカ側の大損だったことが判ります。
逆にP51Dムスタング一機が零戦一機を撃墜してもそれだけ高い金額をかけて造っているわけですから勝って当たり前ということになります。
一機一機の単位で価格で比較するとそうなるようです。
それでも当時のアメリカ軍戦闘機の中ではP51Dムスタングは価格の安い方だったようです。
具体的な価格は判りませんが、リパブリックP47サンダーボルトの価格の方が高価だったそうです。
0さん、素晴らしい画像ありがとうございます。
↓私の一番大好きな画像です、アメリカ側のカメラマンが、撮影された画像です、これこそ、ビッツア賞、これを撮影されたアメリカ人は、亡くなったかも
我祖国 日本の為に、我が身を犠牲に
雨あられの対空砲火を
くぐり抜け、体当り寸前の零戦、
感激して涙が止まりません、
特攻の写真を見たり特攻にまつわることを思い浮かべると悲しいというか、痛ましいというか、目頭が熱くなって来ますね。
特攻機には零戦以外にもいろいろなものが使われたようです。
ヘルシアさんの貼られたこの写真は零戦ではなく艦上爆撃機「彗星三三型」(水冷式エンジンから空冷式エンジンに積み替えたタイプ)のようですね。
主翼が低翼形式ではなく中翼形式だし、エンジンの下部に幅広い空気取り入れ口があり空中線支柱が風防ガラスの上にマウントされているようですから、主翼の捩り下げもついてなさそうだし。
おそらく彗星ですよ。
愛媛県西条市にはフィリピンで特攻に出撃(初めて組織的に)した関行男大尉を偲んだ神社と資料館がありますよ。
彗星でしたか![]()
こりゃ失礼しました、
主翼の捩り下げがついて いない、
↑
0さん、主翼の捩り下げとは
どういうもの ですか?
教えて下さい、
きんたさん、
フィリピンで特攻に出撃(初めて組織的に)した
関 行男 大尉、
はじめて知りました![]()
ありがとうm(__)mです
愛媛県 いつか行ってみたいです。
10年程前 知覧には行きましたよ、
0さん、零戦が一機 現在の価格
2憶円なら
米軍初期の戦闘機
0さんの言うオチョボグチ、P39エアコブラ
と
グラマンF6Fヘルキャット
はいくらくらいですか?
ヘルシアさんごめんなさい。m(__)m
零戦とP51Dムスタング以外の当時の戦闘機価格は方々探してみましたが判りませんでした。
現代の価格に換算すると希少価値と人気があるほど高値になるとは思います。
たくさん存在するものや人気のない機種は安値になるでしょう。
捩り下げとは主翼端をつまんで前に捩り若干下げた形状の主翼のことで零戦にはこの匠の技のような絶妙な技術が使われていました。
それも含めて零戦という戦闘機は本来大量生産には不向きな戦闘機でした。
参考資料の写真を貼ります。
・雲海上で左にバンクする零戦二二型の新造復元機の一号機です。
左右の主翼が中程から外側へ行くにしたがい若干垂れ下がった造りになっているのが判ると思います。
これが主翼端捩り下げです。
これにより低速度時に起きる翼端失速を防止する狙いがありました。
アメリカ軍は零戦を徹底して研究していましたが、何故だかこの主翼端捩り下げの技術には気が付かず戦後だいぶ経ってからその事実に気付いたらしいです。
捩り下げは低速度時でも墜落し難い特性をもたらしますが、抵抗が増えるため最大速度は上げ難いです。
これもそれから翼面荷重に神経を使っていたことも含めて日本の戦闘機は高速度よりも飛行安定性と小回りを重視していたことが判ります。
諸外国とは違う当時の日本の個性でした。
翼面荷重とは翼の面積1平方mあたり何kgの重量を支えるかという値でこの翼面荷重の値が低い戦闘機ほど空中戦の時に小回りが利き飛行安定性が良いため長い航続距離を得られ易い反面デメリットとしては高速度が出し難くなります。
これらの各性能は表裏一体であり何かを突出させれば何かの性能が低下するというパズルゲームのような関係にあります。
したがって開発を行う国や航空機メーカーによってどの性能項目を第一優先にするかが変わって来るため出来上がった戦闘機の性能や性格がまるで違うものになります。
複葉機の方が単葉機より小回りが利く、これは当たり前のことですが、当時一式戦隼や零戦を開発せよ!と軍から出された性能要求は単葉の翼で複葉機と同等の小回りの良さを造り出せ!と言われたのと同然の無理難題のようなものだったのです。
零戦のような戦闘機を好んで開発していた日本は最大速度よりも機動性と長い航続距離を第一優先にしており、その他の諸外国は概ね最大速度性能を第一優先に考えて戦闘機開発を行っていました。
日本の場合はそういうことだったので軍から航空機メーカーへ翼面荷重の値を何kgにせよ!などという命令が来ることが多かったようです。
一方、諸外国の場合はそのような軍からの強制はほとんどなく自由な開発が認められていたケースがほとんどでした。
どちらが良いかは一長一短ですね。
画像見ましたが、
「主翼端捩り下げ」が
わかりませんが、
何度も何度も戦闘機を見ている、0さんだからこそ
解るんでしょうね、
当時のアメリカ軍も
零戦を解剖しても、主翼端捩り下げ は解らなかった、
↑
納得です![]()
最大速度よりも機動性と長い航続距離を第一優先
それと 零戦の機体は直線的ではなく、微妙にカーブをとっている、
直線と直線の組合せは
量産しやすいみたいですが、
零戦は量産しにくかったでしょうね、
それが1万機 とは![]() 、
、
ヘルシアさんが零戦の主翼端捩り下げについて写真を見ても判らないといわれていたので説明資料写真を作ってみました。
貼りますね。
・アメリカのプレーンズオブフェイム博物館の零戦五二型の飛行中の写真を使いました。
主翼端捩り下げがない主翼の場合はA![]() B間の角度のまま主翼端まで行きます。
B間の角度のまま主翼端まで行きます。
たとえるなら正面から見ると潰れかけたVの字に見えます。
零戦のように主翼端捩り下げが使われている戦闘機の場合はこの写真のようにA![]() B間の角度に比べB
B間の角度に比べB![]() C間の角度は若干下がったようになり、たとえるなら正面から見ると潰れかけたMの字のように見え、カモメの姿のように見えます。
C間の角度は若干下がったようになり、たとえるなら正面から見ると潰れかけたMの字のように見え、カモメの姿のように見えます。
この角度が微妙に緩やかに付けられているため零戦の主翼は正面から見ると直線ではないのでした。
絶妙に捩られた主翼構造だったため実機を手に入れ徹底した調査をしていたにも関わらずアメリカ軍は気が付かなかったということでしょう。
こういう構造を持った零戦の動きに釣られて、よーし俺だってと同じような動きをしてついて行こうとして失速し自ら墜落して行ったアメリカ軍戦闘機パイロットは多数いました。
それもありアクロバット飛行をしている零戦について行こうとしてはならないという通達がアメリカ軍には出されていたわけでした。
零戦にはアメリカ軍戦闘機にはない主翼端捩り下げという技術が使われており翼面荷重も低く造られていた(翼面荷重は零戦二一型で107.89kg/㎡、後期型である零戦五二型でも128.31kg/㎡だった。これに対しグラマンF6Fヘルキャットは184kg/㎡、チャンスボートF4Uコルセアでは187kg/㎡もあった)ためあらゆる低速度域で機動飛行を行ってもほとんど失速は起こりませんでした。
しかし、これは零戦だったから可能だったのですが、日本人パイロットがやれるのなら俺だってやれるに決まっていると決め込み零戦の動きを追いかけて行ったアメリカ軍戦闘機パイロットたちは自ら墓穴を掘り攻撃も受けていないのに勝手に自分で失速を起こし墜落していました。
それはそうでしょうね、アメリカ軍戦闘機は主翼端捩り下げの技術もなく軒並み翼面荷重の高い戦闘機ばかりでしたから日本人パイロットの真似をしようとしても無理な相談でした。
零戦=主翼端捩り下げ技術=匠の技のお国柄
ということもいえそうです。
一枚で二枚ぶんの能力が出せる翼(単葉なのに複葉並の主翼という意味)の賜物でしょう。
0さん、解りましたよ〜![]()
私でも解りやすく
おそれいります、
∧∧← 極端ですが、
これが小回りが効くとは
さすが0さん、
たしか F4Fコルセア
∨∨←ですね
時速400マイルを初めて突破だとか
しかし高速機程、離着陸の性能は劣るようですね、コルセアは零戦との戦いは苦手だったみたいですね、
しかしまいったなぁ
零戦が捩り下げ主翼とはおどろきました
知らんかったです、
太平洋戦争前半戦で日本の零戦がアメリカ軍戦闘機より勝れていた点はもう一つあります。
日本人が造ったものは西洋人の猿真似だという日本人への悪口は昔から良く聞きますよね。
零戦のエンジン、栄エンジンもまたアメリカ人の猿真似だといわれていましたが、実質的にはアメリカのエンジンを参考にしただけの独自開発したものだったため当時欧米諸外国製エンジンには装備されていなかった燃料供給弁(プラスG弁もマイナスG弁も装備していた)が装備されていました。
それにより零戦は空中戦の時に様々な姿勢をとっても燃料供給が途切れることがなく安心して敵機との空中戦に専念することが出来ていました。
一方、そういう装備がなかったアメリカ製エンジンを搭載したアメリカ製戦闘機は逆さまになるなどの急機動を行うと燃料供給が途切れてエンジンが停止するため不自由な動きの空中戦しか出来ず、動きには制約がありました。
世界中で第二次大戦ベストセラー戦闘機といわれたノースアメリカンP51ムスタングでさえ機動制限がありました。
アメリカ製戦闘機で急機動の際に燃料供給が途切れないような装備が付けられるようになったのは太平洋戦争後半あたりからでした。
戦争に勝った国々が戦後言っていること宣伝していることの中には本当のこともありますが、自分の国に都合のいいだけの真っ赤な嘘もたくさんあります。
戦後の平和ボケした日本人にはアメリカの嘘を信じきっている人がかなり多いです。
政治家でもかなり多いです。
嘘と本当は賢い目で見分けて騙されないようにしたいですね。
それからヘルシアさんが貼られていた艦上爆撃機「彗星」ですが、私は彗星には主翼端捩り下げは使われていないといいました。
しかし、彗星では捩り下げは使わず、また別の技術で失速し難い技術を盛り込んでいました。
その技術とは異なる主翼の断面形状の組み合わせによる技術でした。
彗星は旧帝國海軍の航空技術廠が開発した艦上爆撃機で主翼の内翼部分には高速度が出し易い層流翼系断面の翼を使用し、外翼には失速し難い通常の断面翼系の翼を使用してこの二種類の断面翼系を調和させてありました。
これと同じような手法は三菱が零戦の次に開発した局地戦闘機「雷電」にも使われていました。
そのため雷電はスピードが速く突っ込みの利く迎撃専用の戦闘機でありながらも空中戦の機動性も高い戦闘機として連合軍からも高い評価を受けました。
開発当初日本国内では評判の悪かった雷電は私が大好きな戦闘機です。
零戦に比べると太った機体ですが、ただのデブではありませんでした。
アメリカのプレーンズオブフェイム博物館の雷電二一型と零戦五二型をそれぞれ同じアングルから比較した写真を参考資料として貼りますね。
この雷電二一型は飛ぶことは出来ない地上展示機ですが世界で唯一現存する雷電です。
局地戦闘機「雷電」は攻めて来た敵機を迎撃するため専門の戦闘機として開発されたため先ずは高い最大速度を第一に設計要求されました。
しかし、例によって空中戦の機動性第一主義の日本軍は同時に高い機動性も要求したため開発は難航しました。
当時入手出来る小型高出力エンジンがなかったため爆撃機用の大型エンジンを使用したため太った機体になってしまいましたが、強制冷却ファンを内蔵した紡錘型の胴体に層流翼と通常翼をミックスした主翼を組み合わせ、空戦フラップとして機動性を高められるファウラーフラップを装備していました。
強制冷却ファンを装備していたため雷電が飛んで来る時はキーンという独特の金属音がしていたといいます。
太った機体ながらスッキリと纏め上げられたその全容が良く判る写真があったので貼りますね。
アメリカ軍に鹵獲され塗装を落とされアメリカ軍の国籍マークを付けられて飛行テストを受ける雷電二一型です。
アメリカ海軍の艦上戦闘機グラマンF6Fヘルキャットとイギリス製スーパーマーリン・スピットファイア戦闘機も一緒に飛行しています。
こうして眺めると太平洋戦争当時のアメリカ、イギリス、日本、それぞれのお国柄が滲み出て見える写真です。
特に際立って判るのが同じく大きな直径の空冷式エンジンを搭載したために胴体が大型化してもアメリカ人と日本人の戦闘機の造り方ではかなりの違いがあり結果としてこのように纏まり方が歴然と違っていたという事実です。
太った猫グラマンF6Fヘルキャットに比べ三菱の雷電二一型のなんと美しく素晴らしいことかと感じてしまいます。
日本側が戦争当時記録した写真にはないアングルの写真、アメリカ軍が撮ったこの写真がそれを際立たせています。
雷電は胴体がこのように大きかったため零戦のような全周視界の良い水滴型風防ではなくファストバック形式の風防を採用していました。
これが原因で視界が悪いとして日本海軍からは悪い評価を受けていました。
そして日本機離れしたその大きな胴体からくる広々とした操縦席は「雷電の操縦席では宴会が出来る」などと言われ馬鹿にされていました。
なるほど何でも小さく狭く造るのが主流だった当時の日本製戦闘機の中にあっては日本機離れした異質な存在でした。
しかし、アメリカ軍に鹵獲され飛行テストを受けてみるとアメリカ人やイギリス人の評価は悪くなく日本では嫌われていた視界の悪さも全く問題なしと評価され逆にほとんど全ての面で高い評価を受け当時の連合軍が使用していたほとんど全ての戦闘機よりも優秀であるという良い評価を受けました。
スピードも出て、頑丈で、運動性も良く、武装も強力で、使い勝手が良い戦闘機だということだったようです。
雷電はアメリカ軍からはジャックというコードネームで呼ばれていました。
アメリカ軍は敵であった日本軍戦闘機にニックネームであるコードネームを付けて呼んでいました。
(海軍戦闘機)
零戦はゼロやジークやハンプと呼び。
雷電はジャックと呼び。
紫電や紫電改はジョージと呼び。
烈風はサムと呼び。
(陸軍戦闘機)
一式戦「隼」はオスカーと呼び。
二式単座戦「鍾馗」はトージョーと呼び。
三式戦「飛燕」はトニーと呼び。
四式戦「疾風」はフランクと呼び。
という具合に戦闘機には男の名前、爆撃機などにはエミリーやベティーやグレースなどなど女の名前を付けて呼び分けていました。
必死で頑張って戦争をしていた日本人とは対照的に、戦争のさなかにあってもアメリカ人は呼び名で楽しむような余裕を見せていたわけでした。
これもお国柄の違いのなせる業でしょうね。
雷電←たしかに ポッチャリ 機体に厚みありますね
昔の 雷電という お相撲さん、からとった、名前かも ですね
層流翼系断面の翼を使用 ↑↑
また難しい ![]() です
です
零戦に、アメリカの方が乗ったら、座席をうしろに、スライドさせても、かなり操縦しにくいと、なんかの本に書いてありました、ましてや三段腹の大男は、無理ですね、![]() 、グラマンはフロントの前方のガラスは防弾に、なっていた?、 戦闘機のコックピット内 はかなり狭くアメリカでは、パイロットのジャケットは
、グラマンはフロントの前方のガラスは防弾に、なっていた?、 戦闘機のコックピット内 はかなり狭くアメリカでは、パイロットのジャケットは
かなりスリムでピチピチのジャケットを、着ていたようです、
もちろん袖も限界まで
細くしたものを
着ていたようです、
それが 「A-2」と言われるミルスペックのジャケット名で、素材は馬革 です
第二次大戦当時は ナイロン、はまだありません
「A-2」フライトジャケットが有名になったのは
映画「大脱走」で
スティ-ブマックイーン
が着てました、
簡単にいうと翼を飛行機の前方から後方に向けて切った断面の形の違いです。
層流翼系というのは翼の断面の一番厚い部分が真ん中より後方寄りにあり高速飛行に適した翼断面形状として開発されたものです。
翼断面形状に於けるスポーツタイプの翼みたいなものです。
ちゃんと扱えれば素晴らしい結果を出すのですが素人が下手に扱うと危険なことになるみたいな感じです。
最大厚部分がより後方にあるということは真ん中より前の部分は薄い傾向にあり高速飛行に適していたのですが、その反面、高い加工精度で滑らかな翼表面が作り出せないと翼の失速が起こり易くなるという両刃の剣でもありました。
ちゃんと作る実力がないのに安易に層流翼を採用するとちょっとしたことで直ぐに失速して墜落する大変危険な戦闘機になってしまうということでもありました。
技術力に自信がないなら手を出してはいけない翼でした。
日本の零戦搭乗員も
身長が低く 細身のほうが有利でしょうね、
現在の競馬の騎手など
小さい方ばかりですね![]()
私は、日本刀が趣味です![]() 、
、
0さんのコメントの中にある 両刃の剣
刀にまつわる 現在でも使われ 日常用語ですね、
諸刃の剣(刃)モロハノヤイバ
両方に刃がついている刀のことで
一方では大変役に立つが、自分の方にも刃が向いているので、危険が伴い
他方では大きな害をもたらすが
危険のあるもののたとえ ですね、
つい刀の事になると
夢中になる ヘルシアですみません![]()
![]()
![]()
アメリカのノースアメリカンP51Dムスタングも層流翼を採用していました。
当時はまだ弱小の新興航空機メーカーでしかなかったノースアメリカン社がその後の社運を賭けて作り出したムスタングはまだムスタングという名前は付いておらずA36という地上攻撃機でした。
戦闘機としては使い物にならないスピードと搭載量だけが取り柄の粗い航空機でした。
名前はアパッチと名付けられました。
この航空機がサラブレッドの如く生まれ変わったのはエンジンをイギリスのロールスロイス・マーリンエンジンのアメリカでのライセンス生産品パッカード・マーリンエンジンに交換したことが最大の要因でしょう。
他にもラジエーター配置やその形状の表面処理、水滴型風防の採用などいろいろありますが、見違えるようなメジャー戦闘機になったのはP51のD型以降のことでした。
水滴型風防に改造し全周視界が得られたことは良かったのですが、地上滑走時を含め飛行安定性が悪くなり垂直尾翼の前にドーサルフィンを追加装着することで何とか対応しました。
ちなみにP51Dムスタングを作り出したのはアメリカに移住したドイツ人です。
P51Dムスタング誕生の地はアメリカ合衆国ですが設計したのはドイツ人そしてサラブレッドに生まれ変わるためのたくさんのアドバイスと協力をしたのはイギリス人でした。
P51Dムスタングのことを生っ粋のアメリカ的戦闘機だと自負するアメリカ人はたくさん居ますが実は誕生の経緯から何から何までアメリカ以外のドイツやイギリスが大きなウェイトを占めた形で作り出されたのが世界的ベストセラー戦闘機となったP51Dムスタングだったのでした。
同じ第二次大戦時期の他のアメリカ製戦闘機と比較すると妙にアメリカ的ではないでしょう?
豪快に造るアメリカ的戦闘機に対しP51Dムスタングだけ妙に緻密で繊細なのはそういう理由があったからでした。
設計者のエドカー・シュミットはドイツに居た時はドイツの戦闘機メーカーで戦闘機の設計をやっていました。
陸軍のA-2海軍のG-1ですか。
私もフライトジャケットには昔から興味があります。
しかし第二次大戦時期までは専用のフライトジャケットを軍が正式採用して官給品とすることが出来ていたのはアメリカ合衆国だけだったようですね。
さすがは世界一裕福な国の軍隊ですね。
その他の国々は日本もドイツも着ていたのはほとんどが私物として購入したものだったようでやはりアメリカ合衆国の裕福さが断トツで目立ちますね。
ちなみにドイツ軍では戦闘機乗り用の布製のジャケットのことはフリーガーブルゼと呼ぶらしくファイターブラウスという表現らしいです。
ドイツ軍の戦闘機パイロットや戦車クルーが着ていて記録写真にも多く写っている大きな襟のダブルのレザージャケットに憧れて探していたこともありましたが、それらはほとんどが軍正式採用の官給品ではなく個人購入の私物か戦利品だったそうですね。
正式採用官給品ではないため正式に決まった形や名前はないみたいで似たようなものを探すと…ダブルライダースジャケットというキーワードで検索すればその多くが出て来るようです。
耐熱性などを考えると本当は本革が一番良いのですが、値段が高いのと手入れが大変で維持費が高いので足踏み状態→昔の人工皮革は塩化ビニールが主流でしたが最近の人工皮革はポリウレタン製が主流で風合いも上手く本革に近付けてあり通気性も多少良くなっていて雨に濡れても大丈夫で値段も安いのでPUレザー、フェイクレザーなどと呼ばれるこちらの方を買ってみました。
ダブルライダースジャケットというのはデザイン的にもカッコ良くTシャツの上に羽織ってもカッターシャツの上に羽織っても様になり襟を開けて前を閉じてもカッターシャツにネクタイをして上から羽織っても様になりファスナーと大きな襟を全部閉じると意外に風を通さなくもなりデザイン的にも何通りもの着こなしが出来て尚且つ機能的なので気に入っています。
実際にオートバイに乗るのなら転倒時の摩擦に対する耐熱性が必要不可欠ですがオートバイには滅多に乗らないならPUレザージャケットで十分かも知れません。
それに着心地が軽量です。
ダメになったらまた新たに買い替えても良いくらいに値段は安いですし。
例えばこの添付画像のようなものです。
微妙に違うタイプも様々、カラーバリエーションはたくさんあるようです。
画像は、P51ムスタング、初期型ですかね?、
初期型はマリーンエンジンのB型 C型
A-36アパッチのあとカナ?
0さんの言う イギリスの強力なエンジン、マリーンエンジン
そして零戦と同じようなドロップガソリンタンクで航続距離的を延長
としてD型が誕生 ですね
本を読みました![]()
しかし零戦相手の空中戦では 機動性が不十分
とあります、
ダブルのライダースジャケット、
カッコいい
ドイツの軍服
それを知っている人が見たら、振り向くでしょうね、
A-2のフライトジャケットは空軍の将校用で
画像は太平洋戦争前でCBI、中国 ビルマ インド戦線に展開した爆撃飛行隊 または
航空輸送任務 のパッチワークで
不時着した場合
背中の 中国国旗と 中国語 (中国と友好)
というような事が書かれているようです、
画像は アメリカ海軍の
G-1です、素材は羊の革です
これは本にある画像ですが、
1950年代初期の米軍採用で、初期のものは
襟がムートン
湾岸戦争の頃は 襟が
人工毛皮になりました、
ちなみに、私も1着持っています、![]()
オリジナルです
アンティークショップで買いました、
そのA-2の背中に貼られていたものは青天白日マークが付いていますから国旗のマークからアメリカと中華民国(中国国民党政府軍)との間の友好関係を示すとともに中国国内で不時着した際には保護を求めるためのものでした。
現在、中国大陸を占領して住んで居るのは中国共産党が支配する中華人民共和国。
したがって、このアメリカと中国の友好関係を示すパッチワークは現在でいうところの台湾との友好関係を示すものということになりますね。
アメリカ軍の官給品のフライトジャケット、陸軍(後の1947年に一部が分かれてアメリカ空軍を創設)のA-2も海軍のG-1ももう既に昔の官給品となっていますが、今現在の官給品であるCWU-36/PやCWU-45/PよりA-2やG-1の方が良いとして今も尚愛用しているパイロットたちも多いようですね。
特に海軍のG-1の方は特に多いような。
こういう革ジャンからB-15などのコットン製フライトジャケットからL-2やMA-1などのナイロン製フライトジャケット、CWU-36/PやCWU-45/Pのようなアラミド繊維製フライトジャケットまでたくさんありますが、やはり昔ながらの革ジャンが人気があるのも頷ける話ですね。
素材は時代とともに変わって来ましたが、進化したとはいえ、今だに革ジャン人気が衰えない理由は能力的に本革を完全に超える人工的素材を造り出せていないからだと思います。
風合い、防寒性、耐火性、難燃性、耐引き裂き性、耐摩耗性、耐水性、防水性、吸湿発散性、などなど何かの項目は本革の能力を超えていても同時に別の何かの項目は本革には遠く及ばないという現実が装備類が進化した現在でも今だにあるからでしょうね。
いくら新素材が開発されて装備品が進化した現在であっても人類は総合能力で本革を超えるものを今だに造り出せていない証拠でしょうね。
日本の素材メーカー、帝人や旭化成や東レなどは凄い能力があるのでそんなものどうにかなりそうにも感じますが、現実にはそう簡単にはいかないのでしょうね。
蛇足ですが、いろいろな官給品に使用されているいろいろな会社製のファスナーですが、日本のYKK製のものが一番、世界一です。
逆に同じような姿をしていても中国製、韓国製は世界でも最低レベルに粗悪品です。
実際に使い比べてからの感想です。
昔(第二次大戦後しばらくまでの間まで)は牛革、ラム革、馬革、などの本革製フライトジャケットが主流でした。
本革の入手にも限りがあるためコットン製フライトジャケットも開発されました。
その後、軽くて着やすいナイロン製フライトジャケットが開発され広まりました。
しかし、ベトナム戦争などの実戦で敵からの攻撃を受けて火災による引火が原因で死傷者が増えるということが増加したためナイロン製フライトジャケットは危ないという認識が生まれ、別の素材の開発が望まれるようになりました。
そこで努力の末に開発されたのが難燃性を持った化学繊維であるアロマティックポリアミド繊維でした。
アラミド繊維とかノーメックス繊維などと呼ばれています。
たぶんアメリカの有名な会社、世界中で日常の様々な品物や乗り物などに使われている強化プラスチックに必要不可欠な化学繊維ケブラーなどで有名なデュポン社の特許品だったと思います。
アメリカの陸軍海軍空軍で採用されている最新の官給品フライトジャケットはCWU-36/PとCWU-45/Pですが、これがアラミド繊維で作られているフライトジャケットです。
実際に実験して試してみましたが、難燃性はありますが耐火性はありません。
吸湿発散性はあまり良くなく、手入れとしての洗濯はドライクリーニングが必要です。(洗濯代金が高くつく)
フライトジャケット自体の値段は化学繊維製フライトジャケットだとはいっても安くはなく本革製フライトジャケットに匹敵するほどに高いです。
安いものでも最低4〜5万円はします。(円とドルの交換レートにより時期によって多少変動します)
そういう現実を考えると最新官給品フライトジャケットが良いのかどうかは考えものですね。
私の場合はもうだいぶ前の話ですが、CWU-45/Pを購入し、切れっ端を切り取り火で燃やし実験してみたことがあります。
フライトジャケットの特集書籍などで解説されていた通りアラミド繊維それ自体で燃え続けることはありません、直ぐに炭化して炭になるという結果でした。
アラミド繊維製フライトジャケット以前のナイロン製の場合は加熱されると直ぐに火が着きナイロン繊維自体で持続して燃え続け火を消すのは困難になります。
吸湿発散性は悪く、値段は高く、洗濯代も高い、火災から身を守るという意味合いからすると目的は達成されています。
しかし、これ、みんな欲しいと思いますか?
こんなフライトジャケットなら本革製フライトジャケットと同じくらいのお金を払ってまで買いたくはない。
とほとんどの人は思うでしょうね。
開発者だけは特許料で儲かってホクホク顔でしょうが、ユーザー側からすると今の最新フライトジャケットはイマイチであることを否定出来ません。
一万円程度で多く売られているCWU-45/PやCWU-36/Pはデザインが同じというだけでナイロン製の偽物です。
いわゆるレプリカというものです。
ナイロン製のレプリカの中にもタイタンクロス製のものと普通のナイロン製のものが存在します。
タイタンクロス製というのは素材はナイロン繊維で同じなのですが穴が空いた場合に穴の裂け目が広がり難い強い編み立て方法を使っているもので耐引き裂き性が強いフライトジャケットということになります。
コットン製の服(BDUやカーゴパンツなど)でも耐引き裂き性が強い絢目織り(HBT=ヘリンボンツイル)などといわれるものがありますが、そのような類いの違いです。
フライトジャケットを買いたいと思っている人は騙されて低品質なものを高く買わされないように気をつけて下さいね。
妙に安いものは気をつけた方がいい。
良く調べて確認してから買った方がいいです。
アメリカ軍はフライトジャケットなどを使用する作戦地域によって変わる使用環境を温度帯で区分けして運用しており大きく分けると・ヘビーゾーン用(極寒地域用)
・インターメディエートゾーン用(中温度地域用)
・ライトゾーン用(熱帯地域用)
に分けてあります。
代表的なものとしては
ヘビーゾーン用にはN-2やN-3があり。
インターメディエートゾーン用にはA-2やG-1やB-15やMA-1やCWU-45/Pがあり。
ライトゾーン用にはL-2やCWU-36/Pがあり。
という感じです。
今のところアメリカ軍での最新型となっているフライトジャケットCWU-36/PとCWU-45/Pの写真を貼ります。アラミド繊維製の本物はカラーが写真のようなセージグリーン一色しかありません。
0さん、すごいなぁフライトジャケットも、知識豊富ですね、
私は、フライトジャケット勉強しました、
一般に安く売られているレプリカは、殆ど省略されて、造られてますね、
アルファー社が軍に納入 する場合は、テストを重ねて、合格した製品だけ軍に納める事が出来たみたいで、
アルファー社の一般市民用の MA-1は かなり省略されてますね、
下の画像MA-1は
オリジナルに忠実に造ったジャケットで、
日本のメーカーで
リアルマッコイズというメーカーで、
あまりにもよく出来ているので 買いました、
0さんの言う デュポン社のナイロン や
中は、ウールパイルが使われており、袖までとおってます
まぁドテラを着ている
感じで 着たらかなり重たいので、
ジッパーは、今は無き「コンマー社」製 で
フロントのジッパーの横にある、濃い色の片が貼ってあるのは、
酸素ホースをクリップで留める為、
両脇の下にドットボタンも同様で
レプリカながら 5万5千円しました、
私の G-1です↓
襟は天然ムートンで
大型ジッパーはコンマー社、
アメリカのオリジナルで 程度が良かったので
買いました、
このような軍の支給品は 退役した時に 軍に返納しないといけない のですが、これを着たアメリカ人は持ちかえったようで
日本のビンテージアンティークショップで
買いました
私の持っている、
L2-Bです
これも アメリカ軍のオリジナルです
裏地はオレンジ色でリバーシブルになってます
ジッパーは、タロン社
表と裏と2つタロン社のジッパーが付いてます、
貼るの忘れ ![]()
L2-B 0さんの言うライトゾーンカナ?、
これは中にウールパイルが入ってないので、軽いです。
↓↓
もうひとつ 有ります
タンカースジャケットです
米陸軍将校用です
テレビドラマ「コンバット」でヘンリー少尉が毎回着ています、
映画では「タクシードライバー」のロバートデニーロ、で元海兵隊 役
でしたね、
特長は 両ポケットがかなり上についてます、
このジャケットの上からベルトをする為?、
表地はコットンですが、裏地はウールの毛布を張り付けてます、
コットンだからオリジナルは もう殆どがボロボロみたいで
アメリカのスミソニアン博物館も 展示品は数が少ないようです、
私のタンカースジャケットは レプリカですが
リ日本のアルマッコイズが忠実に再現したものを買いました、
↓↓
しかし CWU-45/Pを
一部分を耐火テストするとは、![]()
戦車兵用のタンカースジャケットも戦闘ヘリコプターパイロット用フライトジャケットも現用最新版はノーメックス難燃繊維を使用したCVC コールドウェザージャケットというものが支給され使われています。
変更理由は戦闘機パイロット用のアラミド難燃繊維製フライトジャケットCWU-36/PやCWU-45/Pと同じく戦車や戦闘ヘリコプターに乗って任務を行う兵士たちの間でも敵弾被弾による火災によって死傷するケースが多かったためです。
このジャケットには背中の部分に普段はベルクロテープで閉じてあるホールがあり破壊された戦車や戦闘ヘリコプターの中から乗員を救出する際にそのホールに手をかけて引っ張り出すためのものです。
同じく難燃性繊維を使ったフライトジャケットではありますが、CWU-36/PやCWU-45/Pに比べると手触りはソフトでカラーはカーキ色一色で不人気なことを反映してか値段は安いものだと5千円以下というものもあります。
ニコラス・ケージ主演のアパッチという映画(世界の現用戦闘ヘリコプターの中では最強といわれるアメリカのAH-64アパッチがメインで出て来る映画)で主役のニコラス・ケージらが着ていました。
写真も貼りますね。
追加で添付写真を貼りますね。
・ノーメックス難燃繊維製ヘリコプターパイロット用フライトジャケット
・フレア放出中のマクダネルダグラス(現ボーイング)AH-64アパッチ
・陸上自衛隊のAH-64Dアパッチ・ロングボウ
です。
日本がAH-64Dアパッチ・ロングボウを導入したのは良かったのですが、防衛関係者たちの先見性の無さがたたり価格が高騰し調達数を増やすことも出来なくなり結局調達出来たトータル機数は13機のみに終わりました。
防衛関係者はもっともっと外国の防衛関係企業の動向なども含め世界情勢把握に努めないとダメですね。
日本が導入を決めたAH-64Dアパッチ・ロングボウについて…
当初は63機導入を予定していましたが、日本側がライセンス生産する中味の内容比率を増やすことにこだわりすぎたこと。
導入決定後にアメリカでは軍備削減の煽りでAH-64アパッチの生産ラインを閉じる決定をしたこと。
などなどが重なり陸上自衛隊が導入するAH-64Dアパッチ・ロングボウ1機の調達価格は最終的には216億円(航空自衛隊の現用主力戦闘機F-15Jイーグル2機分に相当する価格)にも高騰したため当然予算の承認が受けられるはずもなく13機で打ち切りてなりました。
世界広しといえども1機216億円もする戦闘ヘリコプターなんて聞いたことがない。
使われるのは日本国民の血税ですが使うことを決める防衛関係者たちが自分の懐は痛くないからなどという感覚でいるとこんなことが起きてしまう。
呆れるばかりです。
0さん、今は夏ですが、
CVC コールドウェザージャケットか、CWU-45/P を是非買いたいです、
本物になるべく近いレプリカ、は売られてますか?
ビンテージショップの
米軍オリジナル は売ってますか?
CWU-36/PもCWU-45/Pも本物は見た目も手触りもゴワゴワしたゴワゴワ感があります。
CVC コールドウェザージャケットの場合は見た目も手触りもソフトで柔らか感があります。
本物かどうか判断する方法は着た時に背中側の首の下部分にあたる部分の位置に貼ってあるタグを見て判断する。
現物の状態と値段を見て判断する。
日本製の服と違い外国製は服全体やポケットなどを裏返すと縫い目よりはみ出た余白の部分がおおざっぱに大きくはみ出している場合がほとんどです。
その切り取っても問題が無いはみ出し部分を切り取りこれを活用して実際に火で燃やしてみて燃え続けずに直ぐに炭化し握り潰すと直ぐに崩れるようなら本物の難燃繊維が使われているフライトジャケットであるといえます。
煙りを出しながら燃え続けるようなら偽物です。
これだけ確認出来れば偽物を買わされることはありません。
難燃繊維製フライトジャケットの場合はユーズド品はあまりお勧め出来ません。
デッドストック品という選択肢がお勧めです。
デッドストック品とは本物の新品だけど使わずに軍やメーカーで保管されていたもののことです。
デッドストック品、ユーズド品どちらも含めて今なら携帯電話で楽天市場を開いてキーワードを入力して検索すれば多数の品物が通信販売で買うことも可能です。
お目当ての品物が出て来るかどうかは入力するキーワード次第です。
探したい品物の名前をどう表現するのか次第でヒットすれば欲しい品物がたくさん表示され、よりたくさんの中から選ぶことが出来ます。
最近はCWU-36/PやCWU-45/Pの本物に巧妙に似せた風合いの精巧なナイロン製という偽物も結構出回っています。
本物か偽物かについてはわざと触れないで安くもない高い値段で平気で売っている場合も増えています。
そういう場合に多いのが精巧な偽物に戦闘機部隊のパッチをたくさん貼り付けた状態でより本物らしく見せかけて売っていることがあります。
値段はぼったくり価格で本物レベル以上に高く設定されていたりします。
しかし本物かどうかの確認の決定打である現物実験確認をすれば偽物は直ぐにバレます。
裏側の生地の切れ端でなくても、その切れ端の端の部分から繊維を一本取り出して燃やして試すだけでも本物と偽物では違いが判ります。
売手が本当のことを教えてくれない場合はその繊維を一本だけもらって試せば嘘は直ぐにバレます。
嘘をついて偽物を売っている場合はその前に白状してしまいますよ。
繊維一本もくれず試すことを頑なに嫌がる場合は偽物ですからそれは買わない方が良いです。
現用アメリカ軍のCWU-45/PやCWU-36/PのCWUというのはクロージング・ウェア・ユニットの頭文字を並べた略称でアメリカ軍内部にはこのようなパンツやシャツ、靴下や手袋、フライトジャケットや極寒地域向けのコートに至るまで様々な被服関係の装備品を全般に全ての開発を一手に行っている組織があり全ては単品開発ではなくシステムとして組み合わせて使い軍務の実行を確実化させることを常に目指しています。
したがってCWU-45/Pにも組み合わせて使うための別の物がいくつか存在しています。
例えば私が知っている限りではCWU-17/PとCWU-18/Pがあります。
CWU-17/PはCWU-45/P用の後付けボア付き防寒フードです。(これを装着することでインターメディエートゾーン用フライトジャケットからヘビーゾーン用フライトジャケットへと変わるという仕様です。)
CWU-17/Pの装着方法やCWU-45/Pへの取付を着脱式にしたい場合はボタンまたはファスナーなどを使い個人個人で工夫するようになっています。
CWU-17/Pはフードの真ん中にファスナーが付いていてこれを開閉することでN-2Bのような着こなしが出来るようにもなっています。
しかし、実際には需要が少なかったことで生産は短期間で終了したらしく、もしも売りに出ているのを発見したらそれは超レアモノということになります。
CWU-18/PはCWU-45/P用のサスペンダー付き防寒トラウザース(中綿入り防寒ズボンのこと)です。
CWU-45/Pという難燃性フライトジャケットの仕様に合わせてこれらは全て難燃繊維製の難燃仕様となっています。
それからGS/FRP2ノーメックス難燃繊維製フライヤーズ・グローブという手袋もあります。
名前は忘れましたが、難燃繊維製の目だし帽(バラクラバ)やパンツやシャツもありました。
CWU-17/PとCWU-18/Pの参考資料写真を貼っておきますね。
GS/FRP2ノーメックス繊維製フライヤーズ・グローブの参考資料写真も貼っておきますね。
こちらはカラーはブラック、セージグリーン、カーキなどバリエーション豊富、しかし、値段は割合高いです。
4〜6千円程度します。
難燃性はありますが、風はスースーなのでオートバイ用には不向きです。
ありがとうm(__)mです、
私は、通信販売ではなく実際に見て、触ってから
近所に ジーパン屋さんやアンティーク衣料の店
を回って、見ます。
お金を少し貯めてから、![]()
昔の話ですが、難燃性が一番高い服とは一体どんなものなのかを自分なりに考えたことがありました。
本革製が一番望ましいということは判ったのですが、それ以外にはないのかといろいろ調べてみた時期もありました。
結果をいうと侍の時代から火消しの人たちがやっていた柔道着のようなコットン製のハッピを着て水を被った濡れた状態が最も耐火性が高いということらしいです。
しかし、そんな使い方で普段から服を着るというのは現実的ではありません。
でも今も消防士の人たちが使っているあれが一番とは意外ですね。
昔の人たちが昔昔からやっていた火に耐える方法です。
零戦の登場員も、
耐火服 は 着てなかったのかなぁ、
もちろんパラシュートなんか 装備されてなかったし
まぁ攻撃専用で 背もたれとヘッドレストは
簡単な薄い鉄板だけカナ?
零戦は1930年代の当時は最先端のテクノロジーを集結した 世界最高の戦闘機、
当時はアジアの国なんて全く認められていなかった、アジアとヨーロッバでは、子供と大人くらいの差があったようで、しかし日本は ヨーロッバやアメリカの飛行機が、敵わない戦闘機を、
突然作り上げた、
「日本人がアメリカの戦闘機に敵う戦闘機をつくれるはずがない」
日本の戦闘機をなめていたようで、
当時の零戦はアメリカの 戦闘機をボコボコに
墜としましたね、
日本軍の戦闘機パイロット用フライトジャケットというのは正式採用品自体がなかったようです。
正式採用品としてあったのは陸軍も海軍も布製のツナギと上下別々にしたセパレートタイプ。
夏用と冬用があり綿混のギャバジン生地(絢織り)、ウール混のギャバジン生地(絢織り)の裏に兎毛皮や犬毛皮を施したものなどがあり、それぞれにいくつかのタイプが存在しました。
それぞれ第○種航空衣袴という名前が付けられていました。
海軍より陸軍の方が早くにセパレートタイプの導入を行い、海軍は冬用では終始ツナギで終わったようです。
当時の日本の陸軍と海軍では同じようなものを指す時でも様々な違いが多かったようです。
例えば、パイロットや偵察要員や爆撃要員を指す呼び名は陸軍では上空勤務者、海軍では搭乗員でした。
パイロットを指す呼び名も陸軍では操縦者、海軍では操縦員といった具合でした。
戦闘機搭載の20mm機関銃でも陸軍では20mm機関砲、海軍では20mm機銃でした。
極極希にアメリカ軍のようなフライトジャケットを着ている日本軍パイロットが当時の写真に写っていることがありますが、それは個人で購入した私物です。
日本軍の場合、士官以上の位になるとそういった装備品は自分で買い揃えることとなっていました。
詳しい詳細までは判りませんが、日本の軍隊内部でも下っ端の兵と士官以上では様々な待遇も違い支給される給料にも天と地ほどの違いがあったのだと思います。
士官学校卒と兵学校卒では戦闘機パイロットとしての腕が上でも昇進のスピードが違い、腕は上でも下手くそパイロットの下に就き部下にならなくてはならない。
という海軍内部の捩曲がった状態を零戦のエースパイロット坂井三郎氏が言っていたのを思い出します。
坂井三郎と言えば
硫黄島、ラバウル、ソロモン諸島のガダルカナルの撃墜王ですね、
まさに大空のサムライ、
元零戦パイロット一人
本田稔 氏 によれば真珠湾のあとに、生き残っても、ガダルカナル戦で戦死したパイロットが、多いそうです
戦死と言うよりも
帰りの燃料切れ、
航路が分からなくなり
スコールや嵐巻き込まれ海で亡くなった方が絶対多いと本に本田稔氏が言ってました、
3時間飛んで戦闘して
また3時間かかって帰る
車で考えたら、7時間乗ると同じようなもので
戦闘機の鉄板の中の狭いところ
恐ろしい 振動と爆音の中しかも高度 300メートルを飛んでいき、
かなりの寒さ、
めちゃくちゃ過酷な中でいつ敵がやって来るかわからないと警戒しながら、
また次の日も 行けと言われる、
本田稔氏は「私は、いつもドライバーを胸ポケットに入れてました」と
帰りに 寝てしまうから
そのドライバーで足を刺すそうで、
それでも寝るから
ドライバーを傷口に、グリグリとねじ込むそうで
それでやっと目がさめるそうです。
実際あと1時間で帰れるかなぁと思っていたら、横にいたはずの戦闘機が高度を下げて、海に墜ちていくのを、何度も見たそうです、
・中国大陸上空を飛ぶ海軍第12航空隊の零戦一一型
・1940年9月13日、中国大陸の重慶上空で初陣を飾った後、漢口基地に戻った零戦搭乗員たちと第12航空隊幹部の記念写真
を貼ります。
中国軍戦闘機部隊は日本軍の戦闘機部隊と空中戦をするのを避けて空中退避を繰り返しており(日本軍戦闘機が居ないと日本軍爆撃機を攻撃して来るくせに日本軍戦闘機が現れると直ぐに逃げていた)零戦部隊は出撃していたものの三回も中国軍戦闘機部隊に逃げられていました。
そして、四回目にしてやっと中国軍戦闘機部隊との会敵を果たしました。
日本軍部隊が攻撃終了後に帰ると見せかけ、長い航続距離能力を持つ零戦部隊は再び重慶上空へ引き返し、ちょうど安心しきって帰って来た中国軍戦闘機部隊を捉えて空中戦が始まりました。
中国軍戦闘機部隊はもちろん国産戦闘機などは持たずソ連製戦闘機ポリカルポフI-15とI-16の混成戦闘機部隊合計27機、対する日本軍戦闘機部隊は零戦一一型合計13機、僅か30分あまりで中国軍戦闘機部隊は全機撃墜され日本軍戦闘機部隊は4機被弾したのみで撃墜されたものはゼロという圧勝でした。
この時の話で、良く当たり難いといわれる20mm機銃弾が敵戦闘機に命中した場合が凄かったといいます。
命中したら敵戦闘機の機体自体が吹き飛んだといわれています。
20mm機銃弾は弾自体が重く発射する戦闘機が空中戦で小回りを利かせ飛行しながら発射するため重力や重力加速度(G)の影響を強く受けるため弾自体が真っ直ぐは飛ばず放物線を描いて飛んで行くため狙った敵戦闘機に命中させるには熟練したコツが必要だったといわれています。
零戦の歴戦のエースパイロットだった坂井三郎氏によると20mm機銃弾を敵戦闘機に命中させる場合は先ず照準器のレチクルから敵戦闘機の姿がはみ出すくらいに接近すること、そして発射の際には絶妙のタイミングで一瞬だけ機首を引き起こすこと、こうしないと普通に射撃していては絶対に命中しない。
そしてモタモタしているうちに装備弾数が少ない20mm機銃弾(初期の型だと1門あたり60発しか装備出来ませんでした。)は直ぐに撃ち尽くしていまう。
といわれていました。
零戦も改良型が造られる度に搭載する機銃の種類も様々何度となく変更されました。
そして実際に零戦を操縦して命をかけて戦うパイロットたちを悩ませたのが搭載する機銃は数種類なのにそれに使う照準器は1種類だけしか搭載されていないということでした。
弾の大きさや重さが違うと飛んで行く弾道特性はまるで別物になります。
どれか一つに射撃精度を合わせるとその他の種類の弾は射撃精度が曖昧になるからでした。
その点は各戦闘機の装備機銃を直進弾道性に優れた12.7mm機銃に統一していたアメリカ軍は賢かったし羨ましかったと坂井三郎氏は語っていました。
ただアメリカ軍の12.7mm機銃弾(ブローニングだったかな?)には炸裂するタイプの弾がなかったのが一つだけ問題点だったという話があります。
ブローニングの12.7mm機銃はいろいろな国で改良版などが造られていたそうで日本でも陸軍と海軍が別々にですが、ブローニングの12.7mm機銃を参考にした機銃を造り使用していました。
弾の大きさは微妙に異なり12.3mmとか13mmとかでした。
しかし、特筆すべき点は世界で唯一日本の弾だけは炸裂弾が造られていた点でした。
初期の頃は暴発や不発などがありましたが、陸海軍共同で改良に取り組み信頼性は向上していました。
この機銃を統一装備すれば良かったのにと惜しまれます。
昭和16年5月26日、黄河中流域の運城(ユンチョン)を出発し、西方約400kmに位置する中国軍根拠地南鄭(ナンチェン)を攻撃するため編隊飛行する海軍第12航空隊の零戦一一型(零式一号艦戦一型)。
胴体に2本青帯の3-141号機は分隊長鈴木実大尉乗機、3-136号機は中仮屋国盛三飛曹乗機
の当時の写真をカラー化したものを貼ります。
私のお気に入りの一枚です。
中国大陸に進出していた帝國海軍第12航空隊、通称12空の零戦の塗装は全体は現用飴色そして胴体の国籍マークのあたりから後ろは明るい灰白色で塗装されていたのが特徴です。
良ーく見ると色の微妙な違いが判ります。
白黒写真でも良ーく見ると色のトーンの違いが判ります。
↑この頃の零戦は最初の量産型であるA6M2a一一型で、その後太平洋戦争初期に空母機動部隊や陸上基地から運用された零戦二一型A6M2bは外見はほとんど同じでしたが、機体全面が明灰白色一色で塗装されていてその点を見れば記録写真も区分けがつきます。
0さん、大変勉強になりました、
百田尚樹(永遠の0の著者) 氏 が いってます、
「なぜ零戦は日本人の魂を揺さぶるのか?、」
「名人の名人による名人の為の戦闘機」
0さんの言う、零戦一一型、〜二ー型番に積んだ当時の20㍉機銃
従来は7、7㍉機銃が主力だったとか、
山本五十六中将が20㍉こだわり、推進、開発させたみたいですね
連合軍は
12、7㍉
調べました![]() ↓↓
↓↓
九九式20㍉一号機銃二型 全長 1331㍉
重量 23キログラム
1秒間に7発
最大射程距離2000メートル、
連合軍の12、7㍉ブローニング機銃
全長1645
重量38、7キログラム
1秒間に1発0程度
最大射程距離1000メートル、
不足を実感したワイルドキャット初期型は4門を6門に増大したとか、
まぁ機銃に関しては双方一長一短ありますが、
零戦は炸裂弾も発射できた、曳光弾(弾道がわかる)も発射、
零戦の搭載武装(機銃)は各型によりさまざま、7.7mm機銃、20mm機銃(銃身の短いタイプと長いタイプ有り、そしてドラム式弾倉とベルト式弾倉が有り)、13mm機銃でした。
参考資料を貼ります。
・昨年再来日し所沢で公開されたアメリカのプレーンズオブフェイム博物館の零戦五二型甲。
・零戦五二型甲と同時に展示された九九式二号二○粍固定機銃と三式十三粍固定機銃、零戦五二型乙と零戦五二型丙に搭載されていました。
・零戦五二型の甲乙丙の三タイプの搭載機銃の違いと装備位置と占有範囲を示した図。
零戦と同時期開発の陸軍の中島一式戦闘機「隼」が装備したホ103(12.7mm機銃)のマ弾(12.7mmの炸裂弾)によって攻撃され撃墜されたアメリカ軍機のパイロットから20mm機関砲弾でやられた20mm機関砲弾でやられたという報告が複数あがっており、それを考えると零戦も武装を13mm機銃に統一装備し海軍でも使われていた13mm(正確には13.2mm)機銃弾の炸裂弾を使えば射撃もしやすく装備弾数もたくさん搭載出来たのにと惜しまれます。
そういう細かな部分だけど戦いに勝つためには実は重要な部分に目を向ける軍の上層部は居なかったのでしょうね。
というか最前線で命を賭けて零戦で戦っていた坂井三郎氏たち零戦パイロットたちが望んでいたのにその要望を叶えてやれなかったのはやはり軍の上層部の責任でしょうね。
そこには零戦パイロットたちの命がかかった実際の実戦での使い勝手よりも、装備でも戦果でも何でもド派手なことだけを望みたがる軍の上層部の体質が見え隠れします。
いくらド派手に見せることが出来ても撃墜されればおしまいだし、戦死すればおしまいだし、負ければおしまいなのに、です。
軍の上層部の人間の頭の中に自分は最前線には行かないから…という考えが頭にあったのならそれは酷い話でしょうね。
海外駐在武官なども務め後に帝國海軍の連合艦隊司令長官になった山本五十六氏が当時としては大口径に分類された20mm機関砲を零戦に装備するようにと強く推したのは世界情勢や海外列強国のことを良く知っていたことによる先見性の高さだと思います。
しかし、命中すれば効果絶大でも実戦使用して判った悪い部分は戦場からの声に耳を傾け改善すべきだったと思います。
改良で改善出来ないなら20mm機銃をやめて13mm機銃を統一装備することも含めて再度考え直すべきだったと思います。
零戦の場合
・7.7mm機銃では1丁あたり700発
・20mm機銃では1丁あたり当初は60発、改良されて100発になり、更に改良されて125発
・13mm機銃では1丁あたり240発
という弾数が搭載出来たといいます。
威力と扱い易さと搭載可能弾数を総合して考えると当時アメリカ軍が12.7mm機銃を統一装備することを選んだのはとても賢い選択だったと思います。
零戦のエースパイロットであった坂井三郎氏が当時のアメリカ軍戦闘機の搭載機銃を羨ましく思っていたのもうなずける話です。
命中すれば威力絶大であっても命中させることが出来なければ重たい重量物でしかない。
直ぐに弾切れになってしまうようでは後は重たい重量物でしかない。
という実際に使用した当事者の言葉にはリアルな説得力がありました。
坂井三郎氏が撃墜した多くの敵戦闘機は20mm機銃によるものではなく、搭載弾数が多く弾道直進性が良く命中させ易い7.7mm機銃によるものだそうです。
しかし、炸裂弾が無い7.7mm機銃弾では命中させ易い反面なかなか敵戦闘機は撃墜出来ないという現実があり、よほど良い場所に命中させ、たくさんの弾を撃ち込まない限り撃墜は難しかったといわれています。
非情なことですが、戦争するということは「やるか、かられるか、です。先にやらないと自分や戦友がやられる。」
致命傷を与え難い7.7mm機銃弾で敵戦闘機を確実に撃墜するためには「それなりの技量が必要だが敵戦闘機の燃料タンクかパイロット自身を狙い撃ちすること」と語っていたのは零戦のエースパイロットだった坂井三郎氏でした。
しかし、敵戦闘機の防弾装備が強化されてくるとそれも難しくなったいったそうです。
なかなか難しいものです。そうなるとやはり炸裂弾を敵戦闘機の弱い部分に命中させることが一番の策だということになるのでしょうかね。
戦争というものは本当に非情なものです。
出来ればしないのが一番です。
0さん、詳しくありがとうm(__)mです、
恥ずかしい質問ですが、![]() 笑わないで下さい
笑わないで下さい
0さんの上記の画像で
7、7㍉のプロペラの、うしろにある 機銃、
発射すると、自分のプロペラを撃ってしまう
事はないのかなぁ?
むっちゃ恥ずかしい、
昔から 疑問に思ってた
もんだから、
(〃▽〃)
ヘルシアさんの疑問への返事です。
世界の戦闘機開発の歴史の中で第一次世界大戦当時からプロペラに装甲を施し防弾化したり、プロペラの動きに機銃の動きを同調させる同調装置を搭載したり、という経緯があったことは私も昔から知っていましたが、おぼろげな記憶でしかなかったので少し調べてみました。
先ずは第一次世界大戦から兵器として使われるようになった飛行機は最初は偵察程度の任務しかありませんでした。
次に敵地上空から爆弾を落とす任務が与えられ、こんな攻撃を受けるようになるとこの手の敵機を撃墜することを主な任務とする戦闘機が必然的に生まれました。
戦闘機が出現以降も出来るだけ確実に敵機を撃墜出来る戦闘機を目指し改良が繰り返されました。
その中の一つに撃ち易く敵機に命中させ易い機銃の装備方法の模索というのがあり、どこの国でも試行錯誤を繰り返していました。
その中で1915年にフランスのモランソルニエが同調装置は着けずプロペラに装甲を施し防弾化して強引に機首から射撃を行うタイプのモランソルニエNを開発し実戦投入しました。
命中させ易い位置からの射撃という新しさからしばらくの間は向かうところ敵なしの状態になりました。
しかし、このモランソルニエNも撃墜される機体が出て来て墜落した機体は敵国ドイツ軍の手に渡ることとなりました。
このモランソルニエNは補助翼(エルロン)を持たず、たわみ翼として造られた主翼を捩って機体の傾きを変える少し変わった戦闘機でした。
結局49機しか生産されませんでしたが、少数機がイギリス軍やロシア軍でも使われました。
参考資料を貼ります。
・装甲化したプロペラを示す図解
・モランソルニエNの機首部分アップ写真
・モランソルニエN側面写真
です。
↓次はプロペラ同調装置について
オランダ人アンソニーフォッカーは撃墜されたフランス軍のモランソルニエNの墜落機体調査に参加する機会を得て弾丸が通過したプロペラの接触面に直ぐに気が付き、それから僅か数日後にはプロペラ同調装置の戦闘機への搭載を思い付いたといわれています。
それからアンソニーフォッカーはプロペラの動きに機銃発射のタイミングを同調させる同調装置(プロペラが機銃前面に来ていない時に合間をぬって機銃弾を発射する同調装置)を搭載したフォッカーEⅢアインデッカーを開発しドイツ軍の前で実演して見せました。
これを見たドイツ軍は一応事実には納得したものの実際の空中戦の際はGがかかるため、そんな時でも確実に作動するのか懐疑的な目で見ていました。
そこでアンソニーフォッカーは彼自身は軍人ではありませんでしたが、自分自身がフォッカーEⅢアインデッカーに乗り込み操縦して出かけ空中戦での確実な作動を実演しフランス軍の偵察機を撃墜して来ました。
これによりフォッカーEⅢアインデッカーはドイツ軍に採用され1915年〜1916年にかけては向かうところ敵なしでした。
参考資料を貼ります。
・プロペラ同調装置を示す概略図
・フォッカーEⅢアインデッカーの写真
これ以降、世界各国が開発する戦闘機には同種のプロペラ同調装置が搭載されるのが当たり前のようになりました。
細かな部分は部品類の発達により変わっているはずですが、基本的には同種のプロペラ同調装置を世界各国が模倣し開発して搭載するということが一般化しました。
日本の戦闘機そして零戦も例に漏れず同種のプロペラ同調装置を搭載していました。
ヘルシアさんの疑問は誰しもが思う素朴な疑問ですから何ら変に思うことは無いですよ。
何の分野でも同じことがいえます。
今は当たり前のように思われる便利な飛行機の存在も一見聞いたらそんな馬鹿な危ないことするの?と思われるような技術開発にも自分たちの命をかけて挑んだ昔の人たちの挑戦がたくさんあったからだということ。
今に比べると昔の場合は次から次へと出て来る個性的な技術の移り変わるスピードが早かったようです。
戦争の期間があったのも技術開発のスピードを早める一大要因でした。
今の技術者の方々も命懸けで開発に取り組んでおられると思います。
複雑な戦闘機の飛行制御をコンピューターに任せるなんて一歩間違えば墜落し死亡しますから、そんな技術開発に携わっている技術者やパイロットの方もいらっしゃると思います。
そんな心血を注いで獲得した技術は大切にしないといけません。
日本の場合は特に韓国人や中国人に盗まれないように気を付けておかないといけませんね。
国防にも関わる大事なことですから。
0さん、さすがです![]()
プロペラ同調装置という機械でしたか![]()
フォッカーEⅢアインデッカー
ものすごいスピードでプロペラが回転する中、
そのプロペラの合間を通って撃つ
プロペラ同調装置
素晴らしい![]()
映画でよくある 第一次大戦時の飛行機で
うしろの座席の方が
爆弾をてにもち、下へ投げている 場面をよく見かけます、
また 車輪の大きい事
零戦はその車輪を格納するようにした とか、
オランダ人アンソニーフォッカー
すごいなぁ![]() 、
、
もし私が、プロペラ同調装置が搭載される 戦闘機 に乗っていい、と
言われても
怖くて 7,7㍉は 撃ちきらないです、
アンソニーフォッカーさん、ごめんなさい
飛行機の分類の中に敵の飛行機を落とすことを専門にする飛行機(最初は攻撃機という呼び名から戦闘機という呼び名に移り変わりました)が生まれて以降、どこの国でもプロペラに邪魔されず胴体前面から心置きなく射撃出来る戦闘機を望んでいました。
その万国共通の願いを反映してプロペラを胴体後部に設けた戦闘機やエンジンのプロペラ軸の中を中空にしてその中から機銃を発射するモーターカノン式液冷エンジンを搭載する戦闘機なども造られ実戦使用されましたが、その全てが成功作になったとはいえませんでした。
ダイムラーベンツ製液冷エンジンのライセンス生産版国産液冷エンジンでさえ手を焼いていた日本ではモーターカノン式液冷エンジンは技術的にも手におえないとして正式採用機には導入出来ませんでした。
日本では太平洋戦争末期に海軍航空技術廠と九州飛行機が局地戦闘機「震電」というエンテ型飛行機(零戦のような在来戦闘機が前後逆になったような鴨型飛行機)を開発しテストをしていました。
この機体はプロペラとエンジンが胴体後部にあり後退角の付いた主翼が後部にあり小さな水平尾翼が機首にあるという現代のジェット戦闘機のような機体配置をした戦闘機でした。
したがって機首に搭載した機銃の発射には邪魔になるようなプロペラの存在自体がなく、しかも30mm機銃を4門も搭載するという強力なものでした。
このような機体だったため武装も強力でスピードも出せるだろうということで期待されていました。
しかし、終戦となったため時間切れでした。
震電は現存しており現在アメリカが戦利品として本国に持ち帰り分解した状態で倉庫に保管しています。
参考資料を貼りますね。
・終戦時進駐して来たアメリカ軍に接収される震電
・現在もアメリカのスミソニアン航空宇宙博物館の倉庫に分解保管されている震電
・十八試局地戦闘機「震電」の平面図
です。
ご覧になって判る通り、ドイツのホルテンといい日本の震電といい、こんな風にアメリカはいろいろな国の当時の最新技術を手に入れアメリカ本国へ持ち帰り、自国の兵器の技術開発に取り込んでいるのが現実でした。
ゲゲゲっ![]()
プロペラが 後ろに![]()
初めて 知りました、
「震電」?
当時の日本は、すごいなぁ、
今、ドイツ対ブラジル
のサッカーやってます、
ドイツの選手で ロングヘアーの方は、いませんね
第二次大戦、ドイツ軍の制服SS親衛隊を着れば
ピッタリの方ばかり![]() 、特にドイツのコーチは
、特にドイツのコーチは
まさに 親衛隊の顔![]()
現在
ブラジル-0
ドイツー4
このような形式の試験機はアメリカ、イギリス、イタリアでもそれぞれに造られてテストされていました。
しかし、いずれの機体も試験機留まりで実用機としては不適合とみなされてそれ以上の発展はありませんでした。
これらの中でも日本の震電が一番実用機には近かったという話もありますが、震電自体は終戦間際のテストということもあり主脚を出したままでの飛行で約300km/h程度のスピードしか出せていません。
搭載していたエンジンは2000馬力級の三菱製ハ43(零戦の後継機「烈風」は中島製の誉(ハ45)エンジンから三菱製ハ43に交換後に海軍の要求性能値を概ね達成しました)
大馬力エンジン特有の癖の影響で右に傾いた状態での飛行だったといいます。
最初の初飛行の際には離陸の時に角度を取りすぎたせいなのか、プロペラの先端が地面を叩いてしまい曲がってしまい失敗に終わりました。
それを補修して対策として二枚の垂直尾翼の下部に小さな車輪を付加して初飛行を行いました。
その様子も含め撮影されていた動画を参考資料として貼りますね。
太平洋戦争当時の日本側撮影のフィルムですから白黒だし見辛いですが他には無い貴重な記録映像です。
サッカーはドイツのキーパーの場合たとえボールをキャッチ出来なくっても弾き返してでもゴールには入れさせないという意気込みが実際の行動に表れていることが多く文字通りの死守であり守護神たる行動だと思います。
日本のチームにもそのような行動が取れるキーパーが欲しいところだと痛感します。
日本の場合は見ていた限りではそこまでの行動は取らずに「あぁ〜入れられたぁ![]() 」で終わっているケースばかりでした。
」で終わっているケースばかりでした。
やはり攻撃力だけを磨いても防御力にも力をさいておかないと安定した強さは確保出来ませんね。
攻撃力一点張りだとたまたま運が良い時だけしか勝つことは出来ませんから。
震電 のムービー
素晴らしい![]()
2分半のロングムービー
見ましたよ、
前から見るとジェット戦闘機に見えますね、大戦末期のドイツのMEジェット戦闘機みたいですね、
上記のムービーで最初のテスト飛行で
浮上する時、後部プロペラが地面に接触し
失敗、
昭和20年に成功で
間に合わなかったみたいですね、
世界各国で似たような軍用機は造られていましたが、中でも日本の震電に近い形態をした軍用機の写真を参考のために貼りますね。
・イタリアのアンブロシーニS.S.4 1939年5月完成
・アメリカのカーチスXP-55アセンダー 1943年7月19日に初飛行
・牽引式双発の爆撃機ながら形態が似ている軍用機としてイギリスのマイルズ・リベルラM.39B 1943年半ばに初飛行
いずれも正式採用されることはなく終わっています。
これら諸外国製の同類機と見比べても日本の震電の完成度の高さが際立って見て取れると思います。
そして、震電の姿をいろいろな角度から見て行くと第二次大戦機というよりは現代ジェット戦闘機に限りなく近い形態をしています。
空冷式ピストンエンジンのプロペラ機ながら動力配置は後部だし、空気取り入れ口はコクピット斜め下後方の両サイドに開口しており、主翼は後退角の付いた層流翼の機体後部配置だし、水平尾翼は機首に配置されているし、垂直尾翼は二枚式だし、どれをとっても戦後数十年たった頃、1960年代に出て来たジェット戦闘機のような形態です。
残念なのは動力がジェットエンジンではなくプロペラ機だったことでしょうか。
震電はこのプロペラ機仕様で30mm機銃(1門あたり160発搭載)4門を機首に集中配置して最大速度750km/h、航続距離1500〜2000kmの性能を目指して開発していたそうです。
もしも、終戦がもっと後になっていたとしても開発は尚難航したことは想像に難くありません。
なにせ今まで世界中の国々が主流派として生産したことのない新ジャンルの軍用機でしたから。
貴重な画像ありがとうございます、
なんか プロペラが後部って ピンときませんね、
そういえば、日本を爆撃した B-29は 主翼に
プロペラでしたね、
元々、これまでの戦闘機の形態とはまるで異なる震電を開発するきっかけとなったのはアメリカ軍の長距離四発重爆撃機ボーイングB29スーパーフォートレス(超空の要塞)の存在でした。
同じく同盟国だったドイツではアメリカ軍の長距離四発重爆撃機B17フライングフォートレス(空の要塞)によるドイツ本土爆撃に苦しめられており、ドイツ軍はメッサーシュミットMe262A(ジェット戦闘機)やMe163B(ロケット戦闘機)を実戦投入して対処していました。
日本は戦争になり連絡手段が極めて限られるようになった同盟国ドイツから天然資源、鉱物資源と引き換えにドイツの優れた科学技術(ジェット戦闘機やロケット戦闘機とそれらのエンジン技術)を輸入しようと試みましたが、輸送にあたった潜水艦が連合軍の攻撃で沈められドイツからの技術情報はほんの一部しか手に入りませんでした。
そのほんの一部の技術情報を元にしてほとんど自前で開発したのが三菱のロケット戦闘機「秋水」でした。
ロケット戦闘機というのはこれまた当時でも現在であっても変わり種中の変わり種的な戦闘機だったため失敗する可能性も考慮されていて、失敗した時のその保険として計画されたのが震電でした。
ということで震電は日本本土に来襲するアメリカ軍のB29を撃墜することを主任務として与えられた戦闘機でした。
したがって20mm機銃弾よりも更に弾が大きく重い30mm機銃を4門も機首に集中配置していたのはメインの敵が戦闘機よりも遥かに大きな標的であるアメリカ軍の四発重爆撃機だったからです。
標的である敵が大きく、急機動などをほとんど行えない四発重爆撃機なら命中させ易く、当たれば一発で撃墜確実だったからでした。
B29の場合は最大速度は530km/h程度と零戦などとあまりかわらない速度でしたが、問題点はそれを発揮していたのが高度10000m以上の高空という点にありました。
ここまで高い空まで来ると空気が薄くなり零戦などの従来機では飛んでいるのがやっとの状態であり530km/hの速度で追いかけるなんて無理な相談だったのでした。
参考資料写真を貼りますね。
・現在も三菱で屋内展示されているロケット戦闘機「秋水」
・秋水のベースとなったドイツのメッサーシュミットMe163Bコメート(英語ならコメット、日本語なら彗星)ロケット戦闘機
です。
ロケット戦闘機「秋水」
初めて知りました、
現在のステルス戦闘機のように、主翼が幅広いですね、主翼の日の丸が 心を熱くします、
ロケット戦闘機と
ジェット戦闘機、とは
どうちがうのですか?
何回も質問して![]()
![]()
![]()
![]() すみません。
すみません。
基本的にピストンエンジンとジェットエンジンの場合は外気から空気を取り込んで燃料と混合させて燃焼させて推進力を得ます。
要はどちらも使うためには常に空気の供給が必要不可欠。
空気の無いところや空気の薄いところでは使い物になりません。
これに対して宇宙開発に使われるロケットエンジンの場合はあらかじめ搭載している燃料を燃焼させて推進力を得るため空気を取り込む必要がなく、大きな推進力が得られます。(高度6000mの高さまで上昇するのに所要時間が5〜6分であれば良い方だといわれた時代にメッサーシュミットMe163Bコメートの場合は高度10000mの高さまで僅か3分で駆け上がる能力を持っていました。水平飛行の最大速度ではアメリカの第二次大戦時最優秀戦闘機といわれたノースアメリカンP51Dムスタングがたとえ最大速度で頑張って飛行していても停まっているように見える1011km/hという超ハイスピードな速度の能力が出せましたが、持続時間が僅か8分と極端に短く、せいぜい100km程度の距離までしか飛べませんでした。)
しかし、あらかじめ搭載している燃料分しか推進力が得られないため持続時間が極端に短くなります。
そして、使用する燃料自体が毒性が強く且つ腐食性が強く(人体をも溶かす大変強い腐食性)爆発反応性が極度に高いため危険性も高くなります。
そういう理由によりロケット推進による戦闘機というのは後にも先にもドイツのメッサーシュミットMe163と日本の三菱の秋水のみで、(ソ連ではB-1というロケット実験機がありました)その後、現在に至るまで他には造られていませんし、たとえ造っても戦闘機として使おうと本気で考える国は一国もありません。
参考資料写真を貼りますね。
・ロケット戦闘機「秋水」のエンジンなしの滑空練習機「秋草」の前方からの写真
・同じく後方からの写真
・現代でも滑空飛行しているメッサーシュミットMe163Bのレプリカでエンジンなしの滑空機です。(赤いコメート=赤い彗星、聞き覚えのある名前でしょ?)
ドイツのメッサーシュミットMe163が搭載していたワルターHWK109-509Aロケットエンジンは燃料として高濃度の過酸化水素水(T液)とヒドラジンとメチルアルコールを主成分とする溶液(C液)を使用していて、この二つを適度に混ぜて爆発的推力を得るものでした。
日本でロケット戦闘機「秋水」用に搭載されたロケットエンジンはこのドイツのものを参考に日本で造られた特呂二号原動機というロケットエンジンでした。
日本ではT液のことを甲液と呼び、C液のことを乙液と呼んでいました。
特呂二号原動機はKR10とも呼ばれていてKRとはくすり(薬、薬液)ロケットの略だったそうです。
いくら強大なパワーを得るためとはいえ高濃度の過酸化水素を作るためには電気分解のために白金を使っており希少金属もあまり持っておらず、これらのロケット用燃料は危険性が高く温度管理なども細心の注意が必要な厄介なものであり太平洋戦争末期の日本にとっては運用する上でかなりハードルが高いものだったと思われます。
ドイツのメッサーシュミットMe163Bコメートは以前お話した無尾翼機、デルタ翼機開発の権威アレキサンダーリピッシュ教授のデザインによるもので無駄を無くし高速を出し易い滑空グライダーからスタートしています。
そのような経緯からMe163Bコメートも秋水も水平尾翼は無くドリーと呼ばれる車輪を装着して飛び立ち離陸直後にドリーは投棄し、帰りの着陸時は幅の狭い橇(そり)を胴体下部から出して草地に着陸するという方法で運用されました。
当時の世界中の戦闘機からすると嘘のような超高速を出せたため強力な戦闘機ではありましたが、急激な上昇が可能だったため搭乗するパイロットたちへの食事はお腹の中でガスが発生し難い食べ物を選んで与えていたそうです。
連合軍もこのMe163Bコメートの手強さにはお手上げ状態だったのですが、しばらく観察し航続時間の短さに気付きMe163Bコメートが配備されている基地の近くは避けて通るようになりました。
Me163Bコメートの側はどうだったかというと危険で特殊な燃料を必要とする関係上、特別な専用施設が必要だったため簡単に基地を移動させることも出来ず、会敵する機会を失ってしまいました。
参考資料として
・ドイツの空軍博物館に展示されているワルターHWK109-509Aロケットエンジン(大阪の弁天町の交通科学博物館にも展示品があります。)
・メッサーシュミットMe163Bコメートの透視図解
・名古屋の三菱社内に屋内展示されている特呂二号原動機(ここにはこの他にも復元されたロケット戦闘機「秋水」と零戦五二型甲も並べて保存展示されています。基本的には非公開ですが、事前に連絡し了解を得れば一般人でも見学可能だそうです。)
を貼りますね。
急遽この内容を…
零戦に代表される日本のものづくり、それらはいろいろな姿に形を変えても現在の日本に継承されていると感じさせられます。
日本のステルス機について久々に特集が放送されました。
先週土曜日2014年7月12日(土曜)夕方から放送された「報道特集 日本のステルス機開発 Japanese stealth fighter ATD X」の動画アドレスを貼りますね。
http://m.youtube.com/watch?v=x6SUttlA_vo&guid=ON
現在我が国で開発が進められているATD-Xというのは先進技術実証試験機で将来的に必要とされるであろう各先進技術を実際の航空機に搭載して確実に使えるものなのかを機能させて実証する試験機です。
プロジェクト名を「ATD-X プロジェクト心神」と呼ばれていたものです。
ステルス機能も含めアメリカのステルス戦闘機F22ラプターが持っているような機能を日本でもエンジンやレーダーも含め全てを自前で開発出来るかを試し、出来得るならアメリカのF22ラプターの性能を上回るものを実現しようと目指すものです。
日本はアメリカから横槍の妨害を受けたF2戦闘機を開発した時点で既にアクティブフェイズドアレイレーダーの技術は確立していますし、小型低出力ながら(しかし出力重量比はラプターのエンジンとほぼ同レベル)エンジンも自前でいけるめどが立って来たようですし、何よりフランスの電波ラボを借りて行ったステルス性能テストの結果は上々でアメリカのF22ラプターなどと同レベルの結果でした。(外国製機の場合はステルス形状の機体にステルス塗装を施して出した結果ですが、日本の場合はステルス形状の機体のみでステルス塗装は施していないにもかかわらず同レベルの結果を出せたことは将来が楽しみです。)
ただ問題は今後のアメリカの動きでしょう。
アメリカが日本にはF22ラプターは売らないと言ったから日本は自前での開発を始めたわけですが、いつまたアメリカが横槍の開発妨害をして来るかは判りません。
アメリカは試験機開発までは何も口出しするつもりはないと言っているようですが、差し詰め猿蟹合戦の猿(アメリカ)に出来上がった技術(熟れた果実)を狙われている蟹(日本)といった感じでしょうか。
電波を反射し難い性質(性能)が同じだった場合は機体サイズがより小さい方がステルス性能的には有利になります。(あまり小さすぎると機内スペースが狭くなるため運用し辛くなりますが)
比較的小型でステルス性能の高い機体にアメリカのF22ラプターのエンジンの1/3の重量で1/3の出力のエンジン、日本は推力偏向パドルも開発出来ていて高機動性もかなりありそうですし。
狙われてそうです。
近い将来アメリカが日本に対してとりそうな態度は三つかも知れません。
徹底して開発の妨害をする、F22ラプターを売ってやるから開発をやめるように迫る、日本の技術がそんなに凄いのなら共同開発をしようと持ち掛け旨味のある部分を日本から独占しようとする、この三つのいずれかでしょう。
F22ラプターに搭載しているレーダーだって日本に強引に同意させた形だけのF2戦闘機共同開発からせしめた日本の技術がベースになっていますから。
いずれにしても自前では何も開発出来ない平和ボケの馬鹿な国でいるよりは、いざとなれば凄いものを自前で開発出来るんだぞといえる日本でいる方がアメリカに対する外交カードとして使えるので賢い選択だと思います。
もしもの際は自前で造ることも出来るし、造らなかったとしても造る実力があることを知らしめることが出来ればアメリカ製を購入する際にも足元を見られずに済みます。(高額な兵器をぼったくりで買わされることはなくなる)
現在の世界のステルス機開発状況を早見出来る参考資料を貼りますね。
上段左からロシアが開発中のT50 PAKFA、中国が開発中のJ20、アメリカが既に実戦配備中のF22Aラプター、アメリカや日本などで現在実質的には主力戦闘機F15イーグル、アメリカや世界各国で現在使用中のベストセラー戦闘機F16、
下段左からヨーロッパ各国での現在の主力戦闘機ユーロファイター・タイフーン、アメリカをメインにして現在国際共同開発中のF35AライトニングⅡ、韓国が構想中のステルス戦闘機KFX G200、同じく韓国が構想中のステルス戦闘機KFX G100、我が国日本が開発中の先進技術実証試験機ATD-X心神です。
早見で世界各国、新旧織り交ぜ比較して機体サイズ、上面、正面の姿を見比べることが出来るものです。
おまけに完成度も判るかも知れませんね。
構想だけは一人前にぶち上げるが実力が伴わず形にすら出来ていない国や外見だけは派手に見せているが技術の未熟さを露呈している国など様々なことが見て取れます。
すごく、勉強になりました。。ATD-X心神
楽しみですね、
アメリカ合衆国は太平洋戦争当時、日本が零戦を含む陸/海/空用の多数の兵器を開発し大量生産して世界中の大半の国々を全て敵に回し戦争をして広大な範囲を自国の占領地域にしていた事実を重くみて、太平洋戦争終戦後は日本の保有兵器のほとんど全部を破壊もしくは没収し、技術資料や工場や生産設備も破壊し尽くして兵器製造会社を解体、優れた技術者たちを公職から追放し公職に就くことを禁止しました。
そして航空機を含む全ての兵器開発、製造を禁止しました。
これは後に朝鮮戦争の勃発に伴い一部禁止は解かれました。
しかし、この間、技術的空白の十年間が日本にとっては他国に比すると大きなハンディとなって現在でもその後遺症は続いています。
これは日本人と真っ向から対峙して太平洋戦争を戦ったアメリカ人がそのままにしておくと日本は将来必ずアメリカを脅かす技術立国になるに違いないと懸念し日本敗戦の機に乗じて技術資料から生産設備や工場や会社に至るまで日本の兵器にかかわるものほぼ全て破壊し尽くして戦後日本の発展の芽を摘み取りまくったのでした。
この事実は当時のアメリカ占領軍が本国へ送った報告資料の中でも「我々は将来アメリカのライバルになるであろう日本の成長の芽を徹底して破壊し尽くした」という意味のことが書き残されていることからも確信犯的な行為でした。
日本にとって時まさに世界中がジェットエンジンを本格的に運用し始める時期の十年間を技術的に空白状態で過ごさなくてはならなかったことはかなりの痛手であったことはいうまでもないことです。
良く話題に上る日米安保というのはアメリカが日本を守ってやる的なことばかりがクローズアップされるのが常ですが、それはほんの一部の限定された話であり、在日アメリカ軍を日本各地に置いているアメリカにとっては日本自体が良からぬことを企てていないか常時監視しておくことの方が重要視されているのが事実、それと並行する形で世界中を監視するために世界各国に進駐させているアメリカ軍のアジア地域の代表みたいな位置付けなのです。
たとえていうならアメリカ軍という戦争専門会社のアジア支店が日本に置かれているようなものであり、日本を守ってやるなどということは二の次三の次の任務なのが本当のところなのです。
アメリカにとって重要なことは日本の監視と世界各国の監視なのでした。
これらのことが本当である証拠として日本が兵器開発や製造を再び行うようになってからも何か素晴らしいものを完成させようとすると必ず出来上がる前にあの手この手で成り立たなくなるように妨害を加えて来ます。
アメリカはこれを長年繰り返しています。
要するにアメリカが認めないものは日本には絶対に造らせないというのがアメリカの一貫したエゴみたいな考え方なのです。
このようなアメリカの身勝手な行為は世界各地で繰り広げられて来ており、被害者にあたる国々の中にはアメリカを憎んでいる国々も少なくありません。
テロ行為を一行に根絶出来ないのはそこらあたりも深く関係するわけで根の深い話でした。
恨みは世界各国で長年募っていますからいくらアメリカが軍事大国でも根絶は不可能でしょう。
参考資料として太平洋戦争当時の日本の最大占領範囲を貼りますね。
地球規模での占領範囲は下半分を見ると判りやすいです。
一時期とはいえども昔、日本はこんなに広大な範囲を自分の領域としていました。
↑これらが如実に指し示すのは「自分の二十倍以上もの強大な国力を持つ国、アメリカ合衆国と世界中の大半の国々を敵に回してでも戦うことを決断した我々現代日本人の祖先の気概の高さ」だと思います。
志し半ばで戦争に負けたとはいえ昔の日本人は物事に対する考え方がビックだったのだなあと感じさせられます。
0さん、
全部読ませていただきました、
私と0さんは、おそらく方向性は、同じですね、
0さん、暑くなりました水分補給を忘れずに、おからだに、十分気をつけて下さい、
敗戦国としての ペナルティ、ジェット戦闘機時代の
10年ほどの技術遅れ
それでも最新ステルス戦闘機、
本当に暑い日が続きますね。
しかし、暑さはまだまだこれからでしょうね。
こまめに水分補給を心がけないといけませんね。
宮崎駿監督の「風立ちぬ」のDVDが少し安くなっていたのをコンビニで見かけ、つい買って見てしまいました。
別にスタジオジブリ作品が嫌いなわけではありませんが、「風立ちぬ」を見終わった後、私が感じたのは宮崎駿監督はなぜこんな映画を作ったのかな?という疑問でした。
これは零戦を設計した堀越二郎氏の半生を綴った実話に基づく映画ですと散々宣伝しておいて堀越二郎氏の恋愛話と結婚した奥さんの話は全く別の人の人生でした。
戦争ものにまつわる話を良く知らないでこの「風立ちぬ」を観た人たちの大半は宮崎駿監督が書いたこのストーリーを史実の本当の話だと信じ込んで零戦の設計者である堀越二郎氏は可哀相に子供にも恵まれず結核の奥さんとは死に別れたんだなあと信じ込んでいるはずです。
実際の堀越二郎氏は子供も居ましたし奥さんと死に別れてもいません。
宮崎駿監督はなぜ一部だけ堀越二郎氏とは違う別の人の人生と入れ換えて映画を作ったのか?その意図するところがさっぱり理解出来ません。
この「風立ちぬ」を観て内容は全て真実なのだと信じた人たちが本当のことを知ったら漏れなく騙されたと感じるでしょうね。
それにしてもなんでこんな変なことをしたんでしょうね。
今や世界中からも注目されるようになったスタジオジブリ作品の中で宮崎駿監督ともあろう人が、自分の立場的なことも良くわきまえていたらこんな嘘を世界中に発信してはいけないと私は思います。
史実とは違う自分の創作も大々的に織り込むのなら史実に基づく実話の映画ですなんて宣伝はすべきではなかったのではないかと思います。
日本を含めた世界中の多く人々がこの嘘を真実だと信じ込んでしまっているはずだと思いますよ。
話は変わりますが、日本を占領した当時のアメリカの軍人の読みは正しかったといえると思います。
なぜなら、その後、戦後復興を成し遂げた日本は平和な時代となり物資も普通に輸入出来るようになると禁止されていない自動車や半導体(IC)の分野でアメリカを追い越し対米経済摩擦が起きるまでに一人勝ち状態になりました。
これこそがアメリカの軍人が恐れていたことそのものだったといっても言い過ぎではないでしょう。
自動車でこんな状態になったのだから航空機分野で同じことが起きたら堪らないと感じているのが今のアメリカ人ですよ。
だから日本の航空機開発への妨害はやめないでしょう。
アメリカは自国の国益が一番大事ですから。
添付画像は上から下へ順番にアメリカ空軍のF16Cファイティングファルコン、F15Cイーグル、F22Aラプター、アメリカ海軍のF18Eスーパーホーネット、F18Cホーネットです。
いずれも現在のアメリカ軍の第一線戦闘機です。
これらの中でもF22Aラプターだけが最初からステルス戦闘機として設計された世界でも最新鋭の戦闘機です。
F22AラプターはこれらF16C、F15C、F18E、F18Cの各戦闘機を相手に何度も何度も模擬空中戦を行い144対1、241対2という嘘のように驚異的な撃墜率を達成したという記録があるようです。
完全に無敵とはいえませんが、限りなく無敵に近い能力を持つ戦闘機であることは間違いないでしょう。
ステルス戦闘機登場以前は世界最強戦闘機といわれたF15Cが4機で1機のF22Aと戦っても1機のF22Aは4機のF15Cを全機撃墜出来るといいます。
もしも日本が購入するなら1機あたり248億円もする(40機購入するだけで1兆円近くもかかる)という世界一超高価な戦闘機ですが、性能も驚異的に高いということのようです。
しかし、日本がアメリカに購入を申し出たものの日本へは売ることは出来ないし、今後とも無理だと断られたそうです。
理由は高度な軍事機密の塊だからだそうです。
現在のところ文字通り世界最強戦闘機といっても過言ではないF22Aラプターは当初750機生産し実戦配備する予定でした。
しかし、世界一高額な戦闘機であることと、何よりもこのようなステルス戦闘機を実戦配備出来ている国がアメリカ以外には存在しないこと、F22Aラプターを使わなければならないような脅威が存在しない現状から750機分の予算要求はアメリカ議会から承認されず、縮小に縮小を重ね結局は試作機も含め合計195機しか生産されませんでした。
皆様御無沙汰しております。『ワルター』なんですが、潜水艦の動力で名前を聞いたような気がします。
きんたさん、こんばんは。
(^O^)/
詳しい詳細は忘れましたが、ドイツでは1930年代初期から高濃度の過酸化水素に別の何かを反応させてエネルギーを得る方法を研究していて大きく分けると低温型のものと高温型のものがあり、第二次大戦期ではこれらの実用化に成功していました。
これを総称してワルター機関と呼ぶようです。
この低温型のワルター機関は潜水艦(新型のUボート)の機関として使われ、高温型のワルター機関はメッサーシュミットMe163コメートのロケットエンジンとして使われました。
低温型と高温型では高濃度の過酸化水素に反応させる相手(化学物質)が違うようです。
低温型ワルター機関もロケットエンジンと同じく取り扱いが厄介で爆発事故を起こす危険性をはらんだものではありましたが、潜水艦の動力としては画期的なものであったのは確かでした。
第二次大戦後の世界の潜水艦はディーゼル/エレクトリック動力か、原子力動力かに二分されましたが、もしも原子力動力が普及しなかったら原子力動力にとって代わっていた可能性もあります。
元々、潜水艦は第一次大戦期も第二次大戦期もディーゼル/エレクトリック機関といって敵の目を逃れては水上航行しながらバッテリーに蓄電し、その蓄電した電力でモーターを駆動して敵の目を逃れて水中を移動するということを繰り返すのが一般的でした。
だからこの方式が圧倒的に主流でした。
ワルター機関というのはディーゼル/エレクトリック機関の補助的機関でしたが、より長く水中を潜航し続けられるという点では近年流行り始めているAIP(非大気依存)型潜水艦のはしり的存在だったといえます。
AIP型潜水艦は大きく分けるとスターリング機関方式と燃料電池方式があります。
いずれもこれまでのディーゼル/エレクトリック機関では水中を潜航し続けられる期間はせいぜい数日が限度だったのに対し二週間程度まで延びています。
現在のドイツ製の潜水艦は燃料電池方式を採用していて、日本製の場合はスターリング機関方式を採用しています。
高度な技術と管理そして放射能汚染問題をなしには有り得ない原子力機関を嫌う国はいずれこれらのAIP型機関の採用という方向へ傾いて行くことは時代の必然だと思われます。
先頃、安倍総理とオーストラリアの会談で防衛装備品の技術供与を含む共同開発の約束が交わされましたが、オーストラリアは日本の優れた通常動力潜水艦(非原子力潜水艦)の技術を導入したいとかねてから望んでいたようです。
浅はかなマスコミが先走って「日本製潜水艦をオーストラリアへ売却か?」などと書き立てたりしていましたが、オーストラリアが欲しているのはあくまでも中味の技術とノウハウだと思います。
オーストラリアも日本同様、中国海軍の近年の不穏な活動には神経を尖らせていますからね。
オーストラリアも日本と同じく大きな海に面しているため運用上都合の良い潜水艦のサイズというものが日本と近いため日本に見習うのは間違いではないと考えているのだと思います。
正面装備しか見ていないのでしょうね![]() ノウハウやマンパワーを組み込まないとどんなに高価な兵器も宝の持ち腐れですね。写真は江田島の海軍兵学校です。今年も見学に行きたいな
ノウハウやマンパワーを組み込まないとどんなに高価な兵器も宝の持ち腐れですね。写真は江田島の海軍兵学校です。今年も見学に行きたいな![]()
オーストラリアは日本より広大な海域を持っており、その海洋権益を維持するためには日頃から広大な海域を哨戒監視しておく必要性があり大型の通常動力潜水艦を必要としています。
そういう立地条件がありながらも自国で独自に潜水艦を開発建造する技術とノウハウを持っていませんでした。
そこでスエーデンと共同で自国用潜水艦を開発しました。
しかしスエーデンでは大型の潜水艦は建造しておらず排水量1000t前後のものしか建造していませんでした。
結局スエーデンの潜水艦をベースにしながら大型の排水量3000tクラスの潜水艦を新規に共同開発することとなり現在使用中のコリンズ級潜水艦(排水量3051/3353t)を六隻建造しました。
しかし、信頼性の悪さと水中ノイズ問題で最悪の結果となりました。
これに懲りたオーストラリアは自分たちが望むちょうど良い仕様の潜水艦を日本が開発建造し運用していることに着目したようです。
そういうことでオーストラリアが日本のそうりゅう級潜水艦(排水量2991/4200tのAIP型潜水艦)に興味津々になっているのが現在なのでした。
オーストラリアは現在のコリンズ級潜水艦六隻を新型の4000t級通常動力潜水艦十二隻に置き換える計画を持っていますからビックプロジェクトといえばビックプロジェクトです。
オーストラリアのコリンズ級潜水艦の画像と日本のそうりゅう級AIP型潜水艦の図解を貼りますね。
オーストラリアにしてみれば元々大型の潜水艦を建造していなかった潜水艦建造国に頼み込んで拡大型潜水艦を開発建造してもそのサイズでの運用実績はないわけですからリスクが大きかったのだと考え、それなら元々大型のサイズで開発建造して問題なく運用出来ている日本の潜水艦があるではないかという考え方かもしれません。
図星といえば図星です。
つい先頃、韓国では水中排水量1800tクラスのAIP型潜水艦の五番艦が完成したらしいです。
第一次大戦、第二次大戦とUボートで有名なドイツが開発した現代版Uボート、214型潜水艦を韓国でライセンス生産した潜水艦です。
現在御本家ドイツ海軍が本命扱いで採用しているUボートは212A型潜水艦で、これはスエーデンや日本が採用しているスターリング機関とは違うAIP型潜水艦です。
AIP型潜水艦ということで同じジャンルの潜水艦ではありますが、ドイツの場合は液体酸素と水素吸蔵合金を使用する燃料電池型の潜水艦です。
そのため開発運用するためには高額な資金と相当高い技術力とノウハウが必要とされます。
信頼性ある確実な運用がなされ的確に制御された反応により動力源が作動している時は素晴らしい動力源なのですが、外圧や水圧などにより燃料のリークなどが生じ反応が制御しきれなくなった場合は簡単に爆発事故を起こしてしまいかねない危険性も同時に同居している機関です。
静粛性が高いという部分ではスターリング機関よりも有利なのですが、リスクも小さくないということです。
韓国がライセンス生産した214型潜水艦は輸出専用の潜水艦で、本命の212A型潜水艦よりも機密レベルを落としてあるといいますが、定期点検や運用をするだけでも開発レベルの高い技術力とノウハウが必要だといわれていますから最近頻繁にニュースに取り上げられる韓国の(陸海空)交通機関や乗り物の大惨事を思い起こすと最新型の潜水艦も近いうちに爆発事故を起こしそうな気がします。
韓国がライセンス生産した(ドイツの輸出専用潜水艦)214型潜水艦の画像を貼りますね。
先日 エノラゲイの最後の搭乗員の方が亡くなられましたね。原爆の正当性を信じて疑ってなかったみたいですが。広島出身としては複雑です![]() 潜水艦の話興味深く読まさせていただきました。日本の場合、伊号潜水艦が有名ですが、愛媛には、呂号潜水艦の記念碑があります。ラバウル近海で戦没したとの事でした。あと松山市沖の興居島には、訓練中に沈んだ伊号潜水艦の鎮魂碑があります。
潜水艦の話興味深く読まさせていただきました。日本の場合、伊号潜水艦が有名ですが、愛媛には、呂号潜水艦の記念碑があります。ラバウル近海で戦没したとの事でした。あと松山市沖の興居島には、訓練中に沈んだ伊号潜水艦の鎮魂碑があります。
アメリカによる日本への原爆投下については「原爆投下により太平洋戦争を早く終わらせ、それ以上の日米双方の戦争犠牲者を出さないようにするのに役立った」とする大義名分がある一方で、時代が進むにつれいろいろ発見公開されて来た事実により、その大義名分の信憑性が大きく揺らいでしまう新事実も出て来ているようですね。
伊號潜水艦は太平洋戦争中に日本海軍で多用された航洋型の潜水艦、当時の潜水艦はどこの国の潜水艦も水上で20ノット前後、水中で8ノット前後のスピードしか出せず、日本海軍ではドンガメと呼ばれていました。
世界各国の海軍では潜水艦の隠密性を活かし軍艦商船問わず攻撃対象としていましたが、日本海軍では基本的には武力を持たない弱い商船は攻撃せず敵の軍艦だけを攻撃対象としていました。
外国人からは馬鹿かと言われそうですが、これが「弱きを助け強きをくじく」という日本人の精神でした。
みなさんも時代劇など見た時に共感を覚えることが多いと思いますが、これが昔からの日本人の精神なのです。
太平洋戦争当時の日本海軍を除く世界各国の海軍では潜水艦の使用方法として軍艦商船を問わず敵国の船ならほぼ全てを攻撃対象としていました。
取り分けドイツ海軍とアメリカ海軍では輸送船や商船を狙い攻撃して沈めていました。
冷酷な言い方をするなら武力をほとんど持たない商船の場合は反撃されて被害を受ける危険性が極端に低い割に商船を沈めれば敵の物資がなくなる分、敵に経済的被害を与えられるため戦略上は非常に賢い戦い方だとして多用されていました。
戦争になればぶっちゃけ礼儀も糞もないのだ!何をどうしても良いから戦争に勝ちさえすれば良い、勝った側の国がその後は何でも好きなように決められるのだから。というのが世界各国の考え方だったのです。
弱いと判っている相手を攻撃して勝っても当たり前であり、これは卑怯者のすること。
強い相手と戦って勝つことこそ素晴らしい勝利であり、正々堂々している者の行いである。
とする考え方、我々日本人にはその考え方が脈々と受け継がれています。
だから時代劇などを見た時に大半の日本人は主人公の行いに共感するのです。
そして韓国や中国の変な行いを報道するニュースを見た時に卑怯だとか非常識だとか感じる日本人が多いのも日本人独特の精神が今も尚脈々と受け継がれているからなのです。
最近は国際的なサッカーの試合で日本は負けたにもかかわらず観客席のゴミ拾いをして帰る日本人観客のことが素晴らしい行いだとして世界各国でもニュース報道されましたが、最近やっと日本人が普通に持っている精神を理解してくれる国々が現れ始めました。
このような行いや精神は世界中に広めていきたいものです。
特に自分勝手が酷すぎる韓国人や中国人には日本人の爪の垢でも煎じて飲ませてやりたいものです。
0さん、きんたさん、
久しぶりに 来ました。
家庭の事で色々
ありましたので、
潜水艦、原爆、読ませていただきました、
ありがとうm(__)mです
アメリカによる 無差別爆撃、原爆しかり
非戦闘員 の 攻撃
軍事拠点、だけの攻撃
であって欲しがったです
映画「男達の大和」
から、沖縄に向かう大和↓↓
皆さん、お早うございます。
欧米列強国に追い付き追い越せの勢いのもとに日本が近代国家へと歩み始めてから日本人が作り出し世界に知らしめた代表作として零戦と並んで有名な存在、戦艦大和関連写真を貼りますね。
・昭和20年4月6日 09:45頃、徳山湾上空高度9100mから米軍偵察機(B29F13)により撮影された沖縄特攻直前も直前の戦艦大和とその護衛艦艇(軽巡洋艦矢矧と駆逐艦群)です。
・同じ偵察写真の中から戦艦大和の様子をピックアップして引き伸ばし拡大した写真です。(艦橋付近の左舷側に居るのは物資運搬用貨物船、三番主砲塔付近の左舷側に居るのは内火艇、そのそばを移動中のものはランチです。)
沖縄特攻直前の無傷な戦艦大和の最後の姿です。
・これらの戦術偵察写真を撮影したB29F13の同型機の写真です。(B29を偵察機に転用したものです。)
当時のアメリカ軍はこれだけの優れた情報収集能力がありながらも大和級戦艦のことを排水量40000t程度の戦艦で主砲も16インチ砲だとしか思っていませんでした。
実際には排水量は70000t前後で主砲は18インチ砲だったのですが、アメリカ人がそれを知ったのは戦後しばらくしてからのことでした。
出来るだけコンパクトな船体に最大限の砲力と防御力を搭載するという設計陳の努力と関わった人たちの機密保持の努力の賜物でしょう。
アメリカ人はまんまと欺かれていたわけです。
実際に戦艦同士での撃ち合いは実現しませんでしたが、日本を過小評価したアメリカ軍が戦艦で対戦していたら(当時のアメリカ海軍の戦艦はどの艦も装甲は大和級より薄く主砲は16インチ砲しか装備していませんでしたから)大損害を被っていたことでしょう。
戦艦同士の撃ち合いの場合、相手に照準を合わせるための気象環境が戦いを大きく左右しますが、遠距離砲戦となった場合は16インチ砲だと最大射程距離が35000m前後、18インチ砲だと最大射程距離が42000mはあるため大和級戦艦は相手をアウトレンジ出来ます。
遠距離で照準出来なくて近距離砲戦になった場合でもアメリカ海軍の戦艦は対16インチ砲弾用の厚さの装甲しかなく、大和級戦艦の場合は対18インチ砲弾用の厚さの装甲を備えているため、その差は歴然だったろうと思われます。
対戦相手が数百機にのぼる敵空母艦載機ではなく敵戦艦だったら戦いの様相はかなり異なったものになっていたでしょう。
徳山の燃料廠での最後の補給時の航空写真ですね?若い兵士官は退艦するように命令されたんですよね!?
亡くなっていかれた方々は若い世代に戦後日本の復興を託されたのだと思います。
当時日本はもうガタガタの状態でしたから復興させるには相当の努力が必要とされる…その担い手までもが死んでしまってはならないという思いから退艦命令が出されたのだと思います。
日本という国は様々な素晴らしいものを作り出せる国だということをアメリカは見抜いていました。
日本と対峙して戦争を戦ううちに理解していったのだと思われます。
そして戦争に勝ち日本を占領したアメリカは近い将来日本が自分たちの脅威にならないように日本の工業基盤を徹底的に破壊し尽くし日本の経済発展を阻害しました。
特に航空関連については特別に徹底的に日本が立ち遅れるように仕向けました。
しかし、皆さんご存知の通り戦後の日本人は早期に戦後復興を成し遂げ高度経済成長を成し遂げました。
様々な分野でアメリカに追い付き、ものによっては追い越す状態にまで成長しました。
それが問題化したのが自動車や半導体分野に代表される日米経済摩擦でした。
太平洋戦争終戦時にアメリカ人が懸念していた事態が現実化したものでした。
もう少しすればいずれ日本は航空関連でも技術的にもアメリカを追い越すでしょう。
現代日本人には当たり前のことのように思われている今現在の日本の経済発展や便利な日常生活は戦後復興を託された日本人の努力の成果であることは忘れてはならないでしょうね。
そして、何よりも私たちがここまで辿り着くことが出来るように昔の日本を命懸けで守ってくれた先人たちに対する感謝を忘れてはならないだろうと思います。
欧米列強国と日本が今のような関係で居られるのもその昔の日本人が懸命に戦ってくれたからこそのことです。
もし戦争もせず戦いもしていなかったら今頃はどこかの国の植民地ですよ。
日本人は戦争をして悪いことばかりしたかのように特定アジアの国々から今も尚言われ続け悪口ばかり言われていますが、もし当時日本人が軍事的に頑張っていなかったら今頃アジアの国々はどうなっていただろうかと考える賢い者はほとんど居ないようです。
特定アジアの国々(韓国、中国)の連中は当時自分たちで自立した国を作る能力すらなかったのにそのまま放置していれば間違いなく欧米列強国の植民地になっていたはずです。
公に発言はしませんが、北朝鮮、韓国、中国以外のアジアの国々はそのことを良く判っているから日本バッシングはしないし、逆に親日なのです。
今の日本人は韓国、中国の捏造歴史観(彼らの作る歴史観は歴史博物館でも何でも突き詰めていくとツジツマの合わないものばかりです。)に洗脳されるのではなく、もっと自分の国の歴史に誇りを持つべきでしょう。
私たち日本人はもう一つ知っておかなければならないことがあります。
アメリカは今は日米同盟などといいながら友好関係をアピールしていますが、敗戦の痛手から日本人が息を吹き返したら世界で唯一原爆を落とされた恨みから核兵器を使ってアメリカに仕返しの報復戦争を仕掛けて来ることを恐れていたため、それをさせないようにするため実に様々な戦後工作をおこなっています。
自分たちが作った憲法を押し付け戦争反対の意識を植え付け、日本人だけに核兵器反対意識を植え付け、自分さえ良ければそれが一番だという個人主義を植え付け、日米安保に代表される外堀で囲い日本人を平和ボケした状態に誘導。
戦後日本を占領管轄していたアメリカは日本占領を終わらせる際にソ連や韓国、中国との領土領海の境目をわざと曖昧にしておいた。
これにより将来これらの国々と領土領海問題で揉め事が起きることは織り込み済みであり、こうして日本は周辺のこれらの国々と仲が悪くなり常に警戒が必要になるためアメリカへの戦争を仕掛ける余裕はなくなる。
という狡猾なことをしていることを知っておかないといけません。
0さんの書き込み
>>670 ←4回ほど読みました、素晴らしい![]()
とくに
「何よりも私たちがここまで辿り着くことが出来るように昔の日本を命懸けで守ってくれた先人たちに対する感謝を忘れてはならないだろうと思います。」
↑↑
この言葉、感激いたしました、
そして 戦艦大和
の本物の写真、ありがとうm(__)mです、
私の画像は映画の作り物からですすみません、
お早うございます。
m(_ _)m
何をおっしゃいますやら、映画「男たちの大和」での映像は今のところ一番精巧に再現された戦艦大和です。
何しろ、実物大の船体前半部分と一番主砲塔、二番主砲塔、一番副砲塔ならびに実物の1/10スケールの戦艦大和という大型モデルを使った超大掛かりなものでしたから。
当時の日本人の技術の粋を結集して造られた大和級戦艦。
当時のアメリカ海軍の戦艦と日本の大和級戦艦が戦艦同士で撃ち合いをして戦っていたらという話の際に必ずといっていいくらい出て来るのがレーダーのことです。
当時のアメリカ軍は既にレーダーによる照準で射撃を行っていたのでレーダーの分野でアメリカより遅れていた日本の大和はアメリカの戦艦に命中弾を与えることが出来ないためアメリカの戦艦から多数の命中弾を浴び続け負けるという話なのですが、確かに当時の日本製レーダーはアメリカのものより信頼性が低かったのは事実、しかし多数の種類のレーダーが造られており、レーダー射撃用としても使える二号二型電探など中には信頼性良好なものもありました。
大和級戦艦はこれを搭載しており実際に使用していましたから一方的にやられるということはなかったろうと考えられます。
アメリカの戦艦は主砲弾が小さいぶんたくさん撃てるでしょうが、大和級戦艦の主砲弾は大きいためアメリカ側は一発でも命中弾を喰らえばその一発が命取りになりかねないものでした。
16インチ対18インチですから、しかも大和級戦艦は対18インチ砲弾用装甲を施していましたから。
二号二型電探の写真と装備位置を示した模型の写真を貼りますね。
ヘルシアさん、0さん今晩はです![]() 尾道の向かいの島にセットがありましたね。かなり巨大でした。10分1のレプリカは大和ミュージアムにあるやつですか?あと『トラ・トラ・トラ』では、長門の巨大なセットがつくられてました。
尾道の向かいの島にセットがありましたね。かなり巨大でした。10分1のレプリカは大和ミュージアムにあるやつですか?あと『トラ・トラ・トラ』では、長門の巨大なセットがつくられてました。
皆さん、お早うございます。
(^O^)/
ごめんなさい。
「トラ、トラ、トラ」のセットについてはよく知りませんが、「男たちの大和」に使われた1/10スケールの戦艦大和は大和ミュージアムにあるものです。
この1/10スケールの戦艦大和と実物大戦艦大和の巨大セットをCG合成などして映画のリアルなシーンを制作したそうです。
実物大戦艦大和の巨大セットを制作した当時は中国が「日本は再び戦艦大和を建造している、日本軍国主義の復活だ!!!」と画像付きで世界に向けてデタラメ報道して日本を悪者にしようと企んだこともありました。
映画のセットのことなので当然中国のいっていることを信じる国なんて一国もありませんでした。
しかし、一党独裁体制で情報統制されている国の人々の中には信じている人も居ることでしょう。
使われていないドックを使用して制作された実物大戦艦大和の巨大セットの写真と造船所で建造された1/10スケールの戦艦大和の写真、大和ミュージアムに展示中の1/10スケールの戦艦大和の写真を貼りますね。
1/10スケールといっても近くに居る人々と比較するといかに巨大なのかが伝わって来ます。
何人か人を乗せて航行出来る規模です。
実物の1/10ですから全長26.3mもあります。
こんばんわ〜![]()
![]() 、
、
実物の 1/10 でも
大きいですね、
レーダー 初めてしりました
出来る事なら、沈んでいる大和を、早く引き揚げてほしいです、
たしか 0さんは
引き揚げるには、莫大な費用が かかる
といってましたね、
引き揚げは かなり深い
かなり 巨大で 重たい
しかし いつの日か
我々 日本の 象徴である 巨大戦艦大和、
引き揚げて ほしいです
大和ミュージアムまた行きたいな![]()
大和ミュージアム行ったことないので私もいつかは行ってみたいです。
鐡の鯨館の実物の潜水艦(海上自衛隊を退役した潜水艦で最新型より数世代前の涙滴型潜水艦)も見てみたいです。
スクリューなど機密が盗まれては困る特定の部分はダミーに付け替えて陸上展示されているらしいですけど見てみたいです。
海上自衛隊の潜水艦は特定のヨーロッパの国々や韓国の潜水艦のような沿岸警備用小型潜水艦とは違って外洋に出て行くための航洋型潜水艦なので陸上展示してあれば大迫力だろうと思います。
当時の日本の技術力を結集して開発建造された大和級戦艦ですが、アメリカ軍は太平洋戦争前からスパイ活動によってその存在を既に知っていました。
1941年には1番艦が完成していたことも知っていましたが、艦名は「紀伊」だと思い込んでいました。
この日本の新型戦艦の存在は早くから知っており詳細なイラストまで描きテクニカル・インテリジェンス・リポート(アメリカ海軍情報部の技術情報報告書)も作成されていました。
武装配置や全体の概要まで実際の大和級戦艦の内容をズバリ言い当てたような正確さだったのですが、肝心かなめの船体が全体的にスリムで主砲の大きさも誤っていました。
戦争末期には大和級戦艦の元乗組員まで捕虜にして尋問し、大和級戦艦の主砲は46cm砲であり9門搭載しているとの情報を得ていたにもかかわらず日本人に46cm砲なんて造れるはずがないとしてアメリカ人は信じませんでした。
そのイラストはどこかで見た記憶がありネット上にあるだろうと思い探してみましたが、結局見付からず、書籍から写真撮りしました。
それを貼りますね。
そしてそれと合わせて次に実際の大和級戦艦初期のイラストも貼っておきますね。
比較して見て下さい。
ここでハッキリ見えて来るのが当時の日本人に対するアメリカ人の見下した偏見です。
自分たちアメリカ人が開発出来なかったものや開発困難だったものは日本人には造れるはずがないという偏見が確実に存在していたのでした。
零戦のことを思い知った時のアメリカ人の反応もこれと全く同様の反応でした。自分たちアメリカ人が作り出せなかった零戦のような戦闘機を日本人が造れるはずがないという偏見でした。
しかし、日本人が大和級戦艦や零戦を作り出せていたのは目の前の現実であり、それを使い命をかけて自分より遥かに強大な国だと判っているはずのアメリカ合衆国に戦いを挑みアメリカ人を苦境に立たせていたことが何よりの真実でした。
こうして「日本人ここにあり」という強烈なイメージをアメリカ人に知らしめたことにより日本人のことを見下し馬鹿にしていたアメリカ人も日本人の何たるかを知りチッポケな島国の住人と過小評価して馬鹿にすることの危うさを実感させられたのだと思います。
そういう経緯(私たちの先人が行った太平洋戦争)により日本人に対するアメリカ人の対し方も大きく変わり今があるのだと思います。
人間にとって戦争というものは良いものではない。
しかし、時と場合によれば自分たちの活路をなくさないために降り懸かる火の粉を振り払うための戦いをしなければならない時もある。
ということを私たちの先人たちは教えてくれているのだと思います。
一番良くない、卑怯で見苦しいのは自分たちは何も出来ず何もせずにいた者が戦争が終わった後になってからアレコレ偉そうにいう行為だと思います。
当時自分たちは何も出来なかったくせにです。
サマール沖海戦時、アメリカ機から撮影された戦艦大和の姿(後方には金剛級戦艦の姿も写っています)をカラー化した写真を貼りますね。
↑で、てつのくじら館の話を出したので日本の場合と比較出来るように外国の場合の実物潜水艦の陸上展示の実例を二つほど貼りますね。
・1996年9月18日に発覚した江陵浸透事件(韓国内に隠密侵入していた北朝鮮工作員を回収に来た北朝鮮軍小型潜水艦が故障して帰れなくなった北朝鮮軍兵士たち26名が韓国内で逃亡を図り韓国軍と戦闘を繰り広げた事件、艦内には日本製の民間品の漁群探知器を利用したソナーなどが搭載してありました)で韓国軍が滷獲した北朝鮮軍のサンオ級潜水艦 排水量256/277t
韓国の江原道江陵市安仁津里海岸に展示中の画像2枚。
・ドイツはキールのラボーでビーチに展示中のU995(第二次大戦のドイツ海軍UボートType ⅦC/41型潜水艦)排水量769/871tの画像を1枚。
日本の広島県は呉にある海上自衛隊呉史料館(てつのくじら館)の画像を貼りますね。
・戦後日本の涙滴型通常動力潜水艦の第二世代となる「ゆうしお級潜水艦」の7番艦にあたる「SS579あきしお」排水量2250/2900t(昭和60年から平成16年まで海上自衛隊で働いた後に退役)の実物がドデーンと鎮座する「てつのくじら館」の画像を2枚。
・移動させる際に「あきしお」を持ち上げた時の画像を1枚。(このサルベージ船は国内最大規模のものらしいです。)
日本の展示がいかに立派なのかが良く判る画像です。
ついでのついでに参考までに現役時代の「あきしお」の画像も2枚貼っておきますね。
・停泊中の「あきしお」
・海中から浮上した際の「あきしお」
です。
ちなみに「あきしお」は艦齢18年で退役後の博物館展示だそうです。
世界に誇れる立派な展示だと思います。
しかも無料です。夏に帰省する時には、寄って帰ります!!
もう四回試したのですが、四回とも「システムエラー。データベースクリエが発生しました。」が表示されるばかりで画像もコメントも反映されませ〜ん。
(T_T)
分割してみましょうか。
てつのくじら館に展示されている「ゆうしお級潜水艦7番艦あきしお」が歴代海上自衛隊潜水艦の中でどの程度の位置付けかというとそれをまとめた添付画像を貼りますね。
この添付画像の内容の通りで、赤い★印を付けてある部分にあたります。
太平洋戦争時にはあまり力点をおかれなかった海上輸送路の安全性確保。
元来、資源をほとんど持っていない日本という国は資源を国外から輸入し知恵と工夫で付加価値を付けた製品を造り販売して利益を得て生きて行くしか生きる道はない貧しい国でした。
基本的には今現在でも根本は同じです。
それを真剣に考えるならば物資輸送のための海上交通路(シーレーン)を防衛することを第一優先にしなければならない。
戦後誕生した海上自衛隊はそれを主眼において対潜哨戒任務強化の訓練をひたすら行って来ました。
初めの頃はアメリカ軍の潜水艦に協力してもらって訓練していましたが、やがて訓練に必要な潜水艦は自前で持とうという声が高まりアメリカと交渉のすえ退役してモスボール保管されていたアメリカ海軍の第二次大戦型潜水艦ガトー級を1隻供与してもらえることになりました。
これが海上自衛隊最初の潜水艦「初代くろしお」でした。
海上自衛隊が使用した外国製潜水艦はこれのみでした。
その後は「初代おやしお」を自力で建造(水上速度よりも水中速度向上を目指した太平洋戦争時の伊號201型潜水艦をベースにして改良を加えた設計でした。)そこから戦後日本の国産潜水艦は発展していきました。
「ゆうしお級」は水中速度重視の国産涙滴型潜水艦の第二世代ということで、そんなに古い設計ではないが最新の設計というわけでもない中位の位置付けになります。
それから国産涙滴型潜水艦は第三世代まで建造され、その後は「二代目おやしお級」という葉巻型潜水艦に移行し現在最新型の「そうりゅう級」(青い★印)が誕生するに至りました。
「二代目おやしお級」の特徴は排水量の増加とそれまで長らく続けて来た涙滴型船体をやめて葉巻型の船体に変わったこと、そして艦首ソナーの他に船体下部両側面にフランクアレイソナーと呼ばれる幅の長いソナーを装備した点です。
これによりこれまでよりもソナーの探知能力と測定能力が遥かに向上しているといわれています。
最新型の「そうりゅう級」はこれに非大気依存型のスターリング機関を搭載し連続潜航時間を延長、艦尾の舵を十字舵からX舵に変更して水中機動性と舵の故障に対する対応能力が向上を図りました。
これら諸々の新技術導入により更に排水量が増加しています。
現在、日本の「そうりゅう級潜水艦」は非大気依存型機関搭載の通常動力潜水艦としては世界でも最大級の大きさの潜水艦となっています。
日本を仮想敵国と公言してはばからず何の分野でも日本に対する対抗意識を剥き出しにしている現在の韓国はドイツの214型潜水艦(日本のそうりゅう級潜水艦とは異なる方式ではあるものの同じく非大気依存型機関を搭載しています。)を導入してこれまた対抗意識を剥き出しにしています。
元が潜水艦技術大国ドイツが設計開発した潜水艦なので侮ることは禁物ですが、大きさ的には日本の半分以下であり船体規模が小さいため沿岸警備用潜水艦の域を出るのは難しい潜水艦です。
しかし韓国海軍が増やし始めたこの新型潜水艦(ドイツにしてみれば輸出専用の潜水艦)も聞こえて来る話は不具合続きな話ばかりです。
何せ韓国でのライセンス生産による建造ですから不具合多発もしかたないのかも知れません。
気の毒なのは韓国人のせいで起きた多発するトラブルのせいで評判を落としかねないドイツの可哀相な立場です。
ドイツも韓国人とはかかわらずにおいた方が良かったのに。
ドイツが開発した非大気依存型機関搭載潜水艦は難しい技術がたくさん詰まっているので開発本家のドイツでは問題なく運用出来ても韓国人にはかなりハードルが高すぎるので、いまに爆発事故を起こしますよ。
韓国がドイツからライセンスを買って自国で建造している214型潜水艦はドイツ海軍が採用している212型潜水艦の準同型艦ではありますが、予め機密レベルを落としてある潜水艦で、しかし動力方式などは同じく液体酸素と水素を反応させて発電し動力を動かす非大気依存型の潜水艦です。
非常に理想的な非大気依存型機関なのですが、酸素と水素を反応させるということは裏返せば、上手く制御して反応させないとそれが出来ない時には簡単に爆発事故を起こすということでもあり船体内に爆弾を抱えて動いているようなものなのです。
高い技術力とノウハウを持ったドイツのような国の場合はあまり問題も起こさないと考えられますが、日頃からよく聴く韓国製の乗り物や交通機関での大惨事を思い起こすと韓国人での運用はかなり危険。
しかもドイツ海軍の場合はその危険性を十分理解しているため液体酸素のタンクは船殻外に外装式に装備しているのに対し韓国が建造している潜水艦は液体酸素のタンクを船殻内に内臓式にして装備しているといいますから一度何か起きれば乗員全員死亡なんてことも簡単に起きそうです。
どうして韓国人というやつは目先の利益にばかり執着して危険性には着目出来ないんでしょうかね。
セウォル号沈没事故も正にそういう点が原因でしたよね。
目先の利益に目が眩み安全性をことごとく無視していた結果の大惨事でした。
おはようございます。
六年ほど使用していた携帯が故障してここしばらくの間使い物にならない状態になっていました。
携帯ショップに修理に出し代替え用携帯の貸し出しを受けて使っている状況です。
・ドイツ海軍が採用した最新型現代版Uボート212型AIP潜水艦と輸出専用214型AIP潜水艦の透視図解
・海上自衛隊が採用した、そうりゅう型AIP潜水艦の透視図解
・2014/7/3午前、韓国の蔚山(ウルサン)東区の現代重工で進水したソン・ウォンイル型AIP潜水艦の5番艦ヨン・ボンギルの写真
ソン・ウォンイル型AIP潜水艦はドイツが開発した輸出専用214型AIP潜水艦であり潜水艦の開発の歴史もほとんどない韓国が日本の海上自衛隊の潜水艦に対抗する目的でドイツから導入を図っている代物です。
ドイツからライセンスを受けて重要部分はドイツから供給を受け韓国内の専用造船所で建造しています。
1隻あたりの価格は韓国より早く同型潜水艦を導入開始していたギリシアよりも3割ほど安くなっています。
これは韓国がドイツの潜水艦メーカーと商売上ライバルになる国の潜水艦メーカーを何度も何度も繰り返し釣り天秤にかけて競わせた結果でした。
自前の技術は持ってもいないのに強気で横着に振る舞う性格は韓国人ならではの態度です。
聞くところによると韓国人というのは優しさや親切と弱さを区別して理解することが出来ないともいわれています。
良くある事例でいえば過去にも現在でも日本は韓国人に対し技術援助と資金援助をしています、これは韓国人への日本人からの優しさや親切なのですが、彼ら韓国人は他人の優しさや親切と弱さを区別して理解することが出来ないため日本人の弱さだと理解します。
まるで他人にたかっている者が持つ心理状態そのものです。
日本は出来るだけ韓国と関わりを持たない方が得策なのですが…
話を韓国の214型潜水艦に戻すと汚い手を使って手に入れたこの潜水艦はトラブルの話しか聞こえて来ません。
実力はないがプライドだけは人一倍高い韓国人に起因するものがほとんどだと思います。
アメリカやドイツから導入した兵器のブラックボックスを無断で開ける行為を何度も何度も繰り返し契約違反を犯すし、身から出た錆でしょうね。
韓国より早く214型潜水艦の導入を開始していたギリシアでの不具合を聞き付けた韓国では2007年に完成した1番艦「孫元一(ソン・ウォンイル)」について同じような不具合がないか取り急ぎ確認作業を行いギリシアと同様の不具合はないことを確認し、ホッと胸を撫で下ろしたという内容が報道されていました。
不具合は見付からなかったはずなのに、その後しばらくして推進軸の不具合からノイズが酷い、船体のボルトが緩んだり折れたりするなどの不具合が伝えられ問題大有りだということに急転換することとなりました。
話の急転換しようがどうにも不思議なお話です。
今では「問題はなかったのにギリシアでの不具合を聞き付けた韓国が似たような不具合があるといいながらギリシアの潜水艦の不具合に無理やりこじつけて契約上分解してはならないと取り決められているブラックボックスを含むすべてをバラバラに分解して元に戻せなくなったのが原因で様々な不具合が起きている。」というのが軍事兵器関係者の見解の常識となっているといいます。
非公式な話ではドイツの進んだ潜水艦技術を盗みたいがゆえに、すべてをバラバラに分解してしまった孫元一を自力では元通りに戻せなくなって困り果てた韓国の関係者は潜水艦技術が優れている日本の防衛関連企業関係者に「どうしよう?助けて欲しい!」と泣き付いたらしいのですが、日本人技術者は「国際的な信用問題に直結する事柄なだけに悪事には荷担出来ない。」といい、けんもほろろに協力を断られたといいます。
今現在でも214型潜水艦建造専用として造られた造船所の中から出ても来れない状態らしくドイツに運び込み修理してもらったという情報もありません。
韓国は自力では問題解決も出来ず完成から何年も経つのにあまりにいつまでも姿を現わさないことから行方不明になり友軍の水上艦艇と衝突し沈没したらしいという話まで出ています。
孫元一級潜水艦のすべての艦についていえる事実としては船体に使われているボルトが緩んだり折れたりする特徴がありますが、これは開発設計者であるドイツが指定した強度のボルトを使わず韓国のメーカーが納品した強度不足の粗悪なボルト(経費を安くあげるためだったと思われます。)を現代(ヒュンダイ)重工が使っていたのが原因でした。
ボルトが緩んだり折れたりした状態でも海水の水圧はかかっていますから圧力の影響で船体各部は歪みまで生じているという最悪な状況。
ドイツのメーカーが設計した通りの性能が出せたなら船体の大きさとそれに伴う様々な許容量を除けば性能的には日本の「そうりゅう型潜水艦」と五分五分という高性能潜水艦だっただけにもったいない。
韓国という国は宝の持ち腐れが尽く尽く多い国です。
猫に小判です。
・近年のドイツのUボートの比較図(214型潜水艦と209型潜水艦改良型の燃料タンク配置の危険さが良く判ると思います。例えば燃料漏れが起きた場合に乗員が化粧品や整髪料などを付けていたら通常の環境より発火が起き易くなり火災事故を簡単に引き起こしてしまうという実例があります。その危険性を熟知しているドイツ海軍が採用した212型潜水艦はもしもの時に備え被害を小さく抑える目的で高濃度の液体酸素タンクは耐圧船殻外部に外付け装備しています。)(黄色いラインが耐圧船殻、深緑の部分が高濃度の液体酸素タンクです。)この比較図解からいえることは潜水艦技術と運用ノウハウが未熟なギリシアや韓国はドイツの優れた潜水艦技術の良い部分だけに目を奪われ危険性の高い構造には気付いていない様子。
・(214型潜水艦)孫元一1番艦が進水した時の写真
を参考資料として貼ります。
尚、従来型の209型潜水艦より流線型になっているため新規開発の新型潜水艦であるかのように見える214型潜水艦も船体を流線型にした点とAIPシステムを搭載した点を除けば実質的には209型潜水艦の改良型です。
だからドイツは214型潜水艦を輸出専用潜水艦として輸出を許可しているわけでした。
0さん、こんちわ〜、
潜水艦、すごい歴史ですね、![]()
ながい間,スレ主不在ですみません![]()
![]()
![]()
しかし
毎日覗いてます、 なかなか専門的な、レスなんで付いていけませんでしたが、
しかし0さんの知識には脱帽です、
素晴らしい![]() です、
です、
先日、骨董品民芸店に
足を運んだら、
面白い物がありました
迷わず購入![]()
「戦陣訓」手帳です
昭和十六年一月廿五日、陸軍省検閲済」
「戦陣訓」
夫れ 戦陣は、大命に基き、皇軍の神随を発揮し、攻むれば必ず取り、戦へば必ず勝ち、邉(アマネ)く皇道を宣布し、敵をして仰いで 御稜威の尊厳を感銘せしむる処なり。……
(以下省略)
陸軍大臣 東條英機
手帳画像
↓↓
こんばんは。(^O^)/
ヘルシアさんそれは貴重なものを手に入れましたね。
(^O^)
日本を特別に良い国だと身贔屓(みびいき)するつもりはないのですが、他の諸外国に比べると特別なしきたりやこだわりの多い国であることは確かですね。
それが良い面も悪い面も表裏一体になっている国という意味では外国人からは理解され難い国でもありますね。
しかし、そういうしきたりやこだわりがあるからこそ日本人の文化はフランス人などからは好かれるのだと思います。
彼らは日本人の文化を大変好意的にまた驚きと感心の目で見てくれています。
ちなみに不甲斐ない周辺アジア諸国を横目に見ながらかつて欧米列強に追い付き追い越せと富国強兵に努力した日本の陸軍はフランスをお手本として成長しました。
海軍はイギリスをお手本として成長しました。
にわか成金みたいなことをしているどこかの国々とは違い日本は数々の失敗と努力を繰り返し長い年月をかけて紆余曲折を繰り返し現在の地位を築き上げました。
皆、御先祖様に感謝しなくてはなりません。
時代が進むにつれ変な奴や変な事件も様々起きて来ている現代の日本ですが、かつて零戦や大和級戦艦や空母や大小様々な潜水艦など優れたものを作り出して来た日本人、その技術やノウハウ、こだわりは現在の日本人にも確実に受け継がれていると思います。
変な奴が出て来たり変な事件を起こしているという点では日本人よりも中国人や韓国人の方が遥かにひどいと思います。
儒教の国が聞いて呆れるだらし無さです。
無法地帯といっても言い過ぎにはならないでしょうね。
日本は明治時代から最初は欧米列強から初期の潜水艦を購入し、すぐにそれを参考にした国産潜水艦を建造し死亡者などを出しながらも試行錯誤を繰り返し潜水艦技術やノウハウの成熟に努めました。
第一次世界大戦後はドイツの当時最新型だったゲルマニア造船所製航洋型Uボートを戦利品として手に入れドイツ人潜水艦技術者らを日本に招き教えを請うなどして更なる技術ノウハウの習得に努めました。
その甲斐あって伊號潜水艦(大洋へ出かけ活動するための比較的大きめな航洋型潜水艦)、呂號潜水艦(近距離作戦用の中型の潜水艦)、波號潜水艦(比較的小型の近海沿岸用潜水艦)などトータル的には太平洋戦争当時合計190隻もの潜水艦を自力で開発→建造→運用していた経験実績があります。
その中には世界各国に類を見ない日本独自の考え方で開発された伊號400型潜水艦という大型潜水艦もありました。
この潜水艦は当時世界最大規模の潜水艦であり、戦後しばらくして誕生した原子力潜水艦を除く通常動力潜水艦の中ではつい2年ほど前まで世界最大規模の通常動力潜水艦でした。
水中排水量は軽巡洋艦(軽巡洋艦といえば軍艦の中では戦艦の次の次に大きな艦艇です。)より若干大きいというビックサイズでした。
このように大型に造った理由は航空魚雷1本もしくは800Kg爆弾1発か250Kg爆弾4発を搭載出来る特殊攻撃機を3機搭載し遠距離まで隠密で進出していきなり敵を急襲しよういう潜水空母的な構想を日本だけが持っていたからでした。
日本本土から出港しても地球上どんなに遠い場所であっても行って帰って来れるだけの長大な航続能力も与えられていました。
最終的には規模が縮小されましたが、当初の計画では1隻あたり特殊攻撃機を3機搭載したこのタイプの潜水艦を18隻建造する予定でした。
仮に全艦が一緒に作戦行動に出れば作戦海域では僅か十数分という短い時間で何もなかった海中から突如として浮上した大型潜水艦群から合計54機もの特殊攻撃機が発進、奇襲攻撃して来るということになります。
他国では考えもしなかった水中機動部隊でした。
日本敗戦により伊號400型潜水艦を接収したアメリカ軍はハワイの真珠湾のドック内で詳しく調査した上でこれらの技術がソ連に知られたらマズイと慌ててハワイ近海で海没処分にしてしまいました。
この伊號400型潜水艦の運用構想と技術に影響を受けたアメリカは大きな水密格納室を設けたグレイバック型という潜水艦を建造し、そこにドイツのV1飛行爆弾(現代の巡航ミサイルの元になります。)から技術を得て作ったレギュラス巡航ミサイルを格納、海中から急浮上したグレイバック型潜水艦から巡航ミサイルを発射するという戦法を考え出しました。
この戦略思想が発展して現代の弾道ミサイル搭載型潜水艦が生まれ今の世の中に至っています。
このような経歴を持ち、戦後も潜水艦の開発技術や運用ノウハウを磨いて努力して来た日本に対しドイツからライセンスを導入して数隻の潜水艦を持っただけで張り合おうなどと考えて吠えまくっている韓国人は勘違いも甚だしいと思います。
それくらい程度の努力でベテランである日本と張り合えるのならどこの国でも苦労はしませんよ。
太平洋戦争当時の日本海軍の魚雷は酸素魚雷と呼ばれて有名ですが、他国の魚雷に比べスピードも速く射程距離などは破格に長く魚雷の航跡もほとんどなく炸薬量も多かったためかなり強力な武器となっていました。
あまりに長い射程距離だったため浜辺にまで到達して乗り上げたものが敵国に回収されたりもしましたが純酸素を使用する魚雷は取り扱いが難しく大変危険だったためどこの国も真似て造ることが出来ませんでした。
この点は何度も何度も爆発事故などを起こしたくさんの尊い人命を失いながらも確立した運用ノウハウと熟練の管理方法に長けた日本人の優れたところでした。
そういう精神や技術や運用ノウハウが継承されてか現在の海上自衛隊の魚雷もかなりの凄いものらしいですよ。
軍事機密のため詳しいことは非公開ですが取り扱いが難しい酸素と水素を動力源としていてスピードも速く射程距離も長いようです。
セールスポイントはかなりの深海まで使用出来て敵艦の下に潜り下から上に向けて命中するため狙われたら回避が困難なようです。
軍備増強著しい中国や韓国ですが、派手な装備の分野ではなく、意外と地味な分野の機雷や魚雷といったものの基本性能の格差によって勝敗は決まるかも知れません。
経験と実績の差です。
0さん 潜水艦すごいですね、
私は、全く潜水艦は知りませんでした![]()
真珠湾攻撃のさい、
深く沈まない魚雷を開発 (真珠湾浅いから)
それぐらいしか![]()
映画
「真夏のオリオン」
「頭上の敵」
ですね、
私の趣味は
日本史(戦国時代)
絵画、焼き物、日本刀
映画は戦争物 時代劇
尊敬する人物
山本五十六
真田幸村
腹がたつのは
北朝鮮の拉致
中国や韓国のコピー販売いずれも大きな犯罪者
最近のニュースで
日本が 戦闘武器それに係わる機械等を、輸出出来るように、法律改正されたようで、
ただし、現在の戦闘国は 輸出禁止、
各国の 展示会があり
日本は、地雷破壊 暗唱レンズ(かなり遠くまで明確に)価格は1千万円位だそうで、
日本の優れた技術に
世界が注目されています
旧帝國海軍の『伊號400潜型潜水艦』と特殊攻撃機『晴嵐』ついて書いておきます。
『伊號400潜型潜水艦』
排水量5223t、水中排水量6560t、全長122m、全幅12m、特殊攻撃機『晴嵐』3機搭載、乗員157名、14cm砲1基、25mm3連装機銃3基、25mm単装機銃1基、魚雷発射管8基、機関出力7700馬力、モーター出力2400馬力、最大速度(水上)19ノット、(水中)6.5ノット、水中航続距離90km、最大水上航続距離14ノットで37500浬、連続行動日数120日と言う当時としては世界最大の潜水艦でした。
伊號400潜型潜水艦の搭載機用格納筒内部は直径3.5m、全長30.5mで専用の愛知 十七試特殊攻撃機『晴嵐』を3機格納可能でした。
搭載機を迅速に発進させる目的の暖機設備(予め温めた油や冷却水を晴嵐に補給しておく為の設備。)も搭載されていました。
艦首部には搭載機(特殊攻撃機『晴嵐』)発進用のカタパルトがあり、この射出用カタパルトは長さ26m、圧搾空気を利用し68ノットの射出速度で搭載機の射出が出来ました。
愛知 十七試特殊攻撃機M6A1『晴嵐』
昭和18年11月に完成、計画では36機以上生産予定でしたが合計26機生産。
全長10.655m、全幅12.262m、全高4.58m、全備重量4250kg、翼面積27.0×2、ダイムラー・ベンツDB601Aのライセンス生産版 愛知『熱田』二一型AE1A離昇出力1200hp/2500rpmの改良版『熱田』三二型AE1P液冷倒立V型12気筒エンジン 1340馬力を搭載、最大速度474km/h.(緊急時にはフロートを投棄すれば最大速度560km/h.零戦とほぼ同程度の最大速度)、航続距離1540km、上昇力:高度5000m迄8分、実用上昇限度9640m、武装は13mm後席旋回機銃×1、爆弾/魚雷(直径45cmの92式改3航空魚雷を使用):800kg×1、若しくは250kg×4、水平爆撃と急降下爆撃も可能。
潜水艦浮上後から所要時間20分で最初の機体が発進可能。
乗員2名と言う仕様/性能の機体でした。
↑この伊號400型潜水艦の航続距離からいうと日本から出港して地球上のあらゆる海域まで進出して作戦を行い再び日本へ帰ることが出来るということであり、原子力推進機関や潜水艦発射型弾道ミサイルなどは開発されておらず世界のどの国にも存在していなかった当時としてはこの日本の伊號400型潜水艦は当時実現し得るすべての技術を現実のものとした戦略兵器の元祖的な存在でした。
それゆえにこの潜水艦を詳しく調査したアメリカはこの技術がソ連に伝わることを恐れ全艦海没処分にしてしまいました。
参考資料として
・伊號400型潜水艦とアメリカのガトー型潜水艦とドイツのUボートC型潜水艦の比較図
・キール近郊のラボーに陸上展示されているUボートC型潜水艦U-995
1941年大西洋で活動中Uボート型潜水艦
・UボートC型潜水艦のカッタウェイ模型
の一枚。
・太平洋戦争終結後ハワイの真珠湾のドックに入れられアメリカによる詳しい調査を受ける伊號400型潜水艦
・現在は復元されてアメリカのスミソニアン博物館に展示されている特殊攻撃機『晴嵐』
・昭和20年9月広島県呉軍港での伊號402潜水艦
の一枚。
・伊號400型潜水艦のカッタウェイ模型
を貼っておきます。
後から気付きました。
↑添付画像にも書かれている通りドイツの潜水艦はUボートVII C型(ローマ数字の七のC型)と書いたのですが、このいつもちゃんねるのシステムでは文字変換から選んだローマ数字の七は正常に反映出来ないようです。
アルファベットでVとIとIを一回一回選んで並べないとしかたがないようです。
不便ですね。
0さん。
いつも画像ありがとうm(__)mです、
詳しく、感謝です
こんばんは。(^O^)/
どう致しましてm(__)m
下手の横好きでやってることですから
要するに被害死亡者なども出しながらも百年近く技術開発と運用実績を積み上げ努力し、このような個性的且つ斬新な潜水艦と搭載特殊攻撃機などまで実用化していた日本に対し対抗心を剥き出しにして敵対的態度をとる韓国人なんぞは身の程知らずというか、百年以上早いわということです。
韓国人のみならず中国人もしかりですが、とかく先進諸外国の技術を盗んで来たり借りて来たりして寄せ集めの自称国産兵器で軍備を拡大し日本を恫喝するような振る舞いが増えて来た昨今。
所詮、借りて来た他人のフンドシでは高い能力は発揮出来ないということです。
インド洋作戦当時の昭和17年4月、発艦して行く搭載艦上機から撮影された空母『赤城』の画像を貼ります。
後部飛行甲板上に待機中なのは残念ながら零戦ではなく愛知飛行機の九九式艦上爆撃機です。
太平洋戦争の前半戦では欧州戦線のドイツ軍のユンカースJu87スツーカと並び強力な兵器として名を馳せていました。
九九式艦上爆撃機もJu87スツーカも艦上機と陸上機という違いはありますが、同様な戦法を使う急降下爆撃機です。
急降下爆撃機とはコンピューターなどなかった時代に熟練したパイロットの飛行技術の腕で爆撃目標の頭上に急降下して爆弾を当てる現代でいうところのピンポイント爆撃を行う軍用機でした。
日本海軍航空隊の場合インド洋作戦当時が一番あぶらがのりきっていてピークの絶頂期だったといわれ80%を超える高確率で爆弾を命中させており狙われた敵艦船はほとんどお陀仏だったようです。
(⌒~⌒)(^-^)q゛グ~
何事も詳しいですね~~…~![]() 感心 感心
感心 感心![]()
706の名無しさん
こんばんは。(^O^)/
どうもありがとうございます。m(__)m
それからコメントは敢えてしないが見て下さっているという方々もたくさん居られるようなので励みになります。
どうもありがとうございます。m(__)m
第二次大戦時の爆撃機は大きく分けると急降下爆撃機で適材適所をピンポイント爆撃する派と大型爆撃機で大量の爆弾を降らせ絨毯爆撃する派の二つに大別されます。
物資を豊富に持っていたアメリカ軍やイギリス軍は大型爆撃機派であり、資源に乏しい日本軍やドイツ軍は急降下爆撃機派でした。
ドイツでは急降下爆撃機の華麗なピンポイント爆撃の素晴らしさに魅了されたヒトラー総統は急降下爆撃に傾倒し過ぎるあまりなんでもかんでも急降下爆撃能力を持たせることを望み、あろうことか大型の四発重爆撃機にまで急降下爆撃能力を持たせるように命令したりして担当の関係者を困惑させました。
こうして見ていくと近代の爆撃機は絨毯爆撃→急降下爆撃→絨毯爆撃→ピンポイント爆撃という具合に時代は繰り返すの言葉通り流行は繰り返されているようです。
ちなみに現代はコンピューターなどを使用した精密ピンポイント爆撃が主流で絨毯爆撃のような無駄な爆弾の使い方はほとんどしません。
昔は急降下爆撃機のパイロットの職人技で行っていたピンポイント爆撃は現在ではコンピューターなどの精密機械が代行しているという風にもいえそうです。
現代の精密ピンポイント爆撃に使われる爆弾と爆撃の作動原理の資料を貼ります。
第二次大戦時や朝鮮戦争、ベトナム戦争の中盤くらいまでの爆撃では自由落下爆弾(いわゆるただ落とすだけの昔ながらの爆弾)しかなかったため爆撃機が落とす爆弾の命中精度は爆撃照準器の精度とそれを扱う爆撃手の経験と腕そして気象条件の良し悪しと運に全面的に依存していました。
そのため爆撃で破壊する目標(敵の基地、飛行場、兵器生産工場などの比較的広大な敷地にある施設)を爆撃して破壊するためにはちゃんと目的を達成し破壊しようとすれば大型の双発爆撃機か四発重爆撃機を数十機から百機程度もの大集団で投入し出撃させないとダメでした。
それだけこの当時の爆弾は命中精度が悪かったということです。
本来狙っていた目標物から数十から数百メートル離れた距離に着弾することは日常茶飯事で命中しなくても至近距離に落ちれば良くやったといわれるレベルでしかありませんでした。
この現実を考えるとヒトラー総統をはじめとする急降下爆撃機擁護派の人たちが急降下爆撃機のピンポイント爆撃能力に魅了されていた気持ちも判らなくもないなと感じます。
現代のスマート(賢い)爆弾に話を戻すと
↑に貼った爆弾は自由落下爆弾の先端に赤外線レーザーを関知するセンサーを取り付け、後部に赤外線レーザー関知センサーの情報に対応して姿勢偏向するための舵を取り付けただけの物なのですが、これがスマート爆弾なのです。
そしてその作動原理ですが、まず爆撃目標に対して赤外線レーザーを照射すると爆撃目標に当たった赤外線レーザーは円錐状のスポットライトのように反射されます。
この円錐状のスポット反射の中に爆弾を投下すれば爆弾は落下していく過程でスポット反射の範囲から外れそうになる度に赤外線レーザー関知センサーが関知してその情報に反応してスポット反射の範囲から外れないように舵取りが繰り返され命中する時には目標のど真ん中に命中するという仕組みになっています。
したがって現在のこの種のスマート爆弾の命中精度は物凄く高く今やどの建物を狙うかではなく、どの窓を狙うかという程に高精度化しています。
ベトナム戦争の後期には実用化されていましたが、あまり取り上げられることはなく大々的に注目されるようになったのは湾岸戦争でアメリカ軍がステルス攻撃機に搭載して少数精鋭で大戦果を挙げて以降です。
たとえ少数機であってもほぼ百発百中に近いスマート爆弾とほとんどレーダーに映らないステルス攻撃機で夜間に奇襲攻撃をするという組み合わせは極めて絶妙で攻撃を受けたイラク軍はなすすべもなかったのでした。
昔だったら大型爆撃機を数十から百機程度の大集団で投入し併せて護衛戦闘機などの各種支援機も随伴させなければならず爆弾の命中精度も悪い上に大集団で出かけるということは敵の攻撃による損害を受けるリスクも大きかったことを考えると非常に効率の悪いものでした。
湾岸戦争初戦のアメリカ軍のような運用を行えば爆弾の無駄も少なく支援機もほとんど不要でほんの数機のみで出かけるためステルス特性とも相俟って損害を受けるリスクもかなり低減されるという相乗効果がもたらされました。
0さん 素晴らしい![]()
よくこれだけ 勉強されましたね![]() 、
、
最近 CSスカパーの
「ヒストリーちゃんねる」
を契約しました、
その中で、無人爆撃機
「ドローン」
を見ました、
テロの首謀者をヒンポイントに爆撃可能ですが、イランの民間人も 犠牲になってるようで
問題になってます、
しかし遠隔操作で
戦争とは ![]()
「ヒストリーちゃんねる」
いいのが たくさんあります
世界の潜水艦の、歴史、
世界の戦車の歴史
大砲の進化
戦闘機のベスト3
第一次大戦
第二次大戦
ロンメルとパットン
ベトナム戦
冷戦時代
ミッドウェー、南雲の誤算、
などなど
そのうち
携帯でムービーとりますね、
ヘルシアさん、こんばんは。(^O^)/
そうですね、無人機もかなり使われはじめていますね。
無人機にもヘルシアさんがいわれてたように日本製の高性能なカメラなどが使われていますよね。
これら無人機には民間用に使用されている人物判別の技術も取り入れられておりいくら変装しても変わらない部分(人それぞれ自分が持つ目と目の位置関係、目と鼻や口や耳との位置関係は固有であり異なります、またそれを変えるのは難しい)によりかなりの精度で判別出来るようです。
イギリス国内の至る所に設置されている防犯カメラはそのような技術を使い変装した犯人が映っていたら自動で警察に通報するといいます。
そういう意味では犯人探しは人間より上手かも知れません。
誤射や誤爆に関しては機械やシステムの不具合もあると思いますが、戦争では頭のおかしくなった兵士も出ます、そんな兵士が操作する兵器は間違ったというわけではなく民間人に対し撃とうと思って撃つ猟奇的行動に出る人間もいます。
また、敵が弱すぎて攻撃すべき敵が居なくなったら手当たり次第になんでもゲーム感覚で撃ちまくる人間も居たりします。
アメリカ軍の場合はイラクでもやりましたが、遠くは太平洋戦争中の日本本土でも日本人民間人に対しても同様の猟奇的行動を行った記録があります。
そういうわけでほとんどの場合は誤射や誤爆ではない可能性が高いです。
アメリカの場合はもうステルス無人機のカタパルト発進と拘束フックでの着陸にも成功していますから空母からステルス無人機が運用される日もそう遠くないでしょう。
その動画を貼ります。
爆撃なども出来るステルス無人機X-47Bです。
現在アメリカは世界の中で唯一、空母用の蒸気式カタパルトを造れる国ですが、長らくズーッとこの状態は続いていて今現在もそうです。
地味な話のようですが、この蒸気式カタパルトを実用化する技術を持てずにいたため長年ソ連/ロシア、中国は空母を実用化することが出来ずにいました。
空母用の蒸気式カタパルトのシステムを考え出し考案したのはイギリスで完成させたのはアメリカでした。
アメリカはイギリスやフランスなど仲良しと思える国々には売るものの敵対している国々には当然のことながら売らず関連技術やノウハウも教えませんでした。
結果、スパイをしたりあの手この手で真似て造ろうと試したものの実用に耐え得るものを造れずソ連/ロシア、中国は長年空母を持つことができませんでした。
結局、これまたイギリスが世界で初めて考案し実用化したスキージャンプ台式飛行甲板を見よう見真似で模倣してソ連/ロシアがまずなんとか空母らしきものを一応実用化して今に至り、そのソ連崩壊で財政難により建造を続けられなくなった2番艦を中国がスクラップ扱いで買い取り入手して改造し今の中国の空母になりました。
そういう経緯があり今のロシアの持つ唯一1隻の空母と中国の持つ唯一1隻の空母は準同型艦となっています。
準同型艦とはいえ能力的には建造した御本家だけあってロシアの空母の方が中国の空母より上です。
しかし、どちらの空母も蒸気式カタパルトを持たずスキージャンプ台式飛行甲板によってなんとか搭載機を飛び立たせることが出来るというレベルのため能力的にはアメリカの空母には遠く及びません。
なぜかといえば蒸気式カタパルトが無いため搭載機を勢い良く打ち出すことが出来ないので、辛うじて飛び立たせるためには搭載する燃料や弾薬を減らし軽くしないとダメだからでした。
仮にいくら搭載機が性能が良くてもフル装備で使うことが出来ないので戦力としてはたいしたものにならないということです。
アメリカは近年、次世代型になる電磁式カタパルトの実用化試験にも成功しています。
その動画を貼りますね。
使用されているのは現在のアメリカ空母の主力艦上戦闘攻撃機F/A-18Eスーパーホーネットです。
日本もリニアモーターカーの技術は世界最先端をいっていますからこういう分野ではトップに踊り出ることが出来そうな気もしますが…
↑添付動画、蒸気出てないのに射出されてるでしょ。
これが電磁式カタパルトです。
電磁式カタパルトの利点は蒸気を使わないため熱気や錆が発生し難いのと、蒸気式カタパルトに比べより細かい力の調整が出来る点などいろいろとあるようです。
カタパルトを使える場合と使えない場合では搭載機の発進に要する時間が段違いに違い、搭載機に載める燃料や弾薬の量にも違いが出るため搭載機1機1機の攻撃力と航続距離に大きな違いが出ます。
第二次大戦前から長い間空母を開発運用して来たアメリカはカタパルトの力に耐えるための搭載機の機体強度の補強の要領も熟知していますが、経験自体を持たないロシアや中国ではアメリカと同じような強力な空母を持とうと思えばまだまだ勉強しなくてはならないことが山積みなのが実状でした。
形だけそれらしく真似たものを持ってもすぐには戦力として活用出来ないのが空母なのです。
それだけ奥が深いということですね。
日本も空母の創成期から第二次大戦期まではアメリカと同じく自分で試行錯誤を繰り返して数十隻に及ぶ空母を開発運用していた実績がありますから、また本格的な空母を誕生させて欲しいものです。
そしてせめて最低限、外国に舐められないような日本になって欲しいです。
カタパルトって
紙飛行機をゴムで引っ張って、飛ばすような感じですね、
以前 映画であった、
ラクピーボウルを戦闘機の替わりに
カタパルトにのせて
高く上がるラクピーボウルを キャッチしたら
10ドル を掛けて、遊んでいました、
単純にイメージとしてはそんな感じです。
太平洋戦争時のカタパルトは当時のプロペラ機だった艦載機(重量2.5t前後〜7t前後)を140km/h前後のスピードに瞬時に加速して打ち出す性能が必要とされていました。
現在のカタパルトはジェット化の波と大型化によりとてつもなく重くなった艦載機(重量30t〜35t前後)を300km/h前後のスピードに瞬時に加速して打ち出す性能が必要とされます。
しかも多い場合は85〜90機にもなる大量の艦載機を次から次へと連続して打ち出す場合も少なくはなく、だからといって故障するようでは使い物にならないため強靭な耐久性というかタフさも同時に要求される代物だけにアメリカ以外の国々は長年実用化出来ずに居るという特異な現象が生まれているわけでした。
中国はかなり昔から諸外国の使用済み空母(第二次大戦期に建造された古いタイプ)をスクラップとして買い取りカタパルトなども分解してその構造や技術を盗もうと画策していますが今のところ全然ダメなようです。
第二次大戦前のこと、本格的な連続使用に耐え得る空母用カタパルトを世界で最初に実用化したのはこれまたイギリスでした。
この頃の空母用カタパルトは油圧式カタパルトでした。
アメリカもイギリスからの油圧式カタパルトの技術提供を受けて空母用に使用していました。
日本は同様のカタパルト開発には失敗したため空母にはカタパルトを装備出来ませんでした。
そのため艦載機の飛行特性(翼面荷重の低い航空機設計)と空母の最大速度(合成風の活用)と飛行甲板を長く使うことで運用していました。
日本は空母以外の艦艇には火薬式カタパルトもしくは圧搾空気式カタパルトを実用化し使用していました。
世界的に後にも先にも日本海軍だけが大量運用(数十隻も建造され普通に使われていました)していた潜水艦搭載型の水上機は圧搾空気式カタパルトで運用されていました。
日本海軍ではカタパルト発進で航空任務に就くと射出を実施する毎に『ポン六手当て』と呼ばれる危険手当てが付き六円支給されました。(今の価値に換算すると二万七千円くらいになります)
しかし、いずれにせよ空母の世界的な誕生時期から継続的に自前で研究開発に取り組み建造して運用し続けていたのはイギリス、アメリカ、日本くらいでその他国々はあまり熱心ではなかったため空母に関する技術力もノウハウも持っていない国々が大多数でした。
太平洋戦争当時のカタパルト発進はうまくいかず海に落ちたり、急加速による衝撃でパイロットや搭乗者が怪我をしたり死亡したりする危険性が高かったため日本海軍では危険手当てであるポン六手当て(カタパルト発進1回につき六円【現在の価値に換算すると二万六千円程度の金額】支給される危険手当て)を支給していました。
だから遊びや飲み食いにお金を使いすぎて文無しになるとポン六に行って来るわってな具合で稼いでいたともいわれます。
ちなみに同じ時代に他の国々ではそういう手当てがあったのかどうかについてはよくわかりません。
紛らわしかったですね。
失礼しました。m(__)m
↑換算価値ですが、だいたい二万六千九百円前後だといいますから二万七千円前後でも二万六千円前後でもどちらも間違いではありません。
太平洋戦争という国家総力戦の戦争中だったので日本はお金のほとんどを戦争兵器に注ぎ込んでいてその他のことについては貧乏暮らしだったようなイメージが私たちにとっては強いですが、当時の日本海軍は意外にも福利厚生も手厚かった印象を受けます。
話を現在の時代に移すと核兵器、特に核弾頭を搭載したミサイルが実用化されて以降は核ミサイルを持っている国が一番強いという世界的な認識により核ミサイルさえ持っていれば好き勝手放題の行動が出来るという間違った認識も生まれているのが現在の世界ということもいえます。
特にその間違った自分勝手な考え方を強く持っている節が良く見え隠れしているのが中華人民共和国と北朝鮮です。
時代が進むにつれて世界的に認識されるようになってきた核が兵器としてだけではなく様々な悪影響をもたらす存在である事実を考えるとその悪影響もさることながら特に最悪の非人道兵器であるという認識が世界中に広まっているため核ミサイル自体は持ってはいても実際問題的には使えない兵器であり、開発製造と維持管理費用だけがかかり続ける国家の金食い虫的お荷物という考え方も生まれてきています。
この考え方は先進国ほど強く、後進国ほど弱く、遅れた国ほど核ミサイル神様になっている現状が浮き彫りになっています。
つまり遅れた国は様々な通常兵器をすべて高性能なものに作り上げる能力がないため核ミサイルだけに力を入れ核ミサイル神様になってしまうという現象です。
昔の零戦のように優れた工業製品を作り出す国家の力という意味では核ミサイルを作り出す技術力にも国によって微妙な技術力、品質力の差があります。
たとえば核弾頭を運ぶミサイルのロケット技術など。
日本は核ミサイルを持ってはいませんが、衛星打ち上げ技術など(衛星打ち上げの成功率は諸外国に比べると破格に成功率が高いのが日本なのです。諸外国の場合は打ち上げに失敗すると報道管制をしき隠してしまう場合が多い。特に共産独裁国家ほどそれが当たり前)を見ていれば一目瞭然です。
イプシロンロケットなどはその最たるもので日本がその気になれば核ミサイル保有は極短期間で出来るでしょう。
また、それを恐れ警戒している国もあります。
イプシロンロケットの打ち上げ成功の際に日本人のほとんどは新型のロケットが打ち上げに成功した、新型ってことだけに注目して話題にしていました。
しかし、外国人は固体燃料ロケットであることとその中でも推力が大きいこと、コスト低減のための量産化にめどをつけたこと、ここに注目し将来兵器へと転用出来る可能性について注目していたのです。
兵器の運搬手段としては液体燃料ロケットよりも固体燃料ロケットのほうが望ましく、それでいてより大きな重量物を運搬出来る推力があると更に適しているということなのです。
しかし、固体燃料のロケットを制御する技術は簡単には達成出来ない難しいものなのでした。
簡単にいえば液体燃料ロケットでしか打ち上げを出来ない国はそこまでの技術力しか持っていない国といういい方も出来るわけでした。
たとえ衛星打ち上げを成功したと喜んでいてもその程度の国ということ。
固体燃料ロケットがなぜ兵器用に適しているのかというと消費期限的なものはあるにしても液体燃料よりは遥かに長く、保有していて使いたい時に即使用が出来るという使い勝手の良さと液体燃料ほどの普段から手間暇が必要ない点、メンテナンス性の良さと有事即応性の高さがあるからでした。
第二次大戦中のドイツのロケット戦闘機の話をした際にも話しましたが、液体燃料ロケットの場合は爆発的推力は生まれますが、その液体燃料は有毒性、腐食性、発火性、爆発性がともに強く、ということは発火性と腐食性が強いため長時間燃料タンクに入れておくと危険なので使用(発射)直前に燃料注入をしてからでないと使用出来ない。
そのため人体に有毒なこともあり使い勝手も非常に悪く使用(発射)するためには準備する時間が必要なので有事即応性なんてないに等しいのでした。
よくニュースで北朝鮮がミサイル発射の準備をしている模様なんて報道されていましたが、これがいわゆる液体燃料ロケットを使用している証なのです。
兵器に液体燃料ロケットしか使えない場合は発射の何時間も前から敵に悟られてしまうため兵器としての有用性は非常に悪いものにならざるをえないといえます。
だから小さい固体燃料ロケットは作れるが大きな固体燃料ロケットを作れないということはそれだけ技術的には遅れた後進国であるという裏付けなのです。
ロケット推進部分を必要とするミサイルというものは有用だとしても核弾頭を搭載した核ミサイルは人道的観点と長く消えない放射能汚染を考えると実質的には使えない兵器であるという認識が世界的に広まっている現在、そうなるとどの国でも考えることはあまり変わらず空母が次に来る兵器の主役ということになり、空母を無力化出来る兵器は潜水艦ということに行き着きます。
それで現在、空母もしくは空母に近い軍艦を欲しがる国が増えています。
それと同時進行的に空母の天敵たる潜水艦を持ちたがるもしくは増やしたがる国々が増えています。
しかし、前述の通り空母を実際に持っても兵器として有効に活かすためにはいろいろな障害があり機材が揃ったとしても直ぐに使いきれるような簡単なものでもありません。
空母も潜水艦もそうですが、経験と技術とノウハウと運用実績がものをいう分野だといえそうです。
ごく代表的な各国空母の画像を参考資料として貼ります。
それぞれの国の空母の姿と同時に運用方式や規模の大きさの違いも良く判ると思います。
参考資料を貼ります。
・アメリカ海軍空母よりカタパルト発艦準備中のFA-18Cホーネット
・イギリス海軍のV/STOL空母のスキージャンプ台式飛行甲板から短距離発艦を行うハリアー
・ロシア海軍空母アドミラル・クズネツォフのスキージャンプ台式飛行甲板から短距離発艦を行うスホーイSu33別名Su27K(NATOコード名:フランカーD)シーフランカーと呼ばれる場合もある。
・中国海軍空母遼寧(建造途中だった旧ソ連海軍空母ワリヤーグを中国が改造したもの)のスキージャンプ台式飛行甲板から短距離発艦を行う殲15(スホーイSu33のパクリ)
です。
アメリカ空母の場合はカタパルト発進が可能なため自重が10.8tのFA-18Cホーネット最大速度マッハ1.8(2203km/h)は最大離陸重量23.5tで発艦することが出来るので燃料弾薬を合わせて12.7t搭載して飛び立つことが可能となっています。
フェリー飛行時航続距離は3700kmで戦闘行動半径は1063km。
現在既にアメリカ海軍の主力戦闘攻撃機になっている改良発展型のFA-18E/F最大速度マッハ1.6(1958km/h)の場合は更に強力になり自重14.5tに対し最大離陸重量は29.9tとなっており14.5tもの燃料弾薬を搭載して発艦出来るまでに成長しています。
フェリー飛行時航続距離は3705kmで戦闘行動半径は1475km。
イギリス軍のハリアーは元々は敵(旧ソ連軍とワルシャワ機構軍)の攻撃により核攻撃を受け飛行場などの施設が破壊された場合でも狭い土地から飛び立ち核報復攻撃が出来るようにと開発された短距離/垂直離着陸戦闘攻撃機でした。
しかし、他の戦闘攻撃機には出来ない垂直離着陸を実現したのは良かったものの、その特殊な能力の副産物として航続距離と搭載量が小さなものとなってしまいました。
それをいくらかでも改善するためにイギリスが試行錯誤して考え出したのがハリアー特有の推力偏向式ノズルの能力とスキージャンプ台式飛行甲板を組み合わせた短距離離陸でした。
発進はこれで行い帰還時には垂直で着陸する今で言うストーブル方式でした。
これにより20%以上航続距離と搭載量が改善されました。
垂直離着陸が出来る能力は夢のような能力でしたが、燃料が半減するほどに馬鹿食いしたためその能力はそのままに新たな運用方式を考え出すことでもっと魅力的な戦闘攻撃機にしようという目的でイギリスは世界初のスキージャンプ台式飛行甲板を実用化しました。カタパルトが無いからという理由ではありませんでした。
一方、自分も空母を持ちたいと願っていたが実用に耐え得るカタパルトを開発出来ず長い間空母を実用化出来ないでいた旧ソ連はこのイギリスの発明に注目し見よう見真似で真似たスキージャンプ台式飛行甲板を付けた空母を造りそこから通常形式の戦闘攻撃機を発進させ帰還時には制動索に着艦フックを引っかけて着艦させる今で言うストーバー方式によってなんとか使える空母を持つことに成功しました。
しかし、自重が18.4tのスホーイSu33最大速度マッハ2.165(2300km/h)は陸上基地の長さに特別な制約も無い滑走路からの運用ならば最大離陸重量33tであり搭載出来る燃料弾薬は14.6tあるものの空母艦上では最大離陸重量26tとなり搭載出来る燃料弾薬は7.6tしか搭載出来なくなります。
たとえスキージャンプ台式飛行甲板によって辛うじて空母から発艦出来てもカタパルトが無いために本来の能力よりも航続距離と搭載量が約半分に半減する結果となっています。
本来の陸上基地運用ならフェリー飛行時航続距離は3000kmで戦闘行動半径は1220kmですが、同じ理由により艦上運用の場合はフェリー飛行時航続距離は1500kmで戦闘行動半径は610kmと半減してしまいます。
それでも空母アドミラル・クズネツォフを自前の技術で建造した旧ソ連/ロシアの場合は風上に向かい艦の最大速度を出しながら合成風を活用し発艦させることが出来るため能力低下もなんとかこの程度でおさまっています。
建造途中だった2番艦ワリヤーグをスクラップ扱いで購入し改造した中国もイギリスのスキージャンプ台式飛行甲板をパクった旧ソ連/ロシアを更に真似てパクり初発艦を成功させました。
しかしながら中国の場合は空母の動力を自前では造れず民間船舶用エンジンを仕方なく搭載したため最大速度が鈍速過ぎるため合成風の効果もどれほど得られるのかかなり疑問が残るので搭載戦闘攻撃機の能力は更に低性能になるのはさけられません。
ちなみに中国が搭載戦闘攻撃機として使っているのも旧ソ連/ロシアのスホーイが開発したスホーイSu33の試作機を無理矢理強引に購入して技術を真似てパクった殲15という模倣品なのでこちらの性能もどうなのかなという疑問符が外せない存在です。
現在CATOBAR(キャトーバー:搭載機をカタパルト発進させ帰還時にはアレスティングフックを制動索に引っかけ着艦させる)方式で運用する空母を使っている国はアメリカとフランスとブラジルだけです。
参考資料として
・アメリカの原子力空母エンタープライズ、フランスの原子力空母シャルルドゴール
・ブラジルの通常動力空母サンパウロ(旧フランス海軍空母フォッシュ)
の写真を貼ります。
フランスもブラジルもアメリカからの協力によりこの状態を実現しています。
フランスはまだしもブラジルとは意外な感じがしますが、中南米諸国の中でこの手の空母運用実績と運用能力を持つのはブラジル一国だけです。
これが示す意味合いは重くブラジルもこの運用能力は手放したくないところでしょう。
中国はこのブラジルに目を付けかねてよりブラジルから運用能力を習っているようです。
何十年もかけて中国はマカオの企業という表向きの姿をしたペーパーカンパニーを作り旧ソ連邦の主要国だったウクライナからソ連邦崩壊のどさくさに紛れ海上カジノにする目的で買うといいながら世界中に大嘘をつき未完成空母をスクラップ扱いで購入、中国の港に到着すると中国政府が立入検査し不備があるため違法だとして没収するといい出し、それと同時に購入したはずの企業はドロンです。
気付けばもう中国政府の指示により空母として完成させるべく改造中という報道が世界を駆け巡りました。
元々、中国共産党中央政府が企んでいた筋書き通りの結果でした。
結局中国政府は多数の反対意見も聞かず世界中の国々を騙したのでした。
その中国では唯一1隻だけ保有の空母が遼寧(旧ソ連空母ワリヤーグ)なのです。
この空母はもちろんカタパルトなど持ち合わせていませんから、ブラジルから空母の運用方法を習っているということは次に中国が建造しようとしている中国国産空母はカタパルト装備としてアメリカに肩を並べようと企てているのでしょう。
しかし、アメリカは大型の原子力空母を11隻も保有し運用中ですからね。
その程度で対抗しようとしている中国政府の頭の中が理解出来ません。
アメリカの原子力空母は大型なため1隻あたり85〜95機程度の艦載機を搭載出来ます。
それを11隻も運用しているのです。
中国の空母遼寧はせいぜい40〜50機程度が関の山。
仮に中国が建造を進めているといわれる国産空母がアメリカの空母と同程度搭載出来たとしても圧倒的に敵わないでしょう。
子供でもわかるでしょうに中国共産党は頭がおかしい。
ちなみにその昔(大きな図体しているにもかかわらずアヘン戦争でイギリスにコテンパにやられ手も足も出せなかった中国の時代)は『眠れる獅子』と呼ばれていて今に強大な大国になるぞといわれていた中国、その悲願ともいわれる空母の保有をなんとか実現した現在の中国。
そうなると次は中国国産空母を建造するのかと世界中でいろいろな話が飛び交っています。
先ずは排水量6万t前後の通常動力空母を2隻と排水量10万t前後の原子力空母を2隻建造する予定らしく通常動力空母の2隻はもう建造中のようで進捗の早い方の1隻は早ければ来年にも進水するだろうといわれています。
しかしながら当面どの空母もカタパルト装備は見送られる見通しのようです。
まあ、実用的なカタパルトも原子力空母も技術力もないのに造れるはずはない話ですけど。
夢を語るのはタダですね。
しかし、これだけのものを持ったら中国も大変でしょう。
先ず揃えるだけでも巨額のお金が必要。
持った後がまた大変。
まとも運用していくためには更に莫大なお金が必要になる。
これがきっかけで中国は経済崩壊する可能性すら否定出来ません。
一方面に1隻の空母戦力を充てておくだけでも空母3隻は必要ですから。
戦闘用と訓練用と整備中の三つを常にローテーションさせておかないと戦力にはなりませんから。
0さん、素晴らしい
さすが 詳しいですね
おそれいりました
いいえ、そんなそんな恐れ入ります。m(__)m
いろんな情報の氾濫する今の時代、ネット社会といわれるようになってたくさんの情報が氾濫する中、当然騙そうとする情報と本当のことを伝えようとする情報が混在しているため便利な時代になったもののそれぞれの情報を信じるか信じないかは個人の自己責任による判断が必要不可欠です。
日本を取り巻く国際情勢もニュースが報道して伝えるのはほんの一部でしかありませんし、それも何らかの勢力によって誘導されたものが大半です。
だから私たちはそんなものに惑わされたり騙されたりしないようにするにはよりたくさんの情報を見てどれが正しいのか自分で判断する必要があります。
私は日本人の一人として日本の周囲で今何が起きているのか正しく知っておきたいと常々思っています。
だから簡単にいえばそういう理由で過去現在の軍事世界情勢を調べているだけです。
まあ、そんなとこです。
たとえばですけど
宝島はいろんな内容を掲載してくれるから好きではあるんですが、数値類の間違い桁が違ってたりする間違いが多く、文面の内容を読んでいくとこれを書いた人は明らかにこの分野のことをよく知らない素人だなとバレバレなのが多いです。
気持ちは判るんですが、日本のステルス機の話や国産空母の話などその内容にはかなり勇み足の情報掲載も多いです。
現在、陸上自衛隊で最新型(世界中を見渡してみても最新型の部類の戦車になります。)の10式戦車について宝島の書籍に掲載された内容で笑ってしまったのが「防御装甲は前面部分だけの自走砲でしかない」という説明でした。
基本的に現代の戦車はどこの国の戦車でも前面部分だけに一番強力な装甲を配し他の部分には軽装甲を施すのが常識化しているため宝島で書かれていた内容は驚くべきことでもなければ単に当たり前の話であり、だからといって自衛隊の10式戦車が防御力的に弱いと評価するのはド素人的考え方なのです。
間抜けな韓国人の報道と正に同レベルです。
韓国では開発が難航中の最新型戦車K2(当時は試作車輛だったためXK2と呼ばれていました。)が完成した時(7年ほど前)にはネット上で盛んに自画自賛していました。
世界中のどの戦車に攻撃されても防御出来、他方では世界中のどの戦車でも撃破出来ると豪語し、日本の90式戦車なら3輛並べても側面から撃てば3輛全ての側面装甲を貫通出来ると意味不明な宣伝を盛んにやっていました。
繰り返しですが、現代の戦車は世界中どこの国の戦車でも側面装甲は薄いのが常識なのに韓国人の報道も意味不明でしょ?
韓国最新型のK2戦車だって側面装甲はどこからどう見ても薄いのにアホかって感じです。
韓国は国産国産と息巻いていますが、K2戦車とは全ての主要部分は先進諸外国の開発品を輸入して持って来て寄せ集めた最新型戦車なのが実態であり、それを韓国製部品の使用率を後から増やしていこうとしている戦車であり、韓国国産というにはかなりの語弊がある戦車なのでした。
このK2戦車も計画では2011年には配備を始め合計600輛は生産する予定でしたが、度重なる技術的トラブルにより開発は遅延し、当初の性能はスペックダウンを余儀なくされ、価格は高騰し、一部装備は装備されないことになり、生産数量は200輛にまで削減される結果となっています。
ちなみに2014年、今年になってやっと生産された一次生産分車輛100輛分は韓国国産エンジンではなくドイツから輸入した外国製エンジンによる車輛です。
韓国が盛んに自画自賛していた頃のK2戦車の資料を貼ります。
韓国製の戦車は世界一世界最強といわれ信じ込まされて、実際に戦争になった時こんな戦車に乗り込んで戦う羽目になるであろう兵士たちは気の毒ですね。
韓国国産では動力には不安が残るし、威力は高くても射撃精度は悪く命中させられない主砲だし、長い主砲は取り回しを悪くし身動き取り辛いでしょうし、アクティブプロテクションシステムは装備されなくなっているし、仮に装備されても作動すれば戦車自体には良くても周囲に居る無防備な味方兵士が確実に死亡するでしょうね。
韓国上層部ではそんなこと気にしていないでしょうから実戦になったら確実にそうなるでしょう。
セウォル号沈没事件と同様に起きるべくして起きるでしょう。
お気の毒です。
歴史カテともスレタイの零戦とも掛け離れすぎの内容になっちゃったね
別スレ立てるか軍事カテでやるかどちらかにしないと
ここは歴史カテです
いいんじゃないの?
スレ主さん自身がいろいろ書いて下さいって言ってたのもあるし
そもそもここは歴史だけの掲示板って名前ではなくて歴史・学問の掲示板だとはっきり書かれてるでしょ?
歴史と学問にまつわる話なら全然正当でしょ?
零戦は空母で使うための艦上戦闘機です。
空母の歴史にまつわる話が出てきても何の不思議もありません。
韓国の戦車、これも韓国は国産戦車だと言っている以上、今まで戦車なんて国産で作り上げたことなどなかった韓国人にとっては歴史的なことでしょ?
立派に歴史にまつわる話だと思いますがね。
どこか一つでも間違ってますか?
まぁ何ていうかコメの内容は、レベルが高くて勉強になる事は確かだね。
しかし同じスレ
まぁ何ていうかコメの内容は、レベルが高くて勉強になる事は確かだね。
しかし同じスレの中で二人だけのやり取りが延々と続くのは、排他的な印象がして他の人が参加不可能な感じがするのも確かだね。
軍事の事柄でテーマ事にスレ建をするのが好ましいと思うよ。
皆さん、新年おめでとうございます、
最初 スレたてた時、は
日本の 歴史として
零戦も歴史の一部分と考え![]() 時代は 私ヘルシアは
時代は 私ヘルシアは
万次郎 ハンネで
歴史 学問カテゴリーで
投稿してましたので、
こちらにスレ建てた次第です、
0さん ありがとうです
私の知らない歴史の一部を勉強させていただきました、
まだまだ、教えて下さい 今年も よろしくお願いいたします、
昭和17年(1942)5月7日
珊瑚海海戦
当時、世界初の、空母対空母、同志の戦い
日本側、小型空母1隻喪失、
米側、米大型空母 大破
(後に、真珠湾で修理)
、
画像は 珊瑚海で
炎上する ヨークタウン
↓↓
1.
青き花咲(はなさ)く大地
気高(けだか)きわが故郷よ
響(ひび)け 歓喜(かんき)の歌
神の加護(かご)は われらとともにあり続けん
ガーレ=ガミロン*1
讃(たた)えよ 祖国の勝利を
2.
気高(けだか)きは勝利の意志
示せ 遍(あまね)く宇宙に
理想 貫(つらぬ)く愛
神の加護(かご)は われらとともにあり続けん
ガーレ=フェゼロン*2
誇りある鋼(はがね)の国家
*1ガーレ=ガミロン:ガミラス萬歳(ばんざい) 「ガミラス」が「ガミロン」となっているのは、格変化(かくへんか)によるものだろう。英語は、格変化が基本的にないが、人称代名詞だと、I my meなどと、主格、所有格、目的格で変化するようなもの。
*2ガーレ=フェゼロン:総統萬歳(そうとうばんざい) 「フェゼロン」は、ドイツ語の「総統」であるFührer(フューラー)に由来(ゆらい)するようだ。
久し振りに 書き込みしました
何年か前に {永遠の0〕の CD 見ました
どなたか 見られた方が いらっしゃいましたら コメント
いただけたら幸いです
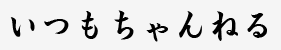

























































































































































































































































































































































































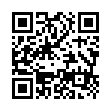
皇紀2600年を記念して、下1ケタをとり、零式戦闘機としたとか、
用途:戦闘機
分類:艦上戦闘機
設計者:堀越二郎
製造者:三菱重工業
運用者: 大日本帝国(日本海軍)
初飛行:1939年(昭和14年)4月
生産数:10,430機
運用開始:1940年(昭和15年)7月
退役:1945年(昭和20年)8月